自由なラジオ Light Up! 014回
「 沖縄や福島の人たちだけに背負わせて手に入れた「偽りの安全」について考える 」
https://youtu.be/h9w9WDW-S6U?t=17m12s
17分12秒~第014回Light Up! Journal
関西電力高浜原発3、4号機の運転差し止めを命じた大津地裁。 不服として関電が行った執行停止の申し立てを、同地裁は却下
http://jiyunaradio.jp/personality/journal/journal-014/
木内みどり:
今日も元京都大学原子炉実験所の小出裕章さんと電話が繋がっています。
小出さ〜ん、今日もよろしくお願いします!
小出裕章さん:
はい。こちらこそ、よろしくお願いします。
木内:
それでですね、目の前に落合恵子さんがいらしてます。
小出さん:
はい。嬉しいです。
落合恵子さん:
はい。よろしくお願い致します。
小出さん:
はい。こちらこそ、落合さん、こんにちわ。
よろしくお願いします。
木内:
まず、ひとつ質問をさせてください。
関西電力高浜原発3号機、4号機の運転差し止めを命じた大津地裁の仮処分決定を不服として、関電が行った執行停止の申し立てについて、6月17日同地裁は却下する決定を出しました。まず、こちらについて小出さんご感想を。
小出さん:
私は日本の司法、裁判というものに絶望していまして、少なくとも原子力に関する限りは、期待をかけないということをしてきたのですが、今回の決定、また「高浜3号機、4号機を動かしてはならない」という決定を出してくださったわけで、大変ありがたく思いました。ただ、今回の決定を出してくださったのは山本善彦裁判長で、彼は既にご自分で仮処分の決定を出して、高浜を動かしてはならないと言ってくださった方ですので、こういうことになるだろうなとは思っていました。
木内:
はい、ありがとうございます。
今日は、落合さんがいらっしゃるので、落合さんと小出さんについて話を繋げたいなと思っているんですけど。と言いますのは、このラジオを聴いてらっしゃる方は、小出さんの発言をずっと聴きたくて、ずっと聴いてた方が今も聴いていらっしゃると思うんですね。原子力を止めたい、危ないんだということをおっしゃった小出さんを片や知りつつ、片や落合恵子さんも事故前からずっと運動をされていて、この2人が今日一緒だっていうことは、ちょっとやっぱり両方のファンとしては特殊な瞬間なので、私としてはその辺りをお伺いしたいと思うのですが。
まず、小出さんが41年も前から原子力は危険だとおっしゃっていて、落合さんも事故前から…事故の何年ぐらい前ですか?
落合さん:
そうですね、チェルノブイリの原発事故の後ですね。その前のスリーマイル島の時は、秘密のプライベートのフィルムを米国の活動家から頂いていて、それを見た瞬間にやっぱりおかしいと思い、そしてチェルノブイリ以降は特にそう思ったのですが、これは私の中の何かが緩んでしまったか、もちろん力がなかった結果ですが、原発は止められないし、気がつけば福島にいってしまった。そのことが私の中でとっても大きな、何と言ったらいいんでしょうね、罪のようなもの、意識があって。だから、今度はもう後戻りはもちろんしないっていうこと。そして、小出さんと私は、存在はもちろん知っていました。
木内:
それは生まれた時から知っているわけではないですから。小出裕章さんの発言とか本とか、なんかこうちょっと知るきっかけがあったと思うんですけど。
落合さん:
私が大変信頼をしている新聞の記者の人とか雑誌記者の人達、皆さんから小出さんのお名前はずいぶん前からお聞きしてたんですね。それで、私が直接、小出さんという存在と向かい合ったのは2011年の4月、十三での講演会をされてたんですよ。それで私は他の仕事で行っていて、小出さんの講演会があるということで入れなかったのね(笑)、それで並んだんですが。
木内:
小出さん、そのこと覚えていらっしゃいますか?
小出さん:
もちろん覚えています。
落合さん:
ありがとうございます。
小出さん:
落合さんが来てくださったんですけど、会場に入って頂けなくて、1階下の階にスクリーンで映写するというような部屋を主催者が作ってくださって、そちらに落合さんがいてくださいました。終わってから、私、落合さんにご挨拶できて本当にありがたいと思いました。
落合さん:
でも、私、その前から「種まきジャーナル」もちろん知ってまして、大阪の友人が録って送ってくれてたんですね。ですから、いっぱいその時も勉強させて頂きました。
木内:
その時に名乗り合ってというか、知り合いにもなって。
落合さん:
そうです。私がやってますクレヨンハウスからも、小出さんのお話や思想、姿勢をある意味で聞き書きのような形ですが、本を出させて頂いたこともありますしね。ずっと、どういう風に言ったらいいのかな?「いて下さってありがとうございます。学ばせてください」そんな気持ちが続いてます。
木内:
小出さんにとって落合さんというのは、それまでも原子力はダメだとかいう運動をしてらした男性も女性もたくさんいたと思うんですが、そういう女性達の中で、落合さんというのは飛び抜けた存在だったと思うんですけど。古くから活動してらっしゃる女性を傷つけないように経由して頂くとしたら、落合さんがどのように今までの活動をしてらした方と違ったかというのを教えてくださいませんか?
小出さん:
落合さんがですね、もちろん原子力に対しても反対してくださっている訳ですけれども。彼女は、もともと子供達の絵本を作るという活動をずっと続けてきてくださっていた。そしてその中から、憲法を大切にしようであるとか、沖縄の問題に関わるであるとか、非常に原則的なことをやってきた方です。そして彼女は、それら全てが繋がっているんだと、原子力も含めてですね、繋がっているんだということをしっかりと発言してくださって、それをときどき原発的なもの、原発的な社会という風な言葉で呼んでくださっていて、私は、「あっ、本当にそうなんだな。ありがたいことだ」と思ってきました。
木内:
ありがとうございます。あんまり時間がないんですけれども、今日、こうして落合さんをゲストに迎えて、私がラジオのパーソナリティをやっていて、電話で小出さんと繋ぐ、一緒にしゃべれるなんてことが、こんなことが起きるんだなと、やっぱり人生諦めちゃいけないなと。嬉しい事起きますね。
落合さん:
私が昔20年ぐらい前番組を作っていて、そこに例えば青森県で「核燃まいね、核燃は嫌だよ」という活動をしている当時は若い女性、お母さんだった人に出ていただいて、その方と何十年ぶりに再会してみると、その方達が小出さんがおっしゃってこられたことを学んできた。どっかでね、木内さんともそうですが、1つの意識を持って歩いていくと繋がっているっていうことをとても感じますよね。
木内:
ありがたいことです。
本当に聴いていてくださるリスナーの方も、ずっと小出さんを追いかけて、落合さんを追いかけて、それでたまたま私がパーソナリティをしているところに、落合さんがゲストで小出さんが出るということで本当に楽しみに聴いてくださっている。あなたも今日はラッキーですよね!本当に嬉しい嬉しい時間でした。はい。小出さんありがとうございました。
小出さん:
こちらこそ、ありがとうございました。今日はとても楽しかったです。
落合さん:
ありがとうございました。嬉しかったです。
木内:
今度、3人で飲みましょうね!
小出さん:
そうですね、そう願いたいです。
落合さん:
よろしくお願いします。
木内:
ありがとうございました。
そもそも福島の支援法が骨抜きになっているのではないか?
http://dai.ly/x17hs0k
自由なラジオ Light Up! 015回
「「国策紙芝居」を知っていますか? 人気メディアを巧みに利用して幼い心を洗脳していった国家権力の恐怖」
https://youtu.be/nczokaePJ7k?t=20m16s
20分16秒~第015回Light Up! Journal
核のゴミを佐賀県玄海町が受け入れ?どうなる原発の高レベル廃棄物
http://jiyunaradio.jp/personality/journal/journal-015/
西谷文和:
今日のテーマは、「核のゴミを佐賀県玄海町が受け入れ? どうなる原発の高レベル廃棄物」と題してお送りしたいと思うのですが、今中さん、これどういう風に感想をお持ちです?
今中哲二さん:
私、細かい話は調べてませんけども、海の底って言うんですよねえ。
西谷:
海の底ですよねえ。はい。
今中さん:
やっぱり海の底はマズイでしょうし、日本でそんな掘って、ずーっと何百年も何万年も安定してるようなとこがあるとも思えませんし。はい。
西谷:
地震国ですからねえ。
今中さん:
はい。
西谷:
まさに熊本で地震が起こってる今に、佐賀県で受け入れるなんていうのはねえ。
ちょっとおさらいをしますけれども、日本の場合、原発から出る使用済み核燃料棒、これを高レベル廃棄物と呼んでいるんでしょうか?
今中さん:
原子炉の中でウランが核分裂を起こしますよね?
西谷:
起こしますよね。
今中さん:
核分裂連鎖反応。
そして、そこで核分裂で起きてできる物、我々の言葉で言えば核分裂生成物ですね。これが非常に放射能強いんですよ。西谷さん、「死の灰」っていう言葉ご存知だと思うんですけれども。
西谷:
はい、死の灰。
「死の灰」第五福竜丸船体または設備などに付着したもの
今中さん:
要するに、核分裂でできた「死の灰」が原子炉の燃料棒の中にどんどんどんどん溜まっていくという事です。
西谷:
という事はですね、同じ核燃料と言われるものでも、その使用前はまだそれほど出てないけど。
今中さん:
そうですね。使用前の核燃料でしたら私も見たことありますし、近づいて測定したことあると思いますけども。皆さんちょっと単位は分かんないと思いますけども、使用前の新燃料ですよね。新燃料の目の前で放射線量を測っても、いわゆる数マイクロシーベルト。
西谷:
数マイクロ?
今中さん:
はい、1時間あたりね。
西谷:
という事は、今の福島で…
今中さん:
福島の高い所。
西谷:
高い所ぐらいですよね、はい。
今中さん:
それが、たぶん核分裂して出してくると、それの1億倍ぐらいになるから。
初期の使用済み核燃料の表面線量は約100000Sv/hr(10万Sv/hr)
西谷:
核分裂したら、使用後は1億倍になるんですか?!
今中さん:
ええ、私ちょっと計算したことありますけども、1億倍をもっと超えると思います。一番放射能の強い「死の灰」とかいう部分は、いわゆるガラスで固めるというやり方なんですよ。
西谷:
ガラス固化体にするということですねえ。
今中さん:
そうそう。これも高レベル廃棄物です。はい。日本の一応方針は、全部再処理してガラス固化体を処理するという。地下に埋めるという方針にはなってます。
西谷:
このガラス固化体というのは、人が近づくと十数秒で死に至ると……これ本当ですか?
今中さん:
本当です。まさか本当にそんな事をやった人はいませんから。計算上は、それくらいにはすぐなると思います。裸の場合ね。
西谷:
裸の場合。そうですか。日本の場合、そういう物凄い危険なものを300メートル~1キロの穴を掘って埋めるということなんですが、仕方がないですか?
今中さん:
結局、昔の原子力安全委員会とか基礎委員会もそうですけども、要するに、「埋めたら10万年、20万年大丈夫ですよ」というような見積りなんかやるわけですよね。私には、その話苦手なんですよ。というのは、そんなもん10万年先、20万年の先、この地球がどうなってるか、日本がどうなってるか、人類がどうなってるか分かんないのに、そんな保障もしようがないでしょ、ということですね。それで、まず一番最初に確認しなきゃいけないのは、とにかく「これ以上、高レベル廃棄物、使用済み燃料を増やさない」。これが、まず第一の確認です。
西谷:
そうですよね。「これ以上増やさない」。という事は、再稼働させないことですね?
今中さん:
そうですね、もちろん再稼働させないし、これまでに日本で溜まった高レベル廃棄物あるわけですよねえ。これは、やっぱり何とかしなきゃいけない。これについてはやっぱりみんなで議論して、じっくり考えていくしかないですねえ。皆さん詳しくないから、あんなもんなんかしたら核変換とかいろんな話がいっぱい出てきて、いかにも科学技術で消せるようなことを言ってますけども、そう簡単ではないです。
オメガ計画 - Wikipedia
西谷:
そうですか。なんか物凄く暗い気持ちになるんですけど。
今中さん:
そうですね。多分ね、原子力を始めた人達は、いずれ何とかなると思ったんでしょうけども。何とかならない状態で、どんどんどんどん増えていってるわけですよね。
西谷:
それで、なんかまた過疎の村、貧しい村に、またこれを押し付けるなんて、これが一番許せないと思うんですが。
今中さん:
そうですね、はい。
西谷:
もう本当に原発は矛盾だらけ。そして、その格差の問題も絡みますよねえ。
今中さん:
そうですね、はい。
西谷:
本当に原発が問題を絡んでるところがよく分かりました。今中さん、どうもありがとうございました。
今中さん:
はい、どうも。
「核のごみ」どこへ
「沿岸海底下」が浮上
(東京新聞【こちら特報部】)2016年2月4日
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2016020402000134.html
原発から出る「核のごみ」を廃棄する最終処分場の受け入れ先が見つからない中、経済産業省は海底下に処分場を造り、廃棄することを真剣に検討し始めたようだ。海底下であれば、地権者はいない。だが、陸地の地下に埋めた場合でも放射性物質が漏れ出し、汚染が広がることが懸念されている。海底に埋めた場合、海が汚染される可能性があるが、大丈夫なのか。
(中山洋子、白名正和)
「沿岸海底下」が浮上
経済産業省資源エネルギー庁は先月、核のごみの処分を議論する新たな有識者会議を設置した。名称は「沿岸海底下等における地層処分の技術的課題に間する研究会」。エネ庁の担当者によると、名称中の「等」には、「海底下と言うと沖合のイメージが強いが、いわゆる波打ち際も検討するという意味がある」という。
核のごみの最終処分場のイメージはこうだ。地上に管理棟などの施設を設け、その地下を三百メートルより深く掘り進め、地下空間を造って埋める。
担当者は「沿岸部の場合、地下の最終処分場は施設の直下だけでなく、陸地から海底に向けて斜めに坑道を掘って造ることもありうる。研究会では、その場合にどんな課題があるかを洗い出す。『海底下』はあくまで選択肢の一つ」と強調した。
研究会の名称から、最終処分場を「海底下」に絞ったかのような印象を受けるが、担当者は直ちに「違います」と否定した。
では、どこに造られるのか。経産省は現在、最終処分場に適した「科学的有望地」を選定中だ。
火山から十五キロ以内、活断層周辺、地盤が軟弱、鉱物資源が見込まれる地域などを原則除外。それ以外を適性のある地域とし、海岸から二十キロ以内は「より適性の高い地域」とする。運搬中の事故や住民の被ばくリスクを考慮し、核のごみは海上輸送がメーンとなるからだ。
経産省の放射性廃棄物ワーキンググループ委員の一人で、原子力資料情報室の伴英幸共同代表は「『海底下』に最終処分場を造ることは、以前から検討されてきた。だが、陸地の活断層については、一九九九年に核燃料サイクル開発機構(現・日本原子力研究開発機構)が安全評価のリポートを発表しているものの、海底についてはない。海底の断層はわかっていないことが多い」と指摘する。
その上で、「ここに来て、『海底下』を前面に出してきたのは、技術的な難しさとてんびんにかけても、反発が強い陸地よりやりやすいと判断したからではないか」と推測する。
もともと、最終処分場の選定は公募方式で進められたが、うまくいかず、「科学的有望地」を提示する現行方式になった。二〇〇七年に高知県東洋町からあった応募は、町民の反発で推進派町長が落選し、白紙撤回となっている。
核のごみ廃棄に対する自治体の警戒感は強い。共同通信の昨秋の調査では、全都道府県のうち、十三府県が「候補地に選ばれても一切受け入れる考えがない」と拒否し、八道県が「受け入れは難しい」などと否定的な姿勢を示す。
土地取得のハードル低く
経産雀は「海底下」の利点について、「基本的に公有地のため、土地利用に関する制約が小さい」などと説明する。公有地であれば、地権者との協議はいらない。首長の同意は必要だろうが、最終処分場設置へのハードルは陸地より低い。
陸地より調査に手間と金
放射性廃棄物の地層処分に詳しい藤村陽・神奈川工科大教授(物理化学)も、「海底下」の安全性について、活断層に関する文献は少なく、陸地よりも調査が難しいと指摘する。さらに、「ボーリング調査や地下施設を追って行う調査でも、陸地の地下より手間もカネも時間もかかる」。
そもそも、陸地の地下であっても地層処分には課題が多いという。埋める核のごみの主なものは、高レベル放射性廃棄物のガラス固化体だ。隔離する期間は十万年以上だから、何度も地震が起きる。覆っている金属製容器、粘土の緩衝材が壊れる危険性がある。
「ガラス固化体が地下水に触れるとガラスとともに、放射性物質が地下水に溶け出す可能性がある。地下水の流れに乗って地表に出てきて、人が放射性物質を体内に取り込む恐れがある」
埋めるという処分自体にも一長一短がある。「空気と触れないため、金属容器の腐食を防げる。半面、ガラス固化体に異常が起きても近づけず、対処が難しい」(藤村氏)
どう対処するのか。エネ庁の担当者は「地層処分の安全規制は定まっておらず、原子力規制委員会がこれから決める」と話した。規制委に取材すると、担当者は「詳細の議論はしておらず、今後の検討課題」と説明した。
藤村氏は、ほかにも問題があると話す。地層処分では、低レベル廃棄物も埋めることが検討されているという。ヨウ素129や炭素14などだ。ガラス固化体のように固めずに廃棄するため、より地下水に溶け出す可能性がある。ちなみに、半減期はヨウ素129が約千五百七十万年。炭素14はそれよりは短いが約五千七百年だ。
海の汚染 消えぬ懸念
海底下に最終処分場を造れば、放射性物質が漏れ出す先が海になる危険性が高まる。海産物が放射性物質で汚染される恐れがあり、漁業への影響は大きい。
東京電力福島第一原発事故で大きな被害を受けた福島県相馬市の男性漁師(六五)は「原発事故での漁業へのダメージを考えると、海底下に処分揚を造るなんて話は、日本のどこの漁業者にとっても受け入れられない。絶対起きないと言われていた原発事故が起きた以上、海底下の処分揚の安全性も完全に信じることはできない」と語った。
「もしかしたら、福島第一原発の近くに造るということになるんじゃないか。せっかくうまく行きかけている漁業の復興が駄目になってしまう」
「万々歳の選択肢はない」
もちろん、懸念される問題が起きるとは限らない。藤村氏は、推進する側の説明が足りないことを問題視する。「問題が起きないように頑張る、という言い分は、原発事故前の『安全神話』と同じだ。地上だろうが地下だろうが、核のごみの最終処分に、万々歳という選択肢は存在しない。それでも、既に発生したごみをどう処分するか。覚悟の上での国民の合意が必要だ」
九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)に続き、関西電力高浜原発3号機(福井県高浜町)が先月、再稼働した。使用済み核燃料がまた増える。最終処分揚が決まらず、再処理事業がうまく進まなければ、いずれ原発内の燃料貯蔵プールは満杯になる。
ドイツ:アッセ核廃棄物貯蔵所に浸水:二進も三進もいかない核のゴミ
https://youtu.be/-3Ur6FxmVKo

原発という「麻薬」
玄海町・最終処分場問題
(東京新聞【こちら特報部】)2016年5月10日
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2016051002000146.html
九州電力玄海原発のある佐賀県玄海町の岸本英雄町長が先月下旬、高レベル放射性廃棄物の最終処分場建設をめぐり、国との協議に前向きな発言をした。町長はその後、発言をトーンダウンさせたが、背景には玄海原発1号機の廃炉に伴う町財政の減収が透ける。原発依存という「麻薬」だ。一方、国は九日の東京を皮切りに、最終処分場の必要性を訴えるシンポジウムを全国で開き始めた。
(池田悌一、沢田千秋)
最終処分場撤回せず
岸本町長が最終処分場の受け入れに前向きな姿勢を示したのは、先月二十七日のことだった。
「こちら特報部」は九日、あらためて町役場で岸本町長に真意を聞いた。
町長は「自ら手を挙げるつもりは、いまのところ全くない」としつつも、「国が玄海町を最終処分場の適地と判断し、調査を要請してくれば、協議に応じ、住民にも説明する。町民も原発には一定の理解がある。国のエネルギー政策には協力したい」と話した。
高レベル放射性廃棄物は原発の使用済み核燃料を再処理し、プルトニウムなどを取り出した後の廃液。これをガラスと混ぜて「ガラス固化体」にする。これが無害化するまで、数万~十万年の間、生活環境から隔離する必要がある。その隔離場所として、地下三百㍍より深い地層の岩盤に埋める(地層処分)方式を採用する計画だ。
岸本町長は「中山間地域の玄海町は平地が少なく、リアス式海岸で海底が浅いため大型輸送船は入りづらい。処分場には適さない」と言うが、九電の広報担当者は「玄海原発付近の地層は二百万年動いておらず、安定している」と語る。
岸本町長は二〇〇六年八月に就任。一二年に、町長の実弟が社長を務める建設会社「岸本組」(佐賀県唐津市)が○五~一一年度にかけ、電源立地地域対策交付金など「原発マネー」を財源とする同町発注工事を二十五億円以上受注していたことが発覚した。
総事業費十五億五千万円で、岸本組が建てた「次世代エネルギーパークあすぴあ」は一三年に完成した。入館無料の施設を孫と訪れた唐津市の主婦(五八)は「最終処分場が安全なら、原発立地自治体が受け入れるべきだ」と言い切る。
町内で買い物をしていた大工の男性(七〇)も「原発のおかげで町民税も電気代も安く、道路も舗装された。処分場は怖いが、よそでは無理」と笑う。漁港にいた漁師の妻(六三)は「原発が来た時から覚悟しとった」と言葉少なに立ち去った。
「これいかんどー」言える町民ほぼいない
「『これいかんどー』と声高に言える町民はほとんどいない。誰のおかげで町が成り立っとるか、と怒られるから。沈黙の町だ」
処分場建設に反対する藤浦皓(あきら)町議(七九)はそう話す。「原発が来た後も町の人口は減り、農業も漁業も衰退し、今や『限界』町だ。地場産業は育たず、町長の会社ばかり潤ってきた」
原発の誘致段階から反対を続ける東光寺の元住職仲秋喜道さん(八六)は「地震大国の日本に安全な場所などない。町長は経済産業省や九電と話し合った末に発言したに違いない。アドバルーン的な役割を町長が務めて、町民やマスコミの反応を見ているのだろう」と強い警戒感を示した。
廃炉で町財政減収
町の財政は完全な原発依存型だ。同町によると、一六年度の当初予算ベースで歳入七二億五千万円のうち、原発関連の固定資産税や交付金、補助金が59%。一四年度決算では、固定資産税の約九割が九電の負担分だった。ただ、昨年四月に玄海原発1号機が廃炉になり、一四年度に一六億円だった電源立地交付金は、一六年度には一二億円ほどに落ち込む見込みだ。
ちなみに玄海原発3、4号機は現在、再稼働に向けた新規制基準に基づく適合審査中だ。町長の発言は再稼働への弾みとなると同時に、町財政の減収を補う新たな関連施設の誘致が狙いという見方が強い。
この点を聞くと、岸本町長は「お金に貧窮して、処分場受け入れを考え付いたと思われるのは心外だ」と不快感をあらわにした。
必要性訴えるシンポ始まる
岸本町長に話を聞いた9日、東京でも最終処分場をめぐる動きがあった。
東京・大手町で、経済産業省資源エネルギー庁と電力会社が資金拠出する経産相の認可法人、原子力発電環境整備機構(NUMO)の共催で、「いま改めて考えよう地層処分」というシンポジウムが開かれた。東京を皮切りに、全国九カ所で開かれる予定だ。
最終処分場はNUMOが0二年以降、候補地を公募したが、応募は0七年の高知県東洋町だけ。しかも住民の反対運動から町長が辞職に追い込まれ、出直し町長選で反対派が当選したため、応募は撤回された。
その後、進展のない状況に業を煮やした国は昨年、自治体の公募方式から国が自治体に申し入れる方針に転換。シンポジウムはその「地ならし」に当たる。
あいさつに立ったNUMOの近藤駿介理事長は「安全性を最優先に調査を進めていく」としながら「処分場を受け入れていただければ、さまざまな事業インフラや生活インフラの整備を通じて、地域の持続的発展を実現させる決意だ」と利益誘導を忘れなかった。
質疑では、参加者らから「もし廃棄物の容器が壊れたらどうなる」「このシンポで同意を求めようというのか」といった声が上がった。それに対し、主催者側は「容器は頑丈」「ご理解をいただくためのシンポだ」と説明に追われた。┐(´д`)┌
処分場整備急ぐ国
再稼働の障害 除く思惑
ただ、国が最終処分場の決定を急いでも、前提となる再処理はできる状態にない。青森県六ケ所村の再処理工場は二0回以上、完成予定を延期している。
今回の岸本町長の発言翌日、東洋町で最終処分場の応募を撤回した沢山保太郎前町長が、玄海町役場を訪れ、抗議文を提出した。
その沢山前町長は「もし地下で事故が起きれば、手が付けられない。地域住民の考えもよく聞かずに、町長が独断で判断するのは許されない」と憤る。
「当時の東洋町も財政はじり貧状態で、負債が予算額の二倍に膨れ上がっていた。元町長は数千億円の経済効果というアメに目がくらんだのだろう。だが、電力は都会で大量に使いながら、ごみはさびれた地域に捨てればいいという差別的な考えは通らない」
九州大の吉岡斉教授(原子力政策)は「原発マネーで潤うのは、地方自治体と建設業界。いずれの利権にも関わる玄海町長は、処分場計画が国主導に転換されたことで『取り残されてはいけない』と危機感を抱いたのだろう」とみる。
「使用済み核燃料は、このまま百年置いておいても問題はない。新たな置き場がなくなると言うなら、原発を再稼働させなければいい。政府は逆に最終処分場の整備を急ぐことで、再稼働の障害を取り除こうとしているのだろう。福島原発事故の対応という喫緊の課題にも十分に取り組めていないのに論外だ」
絶対原子力戦隊スイシンジャー
https://youtu.be/0AcQJE_R0iw
第14・15回Light Up! Journal 小出裕章先生 今中哲二先生 / 「ゴミと麻薬」
標的の村 ´・ω・) 深刻な対米従属の実態 (・ω・`

米軍が1960年代、ベトナム戦争のゲリラ戦訓練などのために沖縄本島の米軍北部訓練場に設置した通称「ベトナム村」において高江の住民をかり出し、ベトナム人の格好をさせ、ベトコンを探し出して捕まえる訓練を行った。
『標的の村』劇場予告編
https://youtu.be/rJcJSZJ4qoI
日本にあるアメリカ軍基地・専用施設の74%が密集する沖縄。5年前、新型輸送機「オスプレイ」着陸帯建設に反対し座り込んだ東村(ひがしそん)・高江の住民を国は「通行妨害」で訴えた。反対運動を委縮させるSLAPP裁判だ。わがもの顔で飛び回る米軍のヘリ。自分たちは「標的」なのかと憤る住民たちに、かつてベトナム戦争時に造られたベトナム村の記憶がよみがえる。10万人が結集した県民大会の直後、日本政府は電話一本で県に「オスプレイ」配備を通達。そして、ついに沖縄の怒りが爆発した。
2012年9月29日、強硬配備前夜。台風17号の暴風の中、人々はアメリカ軍普天間基地ゲート前に身を投げ出し、車を並べ、22時間にわたってこれを完全封鎖したのだ。この前代未聞の出来事の一部始終を地元テレビ局・琉球朝日放送の報道クルーたちが記録していた。真っ先に座り込んだのは、あの沖縄戦や米軍統治下の苦しみを知る老人たちだった。強制排除に乗り出した警察との激しい衝突。闘いの最中に響く、歌。駆け付けたジャーナリストさえもが排除されていく。そんな日本人同士の争いを見下ろす若い米兵たち……。
本作があぶりだそうとするのは、さらにその向こうにいる何者かだ。復帰後40年経ってなお切りひろげられる沖縄の傷。沖縄の人々は一体誰と戦っているのか。抵抗むなしく、絶望する大人たちの傍らで11才の少女が言う。「お父さんとお母さんが頑張れなくなったら、私が引き継いでいく。私は高江をあきらめない」。奪われた土地と海と空と引き換えに、私たち日本人は何を欲しているのか?
http://hyoteki.com/
本格報道INsideOUT<シリーズ・映画で戦争を考える>
「標的の村」
http://dai.ly/x137rr3
沖縄・東村 怒りの高江
参院選の審判無視 翌日から資材搬入
米軍ヘリパッド建設強行狙う
(しんぶん赤旗)2016年7月16日
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-07-16/2016071601_01_1.html
参院選で改めて「辺野古新基地ノー」「オスプレイ反対」の沖縄の民意が明確に示されたにもかかわらず、安倍政権は、沖縄県東村高江(ひがしそんたかえ)の米軍ヘリパッド(着陸帯)建設工事を月内にも強行する構えです。投票日翌日の11日以降、反対する地元住民らを強制排除して工事用資材の搬入を続けています。週明けには全国の機動隊約500人を投入しようとしており、現地住民らは、支援を訴えています。
高江 米軍ヘリパット 5日連続資材搬入に抗議
ウチナーンチュは負けぬ
(しんぶん赤旗)2016年7月16日
機動隊大量投入計画も
米軍ヘリパッド(着陸帯)建設が強行されようとしている沖縄県東村高江(ひがしそんたかえ)の米軍北部訓練場のメインゲート前では、15日も建設に反対する住民らの抗議の座り込みが続きました。
午前6時、機動隊員約60人が県道に広がり住民ら十数人の抗議行動を抑え込み、沖縄防衛局が工事用資材を搬入しました。プレハブの資材や容器、タンクなどを積んだ大型トラックや工事関係車両など約50台が基地内に入りました。資材搬入碍1111日から5日連続と
なります。
住民らは、「高江の森を守ろう」「ウチナーンチュ(沖縄県民)は負けない」と声を上げ続けました。
ゲート前の県道わきには機動隊が車両を止め、抗議行動を妨害するように柵が設置されています。週明けにも全国から機動隊が大量投入される予定で、住民らは警戒を強めています。
同村高江に住む清水亜生さん(36)は、ヘリパッドを使用する垂直離着陸機オスプレイの騒音と低周波がひどく、睡眠障害で体調を
崩し、ずっと風邪気味だといいます。5ヵ月の息子も運日の飛行で眠れず、泣いて嫌がっています。
「昨日も夜9時から1時間、飛び続けていました。落ちてくるのではないかと恐怖を感じ、ストレスになっています」と清水さん。「自然豊かで子どもの成長にもいい環境なのに、このままでは人の住めないところになってしまう。沖縄に住んでいる人の人権を考えてくれないのか]と声を絞り出すように訴えました。
現場に来て見てほしい
日本共産党東村議伊佐真次(まさつぐ)さん
機動隊を大量動員するのは今回が初めてで、何がなんでもヘリパッドを造ろうという圧力を感じます。山奥の見えにくいところでやりたい放題。県民の民意は無いに等しいのでしょうか。
米軍機の騒音がひどく、事故の危険も常につきまとっています。沖縄を犠牲にしてでもアメリカに顔を立てるためにこんなに異常なことをやるのが安倍政権だということを全国の人にも知ってほしい。これを許せば全国でもこうした無理強いをしてくるでしょう。
資材搬入がどんどん行われています。非暴力の抗議行動を続けるには多くの人数が必要です。是非、無理のない範囲で高江に支援に来ていただき、現場を見てほしいと願っています。
解説
住民を標的どこが「軽減」
沖縄県内最大の演習場である米軍北部訓練場(国頭村・東村、約78平方㌔㍍)の高江集落周辺で、同演習場の約40平方㌔㍍返還の条件として計6ヵ所のヘリパッド(すでに2ヵ所完成)建設が狙われています。
安倍政権が高江で強行姿勢を強めているのは、辺野古新基地建設が進まない下で北部訓練場「過半」の返還が実現すれば、全国の米軍専用基地面積の74%が沖縄県に集中するという現状が数字上は改善し、「負担軽減」をアピールできるからです。
また、辺野古の工事と同時並行で進めることで、抗議行動の分断を図る狙いもあるとみられます。
しかし、「負担軽減」どころか、日常的に住民を標的にした訓練が横行しているのが実態です。海兵隊員が民家に向かって銃を構えている姿もしぱしば目撃されています。
1996年のSACO(日米特別行動委員会)合意以来の日米両政府の狙いも、「負担軽減」ではなく、基地の再編・強化が主眼でした。北部訓練場は98年には正式名を「ジャングル戦闘訓練センター」(JWTC)に改称され、対ゲリラ訓練やヘリの超低空飛行、兵士のつり下げ飛行などあらゆる戦闘訓練の拠点となっています。
さらに、防衛省の2012年の内部文書からは、自衛隊との共同使用が検討されていることも判明しています。横田基地(東京都)へのCV22配備や辺野古新基地とも連動し、今後は国内オスプレイの一大訓練拠点になる可能性もあります。
小中学生騒音゛気になった”77% 東村でアンケート
琉球大工学部渡嘉敷准教授調査
東村ではヘリパッド2ヵ所が米軍に先行提供されてから「音環境」が急速に悪化しています。琉球大学工学部の渡嘉敷健准教授は今年4月、同村内の小学校4~6年生と中学校1~3年生を対象にアンケートを行い、その結果について14日、東村役場で報告会を行いました。アンケートは94人から回答を得、回収率は93%。
「学校で遊んでいるときや授業を受けているときに飛行機やヘリコプターの音が気になったことがありますか」の問いに、「よくある」39%、「ある」38%、「あまりない」19%、「ない」は4%でした。
「オスプレイの音を聞いて怖いと思ったり、嫌な気持ちになったことがありますか」の問いには、「よくある」6%、「ある」34%、「あまりない」24%、「ない」36%。
自由記述では、「いつも飛んでいるときに落ちてきそうで怖い」「うるさくで寝られない、家の上は飛ばないでほしい」「夜10時頃よく空を飛んでいるのでうるさい」「うるさくて授業に集中できないことがある」などと訴えています。
渡嘉敷氏はアンケート結果について「夜間遅くまで訓練を行っていることで、児童生徒の睡眠が脅かされていることを、調査の自由記述から知ることができた。学校周辺の音環境はとても悪化していると考えられる」と分析しています。
陸上自衛隊の特殊任務部隊が米海兵隊の戦術を観察・ジャングル戦闘訓練センター(沖縄・北部訓練場)の共同利用を検討
https://youtu.be/Xy8RnQz9umA
琉球諸島の将来に関する日本の天皇の見解
テレメンタリー2012標的の村
国に訴えられた東村・高江の住民たち
https://youtu.be/raJ8vTr8r4c
事故が多発しているアメリカ軍機「オスプレイ」の着陸帯が自宅のすぐ近くに建設されると聞き、やめてくれと声を上げた沖縄県東村・高江の住民たち。6人の子供を抱える安次嶺現達さんは「住民の会」を作って座りこんだところ、国に「通行妨害」で訴えられてしまった。
国が、国策に反対する住民を訴えるという前代未聞の裁判。
反対意見を封じ込めることを目的に権力のある側が個人を訴えることをアメリカではSLAPP裁判とよび、多くの州で禁じている。しかし日本にその概念はなく、被告にされた高江の住民らは3年半に及ぶ裁判の間、資金も時間も奪われ身体的・精神的な苦痛を強いられた。沖縄の住民運動が最後の抵抗手段にしてきた「座りこみ」。それを「通行妨害」に矮小化して住民を裁判にかける手法が成立するなら、国に都合が悪い沖縄の声はますます封殺されてしまう。
人口160人の高江集落はアメリカ軍のジャングル訓練場に囲まれている。頭上では日常的にヘリが旋回し、住民らは「まるで自分たちがターゲットだ」と憤慨する。
それは消して大げさではなかった。実際にアメリカ軍は、高江区民を標的に訓練をした知られざる歴史があった。ベトナム戦当時、沖縄の山岳地帯に襲撃訓練用の村が作られていた。その「ベトナム村」に近くに住む高江の住民たちが連行され、ベトナム人役をやらせられていた。
現在建設予定の6カ所のヘリパッドも、ちょうど集落を取り囲む配置になっており、そこにオスプレイが来ることも明らかになった。住民らは、高江をさらに標的にするような基地建設は許せないと、(※2012年)10月のオスプレイ配備に向け、正念場の座りこみを続けている…。
米軍「対ゲリラ戦」訓練で県民を徴用
新川区民を狩り出す
(人民)1964年9月9日
激化する演習で荒らされる山村
敗北につぐ敗北をかさね、もはや南ベトナムから追い出されるのは時間の問題となっているアメリカ帝国主義は、その侵略拠点となっている沖縄で必死になって戦争拡大の演習を強化しているが、日本国民である県民をかれらの対ゲリラ訓練にかり出すという重大行為に出ている。これはアメリカの19ケ年にあたる占領支配の中でもかってなかったことであり、県民を直接侵略戦争の「協力者」に仕立てるもので、重大な問題であるとして県民各階層の間に激しい怒りの声がわきおこっている。
米第3海兵師団は、8月26日東村高江-新川の対ゲリラ戦訓練場で、ワトソン高等弁務官、在沖第3海兵師団長コリンズ中将の観戦のもとに、「模擬ゲリラ戦」を展開した。この訓練には乳幼児や5,6歳の幼児をつれた婦人を含む約20人の新川区民が徴用され、対ゲリラ戦における南ベトナム現地部落民の役目を演じさせられた。作戦は米海兵隊1個中隊が森林や草むらに仕掛けられた針や釘のワナ、落とし穴をぬって「ベトコン」のひそむ部落に攻め入り、掃討するという想定のもとに行われた。
その日、米軍は新川区からつれてきた人々を、南ベトナム現地民の住む家として作った茅葺き小屋におしこめ、その中に仮想ベトコン2人を潜伏させた。また、彼らは南ベトナムに似た状況を作り出すためにあらかじめ部落から山羊を借りていき、小屋の周囲にこれを放った。「対ゲリラ戦」は50人の海兵隊員が彼らを悩ましている「ベトコン」2人を捉え、筋書どおりの「成功」をおさめて終わった。
以上が実戦さながらの情況のもとで行われた「対ゲリラ戦」の模様である。さて、それでは問題化している新川区民の訓練への駆り出しはどのようないきさつをだどって行われたのであろうか。
中略
「ねえさん出せ」と放火
新川区民をはじめ山に依存して生計を立てている東村の人々は、山林の中に雨露をしのぐための小屋をつくっている。「対ゲリラ訓練場」の司令官(少佐)は自らヘリコプターを操縦、小屋をめがけて焼夷弾を投下し焼き払った。これは南ベトナムにおけるナパーム弾、焼夷弾投下を地でいく訓練である。焼夷弾はさいわい、部落民が入っていた小屋に命中せず、側にそれたので、中にいた人々は九死に一生を得たと話している。
山の中には夜となく昼となく、米兵が潜伏しているため、婦人たちは一人ではもちろん、少人数で山に出かけることはできない。婦人たちは必ず、7、8名、10名ずつ組を組んで薪とりに行く。昨年9月頃、10名組の婦人たちが山に着いたとたん、偵察飛行中の米機がこれを発見し、まもなく訓練場から米兵たちがやってきて逮捕した。米軍では「訓練場に拾い物をしに入ったから捕えるのだ」といっていたが、これは明らかに口実であった。いうまでもなく彼女たちが捕えられたところは米軍のいう立入禁止区域ではなく、普通の国有林だった。このように米軍は高江の住民を本当のゲリラとみなして、これを対象に対ゲリラ戦訓練を行っているのである。
それだけではない。彼らは婦女子を恥ずかしめようとしたり、区民の家を焼き払ったり、農作物を盗んで食べるなど幾多の悪事を働いている。さらに6月の下旬、高江-小浜の上に火事がおこり、江洲義仁さん所有の三間四方の空家が全焼した。
この日午後8時頃江洲さんの家屋に隣り合わせの石原昌亀さん(62)のところに米兵3人があらわれ、「ねえさんを出せ」とせまった。石原さんが「ねえさんはいない」と答えると、「ノー、ねえさんある。ウソ!」といって、家の後ろにまわり、火を放ったのである。かれらは放火しても逃げはせず、近くの空家の床下に隠れていた。
小浜の上の部落には戦後、約9軒の家があったが、交通の不便、物騒であることなどの事情により、次々と引き上げ、事件のあった頃には石原さんと高里盛保さん(32)の家がわずかに2軒残っていただけだった。米兵は高里さんの妻カズ子さんを狙って襲ってきたのである。さいわい、30分後には新川区民が救援にかけつけたため、類焼を防ぎ、その他の被害も食い止めたわけである。
この事件でこの部落にはこれ以上住めないというので石原さん夫婦はコザ方面に出稼ぎに出ている子どものところへ、高里さんは新川にいる親戚の家に間借りし、それぞれ引き上げていった。いまや小浜の上部落は人間が一人もいない部落となり、かっては部落民が住んでいた家がそのまま残されその荒廃した姿がアメリカ帝国主義に踏みにじられた沖縄の姿を象徴しているかのようである。
自衛手段とる区民
米軍はまた、パインを盗んで食べたり、狭い道路から車を猛スピードで運行、村の電柱をへし折ったり、県民の車に衝突し、大きな被害を与えるなど、全く戦場と同じ行為をやっている。もちろん、県民に与えた損害に対しほとんど賠償を行っていない。ではこのように言語に絶する蛮行を働いている米軍にたいし新川区民はどう抵抗し、たたかっているのであろうか。
今から約10年前、米第3海兵師団対ゲリラ訓練部隊がきた直後のことである。ある日の晩11時頃、米兵が新川区のある婦人をはずかしめようとした。これに怒った区民は子どもから年寄にいたるまで全員部隊に押し掛けた。区民は婦人をはずかしめようとした犯人の米兵を引き出すよう要求し隊長にたいし謝罪と今後このようなことをしないという保証を求めたが、部隊長は当初区民の要求を一切拒否してとりあわなかった。そこで県民は部隊の前に薪を運び、これをともし、「もし米軍が犯人の米兵を捕え、このようなことは再びやらないという約束をしなければ、われわれは薪をたき、いつまでもがんばる」と宣言、そのとおり実行した。
ついに一昼夜が過ぎ、翌午前11時頃、部隊長が区民の前にあらわれ、「全将兵を整列させ、首実験をすれば誰が犯人であるか、君たちは指摘できるか」と聞いた。区民はいささかのためらいもせず全隊員を整列させるよう要求した。 米兵は整列した。いよいよ首実験だ。何百人という米兵の中から区民は3人の米兵を見つけだし、部隊長につきつけた。米兵は全区民の前で犯行を認めたのであれほど強気だった部隊長も認めないわけにはいかなかった。
結局、部隊長は「今後自分の部下にこのようなことはさせない」と約束させられたたかいは区民の完全な勝利となった。だが米軍は犯人の米兵を罰せず、事件がすんで間もなくすると、彼は再び部隊に姿をあらわしていた。
新川区民はたたかいのなかから自分たちの生命と権利を守る手段を学んだ。すなわち、米兵の悪あがきに反対して団結することを---。それ以来、新川区では米兵が区民に危害を加える場合青年会長の非常招集でまず青年会員が集合、さらに全区民を動員して対処するという自衛手段をとっている。いま、15人の青年会員は何時でも非常事態に応じられるように、その態勢を固めている。
しかしこのように勇敢なたたかいの経験をもつ新川区民の自衛手段にも限度がありいまこそ全県民がベトナム侵略反対闘争の一環として対ゲリラ訓練に抗議するたたかいをくまなければならないときである。
東京・米軍横田基地変貌
より攻撃型へ
自衛隊との「調整所」で密接に
(しんぶん赤旗)とくほう・特報 2016年2月22日
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2016-02-22/2016022203_01_0.html
在日米軍司令部が置かれ、首都東京に居座る横田基地がいま変貌を遂げようとしています。日米新ガイドライン(軍事協力の指針)や戦争法を実行する米軍・自衛隊の「調整所」が設置されるとともに、特殊作戦機CV22オスプレイの常駐化などで、より“攻撃型”の戦争拠点に変わろうとしています。周辺住民は「戦争の拠点、横田基地はいらない」と声をあげ続けています。
(山沢猛)
訓練拡大で住民被害増加
「ブオーーン、ブオーーン…」
爆音が頭上から覆いかぶさるように襲い、重い低音が腹に響きます。米軍横田基地所属のC130輸送機の「夜間訓練」は底冷えのするこの日、午後6時15分から始まり、9時までくりかえされました。翼を傾けて、あきる野市の上空をぐるぐる旋回する姿も。
基地から2㌔㍍の同市二宮に住む前田眞敬さん(71)は「低空の時はもっと騒音がひどい。隣のお年寄りは『低空で迫ってくるようで怖い』といっています。わが物顔のやりかたで、市役所にたいし(当局に)抗議するよう申し入れました」と怒ります。
あきる野市は、爆音被害が最も激しい横田基地滑走路(全長3353㍍)の延長線上一帯から外れています。そのため訓練拡大の被害をうけながら、なんの補償もありません。
C130輸送機の夜間、低空、旋回訓練が激しくなったのは、航空自衛隊横田基地が新設された2012年からです。
さらに外来機が激増しています。1月20~26日に、レーダーに捕捉されにくいステルス戦闘機F22が14機、F16戦闘機6機が飛来したことが、周辺住民を驚かせました。この飛来は防衛省も事前の通告を受けていませんでした。
「横田基地の撤去を求める西多摩の会」の高橋美枝子代表は「ベトナム戦争が終わった後は横田基地は兵たん・輸送基地です。これだけの戦闘機が一度に来たことはありません。横田をより攻撃的な拠点に変えたいという日米両政府の狙いがはっきり見えています」と話します。
オスプレイも特殊部隊も
昨年、米政府が特殊作戦機CV22オスプレイを2017年後半まで3機、21年まで7機、計10機配備し、要員430人を横田基地に常駐させると発表。兵士・乗組員41人の死者を出している危険なオスプレイの配備に、住民は「オスプレイは来るな」という声を高くあげました。
「特殊作戦部隊の訓練の先取り」と住民が警戒するのが、パラシュート降下訓練。2012年1月に、アラスカの部隊の訓練に始まり、その後、沖縄の特殊作戦部隊などが横田で実施。降下人数は15年までの4年間でおよそ2000人にのぼります。
在日米軍研究者の軍事リポーター石川巌さんは「横田に来るCV22の親部隊は、昔から嘉手納基地にある空軍の第353特殊作戦航空群。ここに特殊作戦機MC130コンバットタロン(たたかう猛鳥の爪)など十数機がいる。任務は敵勢力の背後に夜間に潜入し兵士を投入、回収することで、『こうもりネコ』軍団の異名を持つ。CV22はMC130の弟分だ」といいます。
CV22オスプレイは、沖縄に24機いる海兵隊のMV22と機体は同じですが、専門機器をつけています。
石川さんは東富士演習場(静岡県御殿場市)で、オスプレイ訓練通報に反して直前に中止という〝ドタキャン〟が9回も繰り返されたことを体験(2014年9月から翌年6月)。「そのとき富士山麓が雪や悪天候だったのを、自分の目と肌で確かめた」そうです。
その後調べ直した英語文献で「オスプレイは結氷が予想されている地域での飛行は、現在、禁止されている。氷結防止装置が故障しやすく、天候レーダーを持っていないからだ」(2009年米会計検査院リポート)との一節を見つけて「あっ」と声をあげたといいます。その後も、高地や砂漠に弱い、エンジン故障が起きやすいなど〝特異体質〟ぶりがいろいろわかったといいます。
この冬も10月18日以降、冬季の本州には姿を見せない一方、温暖地の長崎県佐世保には12月と1月で4回、のべ6機が飛んできています。
隣接するF35整備拠点化
2014年12月、米政府は、今後主力となるステルス戦闘機F35Aのアジア・太平洋での地域整備拠点(リージョナル・デポ)を、オーストラリアと日本におくと発表。その後、機体の整備は三菱重工業(愛知県の小牧南工場)、エンジンは横田隣接のIHI瑞穂工場(旧石川島播磨重工業)にすると発表しました。
IHIではエンジン組み立てと試運転設備のため地上5階建ての新工場建設中(3月末完成予定)で、専用ゲートもつくられます。
防衛省はF35Aを42機取得予定で、米国の同盟国も導入をすすめており、世界では3000機を超えると試算されています。
昨年9月、日本共産党が暴露した自衛隊内部文書で、自衛隊トップの河野克俊統合幕僚長が14年12月訪米時「今回F35のリージョナルデポが日本に決まり…、本件は相互運用性向上のために重要な決定であると認識している。オスプレイのリージョナルデポも置いていただければ」と話していました。
「横田基地の撤去を求める西多摩の会」の寉田一忠事務局長は「整備工場が稼働すれば、アジア・太平洋各地からF35戦闘機が頻繁に飛来することは間違いないだろう」と懸念を表明します。
戦争に組み込む日米同盟
「横田基地は、日本にたいする政治的支配の拠点でもあり、在日大使館・太平洋軍司令部(ハワイ)・在日米軍司令部・自衛隊統合幕僚監部と密接な関係が築かれている」。こう指摘するのは、日本平和委員会代表理事の内藤功弁護士です。
2005年10月、日米安全保障協議委員会(日米2プラス2)が決めた米軍再編計画にもとづき、航空自衛隊横田基地が新設されました(12年)。米軍と自衛隊との「共同統合運用調整所」設置がされ、「平時」から「戦時」まで切れ目なく、米軍と自衛隊が情報を共有し連携する仕組みがつくられました。
在日米軍司令部と中庭をはさんで置かれた自衛隊航空総隊司令部の庁舎地下には「調整所」が置かれ、米軍・自衛隊の要員が対面で任務についています。
「西多摩の会」の高橋代表は「日米同盟の深化が安倍政権によって加速され、それが横田基地にも表れています。2000万署名はじめ戦争法廃止のたたかいを強めるとともに、日本を戦争に組み込む日米同盟そのものの危険性を告発していきたい。住民一人ひとりの平和な世界で生きたいという願いを大切にしていきたい」と話します。
横田に空軍用 海軍も検討
千葉・木更津で日米の「整備」拠点工事開始
オスプレイの”巣”に
(しんぶん赤旗)とくほう・特報 2016年3月16日
垂直離着陸機・オスプレイの「定期機体整備」拠点の工事が、東京湾に面した陸上自衛隊木更津駐屯地内(千葉県木更津市)で始まっています。昨年5月のハワイでの墜落・死亡事故など兵士・乗務員41人の死亡者を出している危険なオスプレイの整備場化に、周辺自治体の住民は「オスプレイはくるな」の声をあげています。
(山沢猛)
木更津市の渡辺芳邦市長は2日の市議会で、整備・配備中止を求めた日本共産党・佐藤多美男議員の質問に、「現在、工事の準備作業をすすめていると聞いている」と答えました。市内外の2社が防衛省と契約し、駐屯地内の「K格納庫」にスプリンクラーなど消火設備、塗装区画の設置や機械・電気工事の準備作業をしています。工事は12月28日までの予定。経費は日本の負担です。
さらに滑走路近くに耐熱型のホバリング(空中停止)エリアを新設します。
来年から米軍機
整備場が完成すると、沖縄の米海兵隊普天間基地のMV22オスプレイ24機が順次、木更津に来て、1機当たり3~4カ月かけて分解整備を行う、対象は「年間5~10機」です(防衛装備庁)。年間10機なら常時3、4機が木更津に居座ることになります。
米軍の入札で富士重工業が昨年10月定期整備を受注。オスプレイ4機を収容できるK格納庫で分解し故障部品があれば交換・修理したり、排水・廃液をだす塗装も行います。富士重工の前身は戦前の軍需産業・中島飛行機で、戦後、財閥解体の対象になりました。
日米一体を美化
政府はこの整備拠点をどう位置づけているのか―。
安倍首相は1月22日の所信表明演説の日米同盟強化の項で、「沖縄の基地負担軽減」の一つとして「オスプレイの定期整備は千葉・木更津駐屯地で行う」と表明しました。危険な低空飛行を繰り返す24機ものオスプレイを沖縄に押し付けておきながら負担軽減はありえず、米軍機の定期整備拠点を首都圏に固定化することを〝改善〟のように言うのは、主権と国民の安全を無視した態度です。
昨年9月、日本共産党が暴露した自衛隊内部文書では、自衛隊制服組トップの河野克俊統合幕僚長が2014年の訪米時に、米軍最高幹部と会談。そのなかで、安倍内閣で軍事予算が増加傾向にあるため、次期戦闘機F35、無人機グローバルホーク、オスプレイなどの自衛隊導入が決まったと報告するとともに、F35だけでなく「オスプレイのリージョナルデポ(=定期整備拠点)についても日本に置いていただけるとさらなる運用性の向上になる」と要請しました。これが昨年の米軍による木更津整備拠点化の表明につながった可能性は大です。
日本政府が佐賀空港配置を狙い18年度末から導入を開始するV22オスプレイの整備も、米軍と同じ場所でできることを「運用性の向上」といっているのです。
制服組トップが米軍と同じ兵器をそろえ、その定期整備拠点を首都圏にもってくることをお願いするという異常で危険な米国追随の姿が表れています。
住民説明会なく
木更津がオスプレイの整備拠点になれば、来年から沖縄の米軍オスプレイが年間通じて飛来し、整備が終われば周囲で「試験飛行」を繰り返すことになります。しかし、防衛省は市当局に「安全」と説明しますが、住民への説明会は一度も開いていません。
「きわめて不当。おそらく防衛省も自信がないからでしょう」と話すのは、「オスプレイ来るな いらない住民の会」(吉田勇悟会長)事務担当・野中晃さん。「その証拠に、たとえば飛行ルートの説明では、自衛隊と同じく市街地でなく海側上空の経路(場周経路)の使用を『考えている』とか、米軍には周辺に配慮した時間での離発着を『要請する』とか、試験飛行も自衛隊と同じ地域でやるよう『要請する』とか、日本側が考えたり要請しているだけです。そうなる保障を米軍から何もとれていないのではないか」と指摘します。
首都圏はどう変わるのか―。米軍横田基地(東京都)では空軍特殊作戦機CV22オスプレイ部隊の17~21年配備(計10機)が狙われています。
米海軍は空母に搭載できるHV22オスプレイの導入を決めており、横須賀や厚木基地(神奈川県)も配備の対象になりえます。米軍や安倍政権の思惑を許せば、首都圏がオスプレイ(猛鳥ミサゴのこと)の〝巣〟にされる危険が高まります。
これはイカン!( ゚Д゚)
新聞と娯楽雑誌ぐらいの違いがある見出し。きょう7月23日の一面トップ。ポケモンに浮かれている時、沖縄では国家権力が牙をむき出しにしていた。何を取り上げるかでこうも違う。東京と朝日で、見事に日本の光と影を映しだした。 pic.twitter.com/KpR9gnArrs
— 高瀬毅 (@seitakajin) 2016年7月23日


20160722-報ステ・高江報道
http://dai.ly/x4ld4xn
【沖縄・高江】女性の首を締める機動隊
https://youtu.be/_GBrJqYhcmk

警察車両に はねられ 倒れた男性。はねた警察官は救けに降りてこようともしなかった。=21日午後6時49分頃、撮影:田中龍作=
RBC THE NEWS「東村高江ヘリパッド工事再開」2016/07/22
https://youtu.be/rxQq3u_DN2Y




横田の空兵 地元の中学校でミニ・ブートキャンプを指導
Yokota Airmen provide a mini boot camp to middle school students

http://www.yokota.af.mil/News/ArticleDisplay/tabid/2053/Article/837341/yokota-airmen-provide-a-mini-boot-camp-to-middle-school-students.aspx(リンク切れ)
July 14, 2016
Original text by Yasuo Osakabe
374th Airlift Wing Public Affairs
「右向け右!・・・左向け左!」アメリカの軍人たちが戸惑う日本の生徒たちに動作の指示を出す号令が校庭に響いた。
だが、これは軍の学校とは違う。7月2日、地元の武蔵村山市立第5中学校の生徒たちが、同校の第13回5中フェスティバルの一環として横田基地第374医療群のメンバーが指導するミニ・ブートキャンプ「障害物競走コース」に参加した。
第374医療支援中隊カスタマーサービス下士官指導責任者ゲアボン・ハミルトン軍曹は「我々と地元の生徒たちが交流ができる他に類のない方法だと思う。我々としても日本の中学校を訪問し、生徒たちと交流できたことは有意義な経験だった」と振り返る。
同コースでは、中学3年生の各クラスの生徒たちに整列の動作、マーチング、障害物コースの進み方等を教えた。

「学ぶのに通常一週間掛かるものを、このキャンプでは教える時間が20分に限られた。それに生徒たちは英語を学んでいるものの、言葉の壁もあった。そういうことがあっても、生徒たちはうまく指示を理解し、綺麗に整列してマーチもできた」とドリルコースを指導したハミルトンは言った。
軍のしきたりや伝統を体験するのに加えて、当プログラムは生徒たちに直に生の英語に触れる機会も与えた。
参加した武蔵村山市立第5中学校の生徒の一人ヤマグチ・ヒナさんは、自分もクラスメイトも自分達の英語力が心配だったが、体験を通じて段々と馴染み、指示が分かるようになったと話していた。
「何よりもこれは日本の生徒たちと空兵にとって人生の宝となる経験。我々がこの日本にいることで新しい体験をさせてあげられることの一つ。将来、これらの生徒たちが中学時代の経験を思い起こす時、このコースで楽しんだことを思い出して欲しい」とハミルトンは述べた。
2時間に渡るブートキャンプを通じて、生徒達はアメリカ空軍の一部を垣間見、知る機会を得た。



「弾圧許さない」 怒りの抗議
ヘリパッド工事再開 沖縄の海も森も渡さない
機動隊員が住民排除 高江県道封鎖、生活権はぎ取る
(しんぶん赤旗)2016年7月23日
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-07-23/2016072303_01_1.html
防衛省沖縄防衛局は22日、同県東村高江の米軍北部訓練場のヘリパッド(着陸帯)建設工事を再開しました。「生活が壊される」と反対する住民らの抗議行動を力ずくで抑え込んでの強行に、現場に駆け付けた県民からは「弾圧は許さない」と怒りの声が響きました。
(柳沢哲哉)

前日深夜から早朝にかけて住民ら約200人がN1ゲート前に座り込む中、全国から大量動員された機動隊が県道を封鎖。午前5時すぎに強制排除を開始しました。
「人が住んでいるんだぞ」「この森の動植物を殺さないで」と訴える住民一人一人を、機動隊員7、8人が取り囲んで腕と足をつかみ、引っ張り上げます。問答無用で手をねじり上げることもしました。住民らを強制排除した後、ゲート前に近づけないように囲い込んで動けなくし、トイレにも行かせません。「人権侵害だ」と抗議の声が上がりました。
県警がゲート前に住民らが止めていた車をレッカー車で移動させました。前日夕に突然、名護警察署長がゲート前を駐車禁止規制して、それを根拠にした撤去です。住民らは「泥棒するな」と抗議し、怒号が飛びかいました。
暴力的な機動隊の対応に、3人が体調を崩し救急搬送される事態となりました。
午後0時20分ごろ、民間警備員約60人がN1ゲート前に配備され、工事用フェンスを設置しました。住民らが座り込んでいたテントを強制撤去し、草刈りなどで整地したあと、ゲートから重機を次々に搬入。プレハブなどを建てました。
同村に住む宮城勝己さん(63)は「県道を封鎖することは住民の生活権はく奪だ。こんなことをして本当に民主国家、法治国家なのか」と憤りました。
「ヘリパッドいらない住民の会」の伊佐育子さん(55)は「暴力を使って押し込めて、法律も何もない。信じられない。生活があるのにそれも自由にできない。人権があるのか。このまま絶対に犠牲にならない。これまで9年間たたかってきた。最後まで頑張りたい」と話しました。
菅長官は工事を正当化するが
「軽減」どころか負担増
菅義偉官房長官は22日の記者会見で、沖縄県東村高江でのヘリパッド(着陸帯)建設強行について。「(ヘリパッド建設で)北部訓練場の過半返還が実現すれば沖縄の米軍基地の面積約2割が減少する。基地負担軽減にも大きく資する」と正当化しました。
実態は「負担軽減」どころか、大幅な負担増です。北部訓練場「過半」返還の条件になっている6ヵ所のヘリパッドは、住民約160人が暮らす高江集落の至近距離にあります。昨年、先行して提供されたN4地区の2ヵ所のヘリパッドには連日のように垂直離着陸機MV22オスプレイやCH53ヘリなど大型の海兵隊機が飛来。集落上空を昼夜分かたず飛行し、深刻な騒音や低周波による健康被害をもたらしています。
国の天然記念物ノグチゲラなど多くの固有種が息づき、生命の宝庫といわれる”やんばるの森”を切り開き、貴重な生態系を破壊することになります。
また、比較的道路から近いN4地区の2ヵ所のヘリパッドも完成まで長い年月を要しました。新たに着工されるN1地区は道路もなく、密林の奥深くにあります。難工事になることは確実です。それまでは、北部訓練場も返還されず、住民はオスプレイの騒音や低周波に苦しめられることになるのです。
安倍政権には、辺野古の新基地建設に加え、1996年のSACO(沖縄に関する日米特別行動委員会)最終報告で合意されたヘリパッド建設も住民の抵抗で進まず、対米公約を果たせないという焦りが垣間見えます。辺野古に加え、高江でも強硬姿勢を見せたことで、沖縄全体で住民の基地に対する反感は高まり、日米同盟の基盤を弱めていることを、安倍政権は気づいていないのでしょうか。
(竹下岳)
参院選翌日沖縄ヘリパッド工事再始動
基地反対民意示しても
(東京新聞【こちら特報部】)2016年7月20日
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2016072002000132.html
参院選直後、沖縄県東村高江周辺の米軍ヘリパッド建設計画がにわかに動きだした。住民らの反対運動で中断されていた工事の準備が再開され、警視庁など全国から機動隊員も続々集結。先の参院選沖縄選挙区では、自民の現職大臣が落選している。「基地反対」の民意を無視する国の強硬姿勢に、反発が強まっている。
(佐藤大、池田悌一)

基地反対民意示しても
連休明けの十九日午前六時。沖縄県東村と国頭村にまたがる米軍北部訓練場の「N1ゲート」前には、住民や支援者約百人が集まっていた。
集落に近く、米軍輸送機オスプレイに利用される懸念から、ヘリパッド建設予定地に近いこのゲート前では、住民たちが工事車両を通さぬよう車二台を置いて工事に反対している。その二台をガードするよう車数十台が一列に並んだ。車列前で、沖縄防衛局の職員十数人や機動隊員数人が無表情のまま住民らと対峙していた。
突き刺すような強い日差しに、機動隊員らも二時間ごとに交代。住民らはわずかな日陰を探しながら座り込みを続けていた。この日も約二㌔離れたメイングートから工事車両が資材を搬入、現場の緊張はますます高まっている。
ヘリパッド建設工事が急展開をみせたのは、参院選翌日の十一日朝だった。訓纏場のメイングート前に沖縄県警機動隊が配置され、沖縄防衛局がヘリパッド建設に向けた資機材を搬入し始めた。N1ゲート前でも機動隊員と住民が小競り合いになる一幕も。十七日には、もみ合いに巻き込まれた女性(五らが頭部などを打ち搬送された。
機動隊全国から大量投入
沖縄には全国から機動隊員も次々に投入されている。地元紙は「約四百~五百人」規模の派遣になると報じている。「こちら特報部」の取材に、沖縄県警広報室の担当者は「警備体制に関わることなので、応援人員などは一切広報していない」と話すが、N1ゲート前では十九日だけでも、品川や多摩、横浜、福岡のナンバーの機動隊車両が確認された。
北部訓練場周辺には十六日ごろから警視庁、神奈川、福岡、千葉、愛知などの警察車両が続々集結。練馬や足立ナンバーの機動隊車両が訓練場に入るのも確認されている。
参院選では、米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設反対を掲げた伊波洋一氏が、沖縄北方相で自民党現職だった島尻安伊子氏に十万六千票の大差をつけて当選したばかり。翁長雄志知事も十一日夜に緊急会見し、資機材の搬入を批判した。米軍輸送機オスプレイを運用する計画があることから、工事に否定的な見解を示している。
だが、菅義偉官房長官は十九日の記者会見で「必要な準備が整い次第、工事に取りかかりたい」と早期に着手する考えをあらためて強調。「沖縄県も協力してほしい」と繰り返した。

国策強行住民排除再び
民意をないがしろにした動きに住民らの怒りは深い。
反対運動をして国に訴えられた安次嶺現達さん(五七)は「沖縄県民の声を一切無視してる。安倍首相は沖縄の方々に丁寧に説明する、と言っているが、やっていることがこれだ。住民が百六十人しかいない高江に大量の機動隊を投入しようとしている」と憤る。
既に完成している二つのヘリパッドを使ってオスプレイが夜間も飛び回り、騒音のために眠れなくなった子どもたちは、避難生活を余儀なくされている。「安倍政権は沖縄を日本とは見ていない。同じ国民だと思っていたらこんなことできませんよ」と嘆く。
同様に国から訴えられた伊佐真次・東村議の妻育子さん(五五)は、警戒のために支援者らとともにN1ゲート前に寝泊まりする生活が続いている。「何も手につかないが、戦争を生き延びてきた方たちのことを思えば、何ともない。何かあっても立ち向かうしかない」
「やんぱるの森」の危機に、全国から支援者も駆け付けている。名古屋市の小学校非常勤講師丸山悦子さん(六六)は「名古屋にもかつて米軍の住宅施設があった。沖縄にだけ基地の負担を強いるのは申し訳ないという気持ちがある。知らないふりはできない」と、炎暑の座り込みを続けた。就職活動中に駆け付けた東京
都八王子市の宮南洋さん(二五)は「知り合いに話を聞いてやってきたが、東京の政治が沖縄をいじめている、ということがよく分かった」と走り回った。
沖縄県在住の芥川賞作家目取真俊さん(五五)の姿も。辺野古移設に対する抗議活動中に逮捕された経験を持つ目取真さんは、政府のやり方に「沖縄の民意や選挙結果を最初から無視するという宣言。辺野古移設が進まないんだったら高江から進めて、米軍に基地を提供しましょう、ということ。強権むきだしだ」と批判。
「沖縄県民の気持ちは怒りから憎しみに変わる段階に来ている。沖縄とヤマト側のギャップがどんどん拡大している」と危機感をあらわにする。
「大きな動き必ず選挙後に」
選挙前は基地建設を控え、選挙翌日に強硬姿勢に転じる政府の姿勢には「前例」がある。
政府は三年前の参院選翌日、二〇一三年七月二十二日にも、住民の抗議活動阻止に動いていた。
このときは住民らが米軍普天間飛行場(宜野湾市)のゲート前でオスプレイ追加配備に反対していたところ、沖縄防衛局職員が高さ二㍍の鉄柵を二十㍍以上にわたり設置。住民らを排除した。
当時はオスプレイ配備について「県民の民意はノーだ」と訴えていた野党候補が、自民新人を破って三選を果たしたばかり。
十九日も高江のゲート前で声をからしていた沖縄平和運動センターの山城博治議長も「大きな動きは必ず選挙が終わった後に起きてきた」と指摘。反対派住民たちは、二十日にも機動隊が大量投入され、本格的に工事が着手されかねないと警戒を強めている。「沖縄は絶対屈しないと、この場所から示したい。基地をつくらせない闘いであり、民主主義を発信する闘いでもある」と力を込めた。
政府が今回も三年前も選挙直後、抗議の声を封じ込める強硬策に打って出たのは偶然なのか。
高良鉄美・琉球大法科大学院教授(憲法)は「沖縄では米軍基地に反対する声が高まっている。今回沖縄選挙区では現職大臣の当落がかかっており、与党は票が目減りするのを避けようと考え、投開票後に動いたのだろう」と推測する。
「参院選は今回も三年前も、全国で見れば与党が大勝した。沖縄の民意は全国の選挙結果とは異なるのに、安倍政権は『国民から信任された』とぱかりに沖縄に圧力をかけてくる。民意を大切にするのが憲法の理念だ。政府が強大な権力で民意を押しつぶそうとするのは大きな問題だ」

アベノファシズムと「存在に値しない命」とは何か…誰の命にも等しく価値があるのだ!(`・ω・´)

オレたちが
この世から
滅べば
汚点が消えたと
笑うやつらが
いる
笑わせて
たまるか
生きてやれ
谺雄二
相模原19人殺害事件の容疑者の背景について。- 2016.07.26
https://youtu.be/Z0YhS8_-Fc4
障がい者大量殺害、相模原事件の容疑者はネトウヨ? 安倍首相、百田尚樹、橋下徹、Kギルバートらをフォロー
(リテラ)2016.07.26
http://lite-ra.com/2016/07/post-2447.html
相模原の障がい者施設で起きた大量殺人事件は、死者19人という戦後最悪の事態となった。しかも、容疑者は「障害者なんていなくなればいい」と供述していると伝えられており、その差別思想に基づいた残虐な行為には憤りを禁じ得ない。
ところが、このニュースに、ネトウヨたちがまたぞろ「犯人は在日」「在日によるテロ」などという根拠のないデマをわめきたてている。
「聖は在日韓国人が好む漢字だろ」「松という字は、キムを姓とする在日が好む姓だよ」「元職員だそうだな、在日雇ってたんだか」「いかにも在日っぽい風貌」「在日によるテロが毎日のように行われているのに、その元締めの民団総連をなぜ放っておくんだ?」
凶悪事件が起きるたびに繰り返されるこの差別的なデマの拡散、ヘイトスピーチはどうにかならないものか。
そもそも、今回の事件に関しては、「容疑者はネトウヨ」というほうがまだ事実に近いのではないか。
たとえば、容疑者がツイッターでフォローしていた有名人を見てみると、安倍晋三、百田尚樹、橋下徹、中山成彬、テキサス親父日本事務局、ケント・ギルバート、上念司、西村幸祐、つるの剛士、高須克弥、村西とおると、ネトウヨが好みそうな極右政治家、文化人がずらりと並んでいる。
また、その中身も、最近、右派発言が目立つ村西とおるの「米軍の沖縄駐留は平和に大きく貢献している、米軍がいればこその安心なのです」という発言をリツイートしたり、「在日恐い」「翁長知事にハゲ野郎って伝えて!!」といった、ネトウヨ的志向がかいま見えるツイートも散見される。
もちろん、ネトウヨ思想を持つものがすべて凶悪事件に走るわけではないし、この事件については、障がい者施設の職員の劣悪な労働環境という根深い構造的な問題もある。また、責任能力の問題というのも今後は焦点になるだろう。これらの問題については追って報道するつもりだ。
しかし、容疑者は一方で、衆院議長公邸に「私の目標は重複障害者の方が家庭内での生活および社会的活動が極めて困難な場合、保護者の同意を得て安楽死できる世界です」といった手紙を届け、「障害者なんていなくなればいい」と供述している。今回の犯行は、その弱者を社会から排除するという思想の延長線上に出てきたもので、“ヘイトクライム”的な側面があるのは明らかだろう。
そして、これはネットで在日韓国人や弱者に対して、「死ね」「日本から出て行け」などと叫んで排除しようとしている、ネトウヨ的なメンタリティと決して無関係ではないはずだ。
ネトウヨたちは、この凶悪事件に「在日の仕業」などと無根拠なデマを喚き立てる前に、自分たちの内部にひそむ排除思想のヤバさに気づくべきではないのか。
最悪の「ヘイトクライム」発生!相模原の知的障害者施設で19人殺害——容疑者は衆院議長公邸に「障害者は安楽死」求める手紙を持参した過去も
(IWJ) 2016.7.27
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/321304

障がい者抹殺思想は相模原事件の容疑者だけじゃない! 石原慎太郎も「安楽死」発言、ネットでは「障がい者不要論」が跋扈
(リテラ)2016.07.27
http://lite-ra.com/2016/07/post-2449.html
19人もの犠牲者を出し戦後最悪レベルの事態となった、相模原の障がい者施設での大量殺人事件。
植松聖容疑者は「障害者なんていなくなればいい」「障害者はすべてを不幸にする」「障害者には税金がかかる」などと、障がい者を排除するべきという主張を繰り返していたことがわかっている。
戦後最悪レベルのとんでもない凶悪な事件だけに、容疑者の異常性に注目が集まるが、残念ながら容疑者の“弱者を排除すべし”という主張は現在の日本社会において決して特殊なものではない。
たとえば、昨年11月に茨城県教育総合会議の席上で教育委員のひとりが「妊娠初期にもっと(障がいの有無が)わかるようにできないんでしょうか。4カ月以降になると堕ろせないですから」「(特別支援学級は)ものすごい人数の方が従事している。県としてもあれは大変な予算だろうと思った」「意識改革しないと。生まれてきてからでは本当に大変です」などと発言し、さらに橋本昌・茨城県知事までもが「産むかどうかを判断する機会を得られるのは悪いことではない」と擁護・同調するような発言をするという騒動があった。
教育行政にかかわる人物が公然と「金のかかる障がい児は産むべきではない」という見解を開陳するなどおぞましいが、それを容認してしまう空気がいまの日本社会にはある。
石原慎太郎は、都知事に就任したばかりの1999年9月に障がい者施設を訪れ、こんな発言をした。「ああいう人ってのは人格があるのかね」「絶対よくならない、自分がだれだか分からない、人間として生まれてきたけれどああいう障害で、ああいう状況になって……」「おそらく西洋人なんか切り捨てちゃうんじゃないかと思う」「ああいう問題って安楽死なんかにつながるんじゃないかという気がする」
ほとんど植松容疑者の言っていることと大差ない。舛添のセコい問題などより、こういった石原の差別発言のほうがよほど都知事としての資質を疑いたくなる。しかし、当時この発言を問題視する報道は多少あったものの、そこまで重大視されることはなく、その後、4期13年にわたって都民は石原を都知事に選び続けた。
「障がい者は生きていても意味がない」「障がい者は迷惑だ」「障がい者は税金がかかる」
これらは基本的にナチスの重度障害者を本当に抹殺していったナチスドイツの政策のベースになった優生学的思想と同じものだ。
ところが、恐ろしいことに、こうした差別的発想を、あたかもひとつの正論、合理性のある考えであるかのように容認してしまう、さらに言えば勇気ある正直な意見と喝采すら浴びせてしまう“排除の空気”が、明らかにいまの日本社会にはある。
実際ネット上では、植松容疑者の主張に対しては「やったことは悪いけど、言ってることはわかる」「一理ある」「普段同じこと思ってる」「筋は通ってる」などという意見は決して少なくない。
絶望的な気持ちにさせられる事態だが、こうした弱者排除の空気に重要な視点を与えてくれる小説がある。それは、山崎ナオコーラ氏の『ネンレイズム/開かれた食器棚』(河出書房新社)所収の「開かれた食器棚」だ。
山崎は『人のセ○×スを笑うな』(同)で文藝賞を受賞し、同作や『ニキの屈辱』(同)、『手』(文藝春秋)、『美しい距離』(文藝春秋)で4回にわたって芥川賞候補に挙がったことのある実力派作家だが、同作は、障がい者の子どもをもつ親の苦悩や出生前診断に踏み込んだ作品だ。
舞台は、〈関東地方最果て〉の場所で営業する小さなカフェ。幼なじみだった園子と鮎美というふたりの女性が38歳のときに開店し、すでに15年が経つ。その店で、鮎美の娘・菫が働くことになるのだが、菫は、染色体が一本多いという〈個性を持って〉いた。小説は母親・鮎美の目線で娘・菫を取り巻くさまざまなことが語られていく。
〈生まれてから生後六ヶ月までは、とにかく菫を生き続けさせることに必死だった。菫はおっぱいを吸う力が弱いらしく、鮎美は一日中、少しずつ何度も飲ませ続けた。家の中だけで過ごした。外出は怖かった。人目につくことを恐れた。友人にさえ娘を見せるのをためらった。今から思えばそれは、かわいそうに思われるのではないか、下に見られるのではないか、というくだらない恐怖だった。〉
〈他の子たちよりも菫は多めの税金を使ってもらいながら大きくなり、自分が死んだあとは他人にお世話になるだろうことを思うと、社会に対する申し訳なさでいっぱいになった。〉
そうやって社会から閉じこもっていく母子に、風を通したのは、友人の園子だった。園子は菫を〈ちっとも下に見なかった〉。そればかりか、一緒にカフェをやらないか、と鮎美にもちかけた。そして、「菫のことに集中しなくちゃ……」と鮎美が言いかけると、園子は3歳の菫にこう話しかけた。
「ねえ、菫ちゃんだって、カフェで働いてみたいよねえ? コーヒーっていう、大人専用のおいしい琥珀色の飲み物を提供するお店だよ。菫ちゃん、コーヒーカップを、取ってきてくれる?」
何かを取ってくることなんて娘にはできない。鮎美はそう決め付けていたが、そのとき、菫は食器棚に向かって歩き出し、棚のなかのカップを指さす。菫は、理解していたのだ。園子は言う。「ゆっくり、ゆっくりやればいいのよ。成功や達成を求めるより、過程で幸せにならなくっちゃ」。
社会は、障がいがあるという一点だけで「その人生は不幸だ」と思い込む。母親はそれを背負い込み、かつての鮎美のように身体を丸めてうつむき、子どもの可能性を小さく捉えることもある。だが、生まれてくる命、育つ命が幸せか不幸かは、社会が決めることなどではけっしてない。そして、社会が開かれていれば、その人の幸福の可能性はぐんと広がる。──そんなことを、この小説は教えてくれる。
しかし、今の社会が進んでいる方向は逆だ。たとえば、出生前診断。出生前診断によって障がいがあることが判明すると、中絶を選択する人が圧倒的だという現実。こうした結果が突きつけている問題は、この小説が言及しているように、多くの人びとが「障がいをもった子を産んでも育てる自信がない」「障がいがある人生は不幸せなのでは」「育てるにはお金がかかる」「社会に迷惑をかけてしまう」などと考えてしまう社会にわたしたちは生きている、ということだ。
この現実を目の前にして、鮎美はこう考える。
〈もし、自分も「菫に税金を使うべきではない」と考えるようになったら、それはやがて、「社会にとっては菫のような子はいない方が良い」という考えに繋がっていくのではないだろうか。菫だけではなく、他の菫のような子たちに対しても、自分がそう考えている、ということになってしまうのではないか。〉
〈「強い国になって周りを見下す」というようなことを目標にする社会が持続するとは思えない。「多様性を認めて弱い存在も生き易くする」という社会の方が長く続いていくのではないか。「国益のために軍事費に金を充てて、福祉をないがしろにした方がいい」なんて、鮎美には到底思えない。この国を「弱い子は産まなくて良い、強い子だけをどんどん産め」という社会にするわけにはいかない。〉
しかし、現実には、前述したように、今回のような事件が起きても、容疑者と同じ「障がい者は生きていても意味がない」「障がい者は迷惑だ」「障がい者は税金がかかる」といった意見が平気で語られている。この国はすでに「弱い子は産まなくて良い、強い子だけをどんどん産め」という価値観に支配されているのかもしれない。


多数ノ子女ヲ育成シ国本ノ培養二資スル所少ナカラズ…


障害児出産「減らしていける方向に」
茨城県教育委員の発言が波紋
(東京新聞【こちら特報部】ニュースの追跡)2015年11月19日
「茨城県では(障害児の出産を)減らしていける方向になったらいい」。同県教育委員の長谷川智恵子氏(七一)の発言が波紋を広げている。長谷川氏は発言を撤回した上で辞意を表明した。だが、不見識なのは長谷川氏だけか。日本社会に根強く残る差別意識の表れではないのか。
(中山洋子)

差別意識 日本に根強く
関係者に徒労感、憤り
長谷川氏の「本業」は東京・銀座の日動画廊副社長だ。茨城県笠間市の笠間日動美術館副館長を務めている縁で、今年四月に県教育委員に就いていた。
問題の発言は、十八日の県総合教育会議で飛び出した。橋本昌知事も出席する中、長谷川氏は、障害者らが通う特別支援学校二校の視察に触れながら「妊娠初期に(障害の有無が)分かるようにできないのか。特別支援学校には多くの方が従事し、県としては大変な予算と思う」「生まれてきてからでは大変」「減らしていける方向になったらいい」などと主張した。
この発言が報じられるや、ツイッター上では、「五体不満足」の著書がある作家で東京都教育委員の乙武洋匡氏が「私も生まれてこないほうがよかったですかね?」と書き込むなど批判が噴出。県教育委員会にも二十日夕までに六百件を超える抗議の電話やメールなどが殺到した。
長谷川氏は十九日、「言葉足らずの部分があった。数多くの方に多大な苦痛を与えた」と謝罪した上で発言を撤回した。当初は長谷川氏の発言を「問題ない」と擁護していた橋本知事も、同日深夜に「誤解を与えないよう(問題ないとの自らの)発言を撤回する」とのコメントを発表。これを受ける形で長谷川氏は二十日、県教委に辞職する意向を伝えた。
しかし、騒動は収まりそうもない。来年四月の障害者差別解消法施行を前に、茨城県も障害者差別を禁じる県条例を今年四月に施行したばかりだけに、関係者の徒労感は深い。
茨城県ダウン症協会の渡辺千代子会長は「出生前診断が広まり、周囲から『なぜ検査しなかったのか』と言われた若いお母さんもいる。長谷川氏も、障害者を無駄な存在と思っているから言ってしまうのでしょう」と歯がみする。
日本ダウン症協会は二十日、事情説明を求める質問状を知事と県教育長宛てに送付。全国の障害者団体でつくるNPO法人「DP1日本会議」も県への抗議声明を準備している。
DPIの佐藤聡事務局長は「障害者は生まれてこない方がいいとの発想で、日本も批准する障害者の権利条約の理念を理解していない。障害があってもなくても等しく大切にされる社会を目指すため、変わるべきは社会の側だ」と憤る。
一九九九年に当時の石原慎太郎都知事が重度心身障害者に「人格あるのかね」と放言して問題視されたが、障害者への差別発言はその後も絶えない。
「重大な人権侵害でうやむやにはできない。辞職で終わる問題ではない」と断じるのは、筑波技術大の一木玲子准教授(障害児教育)だ。まずは長谷川氏が教育委員として障害者や保護者らと会って学び、自らの偏見と向き合うべきだと訴える。「障害者を『かわいそう』な存在としてしか見ていない。残念だが長谷川氏のような発想をする人は少なくない」
茨城大で教えた経験がある金沢大の井上英夫名誉教授(福祉政策論)は、あらゆる弱者を軽視する昨今の風潮を危ぶむ。
「高齢者に金をかけない福祉政策も差別を助長している。人の命は等しく価値がある。障害者は生まれてこなかったらいいという戦前の優生思想を克服する方向で曲がりなりにも進んできた障害者政策を後退させてはならない」

『精神医療』より(現代書館 フォービギナーシリーズ)
より 精神病院法成立
http://nagano.dee.cc/begiwar.pdf

「大日本帝国」が日中戦争から太平洋戦争へと突き進む中で、精神病院建設などという金を使う余裕はなくなり、「精神病」者にとっては新たな苦難が始まる。
1938(昭和13)年厚生省が作られる。厚生省は戦争に役立つ「健康な国民」を作りだそうという目的で生まれたのだ。そして「精神病」者、「障害」者の発生予防を目的として国民優生法が1940(昭和15)年に作られる。国民優生法は現在の母性保護法の前身であリ(現在は母性保護法の管轄は厚生省母子保健課である)、これに基づき「精神病」者や「障害」者の断種が行われた。忘れてならないのは、戦時下の精神病院の多くの入院患者が餓死したことである。
一般の食料事情の悪化は当然精神病院など不可能な入院患者には闇の食料など手にはいるはずもなく、監禁されたままで餓死する患者が続出した。たとえば九州の筑紫保養院(現福岡県立太宰府病院)では戦争末期から戦争直後にかけて、何と70%が餓死した。東京の松沢病院でも、戦争末期から戦争直後に大量のが死者を出している(グラフ参照)。さらに松沢病院に対してはかりに本土決戦となれば、陸軍によって「誤爆」するという計画までたてられたといわれている『声なき虐殺』塚畸直樹編、BOC出版1983年
戦時中動物園で猛獣が殺されたことは『かわいそうな象』などのもまた「猛獣」なみの扱いをされ、空襲などで「精神病」者を監禁している檻が壊れたら、「精神病」者が暴れて困るという発想で、その前に「誤爆」ということにして病院を爆撃し入院患者を殺してしまえ、という計画なのである。「精神病」者から社会を守れ、という思想の極限がここにある。
日本ファシズムと優生思想
藤野豊 著 かもがわ出版
http://www.kamogawa.co.jp/kensaku/syoseki/na/377.html

「存在に値しない命」とは何か。
病気・障害者への断種政策はナチスだけではなかった。優生思想が政策として社会に受容されていく過程を克明に描いた労作。
序章 日本ファシズムと優生思想―研究の現状と課題
第1章 第一次世界大戦と優生思想
第2章 優生運動の展開
第3章 人口問題と優生政策
第4章 ナチズムへの憧憬と警戒
第5章 アイヌ民族と優生思想
第6章 ファシズム体制下の優生政策
補論1 近代日本と優生思想の受容
補論2 部落問題と優生思想
補論3 近代日本のキリスト教と優生思想
終章 「戦後民主主義」下の優生思想
ETV特集
それはホロコーストのリハーサルだった
~障害者虐殺70年目の真実
http://dai.ly/x3cyf72
600万人以上のユダヤ人犠牲者を出し、「人類史上、最大の悲劇」として語り継がれてきたナチス・ドイツによるホロコースト。しかし、 ユダヤ人大虐殺の前段に、いわば“リハーサル”として、およそ20万人ものドイツ人の精神障害者や知的障害者、回復の見込みがないとされ た病人たちがガス室などで殺害されたことについては、表だって語られてこなかった。
終戦から70年もの年月がたった今、ようやく事実に向き合う動きが始まっている。きっかけの一つは5年前、ドイツ精神医学精神療法神経学会が長年の沈黙を破り、過去に患者の殺害に大きく関わったとして謝罪したこと。学会は事実究明のために専門家を入れた国際委員会を設置、 いかにして医師たちが“自発的に”殺人に関わるようになったのかなどを報告書にまとめ、この秋発表する。
番組では、こうした暗い歴史を背負う現場を、日本の障害者運動をリードしてきた藤井克徳さん(自身は視覚障害)が訪ねる。ホロコーストの “リハーサル”はどうして起きたのか、そして止めようとする人たちはいなかったのか・・・。 資料や遺族の証言などから、時空を超えていま、問いかけられていることを考える。
人間が人間を見下す行為は、いじめ、ブラックバイト、パワハラなどたくさんころがっている。差別と虐待の究極の姿として、すべてつながっている問題だと思った。それを国家権力が先導し、助長することはあってはならない。戦後70年、日本国憲法が守られるのかどうか、今、私たちの足元ともつながっている。
投稿者:こう ETV特集HPより
「障害者に安楽死を」はナチスの優生思想そのもの・障害者団体の代表が社会の風潮に懸念を表明
https://youtu.be/THdB2n_igOM
インタビューズ (2016年7月27日)
藤井克徳氏(日本障害者協議会代表)
「障害者には生きる価値がないのか。」「この事件に同調者が出ることが心配だ。」
障害者の人権を守る活動に尽力してきた日本障害者協議会の藤井克徳代表は、今回の障害者を狙い撃ちにした大量殺害事件について、「障害者の人権のためにわれわれが時間をかけて少しずつ積み上げてきたものが、(この事件で)音を立てて崩れていくのを目の当たりにしている思いだ」と、障害者の心の内を代弁する。
神奈川県相模原市の障害者施設に刃物を持った男が侵入して、入所者19人が刺殺された事件では、殺傷された人数やその惨忍な手口などから、社会全体が大きな衝撃を受けている。しかし、特に実際に障害を持つ人々のショックは想像を絶するものがある。
殺人未遂容疑などで逮捕された植松聖容疑者が、「障害者なんていなくなればいい」「障害者は生きていても意味がない」などといった考えに基づいて犯行を行っていたことが、報じられているからだ。
あくまで報道された範囲のことしかわからないがと前置きをした上で藤井氏は、植松容疑者が重度の知的障害者は安楽死をさせるべきとの考えを表明していたことについて、「ナチスドイツの優生思想そのもので、恐ろしい」と、衝撃を露わにする。また、藤井氏の元には障害者や障害者団体の関係者らから、事件に対する不安を表明する連絡が多く集まっているという。
また、自身も全盲の藤井氏は、一億総活躍などに代表される現代の風潮は、生産の場での活躍に大きな価値が置かれているため、逆に生産活動に従事できない人や効率の悪い人には価値がないという発想につながりかねないことが懸念されると言う。「今回の事件もそうした風潮と無関係とは言えないのではないか」と藤井氏は語る。
この事件を受けて、障害者たちが最も懸念しているのは、障害者は安楽死させるべきだという植松容疑者の考え方に同調する人が出てくるのではないかということだと、藤井氏は言う。「障害者という弱者を排除して、もし障害者が社会からいなくなったらば、次は何が標的になるかを考えて欲しい。それがナチスドイツの苦い経験からの教訓だ」と藤井氏は指摘する。
ナチスドイツは「T4作戦」として知られる障害者の安楽死政策で、1939年から1941年の2年足らずの間に20万人の障害者をガス室で処刑している。それがその後のユダヤ人大虐殺につながったことから、ドイツでは歴史的には障害者の抹殺がホロコーストの予行練習のように位置付けられているという。
また、今回の相模原の事件の犠牲者の氏名が非公開とされている点についても、藤井氏は「障害者は普通の人たちとは別扱いされるのが当たり前」という差別的な発想につながることを懸念する。障害者は、障害者というグループに所属する前に、一人ひとりが個人として生きていることを考えてほしいと、藤井氏は言う。
障害者を狙い撃ちにした惨忍な犯罪を障害者自身がどう受け止めているか、社会としてこれをどう受け止めていくべきかなどについて、障害者の人権のために尽力してきた藤井氏に、ビデオニュース・ドットコムの迫田朋子が聞いた。
○●○●○

「文春」報道の不可解
選挙妨害の意図的記事
(しんぶん赤旗)2016年7月22日
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-07-22/2016072201_04_1.html

私が週刊文春の鳥越報道を「卑劣だ」と批判した理由
(日刊ゲンダイ)2016年7月26日
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/186447

鳥越さんで都政を転換
(全国商工新聞)2016年7月25日
改憲勢力に大打撃を
上智大学教授 中野晃一さん
分かち合いの経済に
同志社大学大学院教授 浜矩子さん

核廃絶と平和憲法守る
鳥越候補 岡田代表・小池書記局長が応援
新宿・練馬両
(しんぶん赤旗)2016年7月28日
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-07-28/2016072802_02_1.html

核廃絶と平和憲法守る 練馬北口街宣2/都知事選
https://youtu.be/_4hoFfmjOFE
第16~18回Light Upジャーナル
自由なラジオ Light Up! 016回
「これからどうなる日本経済」
https://youtu.be/_8HWreCP9u8?t=18m18s
18分18秒~第016回Light Upジャーナル
トラブル続き棟土壁の汚染水対策の効果について
http://jiyunaradio.jp/personality/journal/journal-016/
西谷文和:
今中さん、今日はですね「トラブル続き棟土壁の汚染水対策の効果について」と題してお話を伺いたいのですが、まず、ちょっとお聞きしたいのはですね、何故ここまで地下水が、この福島第一に流入するのかという根本的な原因についてお伺いしたいのですが。
今中哲二さん:
私も最初よく知らなかったから、地下水が沢山出るんで驚いたんですけども、もともとあそこの地形というのは、崖のような高台になってるとこを削って造ったんですよね。
西谷:
そうですよね、地形に問題がある。はい。
1967年4月福島第一原発1号機起工式の敷地の様子
今中さん:
もともとさら地に近いような所を掘っちゃったんで、周りから水が流れてくるような所を掘って原発を据えたということらしいです。建設当初から、ですから地下水問題は大変だったということを後から調べたら出てきました。
西谷:
なるほど。造ってる時から、もう地下水が溢れるような土地だったと?
今中さん:
そうですね。事故の前からでも、その原発には地下水が沢山入ってくるということが問題だったんだと思いますよ。
西谷:
これ、吉井英勝(よしいひでかつ)さんという元衆議院議員の方から聞いたんですけど、結局、高台にあった。それを削って、東電の福一だけ低くした。
それは何故なんかと言うと、その海水で原子炉を冷やさなあかんから。
※福島原子力発電所土木工事の概要
(1)http://cryptome.org/0004/daiichi-build-01.pdf
(2)http://cryptome.org/0004/daiichi-build-02.pdf
福島第一原発1号機建設工事。タービン建屋から東は埋立か?
赤枠内が1号機原子炉建屋・タービン建屋施工基面 青線が元の海岸線
今中さん:
冷却水として海水を使うのに、高い所だったら電気たくさん食っちゃうから。
西谷:
ポンプアップ代が?
今中さん:
はい。
西谷:
これメチャメチャせこい理由でですね、私なんか。
今中さん:
はい。
西谷:
それでケチった為に低い所に持って来て津波にあったわけでしょ?
今中さん:
はい。それは女川原発ありますよね?
西谷:
女川、はい。
今中さん:
女川原発は福島よりも、この前の地震の震源に近かったんですけども、あそこ女川は出来るだけ高くしようということで、津波の被害をなんとかかろうじて免れたという事情はあります。
西谷:
そうだったんですか。30メートル、40メートルある高台の上に建てておけば、津波は10メートルちょっとですから、この事故はなかったということになりますよね?
今中さん:
そうですね。と同時に、津波に対する警戒をちゃんと考えてれば、容易に防げることが出来た事故だったという風に私は思ってます。
西谷:
非常用電源も地下に置いてましたもんね。
今中さん:
はい。
西谷:
だからもうミス続きだと思うんですけど、本当にミス続きの東京電力なんですが、この事故の最初の時点で、これ地下水が溢れることは分かっていたわけですから、例えば鉄板で仕切るとかですね。それは、何故しなかったんでしょうか?
今中さん:
はい、私、東電のこの間の5年間のやってる事を見ると、常に楽観的。楽観的な対応をしてるんですよね。これで何とかなるだろう、何とかなるだろうと。
西谷:
何ともなりませんよね。
今中さん:
何とかならないと言うんで。それでね、私自身、原子力学をやった人間ですけども、原子力工学のスピリットというのは常に最悪の事態を考えて対応すると。なんかそのスピリットを全く感じなかったですねえ。
西谷:
これ危機管理の鉄則ですよねえ。常に最悪のことを考えて予防、予防していくっていうのはねえ。
今中さん:
ええ。これで何とかなるだろう、何とかなるだろうって言うんで裏切られた結果が積み重なって、まさに棟土壁もその最たる物ですよねえ。
西谷:
でも、その何とかなるだろうで、福島の人はどれだけ不幸に陥ったかということですよねえ。それでですね、先生ね、当初はこの2015年度中だったんですけど、今年の3月末にやっと始まって、始まったら2カ月後に凍っていないという、この凍土壁。これ散々な問題ですよねえ。
今中さん:
ええ、そんなもん最初から分かってる話だと思うんですけども。
西谷:
やっぱり分かってたんですか?凍らないというのは分かってたんでしょうか?
今中さん:
だから、2年前ぐらいですかねえ。これさえやればちゃんと凍りますと言ってたわけですけれども、それを事実と考えて、キチンと分析すれば、「ああ、ここには配管があるし、ここには溝があるし、これもひょっとして上手くいかないんではないか」という事を考えながらやってもらわなきゃ。
西谷:
国の税金345億円が投じられたということなんですねえ。そして、これから凍らせる電気代とかランニングコストが年間十数億円。
今中さん:
そうですね。超えるとか言ってましたね。
西谷:
これうがった考え方なんですが、こうやって年間のランニングコストとか工事費が高くなると、造ってるゼネコンは儲かりますよね?
今中さん:
そうですね。なんか除染でも似たような話がありますけども。はい。
西谷:
例えばですよ、これ小出先生もおっしゃってたんですが、「もう水で冷やすのを止めたらどうか」って、こういう意見があるんですがどうなんでしょう?
今中さん:
これね、東電なり廃炉の側で、もしそれが可能だったら是非やりたいと思ってると思います。ただ冷やすのを止めたら、今度は温度が上がりますから、まだ発熱してますんで。
西谷:
ああそうか、まだ崩壊熱を出してるということですよね?
今中さん:
そうです。100キロワット~200キロワットぐらいの間ありますんで。デブリ、いわゆる溶けた塊がどういう風な状態になってるか。それによりけりなんですよね。
西谷:
でも、その燃料デブリの形さえ、今分からないわけでしょ?
今中さん:
そうです。チェルノブイリは前も申し上げたかもしれませんけども、ある意味、冷えて固まったんですよね。それ、下に広い部屋があって、そこから空気の流れがおきて、たぶん空冷状態で固まったんだと思われます。
西谷:
なるほど。地下の冷えた風が吹いてきて。
今中さん:
はいはい。福島の場合、そういった構造になってませんから、水を全部抜いちゃったら、また温度が上がっちゃって、そして、温度が上がると放射性物質がまた飛散したり揮発しますんで、また大変なことになりかねないと。
西谷:
だから、しばらくは水で冷やさないといけないという、そういう事ですか?
今中さん:
そうですね、はい。その水がですね、ちゃんとクローズドの、要するに密閉のサイクルになってればいいんですよ。でなくって、原子炉にですから、デブリの分に水を入れますよね。それで汚染された水が、また他の地下水で流れ込んでくると、一緒になってタービン建屋の方に溜まってくると。それを汲み上げて、また汚染水がどんどんどんどん増えてくるという構造ですよね。
西谷:
もうなんかねえ、要は器が割れてるから、やっぱり下へ下へ漏れていくんでしょうねえ。
今中さん:
そうですね、はい。原子炉も割れてますし、建物も割れてますし。
西谷:
だから、水を入れれば入れるほど、地下水は汚染水になって。
今中さん:
私は、建物ひょっとして地震の前から割れてたんじゃないかと思いますよ。
西谷:
地震の前からですか!?
今中さん:
はい。いわゆるね、サブドレーンとかいう周りの地下水の水位を調べる穴があるんですけども、それは、実は事故の前から掘ってあるんですよ。ですから、地下水位が高いんで、建物の中に漏れたりするのをずーっと監視する為に、そういうシステム持ってたんだと思います。
西谷:
そうなんですか。という事は、事故で決定的な破損があったんだけれども。
今中さん:
決定的なダメージ受けたんだと思いますけど。
西谷:
事故前からもう地下水が流れ込んでいて。
今中さん:
そう。ですから、タービン建屋なり何なりとうのは、最初からひび割れなり何なりあったんではないかなあというのが、私の勘繰りです。
西谷:
はい、分かりました。もう本当に、この対策は待ったなしですが、東電が後手後手に回っていて楽観的な結果、被害が大きくなってるということがよく分かりました。
今中さん:
そうですね、はい。
西谷:
今中先生、どうもありがとうございました。
今中さん:
はい、どうも。
自由なラジオ Light Up! 017回
「国益最優先の政治に憤る!拉致と原発、届かぬ被害者の思い」
https://youtu.be/-_Qwn1tCthw?t=18m54s
18分54秒~第017回Light Upジャーナル
小出さんから見た“凍土壁問題”
http://jiyunaradio.jp/personality/journal/journal-017/
いまにしのりゆき:
前回ですね、西谷文和さんの回では、小出さんの同僚でいらっしゃいました今中哲二さんに
福島第一原発の汚染水対策について、凍土壁はどうなんかということでお話を伺いました。
今回はですね、小出さんから見た凍土壁の問題についてのご見解を伺います。熊取六人衆と呼ばれたそれぞれの方、どのようにして福島第一原発の収束作業を見守っておられるのでしょうか?早速、小出さんをお呼びします。小出さん、今日もよろしくお願いします。
小出さん:
はい。よろしくお願いします。
いまにし:
小出さん、今ですね2011年東日本大震災で事故を起こしました福島第一原発ですね、収束作業が続いておるわけなんですが、とりわけ大きな問題の1つに汚染水対策というものがあります。その為、今、凍土遮水壁というのが建設されておるんですけれども、これがなかなか上手くいっていないという報道があります。以前から小出さんは、こんなもんうまいこといくわけありませんわとおっしゃられていましたが。
小出さん:
そうです。はい。
いまにし:
予想が当たってしまいました。
小出さん:
はい。何度もこの話を聞いて頂きましたけれども、今、東京電力が作ろうとしている遮水壁は深さ30メートル、全長にすると1.5キロにも及ぶという巨大な壁なのです。それを地下に作って、地下水の流れをせき止めようとしているわけですけれども、地下水というのは流れの速い所もあるし、流れの遅い所もあるわけです。1.5キロにも渡って作ったとしても、ある所では止まったとしても、ある所では壁が突き破られてしまうということに、必ず私はなると思ってきました。実際に今回そうなったわけで、仕方がないから、そこにセメントを今度注入してですね、そこを固めようということになったらしいですけれども。そこを固めれば、今度はまた別の所が破れるだろうと私は思います。
仮に、某かその水を一応はせき止めたということになっても、凍土壁というのは常時凍らせておかなければいけないわけで。その為にはポンプが回らなければいけませんし、冷媒と言ってる冷たい液体を流している配管が常に健全でなければいけない。詰まってもいけないし、破れてもいけないというそういう物なわけで、そんな物が長い間維持できる道理がありません。やはり、早く凍土壁というやり方は止めて、もっと恒久的な遮水壁を作らなくてはいけないと私は思います。
いまにし:
そうですよね。でも、いわゆる氷の壁作戦がですね、凍土壁上手くいかないと、これから収束作業、廃炉作業にますます大きな影響を与えるんじゃないんかなあと思われてならないんですが。どうなんでしょう?根本的にですね、汚染水対策やはり見直す必要があるのではないかなあとも感じるのですが。
小出さん:
はい。もちろんそうです。皆さん、原子力発電所から出てくる放射能の本体、普通は高レベル放射性廃棄物と呼ばれてるものですけれども、それを日本の国は地下に埋め捨てにすると言ってきました。
いまにし:
はい。
小出さん:
その時に、埋め捨てにする場所で一番大切な条件というのは、そこに地下水が流れ込んでいない、水と接触する可能性がない場所を選んで埋め捨てにするということになっていたのです。つまり、放射能は水と接触させてはいけないというのが大原則なのです。それなのに、今は意図的にどんどん水を溶け落ちた炉心に向けてかけているという作業を続けているわけで、私はもうそんな事はもう止めなければいけないと思っています。
確かに事故直後には、炉心を溶けさせない為に何としても水をかけなければいけないという時期はあったのですけれども、既に、もう5年以上の歳月が流れていて、崩壊熱も随分減ってくれていますので、水をかけて冷却するというその手段自身をもう止めなければいけない。それを転換して、汚染水の増加を防がなければいけない時期なのだと私は思います。
いまにし:
なるほど、なるほど。まず、冷やす所、根本的な所を変えないといけないということですね?
小出さん:
そうです。
いまにし:
分かりました。小出さん、ありがとうございました。
小出さん:
こちらこそ、ありがとうございました。
小出裕章:高濃度汚染水漏れについて:遮水壁=地下ダム
http://dai.ly/x12jom7
何か皆さん今になって汚染水問題ということが起きてきた、あるいは大変だと思われてるようなのですけれども、私からみると何を今更言ってるんだろうと思います。
事故が起きたのはもう既に二年数か月前の2011年3月11日だったのです。
それ以降汚染水というのは敷地の中に大量に溜まってきまして3月中にもう既に福島第一原子力発電所の敷地の中に10万トンの汚染水が溜まっていました。
コンクリートというのは元々割れるものです。
割れのないコンクリート構造物なんていうものはありません。
おまけにあの時には巨大な地震でそこら中が破壊されたわけで原子炉建屋、タービン建屋、トレンチ、ピット、立て抗にしてもコンクリートにそこら中にひび割れが生じていたのです。
ほとんど目に見えない建屋の地下であるとか、トレンチ、ピット、要するに地面の所に埋まってるわけですから見えない所でそこら中で割れて、そこら中から漏れている。
当時もそうだし、二年経った今だって必ずそうなのです。
私はとにかくコンクリートの構造物から漏れない構造物に移すしかないと考えました。
私が思いついたのは巨大タンカーでした。
10万トン収納できるようなタンカーというのはあるわけですから10万トンタンカーを福島の沖まで連れて来て福島の敷地の中にある汚染水をとにかく巨大タンカーに移すという提案をしました。
でもまたそれも次々とコンクリートの構造物に汚染水が溜まってくるわけですから何とかしなければいけないと思いまして私はその巨大タンカーを東京電力柏崎刈羽原子力発電所まで走らせる
柏崎刈羽原子力発電所というのは世界最大の原子力発電所でそれなりの廃液処理装置もあります。
宝の持ち腐れになっていたわけで柏崎刈羽までタンカーを移動させてそこの廃液処理装置で処理をするのがいいという風に3月末に私は発言した。
そういうことはやはり政治が力を発揮しなければできないのであって政治の方々こそそういうところに力を使って下さいと私はお願いしたのですけれども、とうとうそれもできないまま何も手を打たないままどんどん汚染水が増えて今現在30万トンにもなってしまってるというのです。
(3.11からもう二年数か月経ってるわけですけれども、あの時にもしスタートさせていたら今もう間に合ってるんじゃないか)
もちろんです。
また次に10万トン汲み出すということもできたでしょうし現在直面している事態よりもはるかに楽になっていたはずだと思います。
そういう意味では政府と東京電力が無能だったということだと思います。
・遮水壁=地下ダム (2011年6月)
原子炉建屋の外にかなり深い穴を掘ってそこに深い壁を作って溶け落ちた炉心が地下水にできるだけ接触しないようにする。
接触したとしても汚染が海へ流れないようにするそういう作業がこれからできる唯一のことかなと思うようになりました。
本当に対策が後手後手になってしまっていて放射能の汚染がどんどん広がっていってしまっている。
1号機から3号機の原子炉の炉心は既に溶け落ちているのです。
確実です。
溶け落ちた炉心がどこにあるかということなのですが東京電力はまだ格納容器という放射能を閉じ込める最後の防壁の中にあるはずだと言っているのですけれども、残念ながらそれを見に行くこともできないし本当にそこにあるかを確認することができないのです。
場合によっては既に格納容器の床を突き破って地面に潜り込んでいってる可能性も私はあると思います。
もしそうだとすると地下水と必ず接触してしまいますしそうなるともう猛烈な放射能が地下水に混じって海へ流れていくことを食い止められなくなってしまうので私は2011年5月に原子炉建屋周辺に遮水壁を張り巡らせる地下ダムという言葉を使われる方もいますけど、それをやって溶けた炉心と地下水の接触を断つということをやってくれと頼んだのです。

自由なラジオ Light Up! 018回
「なぜ子どもの貧困は起こるのか?」
https://youtu.be/-kBeubUxkoE?t=16m5s
16分05秒~第018回Light Upジャーナル
第18回放送
http://jiyunaradio.jp/personality/journal/journal-018/
矢野ひろし:
伊方原発核燃料装填、そして再稼働について今中さんに伺います。やはり伊方原発と言うと、今中さんや小出さんらが関わった設置許可取消裁判ですよね。大変なじみの深い原発だと思うのですが。
今中さん:
もう40年前になりますけれども、ちょうど私が愛媛の職場に入った時に、いわゆる伊方原発の裁判が始まってたとこでした。
矢野:
そうでしたね。今中さんが75年に入られて。
今中さん:
76年ですね。
矢野:
76年ですか。もう裁判は始まってたわけですね。
今中さん:
ええそうですね。私まだ本当に若くて、それで裁判のお手伝いで傍聴でいろいろ話を聞いてみると、どうも原告の住民側の方が、議論では勝ってるんですよね。いわゆる国側の証人なんてのは、弁護士さんの質問に答えられないというような事態がしばしば起きたりしたんですね。ひょっとしてこの裁判、住民側が勝つんじゃないかなという風に、私、若いながら感じてたんですよ。

矢野:
なるほど。しかし、地裁と最高裁負けていくわけですけど。
今中さん:
そうなんですよ。裁判が結審するちょっと前になると、どういうわけか裁判長さんがぽろっと代わって。

矢野:
代えられるんですよね、あれ。本当に。
今中さん:
何がなんだろうと、私は思いましたけれどね。
矢野:
その時に、今もう伊方原発は1号機2号機3号機と、3機も出来てしまいましたが。
今中さん:
3つになりました。
矢野:
こんなこと想定できましたか?
今中さん:
いやぁー、四国電力、伊方ですよね。いわゆる中央構造線というのが目の前にあって、
それで、まさに瀬戸内海に向いて原発があるんですよね。もう信じられない話ですよ。
矢野:
この核燃料装填というのは、どんな作業なんでしょうか?
今中さん:
原発、原子炉というのは、核燃料というかウランの核分裂連鎖反応とかなりますよね。燃料そのものがウランというやつですよね。ウランというやつを、ですから燃料ペレットというのにして、それを燃料棒というのに、長い細い棒に詰め込んで、それを束ねたやつが燃料集合体です。その燃料集合体、だいたい伊方だったら200本ぐらい集めて1つの燃料集合体になるのかな。それを150体ぐらい原子炉の中に入れると、全体の炉心ができて、ようやく核分裂連鎖反応を始められる体制に入るというものです。
矢野:
これは、作業自体はそんなに危なくはないんですか?
今中さん:
作業はですね、いろいろ水の中でクレーンとか使いますから、クレーンから外れたりすれば問題ですけども、まぁ特に危ないというものではないと思いますけども。
矢野:
なるほど。今回使われる燃料がMOX燃料ですよね。使用済み核燃料を再処理して取り出したプルトニウムとウランを混ぜた燃料。これ、今中さん大丈夫なんですか?
今中さん:
プルトニウムもいわゆる核燃料になる物質の1つですから、電力会社なり、というよりは日本政府がなんとかしたいんですよね。
矢野:
政府がですね。
今中さん:
日本政府は、原子炉から出てくる使用済み燃料を全部再処理してプルトニウムを取り出すという事なんですけども、本来は、そのプルトニウムというのは、いわゆる高速増殖炉もんじゅというのがありますけれども、それで使う予定だったんですけども、その高速増殖炉をやろうという炉心は20年前に破断しちゃったんですよね。
https://youtu.be/rLc5tq-_BBw
矢野:
そうですよね。動いていませんよね。
今中さん:
それでプルトニウムが余ってしまって、なんとかしたいと。たぶん電力会社もMOXをやりたいとは思えないですよ。安全性が悪くなる事はあっても、良くなる事はありませんし。
矢野:
電力会社の説明によりますと、燃えやすいプルトニウムの割合が低いんだと。そして、ウランと混ぜるのだから大丈夫なんだというような事を言われていますけれども、本当なんでしょうか。
今中さん:
私の聞いてるところでは、いわゆる制御棒の効き具合が悪くなるとか、そういった問題はあるようですね。
矢野:
本来、プルトニウムは使う物ではないですよね。原発自体が。
今中さん:
そうですね、プルトニウム燃料は想定してませんから、そういう意味では安全性に対する余裕度みたいなものが減っていく方向だと思います。
矢野:
なるほど。そんなことをしてでも、やはりプルトニウムを消費しないといけないという政策ですね。
Glovebox for Pu
今中さん:
まず、そこの問題は、我々日本政府考え直さなきゃいけないだと思います。
矢野:
プルサーマル計画というのをなんとしてでも諦めきれないということなんでしょうか?
今中さん:
そうですね。再処理工場も残りますし、あのもんじゅさえまだ残ってるという不思議な原子力政策ですよね。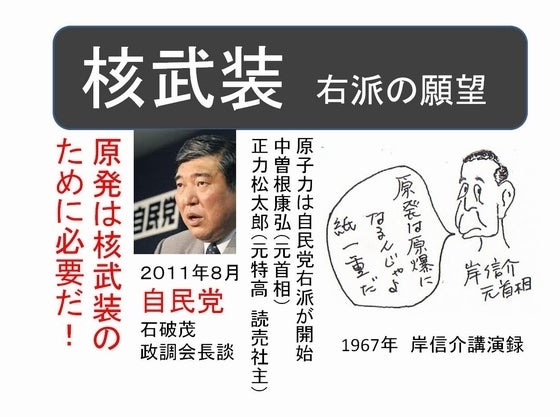
矢野:
さて、再稼働となりますと、新規制基準の下では、九州電力の川内原発の1号機2号機、
そして、関西電力の高浜3号機4号機に続き5機目というふうになるんですが、
今のところ高浜は司法判断で差し止め中ですけれども、本当にこの再稼働必要なんでしょうか?
今中さん:
本当、私が聞きたい話でして、何年か前は夏で暑いと電力が足りない、電力が足りないと言っていたんですけども、この夏なんていうのは、節電のせの字もないんですよ。
矢野:
そうですよね。
今中さん:
はい。私個人的にその辺不思議だなぁと思って調べたら、実は夏の最大電力量というのは、ここのところ毎年減ってるんですよ。
矢野:
えー。減ってるんですか。
今中さん:
減ってます。去年と比べると、夏の一昨年ですか。一昨年、去年と比べると、ピーク需要で1000万キロワットぐらい減っています。
矢野:
そんなに減ってるんですか?
今中さん:
ええ、びっくりしました。
矢野:
それで、節電のせの字も出てこないんですね。
今中さん:
それがよく分からないんだけども、今頃太陽パネルが物凄い普及してますよね。それで、夏のピークを抑えられてるんじゃないかなという気がします。
矢野:
なるほど。ということは原発は必要ないと。
今中さん:
我々庶民には必要ないですよね。我々にはリスクばっかり被さってくるもんですから。
矢野:
そうですね。今、リスクの話をされましたけれども、この伊方原発というのは佐田岬半島の付け根にあるんですけれども、この避難計画も、私はこれ充分にできていないと思うんですが、今中さんどうですか?
今中さん:
そうですね。再稼働もそうですけども、一番けしからんのは原発の安全性の責任を持つべき、いわゆる規制委員会、規制長がきちんと審査しないと。避難経路等には、彼らは責任はないと、そういう態度を取ってる。やっぱり、私はこれは問題だろうと思いますね。
矢野:
規制委員会が責任を持たないんだったら、どこが責任を取るんですか?
今中さん:
安部さんは口だけの人ですから、はい。
矢野:
先程、今中さんのお話の中にもありましたが、この伊方原発の北側には中央構造線という活断層が通ってるということですよね。
今中さん:
皆さん、この前熊本の地震がありましたよね。あれがだんだん大分の方に伸びていって、その先をずっと見たら伊方原発に届くなぁと。たぶん多くの方がそう思って見られたんだと思いますよ。
矢野:
そうですよね。忘れてはいけないいのが、南海トラフもありますよね。
今中さん:
そうですよね。はい。
矢野:
ということは、もう地震の巣のような所に伊方原発があるということですよね。これは何としても、再稼働本当に必要ないんだったら止めてほしいと思うんですが。
今中さん:
というか、そこまでして我々電気を使わんならんのか、作らんならんのかという問題だと思います。
矢野:
なるほど。なんとかこの私たちも賢くならないとだめですよね。すぐ目先のことをすり替えられると、原発のことを忘れてしまう。そうですね。今中先生どうもありがとうございました。
今中さん:
どうもありがとうございます。
そもそも総研 2013年2月7日
「そもそも新安全基準で原発は本当に安全になるの?」
http://dai.ly/xxc7t6
7月から新しい安全基準ができるが、先週、規制委員会の有識者会議で、新安全基準の骨子案が明らかになった。これについて今日から意見募集(パブリックコメント)が求められるので、今だったらこの案に対して何か求めたり言うことができるタイミングだ。
そこで検証してみよう。
新安全基準とは?
問題はありますか?
さらに‥
出演は東大名誉教授の井野博満氏、後藤政志氏にお話を聞く。また今日のメディア報道で、国会事故調に対して東電が虚偽説明をしていたことが報じされた。これは原発が地震で壊れていた可能性を示している。元事故調委員の野村氏にも話を聞く。
チェルノブイリ30年・福島5年救援キャンペーン
小出裕章講演会
https://youtu.be/Z64LmFj8dR4
「チェルノブイリ30年・福島5年救援キャンペーン 小出裕章講演会&チャリティコンサート」
(2016年4月23日(土)練馬文化センター)より、小出裕章氏の講演
今は静かな涙が流れるばかりです…(´;ω;`)

原爆体験記
178頁より
<小学生>
ああ、父と母 長野ふみ子
当時十歳、愛媛県に疎開中に両親を原爆にて失う。
両親を失った私は、どうしてこんなつまらない戦争をしたのかと思うと腹が立って、腹が立ってし方がありません。この戦争をしなければ、私のお父さんも、お母さんも、生きていらっしゃることでしょう。私は広島市堀川町九番地時計商の二女として生れました。軍と県との関係があったため、両親は私達姉妹が、そかいしている田舎に来ることが出来ませんでした。
昭和二十年八月六日、世にもない、世界で初めての強い力を持っている原子爆弾がこの日の八時十分に落ちたということでした。私はこの時、愛媛県越智郡九和村法界寺という部落にそかいをしていました。それで命だけは助かりました。この時私は九和小学校の三年生でした。ある日、とぼとぼと学校から帰る時でした。お姉さんが私の前を歩いていらっしゃるのに気がつきました。お姉さんは「早く帰っておるすばんをしていなさい」といわれました。私がいそいで友達と帰っていると、何だかラジオで放送しているようでした。立ち止って聞いていたが、何の意味か、よくわかりませんでした。
昼食を食べおえた時、お姉さんらしい足音がしたかと思うと、玄関がガラリとあいて、お姉さんの姿が見えました。お姉さんの顔はいつもの顔とは少し違っていました。私はお姉さんにたずねて見ると、元気のない声で「広島が大爆撃に会ったのよ」といわれた。私はこの話を聞くと、お父さん、お母さんのいらっしゃる我が故郷が、大爆撃に会ったとは大変だ。夢にも、またこんなおそろしい原子爆弾があるとも、しりませんでした。これを聞くと、全身冷たい水をあびたような気がしました。
この事が気になっているうちに、早くも五日がすぎました。お父さんからは、なんのしらせもなく、一通の手紙さえ来ませんでした。それで近所の人は、私のお父さんが死んだものと思って、いろいろなぐさめて下さいました。私はなんだか胸が苦しいような気がし、ほろほろと熱いなみだが、ほおをぬらしました。夕方みんながぞろぞろと帰ってしまうと、いっそう悲しくなりました。お姉さんの顔にはなみだのあと、目が赤くなっていました。その夜、私はなかなか眠れませんでした。ねがえりをうつたびごとに目にたまっているなみだが、右へ流れ左へ流れるのでした。
十八日の朝が来ました。だが学校へ行くのに何だか行く気がしませんでした。学校で遊ぶ時も、なんだか体がだるいようでした。授業が終り、家にかけついた。玄関をおけると、お姉さんが奥から元気のいい声で「ふみちゃん、これ」といわれました。私は何だろうと思いながら、奥にはいりました。手紙です。よむ前に封筒のうらを見た。「あっ」とたまげたひょうしにいそいで中をあけました。これこそ待っていたお父さんからの手紙でした。つぎつぎと読んでいるうちに、(母即死)とかいてありました。私はまた目になみだをためて、今にも声をたてて泣き出しそうでした。しかし、お父さん、お姉さん、お兄さんが残っていらっしゃいます。そして私を導いて下さると思うと、やっとなみだの出るのがやみました。おわりに何日に私達のいる田舎に帰るということでした。妹の顔もうれしそうでした。その日を指おり数えて待っていました。
私は朝から、ぴょんぴょんとはねまわりました。学校から帰ると近所へ遊びに行きました。きゃあきゃあと声を立てて遊びました。するとお姉さんが、「ふみちゃん、俊ちゃん、お父さんよ」とよばれた。私はいそいでまだ小さい妹の手を取って、田舎の坂道を下って行きました。玄関に入るとお父さんの顔が見えました。私はいきなり「お父ちゃん」とさけびました。妹もあとについてきました。お父さんはゆっくりと話されました。
「お客さんとお店で話していると、にわかに外が光った。お父さんは、とっさにえいぎょう台の三角形の空間に体をよせ、そして、お客さんの名をつぎつぎとよんだ。だれも答える者はなかった。しばらくして『おじさん、おじさん』と学生の呼び声に光をむけながらはい上った。『康恵、康恵』とお母さんの名をよばれた。するとかすかなうめき声が聞えた。お母さんは、多くの物の下にかさなり、ぴくぴくと足を動かされていた。その瞬間にさえ、子供達のことを思った。崩壊して通る道もなく屋根瓦づたいに一里半もの道を逃げていった。シャツはよれよれになり、ズボンはバンドがなくなっていたため、かかえるようにして逃げ出した……」これを聞くとこの時の、お父さんの苦心がありありとわかりました。
「きずはかるくて、そのよく日、お母さんの死体をかたづけた。うめていた商品は焼けていた。ただ残ったのは水槽の中のおちゃわん類だけだった。それも、二日目にはだれかが持ち去ったものであろう、残されてはいなかった」お父さんは涼み台に腰をかけ、星をあおぎながら、ぽっきりぽっきりと語られた。
お母さんは失ったけれど、お父さんを与えられた私達の幸福は、しかし長く続きませんでした。
二十九日の朝から家のそうじにとりかかりました。それから障子をはりかえた。すると、お父さんは「さむけがする」といって、ねつかれてしまいました。熱はぐんぐんと高くなり、ねつかれて五日目、「だんだん息が苦しくなる」といわれ、やがて口がきけなくなりました。お父さんは苦しそうに、うなりごえをたてて、たたみの上に手で宇をかいたり、口をもごもごさせて、何かいいたそうにしていらっしゃいました。お父さんは、不思議にも、水まくらを取りかえ、自分の着物を取りかえ、床に入り手を組んで胸の上におき、苦しみの色のあとかたもなく、静かに息を引き取られました。みゃくがとまって、よんで見ると、かすかにうなずかれました。そうして、とうとう私達はあの原爆、ただ一瞬間、ピカ。と来た原爆の光に、両親を失ってしまったのです。
あれから五年、苦しい兄弟の生活は続けられました。何度お父さんがいたら、お母さんがいたら、と考えたかもしれません。けれども一度は別れなければならない生と死との考えも自然に身について、今は静かな涙が流れるばかりです。
私達のような運命の子供達のためにも、原爆は二度とくり返してはならないと心から祈るのです。
NHKスペシャル 1998年8月6日
「原爆投下 10秒の衝撃」
http://dai.ly/xv00ky
ピカドンと呼ばれる原爆。爆発から広島が壊滅するのに要した時間はわずか10秒である。
炸裂前から大量に放たれていた放射線、3秒で地上を焼き尽くした熱線、10秒で広島市の全域をのみ込んだ衝撃波。人々が立ち昇るキノコ雲を見た時、広島は既に破壊されていたことになる。
日米の科学者の協力を得て、広島原爆の惨禍の始まりとなった10秒間を科学的に再現・検証し、核兵器の恐怖を描く。
広島平和記念資料館では展示されない事実を伝え続ける被爆者、三登浩成さん
https://youtu.be/1s3TXZBu2v4
NHKスペシャル 2010年8月6日
「封印された原爆報告書」
http://dai.ly/xkca1f
アメリカ国立公文書館のGHQ機密資料の中に、181冊、1万ページに及ぶ原爆被害の調査報告書が眠っている。
子供たちが学校のどこで、どのように亡くなったのか詳しく調べたもの。
200人を超す被爆者を解剖し、放射線による影響を分析したもの…。
いずれも原爆被害の実態を生々しく伝える内容だ。
報告書をまとめたのは、総勢1300人に上る日本の調査団。国を代表する医師や科学者らが参加した。
調査は、終戦直後から2年にわたって行われたが、その結果はすべて、原爆の“効果”を知りたがっていたアメリカへと渡されていたのだ。
「17000人/70箇所にのぼる子供達の被害の調査が日本調査団により行われた。例えば、1.3Km地点では132人中 50人死亡、0.8Km地点では560人中560人死亡など、建物疎開に動員された子供の死亡率が調査され、まとめられた。世界初の爆心からの距離と人間の死亡率との定量的な相関関係図ができあがった。この相関図は、アメリカ空軍のシミュレーションに活用され、例えばモスクワを攻撃するなら6発、ウラジオストックなら3発など、核戦略構築に活用された。つまり、広島の子供達の犠牲がアメリカの核戦略に貢献した。」
なぜ貴重な資料が、被爆者のために活かされることなく、長年、封印されていたのか?
被爆から65年、NHKでは初めて181冊の報告書すべてを入手。調査にあたった関係者などへの取材から、その背後にある日米の知られざる思惑が浮かび上がってきた。
番組では報告書に埋もれていた原爆被害の実相に迫るとともに、戦後、日本がどのように被爆の現実と向き合ってきたのか検証する。
BS1スペシャル 2016年7月24日
「原爆救護~被爆した兵士の歳月~」
https://youtu.be/-tddmqUFuvw
原爆投下直後、市民救助を命じられた兵士たちがいた。炎と煙の中、負傷者を救い出し無数の遺体を葬った兵士たち。戦後、放射能の影響が疑われる体調不良に苦しむが、差別や偏見を恐れて口を閉ざした。大多数が被爆者手帳を取得しなかったため“埋もれた被爆者”となっていく。やがてガンなどを発症するが、原爆症認定の壁も厚かった。爆心地での救護活動の実態と、被爆地から遠く離れた故郷で暮らす元兵士たちの苦難の戦後を描く。
【語り】光岡湧太郎
世界は広島をどれだけ知っているか
研究グループがデータベース化
(東京新聞【こちら特報部】)2016年5月3日
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2016050302000122.html
オバマ米大統領の広島訪問が現実味を帯びてきたが、被爆地の思いは複雑だ。核軍縮の動きは鈍く、被爆者の高齢化は進む一方。「被爆の実相が知られていない」との危機感も広がる。広島では研究者たちが海外で出版された原爆文献リストのデータベース化にも取り組み始めた。世界は被爆体験をどう共有していけるのか。
(白名正和、安藤恭子、中山洋子)
研究グループが
データベース化
「母語で読むからこそ伝わるものがあるんです」研究グループ「リンガ・ヒロシマ」の代表で広島国際大元教授の中村朋子さん(六九)が力を込めた。二年前、ポーランド出身で広島市在住の研究者ウルシユラ・スティチェックさんとともに同グループを結成。国内外の研究者約三十人の協力を得て、各国の図書館の蔵書などを検索し、原爆文献の調査を続けている。
原爆文献 69言語1800点
これまで六十九言語、約千八百点の文献をリストアップしてきた。調査結果は年内にもインターネット上で公開する予定だ。中村さんは「予想以上にたくさんの言語で広島・長崎が語られている。毎日のように増えていく」と感嘆する。
英語が最も多いが、自らも被爆した医師蜂谷道彦氏の「ヒロシマ日記」は二十言語以上に翻訳されていた。被爆した少年少女の体験記を収録した長田新氏の「原爆の子」も多く翻訳され、アイスランドの少数言語の本も見つかった。一方、日本では知られていない作品もある。例えばパキスタン人作家が英語で書いた小説「Burnt Shadows(焼け焦げた影)」は十三言語で出版されている人気作だが、日本語にはなっていない。
リストには、核抑止論の視点で書かれだ本なども加えている。中村さんは「核廃絶が最大多数の声にならない理由を考えるためにはこうした本も大切」こと説明する。
被爆の実相伝えたい
草の根の熱意
大学生のときに姉の夫が原爆症で亡くなり、幼い息子たちを抱えて苦労する姿を間近に見てきた。「広島に住む人間には、核廃絶を強く求める何かしらの原体験がある」と言う。
一九六〇年代から英語の原爆文献のリストアップや解説をライフワークとしてきた。リストはこれまで英語の副読本教材に活用されたほか、原爆文献などにも転載された。「英語だ付では見誤る」と感じる中村さんが、長く温めていた構想が多言語の調査だった。「広島・長崎の体験を人類がどう共有してぎたかを俯瞰(ふかん)できると思た」
原爆文学を研究するスティチェックさんがワルシャワ大の日本学科の大学生だったとき鋩に初めて読んだのも、ポーランド語に翻訳された原民喜(一九〇五~五一)の小説……「夏の花」だった。八六年四月のチェルノブイリ原発事故ではワルシヤワも汚染された。スティチェックさんは事故から五年後に母を喉頭がんで亡くした。「核の被害は人ごとではない。一番心に近い母語で読むから、国境を越えて理解しあえる」と調査の意義を痛感している。
調査からは、反核運動が盛んになった八〇年代に欧州で翻訳が増えた傾向も見えてきたというノ中村ざんは「原書に心を動かされた人々の熱意で多くの翻訳が生まれている。調査から被爆の実相を草の根で届けようとした人々の努力が浮かび上がってくる」と話し、世界が被爆体験を共有する重要性を訴える。
「核なき世界」あきらめない
近年、広島を訪れる外国人は増えている。
広島平和記念資料館の二〇一五年度の外国人入館者は、統計を取り始めた一九七〇年度以降最多の三十三万八千八百九十一人。海外の関心は低くはない。
同館では外国人向けに十六言語の音声ガイドを用意するほか、一五年度から被爆者の声を語り継ぐ「被爆体験伝承者」の英語での講話も実施。約二百回行われたが、本年度はさらに拡充するという。
だが「外国には原爆の被害はまだまだ知られていない」と懸念するのは、広島大名誉教授の葉佐井博巳さん(八五)だ。
原爆投下翌日に市内を歩き回り、十四歳で被爆した。物理学者として放射線を研究する傍ら、修学旅行生や外国人客に体験を話してきた。「ロシア革命や文化大革命について、日本人はその実相をほとんど知らない。それと同じで、自分と直接の関係がなかったら意識することは難しい」とおもんぱかる。その一方、被爆の苦しみを知ることが、核廃絶につながると信じ、国立広島原爆死没者追悼平和祈念館が公開する被爆者の体験記の電子データ化にも協力してきた。体験記は○八年ごろから各国語にも順次翻訳されている。当初は英語や中国語などだけだったが、現在は二十三言語にまで増えた。
関心薄い日本人客 質問も議論もなく
原爆ドーム前に立ち、ボランティアで英語ガイドを続ける元高校教諭の三登浩成さん(七〇)=広島県府中町=も「ここに足を運ぶ人はもともと原爆に関心が強い。来ない人にこそ広島を知ってほしいけれど」とため息をつく。母親の胎内で被爆した三登さんは○六年から、日本人も含めて百六十六カ国約二十六万人を案内してきた。英米よりも多いのがオーストラリアからの訪問者という。「(被爆して白血病を患い十二歳で亡くなった)佐々木禎子さんの話を、小学校で教えているようでした」
むしろ歯がゆいのは日本人客だ。「物見遊山で関心は薄い。現代史を習っておらず、質問もなければ、議論もできない。この間は『東京にも原爆が落ちた』と言っている男子学生さえいた」と嘆く。
先月、米国の閣僚として初めてケリー国務長官が広島市の平和記念公園を訪問。これに続き、今月下旬の主要国首脳会議(伊勢志摩サミット)に合わせ、オバマ米大統領の広島訪問も検討されている。広島に再び世界の注目が集まるが、被爆地の思いは複雑だ。
オバマ氏は就任当初の○九年四月、チェコのプラハで「核兵器なき世界」を訴え、その年のノーベル平和賞を受賞した。
前出の葉佐井さんは「演説の理想はほとんど実現されていない。広島に来るなら、なぜ実現できなかったのかを説明してほしい。ただの話題づくりなら、来なくてもいい」と手厳しい。三登さんは、広島県の湯畸英彦知事らが早々に、訪問を期待するオバマ氏に謝罪を求めない考えを示したことにも違和感を抱く。「なぜ被爆者の側から『謝罪しなくて良い』つて言わなきゃいけないの。心からの謝罪があって初めて、核を使わない未来へと進めるはずだ」
オバマ氏に期待 指導者もっと訪れて
医療ソーシャルワーカーとして延べ二万人以上の被爆者と接してきた村上須賀子・県立広島大元教授(七〇)は「ケリー氏には被爆者の声を聞いてほしかった。貧困や差別、家族の崩壊に死への恐怖。原爆がその後の人生に与える苦悩は展示物ではなく、当事者の思いからしか伝えられない」と訴える。
被爆者の平均年齢は八十歳を超えている。村上さんは「やっと原爆を落とした国の大統領が、広島を訪れる機運ができた」と評価する。「核兵器は絶対悪。二度とこのむごい出来事が起きないように、オバマ氏には今からでも力を注いでほしいし、各国の指導者ももっと広島を訪れてほしい。それが、被爆者の無念をすくい上げ、核なき世界へと踏み出すことにつながるのではないか」
注目の人直撃インタビュー
元広島平和研究所所長
浅井基文
オバマ大統領の広島訪問は日米軍事同盟の完成を祝うセレモニー
(日刊ゲンダイ)2016年7月1日
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/184688
今年5月、現職米大統領として初めて被爆地・広島を訪問したオバマ大統領を日本メディアは「歴史的」と大絶賛したが、本当にそうだったのか。09年4月のプラハ演説で目指す――とした「核なき世界」は前進したとはとても思えない。外務省出身の元広島平和研究所所長・浅井基文氏は、オバマ広島訪問を「単なるセレモニー」とバッサリ斬り捨てた。
広島演説はプラハ演説より“退化”した
――オバマ大統領はプラハ演説でノーベル平和賞を受賞しました。しかし、7年経っても米国は「核大国」のまま。5月にスイスで開かれた国連の核軍縮作業部会でも、米国は核兵器禁止条約の制定に反対し、「核なき世界」の実現は程遠い状況です。
まず、プラハ演説の内容をよく読むと、オバマ大統領が言っていることは2つ。ひとつは「核のない世界へ」というビジョン、もうひとつは「私の目の黒いうちは核廃絶はないだろう」ということ。つまり、核廃絶の理念は掲げるが、すぐにはできない――とハッキリ言っているわけで、実際、この7年間を振り返っても核軍縮に向けた取り組みは何ひとつありません。
――全く何もやっていない?
オバマ大統領が核関連の政策でやったことといえば、核保安サミットを開き、テロリストに核分裂物質が渡らないようにする国際的な仕組みをつくったことぐらい。あとはクリーンエネルギーと称して原発を推進した。しかし、原発はプルトニウムを生み出す機械ですから、潜在的な核拡散です。その意味ではプラハ演説と真逆のことをやったわけです。
――「核なき世界」どころか核を推進した。
そうです。例えば、オバマ大統領は、ミサイル防衛システム(MD)を推進しました。彼はイランや北朝鮮に対抗するため、と言っていますが、本当の“狙い”はロシアと中国です。つまり、MDで先制攻撃を未然に抑え込んで米国の核兵器に絶対的有利な環境を確立しようとしている。その結果、どうなったかといえば、ロシアや中国をますます警戒させることになりました。ロシアのプーチン大統領は米国に対する核攻撃力をさらに高めようとしているし、中国も韓国へのMD配備に神経をとがらせています。そう考えると、オバマ大統領の核政策はマイナス評価しかできません。
――そのオバマ大統領の広島訪問をどう評価していますか。
この7年間、核廃絶に向けた具体的な取り組みは何もなく、当然、実績もない。それをあらためて確認することにもなるため、ある意味、非常に不格好な訪問でした。彼としては、核廃絶の「ビジョン」を繰り返すこと以外、訪問にメリットはなかったと思います。
――それなのになぜ、オバマ大統領は広島に行ったのでしょうか。
私は安倍政権が米国側に積極的に働きかけたのではないかとみています。安倍政権は集団的自衛権の行使を閣議決定し、安保法制をつくった。その結果、米国の戦争に日本が積極的に加担することになりました。日米同盟はNATO(北大西洋条約機構)並みの軍事同盟になったわけです。安倍政権は、日米軍事同盟の完成を祝うセレモニーとして広島訪問を演出した。「日米軍事同盟は平和のため」とアピールするためです。
――日米同盟が強化された“ご褒美”みたいなものですか。
オバマ大統領にとっても決して悪い話ではない。しかも、プラハ演説で始まり、広島演説で終わるということは、「核なき世界」というオバマのビジョンを世界にあらためて発信する効果も期待できる。つまり、広島訪問とは、ありていに言えば、セレモニーであり、アリバイづくりでもあった。だから、原爆資料館もわずか10分そこそこで出てきた。おそらく、入り口近くの大きなパノラマ展示品を見ただけで戻ってきたのでしょう。
――それでも広島県民、市民は歓迎ムード一色でした。
「ノーモア広島」を訴えてきた歴史を考える時、広島市民がもろ手を挙げて喜ぶ姿には違和感を覚えました。まがりなりにも広島は、タテマエは核廃絶を訴えつつ、ホンネは米国の核の傘におんぶにだっこという二重基準の日本政府に対する対抗軸でした。そこに広島の存在理由があり、だから世界の核兵器廃絶運動も広島をメッカと位置付けてきたわけです。
しかし今回、その二重基準の日本政府がお膳立てしたオバマの広島訪問を無条件で受け入れることで、広島は核廃絶運動のメッカとしての立場を自ら捨ててしまった。これは「ノーモア広島」どころか、真逆の方向です。今後、世界の広島を見る目は変わっていくでしょう。
――オバマ大統領の広島演説は「歴史に残る」といわれています。
先ほども言いましたが、核廃絶の実績は何もないため、広島演説はプラハ演説より“退化”せざるを得ませんでした。だから、内容は極めて抽象的で、過去の追憶と理念を17分間話しただけです。あの演説のどこが格調高い優れたものなのか。私には分かりません。
――被爆者の肩を抱く姿もテレビなどで繰り返し報じられていました。
オバマ大統領の人間としてのヒューマニズムにケチをつけるつもりはありません。しかし、米国大統領の広島訪問というものが、あの1枚の写真で美化されるというのは、あまりにも物事の本質のすり替えが行われているような気がします。
――メディアは広島訪問が決まった時から「歴史的訪問」と大騒ぎし、当日はNHKが特番で生中継しました。メディアの取り上げ方、報道のスタンスについてどう見ましたか。
メディアの「ヒロシマ」の取り上げ方はいつも同じで、今回が突出していたわけではありません。つまり、彼らにとって(1945年に広島に原爆が投下された)8月6日というのは、しょせんは「ハチロク」という名の行事、イベントなんです。(広島平和研究所の)所長時代、毎年7月になると、各メディアが「今年の目玉は何ですか」と尋ねてきて閉口しましたが、今回もその延長であり、彼らは特別なイベントとして扱ったと思います。
――メディアは安倍政権発足以降、とりわけ劣化が著しいと指摘されていますね。
今日の日本メディアの体質で、最も病的だと感じるのは、政権側から流れてくる空気に決して抗わず、自己規制する姿勢です。対照的なのは欧米メディアです。権力に対して「報道の自由」という基本的権利を勝ち取ってきた歴史を持っているため、ワシントン・ポストのような保守系メディアであっても、権力が誤った方向に進んでいる――と判断すれば厳しく追及する。
ところが日本メディアはそういう気概がありません。欧米と異なり、「報道の自由」は戦後憲法によって与えられたもので、自ら勝ち取った歴史がないからです。政治的空気が変われば自然と報道姿勢が変わっていく。これが日本メディアの体質なんです。歴史を振り返れば「二・二六事件」で、将校が輪転機に砂をぶっかけた翌日から報道内容が変わっちゃったわけですから。
日本国憲法は世界を脱軍事化に導く指針
――時の権力とメディアが同じ方向を向くと戦前に逆戻りです。また先の大戦のような展開になるのでしょうか。
今の世界は、経済を見れば分かる通り、国際相互依存でがんじがらめの状態です。米中間で銃声が一発鳴り響けば、あっという間に世界はぺしゃんこになる。もはや大国間の軍事衝突はあり得ず、世界は脱軍事化に進まざるを得ません。これは誰でも分かるはずなのですが、残念ながら政治が追い付いていないのです。
そこで今こそ、私は日本の出番だと思っています。日本国憲法は(施行された)1947年当時は「理想の産物」だったかもしれないが、今は世界を導くもっとも現実的な指針です。この憲法に基づき、日本が率先して軍事力を廃止しようと声を上げるべきです。日米軍事同盟を終了すれば、中国の対日姿勢もやわらぐでしょう。日本が率先して非軍事化の声を上げることで世界はガラリと変わっていくと確信しています。
(聞き手=本紙・遠山嘉之)
▽あさい・もとふみ 1941年、愛知県生まれ。東大法中退後、外務省入省。国際協定課長、中国課長などを経て、東大教養学部教授、広島市立大学広島平和研究所所長などを歴任。主な著書に「すっきり!わかる 集団的自衛権Q&A」(大月書店)、「ヒロシマと広島」(かもがわ出版)など多数。
NNNドキュメント 2016年7月31日
隠された被爆米兵 ~ヒロシマの墓標は語る~
http://dai.ly/x4mm5jj
広島の原爆で死亡した12人の‘被爆米兵’。その存在を調べ続けた被爆者がいた。日本とアメリカを取材し彼らの足跡をたどる。今も複雑な思いを抱く遺族の本音とは。
オバマ大統領が広島を訪問し、1人の被爆者と抱擁する映像が全世界に流れた。森重昭さん、広島の原爆で死亡した12人の知られざる‘被爆米兵’の存在を調べてきた。自国民をも犠牲にした原爆。日本とアメリカを取材し‘被爆米兵’らの足跡をたどる。今も複雑な思いを抱く遺族たちの本音とは。そして森さんの願いとは。12人もともに眠る原爆碑に刻まれた「過ちは繰り返しませぬから」-そのために私たちは今、何をすべきか。
ヒロシマの記憶 原発の刻印
http://www.yuubook.com/center/hanbai/syoseki_syousai/syousai_hiroshimaki.html
肥田 舜太郎 著
被ばくの歴史の「学び」
それなくして未来はない。
ヒロシマ・ナガサキに原爆を投下された日本に、どうしてこれだけの原発が建っているのか?
どうして一部の政治家が日本は核武装すべきだと公言して、それが野放しになっているのか?
原爆被害の生き証人である肥田舜太郎の実体験から学ぶ、核の本質、原爆の地獄。
「核は、人が死ぬからだめなんだと、そう言おう」
広島原爆の被爆者の診療に軍医としてあたって以来、今日まで世界各地の放射線被害を見続け、被ばくを広島・長崎への原爆投下を起点として、歴史的にとらえていくことの大切さを訴えてきた貴重な証言者、被爆医師・肥田舜太郎、渾身のメッセージ。
目次より
●「ヒロシマの記憶 原発の刻印」
●「戦後にっぽん「放射線安全ムラ」形成史」(特別寄稿 堀田伸永)


原爆体験記
256頁
なにを記憶し, 記憶しつづけるべきか?
大江健三郎
われわれがこの書物を読み、この書物にみなぎっている人間的な叫び声を忘れさってしまうとしたら、それはわれわれが、今日の核兵器の問題のはらんでいる悲惨と恐怖とにおびえるあまり、意識してそれを回避したとみなすべきだということを、ぼくは強調しておきたいと思います。その場合、すべての責任はわれわれにあり、そうしたわれわれを、弁護できるものはいないでしょう。それこそは戦後二十年の歴史において、広島・長崎の原爆の経験をもつ日本人がみずからに対しておこなう、最悪の背信行為というべきではありますまいか?
小出裕章先生:曇りのない目で事実を見てほしい / そなたたちの母を殺したのは戦争(原爆)である
自由なラジオ Light Up! 019回
「 自然エネルギーなら戦争は起きない。原発ゼロの先を行け! ~『弱い人、困っている人を助ける弁護士』が気づいたこと 」
https://youtu.be/Gwb3nh55l9Q?t=18m33s
第019回Light UP!ジャーナル
身近な放射線管理区域とその情報公開のあり方
http://jiyunaradio.jp/personality/journal/journal-019/
木内みどり:
今日も元京都大学原子炉実験所の小出裕章さんにお電話でお話を伺います。こんにちわ、小出さん。
小出裕章さん:
はい。こんにちわ、みどりさん。
木内:
ありがとうございます。まず、参議院選挙、本当に熱い熱い選挙が終わりましたけれども、鹿児島県知事に脱原発の知事が誕生したのは嬉しかったですね。

小出さん:
そうですね。全体で言えば、本当に悲しくなるような結果でしたけれども。
木内:
本当です。
小出さん:
鹿児島県知事選で脱原発の方が当選して下さいましたし、沖縄、福島とかで、現職を破るような形になって、大変そういう事に関してはよかったと思います。
木内:
嬉しいことだけ大きく見て、悲しいことはちょっと小さめに感じようと私も決意しました。
小出さん:
はい。そうですね。私もそうしたいです。
木内:
今日は、このことについてお伺いします。京都大学附属病院で火事があったそうなんですね。7月1日のことのようです。
https://youtu.be/cEBnMcVHlKU
放射線物質を扱う実験室が全焼、で、この火災によって放射線がでたようなんですけれども。その放射線量の測定が、火事が鎮圧してからなんと4時間後で、それを公表されたのが3日後という対応だったそうなんですね。この原子力関連施設の情報公開のあり方、そのスピードについて小出さんにお伺いしたいんですが、どう思われますか?

小出さん:
一言で言えば、もっと迅速にすべきだなと思いますけれども、病院にはいわゆる放射線管理区域というものが結構あります。例えばX線の撮影室であるとか、CTの撮影室であるとか、そういう所は放射線の管理区域なのです。

ただし、それは放射線の管理区域であって、そこで放射性物質を取り扱っているようなことはないのです。今回火事になった所は、放射能そのものを取り扱うというそんな実験室だったのです。
木内:
火災があった7月1日の午後11頃に放射線量を調べましたら、いっとき毎時16シーベルトあったと言うんですけれども。
小出さん:
今、みどりさんが16シーベルトとおっしゃいましたけれども、単位がちょっと違っていまして、正確に言うと、毎時16マイクロシーベルトです。マイクロですから、100万分の1という意味ですね。いわゆる放射線物質、放射線を取り扱うという現場では、時に、この程度の放射線量率は存在しています。
例えばですね、日本の法律で言うと、1時間あたり0.6マイクロシーベルトを超えるような場所は放射線管理区域にしなければいけません。私がいた京都大学原子炉実験所でも、1時間あたり0.6マイクロシーベルトを超えるような場所は管理区域です。管理区域の中でも高い低いがある訳ですけれども、1時間あたり20マイクロシーベルトを超えるような場所は、高線量区域と呼んで、実験者に注意を促して、立ち入り制限をするとかいうことを私の職場ではやっていました。ですから、1時間あたり20マイクロシーベルトなら高線量区域にした訳ですから、今回の場合は、1時間あたり16マイクロシーベルトなので、かなり管理区域の中でも、放射線量の高いの場所があったということだと思います。ただし、取り扱っていたインジウム111という放射性物質も、

もう1つトリチウムという放射性物質も使っていたのですが、総量がこういう言い方はあまりよくないですけれども、福島の事故なんかに比べれば本当に微々たるものであって、周辺の方々に大きな危害を加えるというような量ではもともとなかったのです。ですから、病院側もそういう事をふまえた上で、まずは火災を鎮火して原因を究明して、それから記者会見ということにしたのだと思いますが、はじめに聞いて頂いたように、やはりもっと迅速にすべきだったなというのが私の感想です。

木内:
はい。ありがとうございました。
それでね小出さん、今日はスタジオに弁護士で映画監督、映画監督で弁護士さんの河合弘之さんがおいで下さっています。いつもいつも小出さんは、「日本の司法に絶望している」と「信じない」と発言されていらっしゃいますけれども、小出さんは河合さんとはもちろん交流は深いですよね?
小出さん:
はい、何度もお会いしています。河合さんも原子炉実験所まで来てくださったこともあります。
木内:
そうですか。
河合さん:
こんにちわ、河合です。どうも。
小出さん:
こんにちわ、ご無沙汰しておりました。
河合さん:
ご無沙汰しております。小出さんのね映画の中で、やっぱり非常に重要な位置を占めてましてね。「原発なんか止めたって、全然電気なんか足りなくないんだよ」と「停電なんておきてないじゃないか」と言うのをね、グラフを以って示してくれて、ああいう分かりやすい説明って凄くねいいんですよね。
小出さん:
ありがとうございます。私も何とかごくごく普通の方々に、曇りのない目で事実を見てほしいと思ってきましたし、その為に、私自身も工夫を凝らしながら、皆さんにどうやって伝えるかと考えてきたのですけれども。でも、河合さんの映画などを見ていると、凄いなあと私も思いました。
木内:
本当ですよね。映画の中で、白板に文字を書きながら説明したっていうのは、もう前代未聞だったと思いますけれども。
河合さん:
あれはね、アル・ゴアのまねなんだよ。アル・ゴアの「不都合の真実」で。
木内:
なるほど。不都合の真実で。なるほど。そんな事言わなければ分からないのに。河合さん。というわけでした。今日も、小出裕章さん、ご出演ありがとうございました。また、出てくださいね。
小出さん:
はい、よろしくお願いします。
木内:
ありがとうございました。
○●○●○●○●○●

平和の泉
のどが渇いてたまりませんでした
水にはあぶらのようなものが
一面に浮いていました
どうしても水が欲しくて
とうとうあぶらの浮いたまま飲みました
―あの日のある少女の手記から
ロザリオの鎖
永井隆
ロザリオの鎖 より(原爆投下、そのとき…)
八月八日の朝、妻はいつものように、にこにこ笑いながら私の出勤を見送った。少し歩いてから私はお弁当を忘れたのに気がついて家へ引き返した。そして思いがけなくも、玄関に泣き伏している妻を見たのであった。
それが別れだった。その夜は防空当番で教室に泊まった。あくる日、九日。原子爆弾は私たちの上で破裂した。私は傷ついた。ちらっと妻の顔がちらついた。私らは患者の救護に忙しかった。五時間ののち、私は出血のため畑にたおれた。そのとき妻の死を直覚した。というのは妻がついに私の前に現われなかったからである。私の家から大学まで一キロだから、這って来ても五時間かかれば来れる。たとい深傷を負うていても、生命のある限りは這ってでも必ず私の安否をたずねて来る女であった。
三日目。学生の死傷者の処置も一応ついたので、夕方私は家へ帰った。ただ一面の焼灰だった。私はすぐに見つけた。台所のあとに黒い塊を。──それは焼け尽くして焼け残った骨盤と腰椎であった。そばに十字架のついたロザリオの鎖が残っていた。
焼けバケツに妻を拾って入れた。まだぬくかった。私はそれを胸に抱いて墓へ行った。あたりの人はみな死に絶えて、夕陽の照らす灰の上に同じような黒い骨が点々と見えていた。私の骨を近いうちに妻が抱いてゆく予定であったのに──運命はわからぬものだ。私の腕の中で妻がかさかさと燐酸石灰の音を立てていた。私はそれを「ごめんね、ごめんね」と言っているのだと聞いた。

長崎原爆爆心地標識

長崎原子爆弾落下中心地碑版
NHKスペシャル 2014年8月9日
「知られざる衝撃波 ~長崎原爆・マッハステムの脅威~」
https://youtu.be/6K2rY3QP97Y
69年前の夏、長崎を襲った原子爆弾。町も建物もことごとく壊滅したため調査の糸口がなく、その詳しい破壊のメカニズムはわかっていなかった。そうした中、去年(2013年)、長崎原爆の破壊力を解明する手がかりが見つかった。
原爆投下直後に長崎入りした学術調査団が残した34点の写真。
着目しているのは爆心直下ではなく、爆心500m地点だ。爆心地の500m先で突如、爆風の威力を増幅させる圧力波「マッハ・ステム」が立ち上がり、破壊力を増した爆風がドーナツ状に壊滅的被害を広げていく様を捉えていた。
爆心地の西500m、旧・城山国民学校を写した1枚は、鉄筋コンクリート建て校舎が湾曲し、厚いコンクリート壁が跡形もなく粉砕されている。死者138人。遺体の半数近くが爆風によって激しく損壊していた。
番組では、新たに発掘した写真や証言記録などをもとに、138人が死亡した城山国民学校の惨状をCGで再現、長崎原爆の破壊メカニズムを徹底的に分析。
69年前のあの日、爆心500mで何が起きていたのか。核兵器の非人道性の原点に迫る。
慶大研究員・高山真さん調査
聞き手が「被爆者になる」
長崎の語り部から見えてくる「継承」
(東京新聞【こちら特報部】)ニュースの追跡 2016年8月8日
被爆七十一年の広島や長崎は、語り部が高齢化から減り、記憶の継承が課題となっている。長崎の被爆者から長年、聞き取り調査をしてきた慶応大大学院の訪問研究員、高山真さん(三七)=写真=は、ある語り部の「被爆者になる」との言葉に注目する。
(三沢典丈)

高山さんは長崎大の学生当時、平和団体主催の中国ツアーに参加した。そこで慰安婦の証言を聞いたことをきっかけに「本来なら語りたくない極限的な体験をした人が、それをどう言葉にするのか」に興味を持ち、二〇〇五年から長崎の被爆者たちから聞き取り調査を始めた。0八年から六年間は、長崎に転居して取り組んだ。
高山さんはまず二人の語り部に注目した。十三歳の時、爆心地から一・三㌔で被爆して母親や友人を亡くしたTさんと、八歳の時に爆心地から四・三㌔で被害に遭ったものの、家族などは無事だったYさんだ。
Tさんは、自らの体験を芝居でリアルに再現しようとしていたのに対し、Yさんは自分や自分より悲惨な被爆者の証言と、遺構めぐりを組み合わせ、平和教育として行っていた。
広島の被爆者の研究からは、より爆心地の近くで、より高い年齢で被爆した人ほど、「体験の価値」が高いという一種の序列が意識され、語り方にも影響することが分かっている。
高山さんは「長崎の被爆者も同様の序列を意識しており、TさんとYさんの語り方の違いとして端的に表れていた」と語る。
二人とも体験の継承に熱心な語り部だったが、高山さんは調査を続けるうちに「Tさんは、忠実に体験を再現するあまり、当時を知らない人からは、特別な存在と見なされてしまう傾向がある。一方、Yさんの語りは分かりやすいが、平和の大切さを伝えるという理念に傾く分、自分固有の体験が埋没してしまう。どちらも、十分に被爆体験が伝えられない可能性がある」ことに気づいたという。
この二つの代表的な方式を乗り越える語り方はあるのか。その問いにヒントを与えてくれたのが、十五歳のときに爆心地から四・八㌔で被ぱくしたMさんだった。自分の体験でも極度に深刻にならず、距離を置いて話す姿勢にひかれ、何度も会ううちに、Mさんは自分の生き方を「被爆者になる」と表現した。
もちろん、被爆者援護法上の意味ではない。高山さんは最初、意味が分からなかったが、やがて「自分の体験を語るだけでなく、他の被爆者の話も聞き、心の傷に思いを寄せるなどして自らの被爆体験を深め、生き方に反映させること」だと分かったという。
高山さんの近著「〈被爆者〉になる」(せりか書房)は三人の被爆者との十年にわたるインタビューの分析から、被爆体験を継承する可能性に迫った。今後、語り部から被爆体験を聞く人に、こう助言する。
「語り部に同情したり、平和の大切さを確認するだけで終わりにしない。わずかでも、自分の意識が変化した部分を捉え、そこから自分の生き方を見つめ直すことが大事だ。それが、被爆者とのコミュニケーションの回路を開くことにつながる」
高山さんの提案は、聞き手自身が「被爆者になる」試みともいえそうだ。

原爆により崩れ落ちた浦上天主堂の鐘楼
ETV特集 2016年8月6日
54枚の写真~長崎・被爆者を訪ねて~
http://dai.ly/x4nkji4
去年、アメリカ国立公文書館で、長崎の被爆者を写した54枚の写真が発見された。ある女性は、泣いているような表情で、まっすぐカメラを見据えていた。ケロイドをさらした少年の姿もあった。敗戦直後の1946年、47年、写真は何のために撮影されたのか。担当したABCC(原爆傷害調査委員会)は、その後、放射線影響研究所となり、放射線リスクの基準作成に携わっていた。54枚の写真をもとに被爆者たちの戦後を訪ねていく
Medical Aspects of the Atomic Bomb, Nagasaki, Japan, 11/12/1945
(長崎原子爆弾投下の医学的側面)
https://youtu.be/G4-nNQTYmmo
語り続ける原爆小頭症の患者さんたち
(東京新聞【こちら特報部】)2016年8月7日
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2016080702000153.html
「原爆小頭症」を知っているだろうか。広島、長崎に原爆が投下された際、母親の胎内で被爆した人たちだ。今年で七十歳を迎えた最も若い被爆者たちだが、戦後の差別で近親者たちが隠したこともあり、あまり理解されてこなかった。全国に十九人いる認定患者の一人、吉本トミエさん(70)は六日、広島市内で「私のような苦しみが二度と生まれないように」と、原爆に翻弄(ほんろう)された人生を若者らに語った。
(安藤恭子)
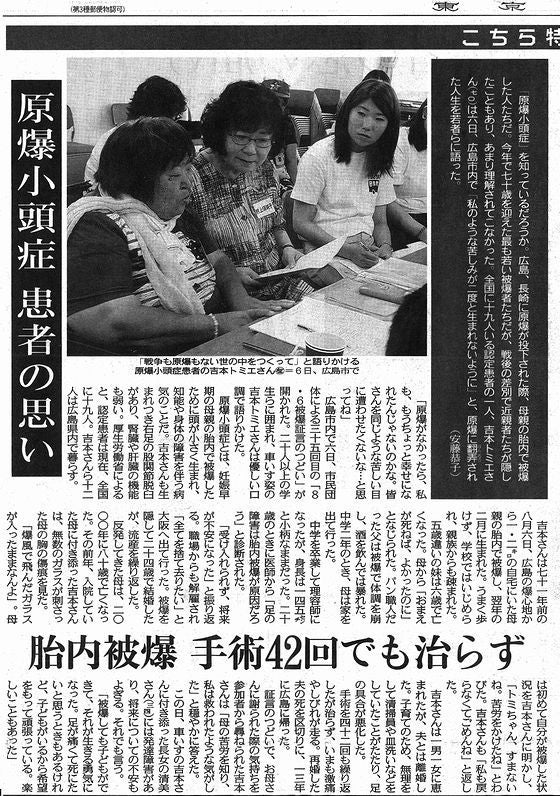
胎内被爆手術42回でも治らず
「原爆がなかったら、私も、もうちょっと幸せになれたんじゃないのかな。皆さんを同じような苦しい目に遭わせたくないな…と思ってね」
広島市内で六日、市民団体による三十五回目の「8・6被爆証言のつどい」が開かれた。二十人以上の学生らに囲まれ、車いす姿の吉本トミエさんは優しい口調で語りかけた。
原爆小頭症とは、妊娠早期の母親の胎内で被爆したために頭が小さく生まれ、知能や身体の障害を伴う病気のことだ。吉本さんも生まれつき右足の股関節脱臼があり、腎臓や肝臓の機能も弱い。厚生労働省によると、認定患者は現在、全国に十九人。吉本さんら十二人は広島県内で暮らす。
吉本さんは七十一年前の八月六日、広島の爆心地から一・二㌔の自宅にいた母親の胎内で被爆し、翌年の二月に生まれた。うまく歩けず、学校ではいじめられ、親族からも疎まれた。
五歳違いの妹は六歳で亡くなった。母から「おまえが死ねば、よかったのに」となじられた。パン職人だった父は被爆で体調を崩し、酒を飲んでは暴れた。中学二年のとき、母は家を出て行った。
中学を卒業して理容師になったが、身長は一四五㌢と小柄なままだった。二十歳のときに医師から「足の障害は胎内被爆が原因だろう」と診断された。
「受け入れられず、将来が不安になった」と振り返る。職場からも解雇され「全てを捨て去りたい」と大阪へ出て行った。被爆を隠して二十四歳で結婚したが、流産を繰り返した。
反発してきた母は、二〇〇〇年に八十歳で亡くなった。その前年、入院していた母に付き添った吉本さんは、無数のガラスが刺さった母の胸の傷痕を見た。
「爆風で飛んだガラスが入ったままなんよ」。母は初めて自分が被爆した状況を吉本さんに明かし、トミちゃん、すまないね。苦労をかけたね」とわびた。吉本さんも「私も戻らなくてごめんね」と返した。(;_;)
吉本さんは一男一女に恵まれたが、夫とは離婚した。子育てのため、無理をして清掃員や皿洗いなどをしていたことがたたり、足の具合が悪化した。
手術を四十二回も繰迴返したが治らず、いまも激痛やしびれが走る。再婚した夫の死を区切りに、一三年に広島に帰った。
証言のつどいで、お母さんに謝られた際の気持ちを参加者から尋ねられた吉本さんは「毋の苦労を知り、私は救われたような気がした」と穏やかに答えた。
この日、車いすの吉本さんに付き添った長女の清美さん(三四)には発達障害があり、将来についての不安もよぎる。それでも言う。
「被爆しても子どもができて、それが生きる勇気になった。足が痛くて死にたいと思うときもあるけれど、子どもがいるから希望をもって頑張っている。楽しいこともあった」

「同じ苦しみ生まぬように」
貧困、差別、死への恐怖…
つどいには、広島市の原爆小頭症患者で、知的障害と身体障害がある川下ヒロエさん(七〇)も参加した。
〽ฺ原爆ドームに やっと光が届く
小さな花も 命の限り咲いている
ガレキの中でそっと 母子草の花も咲く
この小さな花たちの 命を消さないでね
一四年に九十二歳で亡くなった母の兼子さんを思い、川下さんが書いた詩だ。メロディーをつけた歌のCD「この小さな花たちの」が会場に流れ、吉本さんが口ずさむと、川下さんはぼろぼろと涙を流した。
吉本さんらの話に聴き入った広島文化学園大学一年の森脇未来さん(ニー)は「障害だけじゃなく、いじめとか家族とのけんかとか…。原爆は病気だけでなく、人生にも影響するものだと知った」と感想を述べた。
新潟市の中学三年、堀川夏実さん(一五)は「自分が一緒に人生を体験しているように感じ、苦しくなった」と声を落とし、京都市の佛教大学四年、木村史奈さん(ニー)は「生きていく強さを感じた。もっと体験を聞いてみたい」と語った。
「小頭症の患者たちは、原爆の惨禍を見たわけじゃない。でも、被爆二世でもない。お母さんのおなかの中で一緒に放射線を浴び、複合的な障害を受け、社会の冷たい目を浴びた。原爆を語れなかった患者たちの生活の苦悩もまた、原爆の被害の証しなんです」
この日のつどいの司会を務めた村上須賀子・元県立広島大教授(七一)=同県廿日市市=はそう話す。
患者らの話を聞いて悩みを軽減する医療ソーシャルワーカー(MSW)として、延べ二万人以上の被爆者と接してきた。三十三年前からは、小頭症患者と家族でつくる「きのこ会」の活動も支援してきた。
原子雲の下で生まれた命でも、元気に育ってほしい-。きのこ会はこんな思いから名付けられた組織だ。発足は一九六五年。会の母親たちは全員、爆心から一・五㌔ほどで被爆した人たちだった。六月の総会で誕生日を祝うのが恒例となっており、今年も患者九人が集まり、そろって七十歳の誕生日を喜んだ。
小頭症の患者には母子家庭が多かった。きのこ会は、差別や偏見による親の孤立を交流で解消するとともに、国の援護拡大や核廃絶を求めて活動してきた。
同会の要請もあって、小頭症は原爆投下から二十年以上たった六七年、「近距離早期胎内被爆症候群」という名で、ようやく国の認定対象となった。
村上さんは「小頭症の症状は多様で、個人差も大きい」と指摘する。吉本さんのように子どものいる患者もいれば、重度の障害があり、自立できない患者もいる。村上さんは必要な患者への支援を行政に要望し、小頭症の子とその家族の生活史を記録に残そうと努めてきた。
老い迎え生活の支援課題に
「きのこ会の母親の大半は、自らも被爆の不安を抱える中で、障害のある子を産むことになった。貧困や差別を受け、家族はばらばらになり、死への恐怖もずっと付きまとう。原爆がちたらすものは、障害にとどまらない」
きのこ会の親たちは既に全員が亡くなったという。小頭症の患者が老いを迎えている現在、どのように今後の生活を支援していくかが課題になっている。村上さんはこう訴えた。
「爆弾を落とすのは、簡単なことだろうが、その被害はずっと続いている。原爆を背負い、生まれてきた小頭症の患者たちの長い人生を誰が見てくれるのか。患者たちが味わってきた戦後の苦悩を記録し、伝えていくことは、次の世代を支え、核を廃絶する力になると信じている」

NHKスペシャル 2016年8月6日
「決断なき原爆投下~米大統領 71年目の真実~」
http://dai.ly/x4nn2lb
「原爆投下は戦争を早く終わらせ、数百万の米兵の命を救うため、2発が必要だとしてトルーマンが決断した」。
アメリカでは原爆投下は、大統領が明確な意思のもとに決断した“意義ある作戦だった”という捉え方が今も一般的だ。その定説が今、歴史家たちによって見直されようとしている。
アメリカではこれまで軍の責任を問うような研究は、退役軍人らの反発を受けるため、歴史家たちが避けてきたが、多くが世を去る中、検証が不十分だった軍内部の資料や、政権との親書が解析され、意思決定をめぐる新事実が次々と明らかになっている。
最新の研究からは、原爆投下を巡る決断は、終始、軍の主導で進められ、トルーマン大統領は、それに追随していく他なかったこと、そして、広島・長崎の「市街地」への投下には気付いていなかった可能性が浮かび上がっている。それにも関わらず大統領は、戦後しばらくたってから、原爆投下を「必要だと考え自らが指示した」とアナウンスしていたのだ。
今回、NHKでは投下作戦に加わった10人を超える元軍人の証言、原爆開発の指揮官・陸軍グローブズ将軍らの肉声を録音したテープを相次いで発見した。そして、証言を裏付けるため、軍の内部資料や、各地に散逸していた政権中枢の極秘文書を読み解いた。
「トルーマン大統領は、実は何も決断していなかった…」
アメリカを代表する歴史家の多くがいま口を揃えて声にし始めた新事実。71年目の夏、その検証と共に独自取材によって21万人の命を奪い去った原爆投下の知られざる真実に迫る。
いとし子よ
永井隆
より
「いとし子よ。
あの日、イクリの実を皿に盛って、母の姿を待ちわびていた誠一よ、カヤノよ。お母さんはロザリオの鎖ひとつをこの世に留めて、ついにこの世から姿を消してしまった。そなたたちの寄りすがりたい母を奪い去ったものは何であるか?――原子爆弾。・・・いいえ。それは原子の塊である。そなたの母を殺すために原子が浦上へやって来たわけではない。
そなたたちの母を、あの優しかった母を殺したのは、戦争である。」
「戦争が長びくうちには、はじめ戦争をやり出したときの名分なんかどこかに消えてしまい、戦争がすんだころには、勝ったほうも負けたほうも、なんの目的でこんな大騒ぎをしたのかわからぬことさえある。そうして、生き残った人びとはむごたらしい戦場の跡を眺め、口をそろえて、―戦争はもうこりごりだ。これっきり戦争を永久にやめることにしよう!
そう叫んでおきながら、何年かたつうちに、いつしか心が変わり、なんとなくもやもやと戦争がしたくなってくるのである。どうして人間は、こうも愚かなものであろうか?」
「私たち日本国民は憲法において戦争をしないことに決めた。…
わが子よ!
憲法で決めるだけなら、どんなことでも決められる。憲法はその条文どおり実行しなければならぬから、日本人としてなかなか難しいところがあるのだ。どんなに難しくても、これは善い憲法だから、実行せねばならぬ。自分が実行するだけでなく、これを破ろうとする力を防がねばならぬ。これこそ、戦争の惨禍に目覚めたほんとうの日本人の声なのだよ。」
「しかし理屈はなんとでもつき、世論はどちらへでもなびくものである。
日本をめぐる国際情勢次第では、日本人の中から憲法を改めて、戦争放棄の条項を削れ、と叫ぶ声が出ないとも限らない。そしてその叫びがいかにも、もっともらしい理屈をつけて、世論を日本再武装に引きつけるかもしれない。」
「かけがえのない命」なはずなのに… 許されぬダブルスタンダード「生存権」と「優生思想」

ナチスが作ったプロパガンダポスター
「この立派な人間が、こんな、我々の社会を脅かす病んだ人間の世話に専念している。我々はこの図を恥ずべきではないのか?」
相模事件を考える
竹内章郎
重度障がい者との日常
優生思想の克服
学問文化(しんぶん赤旗)2016年8月9日
神奈川県相模原市の津久井やまゆり園で重度障がい者が殺傷された惨禍。以前は「普通」に-何が「普通」かは本当は難しい-障がい者と接していたらしい元職員が、重度障がい者の人権無視や殺害を正当化するに至ったのだから、ナチスだけには限られない優生思想の問題は深刻だ。

ナチスだけか
意外に思われるかもしれないが、英国の社会保障制度の土台となる「ペバレッジ報告」(1942年)を作ったW・ペバレッジは、最低収入に値しない欠陥ある人の隔離収容と彼らからの自由や生殖の権利の剥奪を力説した。漸進的な社会主義的改革を目指したフェビアン協会の中心人物シドニー・ウェッブらも、自らを優生主義者だと公言し、産業社会に役立たない人を消耗品扱いしてその排除を主張した。
『青鞜』で有名な平塚らいてふが、「普通」に生活できない子どもの出生は大きな罪悪だとし、福沢諭吉が人間の産育を家畜改良と同じにせよと言うなど(同じ発言は電話の発明者ベルにもある)、「不適合者」の排除思想である優生思想は広くはびこっており、効率至上の現在の新自由主義の人間観とも結びつく。
米豪由来の生命倫理学で、IQ20以下の存在は人間ではなく殺しても殺人ではないと明言したJ・フレッチャーの優生思想は、”重度障がい者は人間の皮をかぶった物だ”と言った相模原事件の犯人の発言そのものでもある。
もちろん「不適合者」の排除とはいっても、殺傷にまで至るか、施設などに隔離しての貧困なケアの強要にとどまるかではかなり違うが、今回の惨禍の背後にある優生思想は、僕たち自身をも捉えかねない。
共同の豊かさ
そこで優生思想の克服を本当に考えるための一助として、身近に重度障がい者と接するものとして、障がい者を巡る日常が「普通」になること、またその豊かさにふれたい。そんな話があまり知られていないことも優生思想がはびこる要因の一つだと思うからである。
「優秀」な介助者ならくみ取れる意思を示すとはいえ、通常の言語的な意思疎通はままならず、食事や衣服の着脱はもちろん排泄も一人ではおぼつかない、それこそIQ20もない重度の知的障がいをもつ彼。彼が僕によりかかってテレビアニメに夢中な中、臭ってきた。ああ、やったなあ、と大便の後始末が頭に浮かび、直前の少し尻を浮かせるサインの見逃しを悔やんで、やれやれと思う。
けれど、やれやれと思う仕事が誰にでもあるように、この思いも当たり前で「普通」となる日常がある。「駄目でしよ、トイレでしよ」と僕に叱られる彼は、少し困惑しつつもオウム返しに「おトイレよー」と二コニコ顔で言い、便座に座って脚を広げ協力してくれる。だから便の拭き取りなども、手間はかかるが、信頼の視線を感じる僕のほほ笑みを誘う共同作業となる。
どんな共同作業にもあり得る協力の楽しさを、彼との生活に慣れた僕は実感するし、そんな中で排泄の場の大切さを学びもする。
腰や脚の付け根にもおよぶ軟便の処理には、確かにため息をつくこともあるが、その場合はトイレ後の風呂で、汚れに彼の手が触れないように工夫しての洗浄となる。洗われる彼が浮かべる気持ち良さそうな表情は、自然と理屈抜きに僕にも伝播する。
そこには忙しさに追い立てられる生活とは全くちがう、ゆったりとした時間・空間のもたらす癒やしや豊かさがある。真夏の今頃なら、ついでに一緒にシャワーを浴びて一緒に心地良くもなる。汚い話で恐縮だが、大便を巡ってやれやれと思うようなことの中にも、「普通」の楽しい共同の営みや心地良さがある。
重度障がい者とのこんな「普通」の生活の積み重ねから(特に彼らに直接関わる人たちによって)紡ぎ出される新たなコミュニケーション技法やより豊かな文化がなければ、優生思想の本当の克服と真の共生は難しいのだと思う。
相模原障害者施設殺傷事件
雨宮処凛さん
「かけがえのない命」
時に値踏みされ
二重基準まかり通る
(東京新聞)2016年7月31日
十九人という戦後最多の死亡被害者を出した相模原の障害者施設殺傷事件をどうみるか。現場なども取材した上で、作家・活動家の雨宮処凛さんに寄稿してもらった。

叔母がこの事件を目にしなくて、よかった。
事件の第一報を聞いた時、思った。今年六月、肺がんで亡くなた叔母は、長らく障害者の権利向上を求める運動に携わってきた。それは自らの娘が知的障害を抱えていたからで、私のいとこにあたるHちゃんは十数年前、二十代の若さで短い生涯を終えた。
身体は健康だったのに、たまたま風邪の菌が脳に入ったとかそんなことで、急激に体調が悪化。救急車を呼ぶものの「知的障害の大は受け入れられない」と病院に拒否された。自分の状況を説明できないからだという。
結局、翌日に受け入れ先の病院か見つかった時には既に手遅れの状態で、数日後に亡くなった。
今回の事件では、十九人の命が失われた。あまりにもむごく、今でも信じられない思いでいる。同時に、報道などで繰り返される「かけがえのない命」「命は何よりも大切」という言葉にうなずきながらも、ふとした違和感も覚える。この社会は、果たして本当に「命」を大切にしてきたのだろうかと。
「ああいう人って人格かあるのかね」「ああいう問題って安楽死なんかにつながるんじゃないかという気がする」
この発言は一九九九年、東京都知事になったばかりの石原慎太郎氏が障害者施設を訪れた際に発した言葉だ。
一方、今年六月、麻生太郎副総理は高齢者問題に触れ「いつまで生きるつもりだよ」などと発言。また、二〇〇八年には「たらたら飲んで食べて、何もしない人の医療費をなぜ私か払うんだ」という発言もしている。
「かけがえのない命」と言われる一方で、その命は常にお金とてんびんにかけられる。費用対効果などという言葉で「命」は時に値踏みされ、いかに利益を創出したかが人の価値を計る唯一の物差しとなっているかのようなこの社会。
ちなみに、これまで障害者の事故死などを巡る裁判で、彼らの逸失利益(将来得られたはずの収入など)は「ゼロ」と算定されるケースがままあった。重度障害者の場合、「働けない」とされてしまうからだ。逸失利益ゼロが不当として提訴した障害者の母親は「生きている価値がないのかと屈辱的だった。働くことだけか人間の命ではない」と述べている。
この国には、このように、命に対するダブルスタンダードがまかり通っている。
軽く扱われているのは障害者の命だけではない。「健常者」だって過労死するまで働かされ、心を病むまでこき使われ、いらなくなったら使い捨てられる。その果てに路上にまで追いやられた人を見る人々の視線は、優しいとは言い難い。
事件から三日後、犠牲になった方々が生活していた津久井やまゆり園を訪れた。山を切り開いたような住宅街の中、緑に囲まれたのどかな場所だった。容疑者の住む家はそこからわずか車で五分ほど。深夜、容疑者はどんな思いで車を走らせ、施設に向かったのだろう。コンビニさえ辺りにない寂しい集落で、彼の悪意はどのように熟成されていったのだろう。
「死刑になりたかった」のではない。「誰でもよかった」のでもない。彼は衆院議長への手紙で「日本国と世界平和のために」とまで書いている。
痛ましい事件が起きた時だけ「命は大切」と言うのはもうやめよう。日頃から、社会が、そして政治が、私たち一人一人が命を大切にする実践をしなければならない。「稼いでいない者」をお荷物扱いするような言説を見つければ声を上げ、自分の中に、近しい誰かの言動の中に差別やヘイトクライムの芽がないか、心を配ろう。
最後に。容疑者の手紙の言葉に対して全メディアにもう少し配慮した報道を望みたい。新型出生前診断が注目されたころ、あるダウン症の子どもは「自分は生まれてこないほうがよかったの?」と口にしたそうだ。
そんなこと、誰にも言わせてはいけない。
自分や誰かの言説に
差別の芽がないか
日頃から、心を配ろう
シリーズ戦後70年 障害者と戦争
ナチスから迫害された障害者たち
(1)20万人の大虐殺はなぜ起きたのか
http://dai.ly/x336fe9
http://www.nhk.or.jp/heart-net/tv/calendar/2015-08/25.html
戦後70年の節目に、「障害者と戦争」について考えるハートネットTV・8月のシリーズ。
日本編に続いて舞台をドイツに移します。
600万人ものユダヤ人犠牲者を出したといわれる、ナチス政権によるホロコースト。これを忘れてはならないとする認識は、戦後ドイツの基本です。しかし、ユダヤ人大虐殺の前に、いわば‘リハーサル’として、20万人以上の障害のあるドイツ人らが殺害されたことは同じようには語られてきませんでした。
5年前、ドイツ精神医学精神療法神経学会が長年の沈黙を破り、自分たち医師が患者殺害に関わったことを謝罪したのをきっかけにようやく今、真実に向き合う動きが始まっています。学会は今年の秋に報告書をまとめる予定です。
なぜ、これだけ大量の障害者が殺害されたのか、止めようとした人たちはいなかったのでしょか。そしてなぜ被害者の遺族もこれまで沈黙を保ってきたのでしょうか――。
日本の障害者運動をリードしてきた藤井克徳さんがドイツを訪ね、当時のドイツと今のあり方、日本を見つめ、歴史を繰り返さないために何が必要かを考えます。

ナチスが学校教育で用いた図=「劣等分子の重荷」
「遺伝病患者は、国家に1日あたり5.50マルクの負担をかけている。5.50マルクあれば遺伝的に健康な家族が1日暮らすことができる」――国民が貧しいのは、遺伝的欠陥のある人たちを社会制度によって支えてるからだと教育をした――
(3)命の選別を繰り返さないために
http://dai.ly/x37uto1
http://www.nhk.or.jp/heart-net/tv/calendar/2015-09/15.html
戦後70年の節目に、「障害者と戦争」について考えるハートネットTV夏のシリーズ・ドイツ編の第3回。
ハートネットTVでは8月に、ナチス政権時代、20万人以上の精神・知的障害のあるドイツ人らが殺害されたことや、ユダヤ人迫害が強まる中、ユダヤ人障害者たちを自らの作業所で積極的に雇い、ナチスからかくまったドイツ人視覚障害者がいたことを伝えてきました。
第3回は、現地を訪れ、これらのことを直に取材してきた藤井克徳さん(日本障害者協議会代表・自身も視覚障害)が、ドイツの精神医学会の元会長を直撃。なぜ、これだけ多くの障害者が殺されなければならなかったのか。そしてなぜ、本来命を救うべき医師が加担したのか疑問をぶつけます。また、もっと早く事態を察知し、止めようとする人はいなかったのか-。歴史家や、障害当事者とも対話し、掘り下げます。
“戦後70年”の馴染みのキャラクターも登場。同じ過ちを繰り返さないために、いま私たちが「命の価値」についてどう考えるべきか、時空を超えて問いかけます。
視聴厳重注意
Hadamar Murder Mills(ハダマー 虐殺施設)
https://youtu.be/BWwD8EtvFFU
相模原障害者殺傷事件
意味なき命はない
(しんぶん赤旗)2016年8月5~8日
神奈川県相模原市緑区千木良の障害者施設「津久井やまゆり園」で19人が死亡、26人が重軽傷を負った殺傷事件。犯行そのものの衝撃に加え、逮捕された植松聖容疑者(26)の「障害者に生きている意味はない」という言葉が地域社会や全国の障害福祉に関わる多くの人を深く傷つけ、悲しみを広げています。
(相模原事件取材班)

元職員「日増しに苦しく」
植松容疑者は同園の居住棟に侵入し、移動しながら室内で就寝していた入所者を刃物で次々に襲ったとされます。犠牲者の氏名は発表されていません。園近くに住み、同園で20年以上働いた70歳代の元職員の女性が語ります。
入所者の顔浮かぶ
「あの部屋には誰がいた、この部屋には誰がいた。入所者の顔が次々に浮かぶ。襲われたのか、痛い思いをしたのか。夜、一人で布団にいると考えが止まらず、眠れない。日がたつにつれ、忘れるどころか苦しさが大きくなっていく」
女性の手元に現役時代の数十枚の写真があります。屈託のない笑顔を見せる女性入所者、安心しきった表情で職員らに身を任せる男性入所者。「自分の子のように感じ、接してきた。辞めてからも心は常に近いところにいた」
アイドル的な存在の女性入所者がいました。「言葉は話せない。勦けない。でも名を呼ぶとにこにこっと最高の笑顔で応えてくれる。苦しいことがあるとき、この人に勇気を与えられたという職員は多かった」。その人は無事なのか。容疑者は障害の重い人から襲ったと聞き、苦しさが増します。
同容疑者は衆院議長宛ての手紙で「障害者は不幸を作ることしかできない」と書きました。
長期的ケアが必要
「とんでもない。私たちは入所者に励まされ、なぐさめられ、たくさんのことを教えてもらった。感謝ですよ。そんなあの人たちがどんなふうに死んで行ったかを聞かされたりしたら、きっと立ち直れない」
事件直後に園に呼び出された現職員たちが受けた心の傷の深さも懸念されています。
同園での勤務経験があり、現在は緑区内の別の障害福祉サービスに従事する女性は「職員たちは残った入所者に通常通りの環境を提供しようと、文字通り歯を食いしばっている。でも時折、やりきれない表情を浮かべているのが心配だ。長期的なケアが必要です」といいます。

声なき悲鳴があふれ
「地域に深くとけ込んだ園」「地域と支えあう園」-。事件現場となった神奈川県相模原市緑区の障害者施設「津久井やまゆり園」を、多くの地域住民がこう形容します。
相模湖近く、緑の尾根に、はさまれた川沿いの千木良(ちぎら)地区に同園はあります。1964年に県施設として開所し、2005年からは社会福祉法人が指定管理者として運営しています。
開所後、同園は地域住民を積極的に雇用したといいます。「住民も大学の通信教育やスクーリングなどで障害者福祉を学び、県職員として勤めた。園も地域に開かれた運営に努め、8月の納涼祭などの『三大行事』には地域の人がこぞって参加するようになった」と、1990年まで25年勤務した元職員の石井明光さん(86)は語ります。
「近くの神社に入所者が散歩に出ると、近くの住人が入所者の名を呼んで声をかける」「散歩中の入所者を住民が家に招いて、お茶を飲ませる」などといった光景が珍しくなかったと、複数の住民が語ります。
職員OBも多く
地域には職員OBも多く、今も田畑での作業訓練や破れた衣類のっくろいなどにボランティアとして協力しています。
自身もボランティアとして園に通う元職員の男性(82)は「こういう地域だからこそ、そして逮捕された容疑者が地元の人たったことでなおさら、事件が与えたショックは深い」と話しました。
元職員で、現在は緑区内の別の障害福祉サービスに従事する女性が、住民の心情を説明します。
「外から見ると『戦後最大の殺人事件』という面が強調される。でもここで生活し、障害者と深く関わってきた地域はそれで済まない深い傷を受けた。容疑者のことだって子どものころから知っている。でも今メディアで流れている彼の写真の表情はまるで別人のもの。『なぜ彼はああなってしまったのか』という思いでいる」
事件はまた、障害者福祉に関わる幅広い人に傷を与えています。
自分否定された
事件後初の日曜日の7月31日、やまゆり園前に設けられた献花台に花を手向ける人が絶えませんでした。
広島県からきた運転手の男性(43)は献花してからうずくまり、顔を手で押さえました。精神障害の手帳所持者。涙ぐみながら語りました。
「悲しいですよね。自分が否定されたようで。さまざまな障害のある人たちにとって、この事件はとてもつらい」

社会を変える原動力
相模原事件の植松聖(さとし)容疑者は「障害者はいない方がいい」などと言って、多くの障害者の命を奪いました。
「重度重複障害を持った人たちは″かけがえのない存在”なだけでなく、社会に大きな影響を与えてきたんです」と東京都三鷹市の深沢智子さん(79)は、静かに語ります。
娘の直子さん(50)は生後間もなく受けた頭部手術の後遺症で、歩くことも話すこともできません。都内の入所施設で暮らしています。
「親子教室」活動
かつては、就学前の直子さんが同年代の子らと過ごす障害児支援の施設などの場がなく、智子さんが病院などで親しくなった親子と「親子教室」の活動をはじめました。
同年代の子どもだちと過ごす中で、智子さんら保護者は、重度障害のある子が刺激を与えあい成長・発達することに気づきました。
直子さんは審査を通り、就学できましたが、中には入学できない重度障害児もいた時代でした。
障害が重い子ほど教育が必要と、「すべての子らに教育の機会を」をスローガンに、保護者や教員らと智子さんは、障害児全員就学運動に取り組みました。
行政を巻き込み
東京都は1974年4月から、障害児の全員就学を実施。国は79年から、障害児学校(特別支援学校)教育を義務化しました。
「電車に乗ったことがない。障害があっても電車に乗りたい」。直子さんが入学した都立小平養護学校の児童の言葉がPTAなどを動かし、地域に働きかけ、最寄り駅の西武線小川駅に81年、エレベーターを設置しました。都内沿線では比較的早い設置でした。智子さんは「障害のある子どもたちが親や地域、行政を巻き込みながら社会を変えていった」と振り返ります。
駅構内で車いすやベビーカーが通るのは当たり前の今。ところが、智子さんは当時、17㌔直子さんをベビーカーに乗せて駅ホームを歩いていたところ、駅員に「禁止だ」と呼び止められました。駅長に実情を訴え、使用承認書を発行してもらいました。
智子さんは強調します。「何もできないと思われていた人が、街に出ることで周囲の意識を変え、理解を深めるきっかけづくりに役立っています。誰にでも優しい社会に変える原動力になっているのです」

人権保障理念広げて
「相模原事件を知り最初に頭に浮かんだのは、私が東京地裁で20分ほどかけて意見陳述した内容でした」
東京都三鷹市の深沢智子さん(79)は、こう話します。重度重複障害がある娘の直子さん(50)は、障害者自立支援法違憲訴訟の元原告です。障害のある人に必要なサービスを”益”として自己負担を強制した同法は、憲法25条の生存権を侵害するなどとして提訴しました。
智子さんは話すことのできない直子さんに代わり意見陳述を行いました。その中で、重い障害のある子が保護者らを巻き込みながら、障害がある子どもの教育権を獲得し、社会を変えていったと訴えました。
政治の流れの中
智子さんは「私たちは重い障害がある人たちの医療・教育・福祉制度の拡充を求め続けてきました。。障害者はお金のかかる人たちだ”という考え方がなんとなく出てきたのは、小泉『構造改革』が始まり、自立支援法ができたころからです」といいます。
障害が重いほど自己負担も重くなる自立支援法施行後、障害のある人がいる家族の心中事件などが相次ぎました。
「障害福祉だけでなく社会保障全般が、じりじりと憲法25条に照らして後退させられている。この政治の流れの中で、無意識に『障害者はいらない』という考えに結びついていったのでは」と智子さんは危惧します。「再発防止策として、安倍政権は防犯カメラ設置や警備強化を言うけれど、憲法に基づいた人権保障の教育が必要です」
社会に潜む危機
全国障害者問題研究会の荒川智委員長(茨城大学教授)は、植松聖(さとし)容疑者が「障害者が安楽死できる世界を」などと主張していたことにふれ、「障害者や高齢者を『社会にとっての負担、お荷物』とみなす考えは、突き詰めれば容易に障害者は不要とする優生思想、安楽死の肯定につながりうる。『社会保障費の増大』と、危機をあおることが、その触媒となります。こうした発想は社会のいたるところに潜んでいます」と指摘します。
茨城県の教育委員が昨年、「障害児の出産を減らせる方向になればいい」という趣旨の発言をし、批判を浴び辞職しました。荒川さんは「典型例だ」と話し、「こうした発想は、弱い立場に置かれる外国人や生活保護利用者なども攻撃・排斥の対象にする風潮につながる」と指摘します。
そのうえで、こう強調します。「人権保障と発達保障の理念・思想が、社会の隅々まで広がることが重要です」
(おわり)
(この連載は岩井亜紀、安川崇が担当しました)
再び悪夢を繰り返すのか…失ってその”ありがたさ”を痛切に感じても…もう遅いのだ!(・ω・`)
NNNドキュメント'15
9条を抱きしめて~元米海兵隊員が語る戦争と平和~
https://youtu.be/3sotOmJUA6w
戦後70年、日本は国家として他国民を誰一人殺さず、また殺されもしなかった。非戦を貫けたのは、戦争の放棄を定めた憲法9条があったからにほかならない。戦争は、国家間の争いだが、実際に戦闘に携わるのは紛れもなく人間。人殺し、殺し合いに他ならない。アレン・ネルソンさん。ベトナム戦争に従軍した元米海兵隊員だ。戦場で数えきれないくらいの人を殺害し、帰還後PTSDに苦しめられるが、自らの過ちを認めることをきっかけに立ち直った。96年から日本で講演活動を開始した彼が最も大切にしたのが憲法9条。暴力的な方法に頼らない唯一の道は9条の理念にあると訴え続けた。ネルソンさんの半生、証言を通し、‘9条’が日本で、そして国際社会で果たしてきた役割、意味を問い直す。
ネルソン氏:
1996年に来日した時、ある人が日本国憲法の冊子をくれました。第九条を読んだ時、自分の目を疑いました。あまりに力強く、あまりに素晴らしかったからです。
日本国憲法第九条は、いかなる核兵器よりも強力であり、いかなる国のいかなる軍隊よりも強力なのです。
日本各地で多くの学校を訪れますが、子どもたちの顔に、とても素晴らしく美しくかけがえのないものが私には見えます。子どもたちの表情から、戦争を知らないことがわかるのです。それこそが第九条の持つ力です。
日本のみなさんは、憲法に九条があることの幸せに、気づくべきだと思います。

ほとんどの国の子どもたちが、戦争を知っています。アメリカの私の子どもたちは、戦争を知っています。イギリス、イタリア、フランス、オーストラリア、中国、韓国の子どもたち、みんな戦争を知っています。しかし、ここ日本では、戦争を知りません。憲法第九条が、戦争の悲惨さ、恐怖や苦しみから、みなさんを救ってきたからです。ご存知のように、多くの政治家が、憲法から第九条を消し去ろうと躍起になっています。断じてそれを許してはなりません。
みなさんと、みなさんの子どもたちは、これまで憲法第九条に守られてきました。今度はみなさんが、第九条を守るために立ち上がり、声を上げなくてはなりません。第九条は、日本人にのみ大切なのではありません。地球に住むすべての人間にとって、大切なものなのです。アメリカにも九条があって欲しい。地球上のすべての国に、九条があって欲しい。
世界平和はアメリカから始まるのではありません。国連から始まるのでもありません。ヨーロッパから始まるのでもありません。

世界平和はここから、この部屋から、わたしたち一人一人から始まるのです。
Down by the Riverside
https://youtu.be/DVXReRfZCM8
Mahalia Jackson
暴力も憎しみも、河のほとりに置いておこう
戦争はもうごめんだ

まんが・わたしたちの平和憲法
創価学会婦人部平和委員会編 1988年刊

第六章 守ろう憲法のこころ
いま憲法(とくに第九条)が変えられる動きがあります
一人ひとりが憲法に関心をもち、第九条の平和の心を

守っていきましょう








「憲法ぐらい変わっても生活はたいして変わらないと思ってね…」
「だって 新聞やテレビですごく宣伝してたのよ」
「憲法改正の意味もわからないままに投票しちゃったのよ」


「どうなってもみーんな わたしたちの生活には関係ないことと思っていたの」









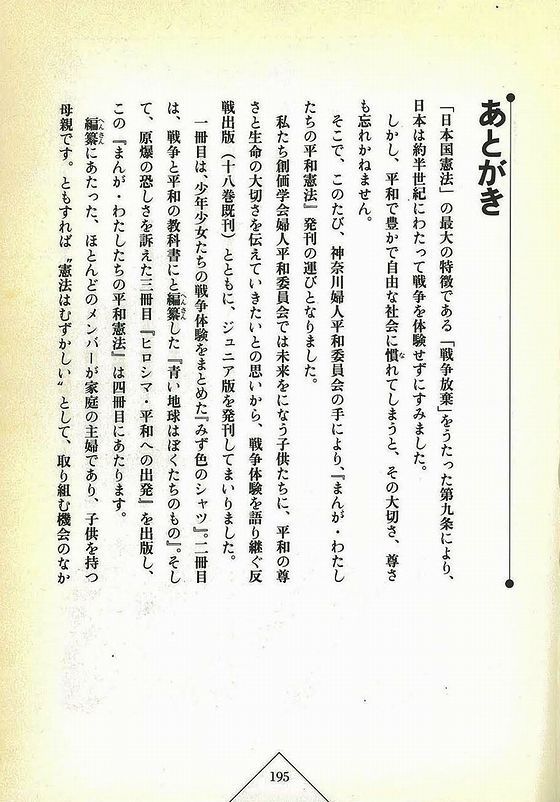

現在の創価学会とは隔世の感ですなぁ…(。-_-。)



アーミテージ元国務長官(左から3人目)と

NHKスペシャル 2015年8月15日
カラーでみる太平洋戦争 ~3年8か月・日本人の記録~
http://dai.ly/x32rh18
1941年12月8日の開戦から4年にわたって続いた太平洋戦争。
その間、各地の戦場での記録映像をはじめ、国内の動きを伝えるニュース、庶民が撮影した銃後の暮らしなど、膨大な映像が残されているが、その大半はモノクロである。
戦後70年にあたり、NHKでは、4年間にわたる「戦争の時代」を記録した映像を国内外から収集。徹底した時代考証を行った上で、最新のデジタル技術を駆使して、映像のカラー化に挑んだ。
フルカラーでよみがえった映像には、雪のアリューシャン列島での行軍から、熱帯の島々での激戦、戦時下の日常や庶民の表情、そして、終戦の日の鮮やかな青空、次の時代に向かってたくましく動き出した人々の姿など、この4年間の日本人の歩みが刻まれている。
番組は当時の人々の日記や手記に残された言葉を織り込みながら、カラー映像で太平洋戦争の4年間を振り返る。
NNNドキュメント 2015年10月8日
祈りの絵筆 ~飢餓地獄を生きのびて~
http://dai.ly/x37e8wl
去年(2014年)、長嶋茂雄さん、山田洋次さん(映画監督)とともに東京都の名誉都民に選ばれた三橋國民(みつはしくにたみ)さん。
72年前、兵士として激戦地ニューギニアで戦った。
そこは飢餓地獄と言われ、多くが餓死した。
帰還後は「鎮魂」と「平和」をテーマに、95歳を目前にした今も、造形作家として創作を続ける。(放送は2015年9月20日)
そして戦後70年の今年、絵筆をとり新たなキャンバスに向き合った。
無謀な戦争を決して忘れない。
三橋さん決意の創作に密着した。
NHKスペシャル 2016年8月14日
村人は満州へ送られた ~“国策”71年目の真実~
http://dai.ly/x4opo90
昭和20年8月、旧満州(中国東北部)。ソ連の侵攻で軍が撤退、取り残された人々は攻撃にさらされ、逃げ惑い、およそ8万人以上が犠牲となり、中国残留孤児など数々の悲劇を生んだ。それが、植民地の治安安定や軍への食糧供給を目的に27万の人々が満州に送り込まれた『満蒙開拓』、移民事業の結末だった。これまで「関係資料は破棄され、人々が渡った経緯は不明」とされていて、その詳細は知られてこなかった。だが、村人を送り出した、ある村長の記録や破棄されたはずの極秘文書が発見され、農村を中心に村人がどのように送りだされたのか実態が明らかになってきた。今回、日記や関係資料の全容取材が許された。また、専門家によって軍や国が『満蒙開拓』にどう関与したかを探る調査も進められている。番組では新たに発見された日記や国側の資料を通じて、国策はいかに遂行され、地方の山村から人々は、なぜ満州へ渡ることになったのか、その真相を明らかにする。
シリーズ戦後71年
忘れられない、雨―認知症と沖縄戦の記憶―
http://www.nhk.or.jp/heart-net/tv/calendar/2016-08/15.html#breadcrumb
Eテレ 2016年8月15日(月曜)
再放送2016年8月22日(月曜)
終戦スペシャルドラマ 2016年07月30日
百合子さんの絵本~陸軍武官・小野寺夫婦の戦争~
http://dai.ly/x4mketf
http://dai.ly/x4mkkdv
昭和16 年―
小野寺百合子(薬師丸ひろ子) は、陸軍武官としてストックホルムに駐在していた夫・信(香川照之) がいるスウェーデンに旅立った。到着したその日から、百合子は夫が入手した極秘情報を暗号化し日本の参謀本部に送る毎日を過ごす事となる。夫婦共同で諜報作業にあたり、機密を守るためだった。
外出の時には必ず見張りがつき、子供の命が危険にさらされる緊張の日々が続いた。百合子は母としての悲痛な気持ちを押し殺し電文を送った。そんなある日、信はヤルタ会談で交わされた連合国の密約の存在を知る。それは「ソ連ガ対日参戦ヲ決メタ」というもの。日本の敗戦を決定づける極秘情報だった。
百合子は、この情報を本国が受け取ればきっと和平に動くと信じ打電し続けた。しかし、小野寺夫婦の情報はついに活かされる事なく、原爆が投下され、日本は敗戦を迎える…。
戦後、百合子は『ムーミンパパの思い出』など児童文学の翻訳に携わる。一方、信は戦時中の事には堅く口を閉ざし、無念の思いで日々を過ごしていた。夫にかつての誇りを取り戻して欲しいと願う百合子は、自分たちはもう1度、過去と向き合うべきだと語る。信は、消えた電文の行方を探る決意をする。
戦争の最前線を生きた稀有な女性の姿を通して描く、夫婦の愛の物語。
【 作 】池端俊策
【原 案】岡部 伸「消えたヤルタ密約緊急電」
【音 楽】千住 明
【出 演】薬師丸ひろ子 香川照之
イヴォ・ウッキヴィ 千葉哲也 利重剛 戸田昌宏 加藤剛 小林勝也 山本龍二 菅田俊 三田村周三 小倉一郎 金田明夫 佐野史郎 吉田鋼太郎 ほか
南東北一人いそぎ旅 :*。・:*≡( _•ω•)
読者の皆さまいかがお過ごしでしょうか?
私が参加しているケイタイ国取り合戦

”ケイタイ国取り合戦”とは一言で言えば、旅好きにはたまらない、電車や旅行の移動で遊ぶ位置情報スタンプラリーでございます(^▽^)
そこで行われる夏のイベント”国盗り2016夏の陣”

国盗り2016夏の陣のポイントゲットのために、お盆休みに日帰りの南東北小旅行してきましたのでご紹介しますね~(^ω^)
元々は大の旅好き・山好き・運転好きの私なのですが、慢性腎臓病を患っているので、近年はたとえ連休がとれても自宅でゴロゴロ静養していることが多いのですね…まあ、お金がないのも理由ですが~(;^ω^)
しかし、せっかく国盗り2016夏の陣が開催中なので、南東北をぐるりと周遊してきました~(((o(*゚▽゚*)o)))
目的地は、三春駅・福島「ねこ稲荷」・蔵王キツネ村・山形「霞城公園」の四ヶ所でございます♪
以前に行ったグルメスポットも紹介しますね(^ω^)
午前5時17分発の普通電車に乗車するべく4時に起床…眠い~( ´O)η ファ~
眠い目をこすりながら新潟駅に到着(´▽`)

早朝の新潟駅

新潟駅万代口改札
おお、私の乗る電車は二番線ですな(^0^)

普通列車長岡行き
もう入線していました。
5:17定刻に発車しました。ここは信越本線。早朝にもかかわらず、さすが夏休み・お盆休みで、乗客は学生と思しき人や家族連れが多いですね~(^0^)
隣の座席にいた若いカップルが朝からイチャイチャしてました…まあ羨ましい(笑)
5:36新津駅に到着。ここで、磐越西線に乗り換えです。

新津駅
ここ新津駅にはある名物が売っているのですよ~(^p^)

三色だんご wikimediaより
私はこの「ごまあん」のものが好きです(^q^)
さて、普通列車会津若松行きが入線してきました。磐越西線は新津-会津若松間が未電化区間となっていますので、乗り込む汽車は気動車でございます。

普通列車会津若松行き
6:01列車発車しました。
新津駅出発から約20分ほど進むと、珍しい名前の駅に到着します。

猿和田駅
「猿和田」ってどんな由来があるのでしょうか?まったく不明です(;^ω^)
猿和田駅の次の駅も珍しい駅名です。

馬下駅
「馬下」の由来は諸説あって、その一つは「義経主従が奥州へ逃れる途中、当地で馬を乗り捨てたことによる」というものです。この説はちょっと怪しいかな?( ´艸`)
「越後から馬でこの地まで来ても、会津に進むには馬上通行不可能なほどの峻険な道のため『馬を下りなければならない』事にちなんでいる」この節は説得力ありそうですね~(^ω^)
さて、馬下を出て約50分。幻の駅弁が売っていた駅に到着しました!

日出谷駅
ここにはですね、朝陽館の「とりめし」が売っていたのでした。知る人ぞ知る日本一入手が難しい駅弁ということだったのですが…販売終了となってしまいました(・ω・`)

日出谷駅弁とりめし
食べたかったですね~(TεT)
さて、日出谷からしばらく行くと、いよいよ福島県に入ります(^-^)/

喜多方北部から会津磐梯山を望む

喜多方駅
ここ喜多方は何といっても喜多方ラーメン(^q^)(^p^)
地元出身の知人のオススメはやっぱり、坂内食堂です。喜多方ラーメンがブームになる前から通っていますが、ブームに火がついてからは入店が厳しくなりましたね(´・_・`)

坂内食堂「肉そば」
全国チェーン展開しているようですが、チェーン店とここのラーメンとはまるで別物です。ぜひここで食べるのをオススメですよ~(´∀`*)
さて、喜多方駅から18分会津若松駅に到着です。

会津若松駅
会津若松は鶴ヶ城や飯盛山、東山温泉など、観光資源が豊かな場所ですね~(゚∀゚)
ブラタモリ「#43 会津」

http://newskei.com/?p=40624
会津のシンボル・若松城(鶴ヶ城)が会津盆地の南東の隅っこにある理由こそ、会津人のアイデア?普通は敵の侵入を防ぐためにつくられる曲がり角・「クランク」を会津人は驚きの使い方をしていた?地質と地形を見抜いて猪苗代湖からひいた全長31キロの用水に潜入!さらにらせん階段が二重になった不思議な建物「会津さざえ堂」へ。知恵と工夫がぎっしりつまった建物の奥深くに秘められた驚きのアイデアにタモリさんビックリ!
グルメとしてはぜひ、田季野をオススメしたいです。

田季野 会席料理 季の膳
少々お値段がはりますが、輪箱飯と会津郷土料理がセットになった会席料理(コース)がいいですよ~(’-’*)輪箱飯が美味かった!( ゚v^ ) オイチイ
さて、会津若松駅9:09発、郡山駅行快速に乗りました。会津若松駅から進むこと約30分、猪苗代駅を出てすぐ、水田地帯を通過。そこから、磐梯山がよく見えます~

猪苗代東から磐梯山を望む
ブラタモリ「#44 会津磐梯山」

http://video.9tsu.com/video/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%BF%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%80%8C%EF%BC%8344_%E4%BC%9A%E6%B4%A5%E7%A3%90%E6%A2%AF%E5%B1%B1%E3%80%8D_7%E6%9C%8816%E6%97%A5
磐梯山といえば「♪会津磐梯山は宝の山よ~」の歌でおなじみ、さまざまな色が楽しめる五色沼や猪苗代湖からのぞむ雄大な風景に年間500万人が訪れる東北を代表する観光地。そんな磐梯山の数々の「宝」の謎を、タモリさんが解き明かします。噴火によって、磐梯山がいまの形になり数々の湖や沼が誕生したのは、実は明治の中ごろ。その秘密ををさぐるため、スキー場の斜面を延々と登ってたどりついた絶景にタモリさんもぼう然…。
ちなみに、磐越西線から猪苗代湖はほとんど見えないです(;^ω^)
さて、猪苗代駅から約30分、郡山駅に到着です。乗り換え時間に少々、余裕がありますので、駅から出てみることにします。

郡山駅
郡山駅前の空間線量が現在はどれくらいなのか…と考えていたら…

郡山駅前空間線量モニタリングポスト
うーん…0.160μSv/hですか…
年間1mSv超えちゃいますよね?( ̄◇ ̄;)
日本政府は放射能から住民のいのちを守らない
矢ヶ崎克馬(琉球大学名誉教授)
http://sanriku.my.coocan.jp/121125yaga.pdf
時間がきましたので、郡山駅構内に戻ります。
11:19発小野新町駅行き普通列車に乗ります。
約12分で三春駅到着です。

三春駅
はい!ここでスタンプゲット!ヤッタネv(=^0^=)v

三春町観光案内看板
ここ三春といえば、全国的に有名なのが”滝桜”ですね~
実際に行ったことがありますが、ものすごくデカイですよ(゚д゚)!

三春滝桜 wikimediaより
さらに、三春といえば三春索麺。

三春そうめん五萬石
五萬石で食べる「エゴマ」たれの索麺は美味かった!
しかし、東日本大震災以前に閉店したんだって…あんなに美味しかったのに、惜しいなあ(´・ω・`)
さて、三春駅から郡山駅に戻り、12:42発福島駅行き普通電車に乗ります。
郡山から46分、福島駅に到着です。福島駅構内でポチっとスタンプゲット!ヤッタネv(=^0^=)v

ねこ稲荷


Σ(゚Д゚ υ) アリャ時間がなかったので、福島で写真撮るのを忘れてしまいました(;^ω^)
13:41発仙台駅行き普通列車に乗り込みます。
福島駅から35分、白石駅に到着しました。さて、ここからが忙しいですよ~

白石駅
白石駅はエリア外なので、宮城蔵王キツネ村方面へ行かないとゲットできないのですね(´ε`;)

宮城蔵王キツネ村 wikimediaより
事前に公立刈田綜合病院がエリア内だという情報を得ていましたので、刈田病院まで行くことにしました。しかし、仙台駅行き電車が発車するまで29分しかないのですね~(>_<)往復距離が約5km!さらに小高い丘の上にあるそうな(・・;)
歩いていてはとっても無理。自転車でも無理?えい!ここはタクシーで往復じゃ!(笑)
白石駅前に客待ちしていたタクシーに飛び乗り、公立刈田綜合病院に向かいました。運転手さんに急いで欲しいと頼んだら、地元の人しかわからないであろう近道を行ってくれて、約7分で到着!ポチっとスタンプゲット!ヤッタネv(=^0^=)v

公立刈田綜合病院 wikimediaより
運転手さんに「白石駅に戻ってください」と告げたら、キョトンとして「え?病院行かないの~?」はい、実は斯く斯く然然といきさつを説明したら笑われてしまいました~┐(´∀`)┌
運転手さん曰く「仕事としては助かりますワ~♪」と快く白石駅に戻ってきました!往復1660円也(^0_0^)
余裕で、14:45発仙台駅行き普通列車に乗り込むことが出来ました~♪
白石駅から約50分、仙台駅に到着です。

仙台駅

伊達政宗騎馬像
ブラタモリ「#12 仙台」

http://www.myvi.ru/watch/11193027071_-DNJ9hD9IEuTPSIZ4YgOYQ2
ブラタモリ、初の東北へ!今回のテーマは、「仙台の地形」。地形を知りつくしていたという伊達政宗の“まちづくり”の秘密に迫ります。台地、つまり高台の上に都市が広がる仙台市。でもどうして政宗は、水が手に入りにくい台地に、わざわざ城下町をひらいたのか?そこには、「地形マニア」ともいえる政宗の知恵と工夫がありました。仙台一の繁華街に残る、政宗の工夫の痕跡とは?昭和の香り漂う横丁で、タモリさんが見つけたものとは?さらに、4年前に東日本大震災で被災した津波の浸水域も訪問。自分の目ではじめて被災地の光景を見たタモリさんは、何を感じたのか・・・?
仙台といえばやっぱり牛タン(^p^)

牛タン定食
私が行ったことのあるお店の中でオススメなのは「伊達の牛タン本舗」と「たんや善治郎」と「旨味太助」で(^▽^)ゴザイマース
さて、仙台駅より仙山線に乗り換えです。

電車入線を待つ女性車掌 仙台駅にて

山寺駅より立石寺の眺め
17:16分山形駅到着しました(^-^)/

山形駅
ここ山形は霞城公園がポイントになっていますが、山形駅構内もエリア内なので構内でポチっとスタンプゲット!ヤッタネv(=^0^=)v

公霞城園内の最上義光の銅像
さて、山形といえば”芋煮”ですかね~(^q^)
しかし、ここ山形市はあまり知られていないようですけれど、一人あたりのラーメン消費量日本一の都市なのですね~知ってましたか?(^0^)
それにもかかわらず、私の行きつけのお店を紹介いたします。
千歳山こんにゃく店

玉こんにゃく
ここの玉こんにゃくは美味しいですよ~(^p^)
味噌でんがくも( ゚v^ ) オイチイ
山形にお出かけの際はぜひどうぞ( ^ω^)_凵 どうぞ
さて、山形駅より奥羽本線乗り換えです。17:35米沢駅行き普通列車に乗ります。
山形-米沢間は標準軌になっているので、ローカル電車でもかなりのスピードが出ているようですね?速い速い!(^ω^)
50分で米沢駅到着です!

米沢駅
さあ、ここ米沢で米坂線へ最後の乗り換えです。
18:32発新潟行き快速「べにばな」に乗車です~♪

快速列車べにばな
昔は新潟-仙台間がこの「べにばな」が直通運転していたのですけどね~(^0^)
この列車に乗れたことで、一気に疲れが出てきたようです…新潟までうたた寝する自分でした~(=-ω-)zzZZ乙乙
21:22新潟到着!全走行距離589.5k営業距離!いや~お疲れ様でした(^-^)/
第20・21回 Light Up! ジャーナル / 追悼 むのたけじさん
自由なラジオ Light Up! 020回
「Iam not ABE に込めた警告 ひとりひとりの挑戦こそが民主社会をつくる」
https://youtu.be/7_3ShUdR4HI?t=19m47s
19分47秒~第020回 Light Up! ジャーナル
浜岡原発の安全対策工事の遅れについて
http://jiyunaradio.jp/personality/journal/journal-020/
おしどり:
小出先生、先月27日に茨城県で震度5弱の地震があった時、原子力規制庁からの緊急速報メールで「すべてに影響はない」と情報がすぐに来たんですけども、そこに列挙されていた北関東と東北地方の原子力関連施設の多さにすごい驚きました。

小出裕章さん:
そうですね。
おしどり:
はい。本当に。でも私達、東京に住んでいる人間は、3.11の後どうしても北の方に目を向けがちなんですけど、すぐそばには中部電力の浜岡原発があるですよね。
小出さん:
そうですね。
おしどり:
中部電力は、静岡県御前崎市にあるその浜岡原発の安全対策工事の工期を延期する方針を固めたようです。延期は5回目ということで、今回は初めて完了時期の設定も見送るということですが、これは計画も進捗もいい加減ですよね。
小出さん:
そうですね、私もそう思いますが、ただ皆さんもう一度基本的な所に戻って考えてみてほしいのですが、日本というのは世界一の地震国なのですね。

おしどり:
本当に。
小出さん:
そして、地震なんていうものを誰も願いはしないけれども、でもある時突然襲ってくるわけです。そして残念なことに、天災は忘れた頃にやって来るとずっと言われてきましたけれども、地震はいつやってくるというような予知ということは、これまでできた試しが一度もないのです。ただし、この日本という国が世界一の地震国だと言っても、地震の起きやすい場所というのはもちろんある訳で。例えば、世界中の地震学者が「近い将来に必ず東海地震が起きるだろう」と言っている訳です。


日本列島の南側には、南海トラフという巨大な地震域があるのですけれども、その地震域では南海地震・東南海地震・東海地震という地震が古文書をひもとくと、約100年から150年ごとに起きてきたということがはっきりと分かっているのです。

おしどり:
はい。
小出さん:
そして、東南海地震も東海地震も1854年の安政年間の時に起きました。そして東南海地震の方は、1944年つまり90年経って起きているのですけれども、いわゆる東海地震というのは1854年以降、もう162年起きていないのです。それだけ地震を起こすひずみが溜まっているということで、いつ起きても不思議でないという地震なのですが、その予想されている東海地震の予想震源域のど真ん中に浜岡原子力発電所が建っているのです。

もともと、こんな事はしてはいけなかった訳ですし、中部電力の方もおそらくこの事の重大性ということに少しずつ気がついて来ているのだと私は思います。本気で彼らが浜岡原子力発電所を再稼働させる気があるのかどうなのかという事も今となってみると、かなり疑問なのではないかと私は思っていますし、それが工事の遅れ、あるいは完了時期の設定も見送るということに繋がっているのではないかと私は思います。
おしどり:
なるほど。でも、100年から150年にいっぺんの地震がとっくに150年を超えてるというのは、次来るのは今までよりずっと大きい地震かもしれないということですもんねえ。パワーが溜まっていて。
小出さん:
ですから、東海地震、東南海地震、南海地震というのは個別に1つずつ起きたこともあるわけですし、3つがいっぺん同時に動くこともあったわけです。もし本当に、3つが同時に動くようなことになれば、マグニチュード9というような2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震と同じような巨大地震が起きると、地震学者が予想しているわけですし、それがなんと浜岡原子力発電所の直下で起きるという、そういうことになっているわけです。

おしどり:
うわぁ。すごいことですよね。小出先生これまで浜岡原発、どんな経緯で延期が続いたのでしょうか?
小出さん:
もともとは、2011年3月11日の福島の事故が起きてから、当時、菅さんという方が首相をしていたわけですが、菅さんがとにかく浜岡だけは止めようとして動いた訳ですね。そして、「津波でやられるといけないから防潮堤を作れ」と「そうじゃなければ止めろ」と言っていたわけです。それで、中部電力もそれを受けて止めて、とにかく防潮堤を防波堤と言うんでしょうか、それを作ると言ったわけですけれども。

その防波堤がなんとも巨大なもので、もともと高さが18メートルというような、普通だったらありえないような壁をですね、浜岡原子力発電所の目の前の海に全部作るというそんな約束をしてしまったわけです。ですから、もともと工事自身が大変でしたから、思ったよりも時間がかかるということで、1回目の延期がありましたし、その後は18メートルでは足りない、もっと高くしなければいけないということで、また延びましたし。
そうこうしている内に新規制基準というのが出来てしまいまして、地震の揺れの大きさをどうやって考えるかということが、昔とはずいぶん変わってきているわけです。
その度に、中部電力の方は見直しを迫られるということになってきたわけですし、先ほど聞いて頂きましたように、中部電力自身がもうこれは止めたほうがいいのではないかとだんだん思い始めているのではないかなと私は思います。
おしどり:
防波堤が22メートルというのも、ちょっと想像がつかないですよね。
小出さん:
マコさん、ケンさんも見に行かれたそうですけれども、私も見に行きましたけれども、なんか漫画のような壁ですよね。
おしどり:
いや、本当に。
小出さん:
確かに高いけれども、本当に津波が来て、こんなものがポタッポタッと倒れないかというような壁が、今、原子力発電所の目の前の海にそそり立っているというようなそんな状況になっています。

おしどり:
イタチごっこと言うか、津波が来る、地震が来るかもしれない、津波が来るかもしれない、壁を作らなくてはいけない。じゃあ壁を作ろう、じゃあ高さが足りない、もっともっと作ろうみたいな。なんかそれで、どんどん延期していって計画が遅れていますって言う。
なんかお聞きしてると、計画が凄いずさんなように聞こえるんですけど、なんでこんなことになってるんですかね?
小出さん:
もともと原子力発電所の事故の歴史というのを見てもらえば分かって頂けるかと思うのですが、当初は、こんなんでいいだろうと思ってやっていたことが、次々と、「やはりダメだった」と「もっと厳しくしていかなければいけない」というような歴史をずっと辿ってきたわけです。地震に関しても、予想していた地震度の大きさ、もうこれ以上のことなんて考えなくてもいいと言っていたような大きさが、次々と乗り越えられてしまってきたというのがこれまでの歴史でしたので、科学というものはそんなものだと思って頂くしかないだろうと私は思います。
おしどり:
そうですね。今、どの学問も完成形ではなくて、まだ発展途上という事で、今の最新というだけであって、それが完全というわけではないですもんね。
小出さん:
もちろんそうなのです。科学というのは、もともと未知の物を知りたいということで始まっているわけであって、完全に分かるなんてことは絶対にそれこそない訳であって、分かれば分かるだけ、また別の事が見えてきてしまうわけで、これからもそういう歴史が続くと私は思います。

おしどり:
私、以前、全然関係ないですけど、東京電力が福島第一原発の地下水の汚染を調べてた時の言葉を思い出しましたよ。地下水の汚染を調べて、どこから何が漏れているのか東京電力が調べた時に、たくさん井戸を掘って、その汚染水の流れを調べた時に、もの凄い哲学的なことを言ってたんですよね。東京電力が規制庁の発表で。「調べれば調べるほど分からないということが分かりました」と発表してて、それを思い出しました。
小出さん:
非常に正直な科学的な発言だと私は思います(笑)。
おしどり:
そうですよね、そういうことですもんね。でも、その原子力というのは未知の物であっても、できるだけ完全と言うか、万一のシビアな状況をできるだけなくすというものなのにも関わらず、「いやぁ、未知なもので、完全ではないですから」と言うのは、なかなか怖い発言方法ですよね。
小出さん:
そうですね。でもそれは、例えば原子力規制委員会という所が新規制基準への審査というのをやっていて、これまでに九州電力の川内原子力発電所、関西電力の高浜原子力発電所、四国電力の伊方原子力発電所に、規制基準に合格したというお墨付きを与えたわけですけれども。その度に、規制委員会の委員長である田中俊一さんが「合格したからといって安全だとは申し上げない」と言っているわけであって、科学的に分からないということは必ず残っているということは彼自身も認めている訳ですし、科学というものはそういうものだと、皆さん了解していただくしかないと私は思います。

ただし、こと原子力発電所に限ってはそんなことで了解できるようなものではないわけですから。私は何よりもまず科学的に物を考えるなら、原子力というのは止めるべきだと思います。
おしどり:
なるほど。わかりました。ありがとうございます。
でも、よく考えてみたら、その原子力規制委員会というのは地震のご専門ではないけれども、地震と原子力のことを判断していってるというのは、よく考えたらちょっと怖いことですよね。
小出さん:
そうですね。ただ、原子力というのは、非常に広汎な技術の上に乗っていますので、原子力規制委員会の委員というのはたった5人しかいないわけなんですけれども、その5人ではもちろんこぼれ落ちる所はもうそこらじゅうにあるということだと思います。
ただし、今、マコさんがおっしゃったように、地震というものに関して専門家がいないということは、やはり由々しき事だと私は思いますし、原子力発電所にとって、特に日本の原子力発電所にとって地震は最大の脅威なわけですから、ちゃんとした審査ができるようにしてほしいと思います。
おしどり:
なるほど、ありがとうございます。
熊本地震の後、福島県の農民連の方々が100人ぐらい政府交渉があった時に取材に行ったんですよね。福島の農家の方々が熊本地震の後、「もう川内原発を止めてほしい」という要望を原子力規制庁に出していたんですけど。それを原子力規制庁は、「新規制基準をクリアしているので大丈夫です」ということを福島の農家の方々にお話をしていて、それを俺達の前で言うのかっていう。自分達は犠牲者だから、これ以上増えないように話をしに来たということだったんですけど。お一人の農家の方がとても周知の事をおっしゃってらしてね。「熊本地震は地震学会でも気象庁でも今後予測がつかないと言っているのに、なんで原子力規制庁は予測をつけるんだ」と怒っていて。


小出さん:
その通りですね。
おしどり:
いや、本当にその通りだと思いました。小出先生、今日もありがとうございます。
小出さん:
いえ、こちらこそ。ご活躍いつもありがたく思っています。これからもよろしくお願い致します。
おしどり:
こちらこそ、よろしくお願いします。
【追悼】101歳のジャーナリストむのたけじさん
「あなたが、あなたらしくいられる社会を」
https://youtu.be/H67ZGUWtEYA

ETV特集 2015年10月10日
むのたけじ 100歳の不屈
伝説のジャーナリスト 次世代への遺言
http://dai.ly/x398s26
ことし100歳を迎えたジャーナリスト、むのたけじ。戦前・戦中は朝日新聞の記者だったが、「大本営発表のウソを書き続けた責任」をとって敗戦と同時に退職。戦後は、故郷の秋田で地方紙「たいまつ」を30年にわたって自力で発行した。記者として戦前・戦後の日本社会を取材し続け、膨大な記事と発言を残してきた伝説のジャーナリストである。「戦争を絶滅させる」。その言葉や生き方は、読者のみならずジャーナリストをめざす若者にも影響を与えてきた。95歳を過ぎた頃から特に年少者や若者への関心があふれだしたという。「今の若者たちと話していると、新しいタイプの日本人が出てきたと感じる。絶望の中に必ず希望はある。戦争のない世の中を見るまでは死ねない」。100歳になった今も食欲は旺盛、講演や取材をこなし気力は衰えない。戦後70年のいま、伝説のジャーナリストの足跡とそのこん身のメッセージを通じてこの国の未来を考える“熱血”ヒューマンドキュメント。
学ぶことをやめれば、人間であることをやめる。生きることは学ぶこと、学ぶことは育つことである。
北風の中に春の足音を聴き分ける、そんな耳を持ちたい。美女の舞踊に骸骨の動きを見定める、そんな眼を持ちたい。我を失うほどの窮境に置かれても、決して「はい」と「いいえ」は間違えて発音しない、そんな口を持ちたい。
より高く、より遠く跳躍しようとする者は、それだけ助走距離を長くする。現在以降をより高く積もうとする者は、現在以前からより深く汲みあげる。
むのたけじ
自由なラジオ Light Up! 021回
「 中国・北朝鮮は本当に脅威なのか?〜元自衛官が分析する『戦争法のその後』〜 」
https://youtu.be/uw6Uo3erses?t=17m35s
17分35秒~第021回 Light Up! ジャーナル
福島第一原発のデブリが圧力容器の底にあった
http://jiyunaradio.jp/personality/journal/journal-021/
西谷文和:
今日のテーマは、東京電力が福島第一原発二号機で溶け落ちた核燃料がどこに溜まっているのか初めて明らかにしたんですね。これ、どういう物を使って、中を見たんでしょうか?

今中哲二さん:
私も去年か一昨年ぐらいから何かやってるなというのは聞いてたんですけども。宇宙船っていうのはありますよね。
西谷:
宇宙線、X線とかですね。

今中さん:
空から、宇宙からくるやつです。

西谷:
はい。
今中さん:
その中に「ミューオン」っていうのがあるんですよ。
西谷:
ミューオン。はい。
今中さん:
もともと宇宙線というのは、正に宇宙から飛んできて、それはほとんどが陽子、プロトンというやつなんです。陽子というプラス1の電化を持ってるやつ、これ水素の原子核と一緒ですけども。
西谷:
それ理科で習いました。はいはい。
今中さん:
それが凄いエネルギー持って、大気中の原子核にぶつかるんですよ。大気、空気ですよね。空気って言ったら、大体窒素とか酸素とかありますけども。そうすると、窒素と酸素の原子核がまたバラバラに壊れるんですよ。

西谷:
壊れていく。はい。
今中さん:
そして、その時にできる物の一つがミューオンなんです。それで、いろんな物できるんですけども、ミューオンっていうのは比較的透過力が強いので、大気を抜けて、地表までかなり来てるということです。それで、それを使って透過力が強いんで、だから我々の体も毎日毎日ミューオンが突き抜けてるわけですけども。
西谷:
ミューオンが突き抜けてる。
今中さん:
調べてみたら、昔、エジプトのピラミッドってありますよね。
西谷:
ピラミッド。はい。
今中さん:
そのピラミッドの中がどうなってるかとか、それを調べるのに周りでミューオンを、だからピラミッドを通過してくるやつとかね。それで、その他には最近やられてるのでは火山。

西谷:
火山?
今中さん:
うん。
西谷:
阿蘇火山とか。
今中さん:
ええ。
西谷:
はいはい。
今中さん:
火山のを通過してくる、だから山を通過して抜けてくるミューオンを調べて、その中に密度の変化ね。透過力が強いと言っても、重たいものがあると吸収されたり散乱されると。それを、ですから周りで測定して中の様子を調べると。そういう原理。

西谷:
なるほど。火山が噴火しそうになった時は、ミューオンで調べているわけですか?
今中さん:
そうそう。あんまり上手くいってるとは、私聞いてませんけども、一応どこにマグマが溜まってるよと。マグマはちょっと密度が高いんで、それでやってるというのは見たことはあります。それで、それを使って福島の中の原子炉の御釜ですよね。お釜の中の燃料がどうなってるか一度やってみましょうというのを、なんか去年か一昨年ぐらいから立ち上げてやってました。
https://youtu.be/N6oUV7lLRgM
西谷:
これでね、取り敢えず分かったことはですね、いわゆる格納容器の中に圧力容器ってあるじゃないですか?
今中さん:
ええ。はいはい。
西谷:
この圧力容器の下にデブリがあったと。
今中さん:
下というかね、圧力容器そのものは高さが30メートルぐらいあるのかなあ。20メートルから30メートルの長細いやつですね。BWRの場合。

西谷:
沸騰水のね。はいはい。
今中さん:
その真ん中へんに核燃料の置いてある部分がありますよね?

西谷:
はい。
今中さん:
それで、燃料が溶けると、その圧力容器、お釜の底へ落ちる。
https://youtu.be/wwYk62WpV_s
西谷:
底へ落ちる?
今中さん:
はい。それで、それがメルトダウンですよね?
西谷:
はいはい。
今中さん:
それで底へ落ちて、それでお釜の底も抜けちゃったらメルトする。

西谷:
お釜の底が抜けたらメルトする。でも、格納容器がありますよね? その下に。
今中さん:
ええ。そしたら、その格納容器の底へ落ちると。それで、もし水とか全然なかったら、その格納容器の床が温度が上がって分解されて、ズブズブズブズブと、また溶けたやつが地面に潜り込んでいくと。
西谷:
「チャイナシンドローム。」
今中さん:
これがチャイナシンドローム。結局、どうなってるかっていうのをまずは調べたいということでやってたようです。
西谷:
今中先生から見てですね、この二号機に関して場所が分かったと。ある程度ね。
今中さん:
分かったというのか、ぼんやりと。要するに、影がちょびっとあるなあという程度で。

西谷:
これは、だからその廃炉に至る過程を100とすると、1ぐらい進んだんでしょうか? 10ぐらい進んだんでしょうか?
今中さん:
1ぐらいでしょうかねえ。はい。
西谷:
やっぱり、まだまだそういうレベルなんですね。
今中さん:
廃炉というか、要するに、私はまず現場検証ができてないんですよね。

西谷:
入れませんもんね。
今中さん:
うん。現場検証ができて、それからなんですよね。それから、もう本当に廃炉の話になっていくわけで。現場検証への1ステップ。
西谷:
がようやく、ちょっとだけ前に。
今中さん:
ちょっとだけという感じですね。
西谷:
これ、でも一号機と三号機もありますからね。
今中さん:
一号機はね、前にやってるんですよ。
西谷:
一号機やったんですか?
今中さん:
一号機やって、それでですから、圧力容器、お釜ですよね。お釜の中には燃料がないと。要するに、影が写ってないと。

西谷:
ということは、全部スルーしてしまったっていう事ですね?
今中さん:
そうです。ですから、メルトスルーしてると。それで、二号機についてはもともとの燃料があった分じゃない。即ち、メルトダウンはしてるけども。それで、メルトスルーはせずに残ってる部分があると。それは、あくまで影を見てるようなもんですから、どれぐらい、もともとあった分の何割。凄く大雑把の話でしかありません。
西谷:
あとは、どうやって取り出すかですね。
今中さん:
そうです。どういう風に飛ばせるかというのをまず調べると。
西谷:
そうか。どうやって取り出すかは、その後やね。
今中さん:
そうです、そうです。取り出すかは、どうなってるかをまず調べると。私の言う現場検証ですけども。はい。
西谷:
それが、でもまだ放射線が高いから、まだいけないと。

今中さん:
でも、とにかくやってもらわなくっちゃと私は思ってます。
西谷:
そうですね。それをやらない限りは、事故は終われませんからねえ。
今中さん:
はい。
西谷:
分かりました。本当に、最初の最初の一歩のちょっとした一歩が進んだということだろうということがよく分かりました。今中さん、どうもありがとうございました。
今中さん:
こちらこそどうも。
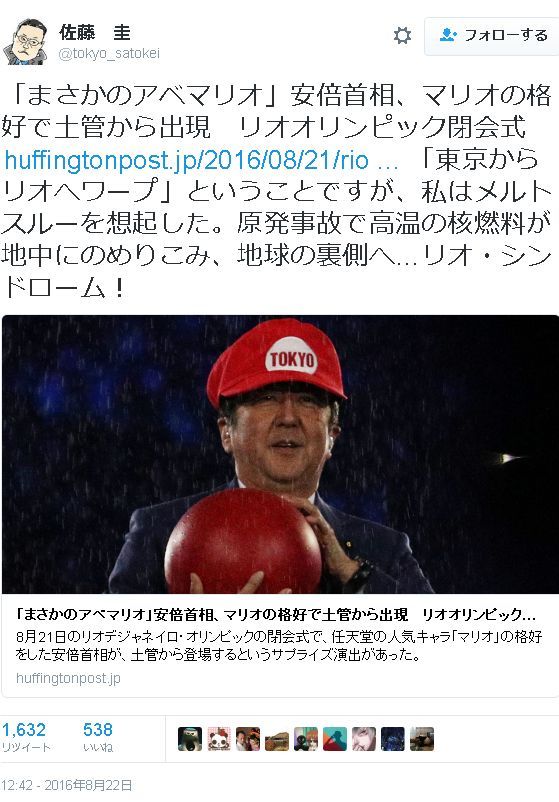
東電 福島原発事故費用
政府に追加支援要請 9兆円越え確実
(東京新聞【こちら特報部】)2016年8月2日
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2016080202000140.html
東京電力ホールディングスが、政府に「追加支援」を求めている。福島第一原発事故による賠償や除染費用が足りない可能性が高まったからだという。政府が設定した東電支援のための上限は当初五兆円だったが、二〇一四年に九兆円に増え、さらに増えることが確実になった。最終的には一体、いくらになるのか。政府と東電は、国民にきちんと説明する責任がある。
(白名正和、三沢典丈)

膨らむ一方の「賠償」+「除染」
訴訟、電力自由化 「経営環境が激変」
先月二十八日、全国知事会議は「東日本大震災からの復興を早期に成し遂げるための提言」をまとめた。風評被害対策、財政支援など四十九項目のうち筆頭が原発事故処理だった。
「廃炉など原子力災害のあらゆる課題については、東京電力任せにすることなく、国主導で早期に解決すること」
福島県の内堀雅雄知事は「日本全体に関わる極めて重要な問題」と訴える。
示し合わせたかのように同じ日、東京ホールディングスが政府に追加支援を求める方針を発表した。数土文夫会長は記者会見で、支援要請の理由について「経営環境が激変した」ためと説明した。一三年に賠償額を五兆四千億円と見込んだが、今年三月の時点で六兆円を超えた。各地で訴訟を起こされ、賠償額はまだまだ相えそうだ。除染費用も見込んだ二兆五千億円では足りない。
「追加」の名の通り、東電はこれまでも、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原賠機構)を通じて政府の支援を受けてきた。原発事故が起きた一一年の時点で、支援の上限は五兆円に設定されたが、一四年に九兆円に拡大された。
今年三月の時点で、東電支緩のための貸与総額は約七兆四千六百億円。実は、まだ、約一兆五千四百億円の余裕がある。なのに、追加支援を求めるのは、九兆円突破は確実と東電が判断したからだろう。
負担しなければならないのは、賠償と除染費用だけではない。総額の見当が付かないのは廃炉費用も同じだ。
「東電は二兆円を用意していたようだが、桁が足りない。これから十兆、二十兆円という規模で必要になってくるだろう」と、九州大の吉岡斉教授(科学技術史)はみる。
先月、2号機の溶け落ちた核燃料(燃料デブリ)の大部分が圧力容器の底に存在することが、ようやく判明したが、1、3号機についてはデブリの状況すら分かっていない。人が近づいたら即死してしまうほどの高い放射線量の中、デブリを取り出せる日が本当に来るのか。
技術の進歩によって、取り出せたとしても、デブリの廃棄場所を確保できるのか。高レベル放射性廃棄物の「ガラス固化体」の最終処分場の候補地すら決まらない。デブリについては、福島県外どころか、福島第一原発の敷地外でさえ搬出するのは困難だろう。
原賠機構は先月十三日、廃炉に向けた戦略プランで、デブリを残したまま福島第一原発を建屋ごとコンクリートで覆う「石棺」に言及した。だが、地元の反発が相次ぎ、二日後、「石棺を検討しているということは全くない」と釈明する事態に追い込まれた。
原子力資料情報室の伴英幸共同代表は「石棺はデブリを長期間、隔離保管することで放射線量の減衰が期待できる、現実的な手段ではなかったか」と指摘する。「石棺を含めた対応について、機構側は福島県側と冷静に話し合うべきだったと思う。今回、逆に総論をする機会が失われ、政策の選択肢が狭まってしまったのではないか」

廃炉費用 2兆円どころか「桁違い」
取りざたされる「新基金」
「税金投入の前に、まず事業者負担」
政府は東電の追加支援要請に対し、慎重な姿勢を見せた。林幹雄経済産業相は先月二十九日の閣議後の記者会見で「東電自ら行うことが大原則」などと述べた。
その二日後だった。三十一日、廃炉費用を支援するための公的基金を新設することを経産省が検討しているという報道があった。
それによると、原賠機構の上限九兆円の支援とは別に、政府が同機構に東電支援のための基金を設ける。デブりの取り出しなど廃炉の作業状況に応じ、基金から資金を援助する。廃炉費用を政府が一時的に立て替えることになるが、最終的に東電が返済する。
原賠機構の支援上限を一四年に続いて引き上げようとすれば、強い批判が出るだろう。だから、基金の新設なのかもしれないが、国民の税金が投入されることに変わりはない。
だが、基金について、林経産相は三十一日、視察先の福島県南相馬市で、「廃炉は東電が責任を持って行うもの。支援のための制度措置について新たな検討を行っている事実はない」と否定した。
では、「基金新設」は誤報なのか。「単なる誤報ではないだろう」と言うのは立命館大の大島堅一教授(環続経済学)だ。「東電の発表に合わせて、政府が国民の反応を見るために、経産省が情報を流したのではないか」
特に気になるのは、「デブリの取り出しなど廃炉の作業状況に応じ」などの点だ。
大島氏は「廃炉費用は原発を設置した電力事業者が利益などから全額負担すべきものだ。だが、四月の電力の小売り全面白由化で、従来のように利益を上げることは難しくなった。そこで、廃炉資金を継続的に東電に支援する仕組みをひねり出す必要が出てくる」と推測する。
大島氏の試算によると、賠償や除染を含め、東電が負担すべき事故費用総額は十三兆三千億円。原賠機構の支援上限九兆円を上回っている。基金新設は、東電には願ってもないことだが、大島氏は「事故を起こした原子力事業者だけ優遇するのはおかしい。電気料金の自由競争もゆがめてしまう」と批判する。
そもそも、福島の原発事故での資金の使われ方がおかしい。「ゼネコンや原子力関連会社の言いなりに、凍土壁などに巨額の資金が投じられる一方、効果について政府は何の検証も行っていない。政府は第三者委員会などを立ち上げ、廃炉にかかる費用総額を精査し、国民に示すべきだ」
九州電力川内原発に続き、十一日には四国電力伊方原発が再稼働する予定だ。東電も、柏崎刈羽原発の再稼働に向けて動いている。だが、ひとたび原発が過酷事故を起こすと、処理にかかる期間、費用が全く分からない。万一の事故が起きる可能性があるのに、原発の再稼働を進めていいのか。
大阪市立大の除本理史教授(環境経済学)は「廃炉費用の負担で債務超過になるのなら、本来、東電の法的整理を進めるべきだ。費用を国民に負担させるのは本末転倒だ」と指摘し、再稼働の前に、国民が事故のコストに対する意識を高める必要があると訴える。
「福島原発事故のコストが、今後、起きるかもしれない事故に向り、各電力会社へのメッセージとなる。今の制度であれば、原発事故を起こしても、電力会社の経営リスクは発生しない。このうえ、廃炉費用まで負担せずに済めば、事故を抑止しようという動機づけすら働かなくなる。事故のコストを誰がどう負担するのか、曖昧なまま再稼働を進めるべきではない」

お久しぶりです(;^ω^)新潟知事選など…再稼働はなんといっても反対!(`・ω・´)
読者の皆様、しばらくご無沙汰しておりますm(_ _)m
持病の慢性腎臓病が徐々に進行しているようです(T▽T)
八月の末に北東北を旅行して以降、薬の種類も量も増えてしまって、副作用?に身体がなかなかついていけてない現状でです(・ω・`)
人工透析を開始するまでまだ時間がありそうですが、何とか透析開始を遅らせて、色々なことをやりたいのですけれども…(;´Д`)
ブログに関しては、まったく不定期になりますが細々とやっていきたいと思いますので、どうかナガーイ目(∋ ̄ ̄ ̄- ̄ ̄ ̄∈)でお付き合い下さいませ(^0^)
なお、音楽ブログは次回より復活予定です( *´艸`)
さて、お休みをいただいている間に世間で色々な災害・事件・事柄が次から次へと起こっていましたね?(。-_-。)まれにナウでつぶやいていたりしたのですけれど、今回、私が住んでいる新潟県の県知事選について、遅ればせながら触れていきたいと思いますので、どうかお付き合いくださいませm(_ _)m
なぜ?新潟泉田知事が不出馬表明
原発再稼動加速も
(東京新聞【こちら特報部】)2016年9月2日
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2016090202000126.html
十月投開票の新潟県知事選に立候補を表明していた泉田裕彦知事が、出馬を「撤回」した。原発政策をめぐり、国や東京電力に対峙(たいじ)してきた「もの言う知事」の突然の翻意には驚くが、断念の理由として地元紙の新潟日報による批判的な報道をあげる異例の事態だ。地元では「理由はほかにあるのでは」との臆測も飛び交う。東電柏崎刈羽原発の再稼働への影響を不安視する声も広がっている。
(佐藤大、木村留美)
批判的報道受け「撤退」…
県民驚きと困惑
「(泉田知事が)自分で決断したんだろう。そんな終わったこと聞いてどうすんの。大事なことは未来のことだ」。自民党新潟県連幹事長の柄沢正三県議は一日、泉田知事の突然の出馬撤回について、「こちら特報部」の取材に突き放すように話した。
突然の出馬撤回が明らかにされたのは、八月三十日のことだった。新潟県庁内にある県政記者クラブ室で、泉田知事個人名の文書が配布された。泉田知事は文書で、自らの実績を並べる一方、県が出資する第三セクター事業「日本海横断航路計画」の問題を指摘してきた地元紙・新潟日報の報道を批判し、「このような環境の中では、十分に訴えを県民の皆様にお届けすることはしい。県知事選からは撤退したい」と告げた。泉田知事は二月の県議会で出馬する意向を表明しており、県民の驚きは大きい。
きっかけとされた日本海横断航路計画とは、新潟港とロシアをフェリーで結ぶ計画。第三セクター「新潟国際海運」は二〇一五年八月、パナマのペーパー子会社を通じて、韓国企業から約五億円で中古フェリーを購入する契約を締結した。
手付金として七千万円を支払ったが、速度不足が判明したとして船の受け取りを拒否。韓国企業が第三者機関「日本海運集会所」に仲裁を申し立て、今年七月、子会社は一億六千万円の支払いを命じられた。仲裁判断では売り主が船を引き取ることも示された。だが、第三セクター側は子会社を破産させてこれを支払わない方針を示した。韓国企業は提訴も辞さない構えを見せている。
この問題で新潟日報は七月以降、県や泉田知事の関与を追及する報道を繰り返し展開。県や泉田知事がそのたびにホームページなどで反論する異例の経過をたどっていた。
地元紙反論「真の理由を説明すべき」
やり玉に挙げられた新潟日報は猛反発。八月三十一日付朝刊一面に服部誠司編集局長名で「知事選から撤退する理由として本社の報道を挙げたことは、報道機関に対する圧力にも等しく、許しがたい行為と言うほかはない」とし、「知事は県民に対し、知事選から撤退する真の理由をきちんと説明すべきだ」とする反論を掲載した。
実際、批判報道を理由にした不出馬表明は不可解と言うほかない。知事選をめぐる情勢が決断に影響を与えたとの見方も強く、不出馬表明後の囲み取材でも質問が集中したが、泉田知事は「選挙の情勢が厳しいから撤退するという判断はしていない」と否定。出馬すれば再選できるとの自信を強調した。
ただ、これまで泉田知事を推薦してきた自民はまだ態度を明確にしていない。今回、推薦依頼を出した自民、民進、公明、社民、生活の五党のいずれからも対応を保留されていた。県市長会や町村会は五月、泉田県政は「独善的だ」と批判する文書を発表。八月十日に森民夫・長岡市長が出馬表明すると、「逆風」はさらに強まった。
泉田知事を支え続けてきた県議会最大会派の自民党からも、森市長を推す声が上かっていた。柄沢県議は取材に、泉田知事の二〇〇四年の新潟県中越地震後の対応を「体を張って不眠不休でやってくれた」と高く評価した一方、「私の政治哲学としては長期政権は良くない」と最近の泉田県政への不満をにじませた。同党は九月六日ごろ、森市長と政策について協議するという。
泉田氏の原子力行政を評価し、独自候補を擁立しない方針に傾いていた共産党なども知事選への対応の転換を迫られる。共産党新潟県委員会の樋渡士自夫委員長は「表面的には新潟日報の記事を理由にしているが、原子力行政をめぐって、ほかに大きな理由があると思わざるを得ない」と困惑を隠せない。
地元の反原発派からは突然の出馬撤回に落胆の声が上がる。「柏崎刈羽原発反対地元三団体」の共同代表を務める矢部忠夫柏崎市議は「鹿児島県で三反園知事が誕生し、自治体が原発に『ノー』という時代に入ったと思っていたのに。新知事のもとで原発政策が骨抜きにならないか心配している」と話した。
原発再稼働を急ぐ国や東電に対し、泉田知事は「福島事故の検証なしに再稼働の議論はできない」との立場を貫き、全国に名をとどろかせてきた。
一三年七月には、東電が県に事前説明しないまま柏崎刈羽原発6、7号機の原子力規制委員会の審査申請を决めたことに強く反発。東電の広瀬直己社長に「約束を破る会社。信頼できない」と一喝。「安全とお金、どちらが大事なのか」と畳みかけた。
福島第一原発事故についても、県独自に専門家らによる技術委員会をつくり検証してきた。
東日本大震災の直前に東電に造らせた「免震重要棟」も泉田知事の功績としてよく知られる。○七年の中越沖地震で新潟県庁への連絡用のホットラインが機能しなかったことから設置を要求、福島第一原発にもできた。完成したのは震災八ヵ月前だった。
東電や国とたびたび対立した泉田知事が退くことで、東電柏崎刈羽原発の再稼働の動きが加速するとの懸念も広がる。
折しも柏崎刈羽6、7号機の再稼働に向けた審査を優先して進める原子力規制委の方針が浮上したばかり。二基はこれまでに再稼働してきた加圧水型ではなく、福島第一原発と同じ沸騰水型だけに再稼働への反発は大きい。東芝の元原子力プラント設計技術者の後藤政志氏は「規制委や電力会社は沸騰水型は再稼働できないという状態を続けたくない。沸騰水型の中でも最新式の6、7号機から動かしていきたいのだろう」と推測。「大規模事故を起こしながら責任もとらない東電が再稼働するのはおかしいが、問題を指摘する泉田知事がいなくなると『国策』が進むのではないか」と危ぶむ。
実際、ツイッターなどでは原発に厳しい姿勢で挑んでいた渦中に、収賄罪に問われた元福島県知事の佐藤栄佐久氏の姿に重ねる声も多い。
佐藤氏は取材に「(泉田氏の不出馬の)経緯や詳細は知らない。私の場合は実態が分からない中で事件報道が先行し、政治生命を奪われた。状況は違う」と述べた上で、「泉田氏は新人知事だったころを知っている。まじめで真剣にやっていた。闘っている者がつぶされることがあってはならない」とクギを刺した。
原子力資料情報室の伴英幸共同代表も、報道を理由にした進退表明に「他に何かおるのか分からないが、批判に対し反論があるのなら主張し信を問えばいいはずだ」と首をかしげながら、原発再稼働への影響を心配した。
「事故を検証しない限り、再稼働については議論しないという新潟県の姿勢が変化しかねない。東電は賠償も終わらないうちに再稼働することになれば、事故の幕引きにもなってしまう。これまでの再稼働とは違う意味を持つ再稼働でインパクトは大きい」

原子力マフィアは大喜び!?(¬_¬)
【終了か?】長谷川豊氏「自業自得の人工透析患者なんて、全員実費負担にさせよ!無理だと泣くならそのまま殺せ!」で大炎上!
(健康になるためのブログ)
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/22146
http://megalodon.jp/2016-0920-1710-28/blogos.com/outline/191041/
自業自得の人工透析患者なんて、全員実費負担にさせよ!無理だと泣くならそのまま殺せ!今のシステムは日本を亡ぼすだけだ!!
( ゚Д゚)ゴルァ!!( ̄^ ̄)凸
優生思想と通低するものである(`・ω・´)
【ぽぽん調査】長谷川豊アナの降板は当然だと思いますか?
https://youtu.be/nuoBvq2Dx5o

知事選告示 有権者が注文
原発 安全論議深めて
(新潟日報)2016年9月30日
12年ぶりに新しい県政のかじ取り役を決める知事選が29日、スタートし、初日から県内各地で舌戦が繰り広げられた。重要な争点とされるのは、墓京電力柏崎刈羽原発の再稼働問題にどう向き合うかだ。有権者は「具体的にどうするのか知りたい」などと議論の深まりを望む。一方、県政課題は原発だけではないとして、人口減少対策など多様な論点についての論戦を求める声も上がった。
政党などの支援を受ける主要2侯補は原発が立地する柏崎市や、原発から半径5~30k圏の避難準備区域がある長岡市で再稼働問題に対する考えを訴えた。
森民夫さん(67)は地元・長岡市のアオーレ長岡前でマイクを握り「皆さんの安全を守るのが最優先課題。東電や国に言うべきことがあれば、私はしっかり言いに行ける」と力を込めた。
原発問題を「最大の争点」とする米山隆一さん(49)は柏崎市の中心街で「皆さんが安全に避難できる方法が検証されない限り、再稼働の議論はできない」と声を張り上げた。
三村誉一さん(70)と後藤浩昌さん(55)も届け出後、記者団に再稼働問題への考えを語った。
再稼働問題には、有権者の注目が集まっている。
「事故が起きれば離島は逃げ場がない。もしもの時にどう行動すればいいのか分からず不安だ」。佐渡市でトマトやサツマイモを作る農業中川文十郎さん(74)は離島の防災問題に目を向けるよう求める。
中川さんが住む佐渡市南部の羽茂地区は、原発から約50よと島内でも比較的近く、事故時の農作物への影響も心配する。原発に代わるエネルギーへの転換を願い、候補には「再生可能エネルギーをどう推進していくのか具体的に示してほしい」と訴えた。
新潟市北区で肥料や農薬を使わない農業を手掛ける宮尾浩史さん(51)も農作物への影響を懸念する。各候補が「住民の安全確保」を掲げるが、「具体性がないので、もっと詳しい主張を聞きたい」と話す。
上越市の自営業広田紀男さん(64)は「森さんも米山さんも再稼働には慎重に見えるが、それが票目当てであっては困る」と指摘し、本音での議論を望んだ。
再稼働を認める立場の人も住民の安全確保については十分な議論を期待する。
柏崎市の無職今井富子さん(66)は足が不自由なため、避難に不安を抱えている。「再稼働してもいいが、きちんと逃げられる態勢を整えてほしい」と切実な思いを語った。
「再稼働推進を力強く言ってほしい」という長岡市の会社員中野謙さん(30)も「しっかりした避難計画は必要だ。県は市町村の計画策定をしっかりサポートしてもらいたい」と強調した。
柏崎刈羽原発再稼働争点の新潟県知事選ルポ
(東京新聞【こちら特報部】)2016年9月30日
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2016093002000137.html
新潟県知事選が二十九日に告示された。東京電力への厳しい姿勢を続けた泉田裕彦知事は突然、四選出馬を翻意した。その結果、原子力規制委員会の適合審査が終盤を迎えている柏崎刈羽原発の再稼働問題などを争点に、与野党が推薦する各候補が争う形となった。七月の参院選新潟選挙区では、野党統一候補が激戦を制した。しかし、知事選では民進党が自主投票を決めるなど、構図は異なっている。有権者の選択は-。
(池田悌一、木村留美)
「泉田路線継承」
「安全確保優先」
民進は自主投票
JR新潟駅前の目抜き通り。午前八時半、雨が降りしきる中、医師の米山隆一氏(四九)=共産、生活、社民 推薦=が選挙カーの上に登り、声を振り絞った。
「福島原発事故からもう五年がたつが、いまだふるさとを奪われたままの人たちがいる。新潟で繰り返してはならない。事故の徹底的な検証なくして、再稼働の議論を進めることはできない」。一拍おいて語調を強める。「泉田路線の継承をはっきりと約束する」。簡単に再稼働に同意しないという宣言だった。
「争点は原発再稼働」。七月の参院選で野党統一候補として、約二千三百票差で当選した森裕子氏も選対本部長としてマイクを握った。「泉田知事は体を張ってきたのに、原子カムラの勢力に引きずり降ろされ」 、
演説を聴いていた鈴木知子さん(六七)は「『再稼働は絶対にやめてほしい』というのが私たちの願い。泉田知事は県民の声を聞いてくれた。米山さんも継承すると言っているし、応援したい」と期待した。
約三十分後、雨脚がさらに強まる中、今度は前長岡市長の森民夫氏(六七)=自民、公明推薦=の陣営が現れた。自主投票を決めた民進党県議の姿もある。
森氏は木箱の上に立ち、全国市長会会長を務めた実績を強調した。「近県とも協力・連携しながら、経済活性化や医療や農業の問題に取り組みたい」
柏崎刈羽原発についてはこう言及した。「安全確保が最優先。国や東電にも私が言います」。自身は「規制委の判断が出てから判断」という姿勢だが、支援する自民党新潟県連は再稼働を求める決議をしている。当選後、反対に回ることは難しいだろう。
「勝つぞー」と皆と合わせて気勢を上げた女性(三五)は「やっぱり自民党ですよ。原発を争点にしようとしている向こうとは違うでしよ」と誇らしげだった。(・3・)
先月の段階では、泉田氏と森氏が知事選出馬を表明していた。しかし、泉田氏は突然、地元紙・新潟日報の報道で、第三セクター事業を巡る問題を追及されたことを理由に、「このままでは選挙で原子力防災が争点にならない」と撤退を表明した。
「自民の地元議員の中で政策への不満から『泉田離れ』が進み、森さんを推す声と二分されていた」という指摘もあるが、ともかく、撤退に野党は慌てた。
民進は候補を探したが、断念して自主投票を決定。( ゚Д゚)共産、社民、生活の三党が目を付けたのが、次期衆院選で新潟5区から民進公認の出馬が内定していた米山氏だった。知事選で支持基盤の連合が森氏支持に回っていることから、民進は反対したが、米山氏は告示六日前に離党して出馬を表明した。
森氏は長岡市長を十七年近く務め、首長として経験は豊富だ。米山氏は二〇〇五、〇九年、一二年の衆院選、一三年の参院選の四回とも落選したが、「森裕子さんが参院選で勝てたことが、知事選につながっている」と初の当選を目指す。
実は、人口減が深刻…
経済振興望む有権者
全国の知事の中で、原発再稼働に最も厳しい目を向けてきたのが泉田氏だった。柏崎刈羽原発は東京電力のものという点で、他地域よりも市民が厳しい目を向けていることも確かだ。
福島の事故直後、魚沼産のコシヒカリが風評被害に遭いそうになったことを覚えている男性(七〇)は「やっぱり、原発は怖い」。一方で、地方の景気が浮揚しない中、経済対策も知事選では争点となる。
新潟市の中心市街地にある古町商店街は、シャッターが閉まった店が目立つ。帽子店の大関文雄さん(五九)は「代々、九十五年やってきたけど、ついに店を閉めました。ほら、ご覧の通りでしよ」と、お年寄りが何人か歩くだけの通りに目をやった。「いったん事故が起きれば、取り返しのつかないことになる」と再稼働には反対だが、暮らしがあってこそ。
新潟県の人口は現在、二百千九万人で、泉田氏が就任した二〇〇四年と比べて十六万人減った。昨年の国勢調査速報値では、東北の宮城県に人口で抜かれ、地元では衝撃が走った。
「地場に産業がほとんどない。みんな大都市に流れていっちゃう。コメどころだからといって人が集まるわけではないので」と大関さん。昨春、北陸新幹線が開業しており、「古都・金沢のように上手なまちづくりができればいいんだろうけど、観光資源が豊富なわけでもないし」とため息をつく。
洋品店を営む山口喜康さん(七七)は「原発が動けば産業面ではいいんだろうけど事故は怖い。難しいよね。でも、とにかく人がいないことには始まらない。新しい知事にはまちを活性化させる施策をしてほしい」。
柏崎刈羽原発には厳しい目
森氏の知事選出馬によって市長選が同日選となる長岡市の有権者はどうみるのか。来月九日告示で、投開票日は知事選と同じ同十六日。元市議の藤井盛光氏(三八)、元市議会議長の小熊正志氏(六六)、前副市長の磯田達伸氏(六四)の三人が出馬を表明している。柏崎刈羽原発から三十㌔圏内にかかる地域があり、市内では再稼働への関心はやはり高い。藤井氏は「政府の責任で避難計画の実効性を高める必要がある」などと森氏よりも慎重な姿勢だ。小熊氏は「是非を問う住民投票をしたい」と言い、磯田氏も再稼働には否定的だ。
だが、「票目当てで原発への慎重姿勢を打ち出している候補がいるという印象を受ける」と、市民団体「原発からいのちとふるさとを守る県民の会」メンバーで長岡市の無職石川智一さん(七二)は話す。
小熊氏は以前、安全が担保されれば再稼働容認という姿勢だったという。当選後、姿勢を転換する可能性がなくもない。とはいえ、なぜ、一様に候補予定者が慎重姿勢をアピールするのかというと、市民の意識が変化してきたからでもある。福島の事故以降、「拒否反応を示す人が増えた」と石川さんは話す。
原発のお膝元の人たちはどうか。柏崎刈羽原発反対地元三団体共同代表で柏崎市議の矢部忠夫氏も「以前は原子力政策を訴えても票にならないと議員らは真剣に取り組んでこなかったが、東日本大震災後は有権者の原発に対する思考が変わった」と話す。
それは、原発を巡る姿勢を泉田氏の姿勢を、評価する有権者が少なくないことからも明らかだ。それだけに、「今回の知事選では原発を争点にしない、福島を忘れさせようとする勢力は強い」と危ぶむ。
「本音は規制委の審査に適合すれば再稼働をしてもいいというのが本音という候補もいるだろう。有権者はよく見極めなければならない」
新潟知事選 米山候補に熱い期待
原発再稼働反対のうねり
自公推薦候補は争点隠し
(しんぶん赤旗)2016年10月6日
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-10-06/2016100601_04_0.html
新潟県知事選(16日投開票)は、東京電力柏崎刈羽原発(柏崎市、刈羽村)の再稼働が大きな争点となっています。米山隆一候補(49)=共産、生活、社民推薦=に、県民から「再稼働の流れを止めてほしい」と期待が集まっています。
(唐沢俊治)
「福島原発事故の検証なしに、再稼働の議論はできない」。米山候補は5日、新潟市東区の露天市場を訪れた人たちを前に力を込めました。泉田裕彦知事の路線を継承するとして、(1)事故原因(2)健康と生活への影響(3)安全な避難方法―この三つが検証されない限り、原発再稼働の議論は始められないと訴えています。
全国的注目集める
一方で、前長岡市長の森民夫候補(67)=自民、公明推薦=は、原発には「県民の安全の確保を最優先課題として対応」と主張。しかし、推薦する自民党は2014年の県連大会で、原発の再稼働を求めることを決議しました。
1300人が参加した「なくそテ原発2016柏崎大集会」(9月3日開催)の実行委員長・植木史将さん(40)=つなげよう脱原発の輪 上越の会代表=は、「米山さんは、私たちの期待に応え、県民の安全を守るために国と電力会社にはっきりとものを言ってくれる人です。新しく知事になったら、原発を再稼働させず廃炉にしてほしい。自民党が推す知事では再稼働に進んでしまう」と言います。
市民団体が行った候補者への公開質問で、米山候補は「エネルギー政策上、原発は必要でない」「柏崎刈羽原発6、7号機の再稼働に同意できない」と、原発問題に関する15項目すべてに回答。しかし、森候補は、再稼働への態度を明らかにせず、「県民の安全と安心の確保を最優先」と抽象的に返答するだけで、項目ごとの回答を避けました。森候補の姿勢に対し、「争点隠しだ」と県民から批判の声が上がっています。
森候補の足元の長岡市で、知事選と同時にたたかわれる市長選に立候補する前副市長の、いそだ達伸氏=日本共産党は自主的支援=は、原発をめぐり「市民の不安が解消されない限り、再稼働すべきではない」と表明し、森候補との政策の違いを明らかにしています。
全国からの注目も高く、首都圏反原発連合(反原連)は、「鹿児島に続き、新潟県に脱原発派の新知事を」と、米山候補を応援する声明を発表しました。
地域疲弊は「神話」
原発の推進派はこれまで、運転停止が地域経済に影響するとして再稼働を求めていましたが、その論拠が崩れ始めています。
地元紙の「新潟日報」(昨年12月13日付)は、柏崎刈羽原発の地元100社を調査し、3分の2の企業が売り上げの減少は「ない」と回答し、原発関連の仕事を定期的に受注したことがあるのは1割余りと報じました。同紙は、「長期停止で地域経済が疲弊している」という説について「具体的な根拠に基づかない“神話”」と指摘しています。
柏崎民主商工会の太刀川孝和会長(73)は、「原発による地域経済への影響は、一部に限られていました。原発事故の原因が解明されていない中での再稼働は、私たちの生活を危険にさらすだけで、絶対にやめるべきだ」と言います。
問題山積みの原発
柏崎市と刈羽村にまたがる柏崎刈羽原発は、事故を起こした福島第1原発と同じ「沸騰水型」。1~7号機の総出力は821万2000キロワットで、一つの原子力発電所としては世界最大です。6、7号機は出力135・6万キロワットで日本最大級。現在、原子力規制委員会で6、7号機の再稼働のため新規制基準の適合性審査がされていますが、審査の論点は絞られ、最終盤を迎えています。
次の知事が再稼働の判断をすることになり、その対応が各地の再稼働に影響する可能性があります。しかし、問題は山積みです。
柏崎刈羽原発は砂地に建設され、構内での地下水くみ上げ量が他の原発に比べて、格段に多いことが分かっています。
福島第1原発では現在も、1日当たり数百トンの放射能汚染水が発生し、事故の収束を阻んでいます。汚染水は、建屋に流入する地下水と、護岸の井戸からくみ上げた地下水に由来します。
隠蔽体質変わらず
しかし、構内に大量に流れ込む地下水量や、くみ上げるための井戸の耐震性などは、規制委の審査対象外だと問題点を指摘するのは、立石雅昭新潟大学名誉教授です。新潟県の「原子力発電所の安全管理に関する技術委員会」の委員を務めています。
立石氏は言います。「人の生命にかかわる重要な問題で、東電の隠蔽(いんぺい)体質が改まらないまま、再稼働の議論に入ることなどあり得ません。県民の半数は、柏崎刈羽原発の再稼働に反対しています。泉田路線を継承する米山さんに、私たち県民の思いをくみ取ってもらい、ぜひ当選してほしい」
野党と市民の力で米山知事誕生を
https://youtu.be/jnLMI_y32yg
2016年10月7日。新潟県知事選10・7新潟駅前共同街頭演説
司会 森ゆうこ参院議員・米山隆一選対本部長
新潟に新しいリーダーを誕生させる会 佐々木寛共同代表
社会民主党副党首 福島みずほ参院議員
日本共産党委員長 志位和夫衆院議員
生活の党共同代表 小沢一郎衆院議員
米山隆一新潟県知事候補
民進党 元官房副長官 松野頼久衆院議員
市民と野党の勝利v(=^0^=)v官邸・原子力マフィアに勝つヽ(・∀・)ノ


新潟知事選米山氏当選
共闘発展促す歴史的勝利
期待 急速に広がった
(しんぶん赤旗)2016年10月17日
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-10-17/2016101702_01_1.html
新潟県知事選で、「新潟に新しいリーダーを誕生させる会」の米山隆一候補が、柏崎刈羽原発再稼働を止めてほしい、農業、暮らし・福祉を良くしてほしいとの県民の熱い思いを受けとめ勝利しました。日本の政治の前途に大きな希望をもたらす歴史的勝利となりました。

原発の危険 根深い不安
勝利の要因は、第一に米山氏が、一度断った出馬要請を県民や野党の熱烈な願いを受けとめ立候補したことです。立候補に当たり、泉田裕彦知事の「福島原発事故の検証なしに、再稼働の議論はできない」という路線を引き継ぐことを表明しました。多くの県民の期待と激励が急速に広がりました。
第二に、福島原発事故を経験し、原発の危険に対する国や東電への根深い不安感が県民・国民に存在し、官邸や自民党、「原子力ムラ」の圧力をもってしても抑えきれないことを示しました。相手陣営は「県庁に赤旗が立つ」などの卑劣な攻撃をしたり、大量の国会議員を動員しての団体締め付けを行いましたが、県民の願いの前には通用しませんでした。この勝利は、原発問題で野党と市民の共闘で勝利した鹿児島県の三反園訓(みたぞの・さとし)知事に続くものです。
安倍政治にノーを示す
第三に、参院選に続く、今回の知事選で、市民と野党の共闘がいっそう進化したことです。市民と野党5党が何としても県民の願いを閉ざしてはならないと、懸命に奮闘し、多くの市民が立ち上がる選挙になり、日に日に野党共闘の結束が強まっていきました。
日本共産党の志位和夫委員長、小池晃書記局長や各党党首クラスが相次いで応援に駆けつけました。選挙戦が進む中で、自主投票を決めていた民進党が松野頼久、前原誠司の両衆院議員、黒岩宇洋県連代表らをはじめ幹部が応援、最終盤には蓮舫代表、江田憲司代表代行が駆けつけました。
米山氏の勝利は、安倍政権の強行政治にノーを示し、新潟にとどまらず、野党と市民の共闘の新たな発展を促す歴史的勝利になりました。
(新潟県・村上雲雄)
新潟県知事選 安倍内閣の原発政策と謀略に有権者が鉄槌
安倍官邸と自民党のデタラメに新潟の「反乱」
問題はこの結果で今後の政治が変わるかどうかだ。民主主義を愚弄する横暴政権は必ずあの手この手で巻き返しに出る。支持率をさらに急落させる有権者の怒りの二の矢、三の矢が絶対必要
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/191981
(日刊ゲンダイ)2016年10月18日

歴史的な快挙だ。原発再稼働が最大の争点になった新潟県知事選が16日投開票され、脱原発派で共産・社民・自由(生活)推薦の米山隆一氏が勝利した。
自公が推薦した前長岡市長の森民夫氏と、事実上の一騎打ち。民進党の支持基盤である連合新潟も早々に森の支援を決め、当初は森の圧勝とみられていた。
「告示の時には遠くに見えた相手候補の背中が、すぐ目の前に迫っている。もしかしたら、追い越せる」
13日に森のお膝元である長岡市で演説した米山は、こう訴えていたが、その言葉通り、驚異の追い上げで逆転勝利を手にした。これは、脱原発を願う民意の勝利だ。NHKの出口調査によれば、投票所に足を運んだ有権者の73%が原発再稼働に反対の立場だったという。
新潟県にある東京電力・柏崎刈羽原発は、原子炉7基の出力が合計820万キロワットと世界最大規模だ。ひとたび事故が起きれば、とてつもない影響が出る。実際、07年の中越沖地震で放射能漏れなどが起きたこともあり、現職の泉田裕彦知事は再稼働に慎重な姿勢を貫いてきた。その泉田は4選を目指して出馬を表明していたのだが、8月に突然、地元紙との確執を理由に出馬を撤回。その裏には原子力ムラの暗躍もあったとされる。
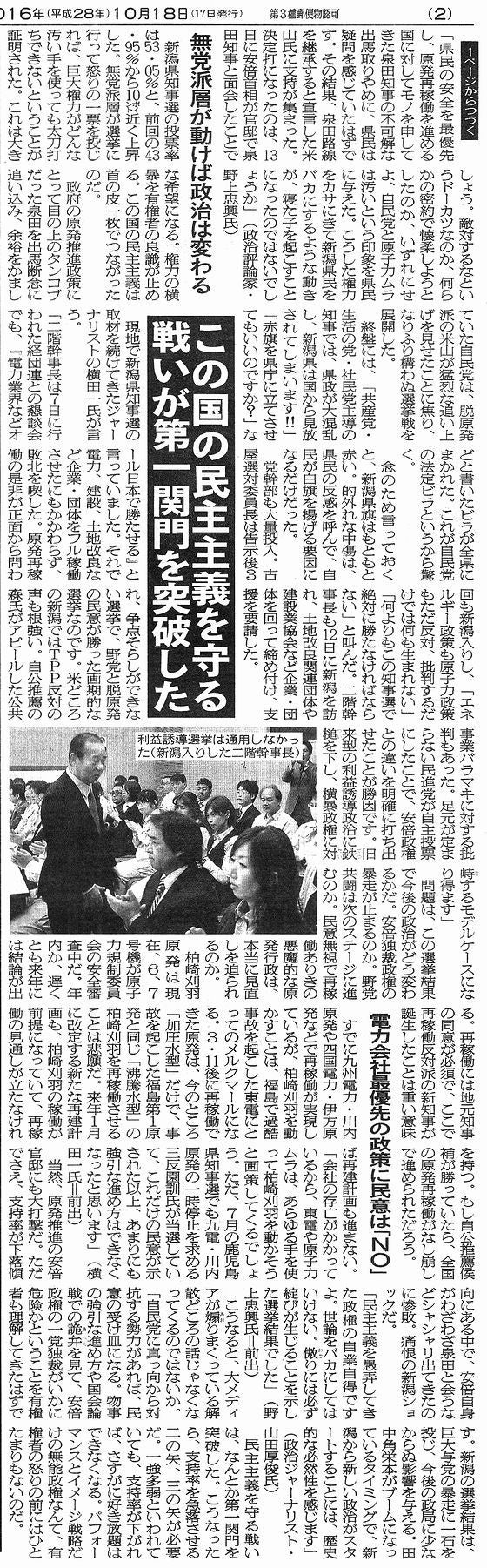
「県民の安全を最優先し、原発再稼働を進める国に対してモノを申してきた泉田知事の不可解な出馬取りやめに、県民は疑問を感じていたはずです。その結果、泉田路線を継承すると宣言した米山氏に支持が集まった。決定打になったのは、13日に安倍首相が官邸で泉田知事と面会したことでしょう。敵対するなというドーカツなのか、何らかの密約で懐柔しようとしたのか、いずれにせよ、自民党と原子力ムラは汚いという印象を県民に与えた。こうした権力をカサにきて新潟県民をバカにするような動きが、寝た子を起こすことになったのではないでしょうか」(政治評論家・野上忠興氏)
無党派層が動けば政治は変わる
新潟県知事選の投票率は53.05%と、前回の43.95%から10ポイント近く上昇した。無党派層が選挙に行って怒りの一票を投じれば、巨大権力がどんな汚い手を使っても太刀打ちできないということが証明された。これは大きな希望になる。権力の横暴を有権者の良識が止める。この国の民主主義は首の皮一枚でつながったのだ。
政府の原発推進政策にとって目の上のタンコブだった泉田を出馬断念に追い込み、余裕をかましていた自民党は、脱原発派の米山が猛烈な追い上げを見せたことに焦り、なりふり構わぬ選挙戦を展開した。
終盤には、「共産党・生活の党・社民党主導の知事では、県政が大混乱し、新潟県は国から見放されてしまいます!!」「赤旗を県庁に立てさせてもいいのですか?」などと書いたビラが全県にまかれた。これが自民党の法定ビラというから驚く。
念のため言っておくと、新潟県旗はもともと赤い。的外れな中傷は、県民の反感を呼んで、自民が白旗を揚げる要因になるだけだった。
党幹部も大量投入。古屋選対委員長は告示後3回も新潟入りし、「エネルギー政策も原子力政策もただ反対、批判するだけでは何も生まれない」「何よりもこの知事選で絶対に勝たなければならない」と叫んだ。二階幹事長も12日に新潟を訪れ、土地改良関連団体や建設業協会など企業・団体を回って締め付け、支援を要請した。
この国の民主主義を守る戦いが一関門を突破した
現地で新潟県知事選の取材を続けてきたジャーナリストの横田一氏が言う。
「二階幹事長は7日に行われた経団連との懇談会でも、『電力業界などオール日本で勝たせる』と言っていました。それで電力、建設、土地改良など企業・団体をフル稼働させたにもかかわらず、敗北を喫した。原発再稼働の是非が正面から問われ、争点そらしができない選挙で、野党と脱原発の民意が勝った画期的な選挙なのです。米どころの新潟ではTPP反対の声も根強い。自公推薦の森氏がアピールした公共事業バラマキに対する批判もあった。足元が定まらない民進党が自主投票にしたことで、安倍政権との違いを明確に打ち出せたことが勝因です。旧来型の利益誘導政治に鉄槌を下し、横暴政権に対峙するモデルケースになり得ます」
問題は、この選挙結果で今後の政治がどう変わるかだ。安倍独裁政権の暴走が止まるのか。野党共闘は次のステージに進むのか。民意無視で再稼働ありきの悪魔的な原発行政は、本当に見直しを迫られるのか。
柏崎刈羽原発は現在、6、7号機が原子力規制委員会の安全審査中だ。年内か、遅くとも来年には結論が出る。再稼働には地元知事の同意が必須で、ここで再稼働反対派の新知事が誕生したことは重い意味を持つ。もし自公推薦候補が勝っていたら、全国の原発再稼働がなし崩しで進められただろう。
電力会社最優先の政策に民意は「NO」
すでに九州電力・川内原発や四国電力・伊方原発などで再稼働が実現しているが、柏崎刈羽を動かすことは、福島で過酷事故を起こした東電にとってのメルクマールになる。3・11後に再稼働できた原発は、今のところ「加圧水型」だけで、事故を起こした福島第1原発と同じ「沸騰水型」の柏崎刈羽を再稼働させることは悲願だ。来年1月に改定する新たな再建計画も、柏崎刈羽の稼働が前提になっていて、再稼働の見通しが立たなければ再建計画も進まない。
「会社の存亡がかかっているから、東電や原子力ムラは、あらゆる手を使って柏崎刈羽を動かそうと画策してくるでしょう。ただ、7月の鹿児島県知事選でも九電・川内原発の一時停止を求める三反園訓氏が当選していて、これだけの民意が示された以上、あまりにも強引な進め方はできなくなったと思います」(横田一氏=前出)
当然、原発推進の安倍官邸にも大打撃だ。ただでさえ、支持率が下落傾向にある中で、安倍自身がわざわざ泉田と会うなどシャシャリ出てきたのに惨敗。痛恨の新潟ショックだ。
「民主主義を愚弄してきた政権の自業自得ですよ。世論をバカにしてはいけない。傲りには必ず綻びが生じることを示した選挙結果でした」(野上忠興氏=前出)
こうなると、大メディアが煽りまくっている解散どころの話じゃなくなってくるのではないか。
「自民党に真っ向から対抗する勢力があれば、民意の受け皿になる。物事の強引な進め方や国会論戦での詭弁を見て、安倍政権の一党独裁がいかに危険かということを有権者も理解してきたはずです。新潟の選挙結果は、巨大与党の暴走に一石を投じ、今後の政局に少なからぬ影響を与える。田中角栄本がブームになっているタイミングで、新潟から新しい政治がスタートすることには、歴史的な必然性を感じます」(政治ジャーナリスト・山田厚俊氏)
民主主義を守る戦いは、なんとか第一関門を突破した。こうなったら、支持率を急落させる二の矢、三の矢が必要だ。一強多弱といわれていても、支持率が下がれば、さすがに好き放題はできなくなる。パフォーマンスとイメージ戦略だけの無能政権なんて、有権者の怒りの前にはひとたまりもないのだ。

再稼働ノー「命・未来守りたい」
新潟県知事選勝利
市民と野党 官邸・”原子力ムラ”に勝つ
(しんぶん赤旗)2016年10月18日
東京電力柏崎刈羽原発6、7号機の再稼働ストップが最大の争点となり、16日投開票された新潟県知事選挙で、市民と共産、自由(旧生活)、社民、新社会、緑の野党5党が擁立した米山隆一氏(49)が自公候補に6万3000票の大差をつけて初当選しました。野党支持層、無党派層から保守層まで支持が広がり、「柏崎刈羽原発の再稼働は認めない」という県民の明瞭な審判です。当選確実の報を受けて、米山氏は「県民の勝利。オール新潟の勝利だ」「これからかスタート」と力強く決意を語りました。
(新潟知事選取材班)

「よくぞ出てくれた」急速に広かった期待
知事選開票結果について、地元紙の新潟日報17日付は「無党派・民進票取り込む 新潟ショック政権激震」と大見出し。全国紙も「政権、新潟ショック」「次期衆院選へ不安も 原発争点野党には効果」(「朝日」)の見出しです。
今回の県知事選でのNHKの出口調査で、原発再稼働反対は73%。そのうち、60%台が米山氏に投票したと答えました。
「泉田知事が降りた時点で絶望感を覚えた。でも、原発再稼働反対の候補が決まった時は、ほんとうにうれしかった」。開票の夜の、米山事務所での声です。「よく出てくれた」の声は各地で出ていました。
米山氏が、一度断った出馬要請を市民や野党の熱烈な願いを受けとめて立候補したのは告示6日前の9月23日。「よし、やるぞ」「参院選に続く、野党の共闘を」と、県民の期待と激励が急速に広がりました。
終盤の10日、上越市で開かれた個人演説会では、100人近いママさんたちが幼児を抱えながら壇上に上がり、「守りたい命。守りたい未来」とアピール。各地の個人演説会でも、「予想を超える人数」などの報告が続きました。
柏崎刈羽原発6、7号機の出力は日本最大級、1~7号機の合計で一つの原子力発電所としては世界最大。2007年の中越沖地震の際には、柏崎刈羽原発で液状化か起きました。
「福島原発事故の検証なしに、再稼働の議論はできない」。オール新潟”の声、県民の願いは明らかです。
今回の勝利は、福島原発事故を経験し、原発の危険に対する国や東電への根深い不安感が県民・国民に存在し、官邸、〃自民党本部直轄”、原子カムラ”の圧力をもってしても抑えきれないことを示しました。
各紙の社説で「原発への不安を示した」(「朝日」)、「原発不信を受け止めよ」(「毎日」)などと論じました。「読売」は3面記事で「原発に抵抗感強く 柏崎刈羽 再稼働困難に」との見出しを掲げました。
「力合わせれば勝てる」をス囗-ガンに猛奮闘
いかに市民と野党の共闘が進んだのか。市民と5野党で構成する「新潟に新しいリーダーを誕生させる会」の終盤の法定2号ビラは、「再稼働に同意しません!」の文字がくっきりと目立ちます。「権力にすり寄る知事ではなく県民に寄り添う知事を!」と打ち出します。「県民が力をあわせれば必ず勝てます」がスローガンです。
それが市民と野党の共闘をさらに励ましました。米山氏の各地の事務所では党派を超えた市民の熱気でいっぱいでした。どの事務所でも、若いママたちが宣伝や電話かけに懸命な姿がありました。
7日には新潟駅前で、日本共産党の志位和夫委員長、自由党(旧生活の党)の小沢一郎共同代表、社民党の福島瑞穂副党首、民進党の松野頼久衆院議員らのそろい踏みも実現しました。司会をしていた森裕子選対本部長(参院議員)が「前に詰めて通路をつくってください」と訴えるほど、聴衆であふれました。
日本共産党の小池晃書記局長は3回応援に入りました。選挙戦が進む中で、「自主投票」を決めていた民進党も前原誠司衆院議員、黒岩宇洋県連代表ら国会議員が続々つめかけました。最終盤の14日には、蓮舫代表、江田憲司代表代行が駆け付けると、「来てくれてありがとう」などの声が出ました。
こうしたスクラムが「県庁に赤旗が立つ」などの卑劣な攻撃をはね返しました。

「だいたい新潟県の旗の色は赤、候補者が旗の色も知らないのか。官邸が作ったのではないか」との批判も。

電話かけの中で。「俺は17年間、自民党員たった。今日ばかりは我慢ならない。『赤旗が立つ』なんてぱかなことを言う自民党はだめだ。米山に入れてきた」との声も寄せられました。
政権与党は総ぐるみで襲いかかってきました。安倍晋三首相まで乗り出し、泉田裕彦知事との会見を13日にセット。自民党の二階俊博幹事長は7日、経団連幹部との会合で、知事選に言及し「何とか(森民夫候補の)勝利を考えていきたい。電力業界などオールニッポンで対抗していかなければならない」と訴えました。県民の共同と、〃首相官邸・財界・原子カムラ”との対決がますます鮮明になりました。
公明党の井上義久幹事長も乗り込み、自民党は異例の”党本部直轄”態勢で、大量の国会議員を動員し、業界、各種団体の締め付けを行いました。投票日も、すさまじい締め付けが続きました。
原発再稼働推進の安倍首相から直接推薦状を手渡された相手候補。最終盤には、再稼働問題で、米山氏と違いがないかのような訴えをし、争点回避に躍起でした。
しかし、県民の願いの前には通用せず、敗北した相手陣営。「読売」は「与党総力戦で痛手」と論評しました。
自民支持層からも3割 共闘の力の進化示す
参院選に続く、知事選では多くの市民が自ら立ち上がり、野党と市民の共闘が進化する選挙戦となりました。
野党と市民が、はっきりした大義のもとで共闘すれぱ、自民党が圧倒的に強い地盤でも勝利できる、保守層の支持も広がることが浮き彫りになりました。本紙には、元自治相の白川勝彦氏も登場し、米山氏にエールを送りました。NHKの「出口調査」では、無党派層の60%台に加え、自民党支持層の30%程度が米山氏に入れたという結果も出ています。
この勝利は、「野党と市民の共闘の新たな発展を促し、日本の政治の前途に大きな希望をもたらす文字通りの歴史的勝利」(志位委員長の会見)です。

渡辺謙さん「どうやってこの地球から無用な兵器を無くしていくつもりなのか」(`・ω・´)


「日本の立場に合致せず」“核兵器禁止”日本は反対(16/10/28)
https://youtu.be/Unck84czzTg

核兵器禁止条約に日本が「反対」という信じられないニュースが流れました。いったいどうやってこの地球から無用な兵器を無くしていくつもりなのか?核を持つ国に追従するだけで意見は無いのか。原爆だけでなく原発でも核の恐ろしさを体験したこの国はどこへ行こうとしているのか、何を発信したいのか。



アメリカ軍事政策委員会 1943年5月5日
①日本人はドイツ人と比較して、この爆弾(原爆)から知識を得る公算が少ないとみられる。
②太平洋はほぼアメリカの戦場であって、同盟国に対して密かに投下準備ができる。
③ドイツ投下には原爆完成まで時間的に間に合わない可能性がある。
ハイドパーク覚書
ルーズベルト大統領とチャーチル首相は、ニューヨーク州ハイドパークで首脳会談した。内容は核に関する秘密協定(ハイドパーク協定)であり、日本への原子爆弾投下の意志が示され、核開発に関する米英の協力と将来の核管理についての合意がなされた。
→原爆投下目標は最初から日本




正体割れた父親と同じDNA
健康ゴールド免許ってなんだ?
ガッカリした小泉進次郎
(日刊ゲンダイ)2016年10月31日
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/192868
弱者を切り捨て、下流老人を増やすだけの格差固定の差別社会を自民党のホープが助長している恐ろしさ
「政界のプリンス」などとチヤホヤされても、やはりお里が知れる。自民党の小泉進次郎農林部会長ら若手議員が今週26日、2020年以降の社会保障制度のあり方に関する提言を発表したが、その内容たるや、おぞまし過ぎる。詰まるところ、健康の維持管理にカネをかけられない貧乏人はバッサリ切り捨てる、と宣言しているのに等しい。進次郎は親父そっくりの米国型の弱肉強食路線を地で行っている。
「人生100年時代の社会保障へ」と題した提言をまとめたのは、自民党の「2020年以降の経済財政構想小委員会」だ。進次郎は委員長代行として事実上のトップを務めている。提言は〈我が国の社会保障は、戦後の高度成長期に形成された〉として、終身雇用・定年という1つだけのレールに縛られない〈多様な生き方〉を反映することに主眼を置く。
進次郎たちが目玉の1つに掲げたのは、「健康ゴールド免許」の導入だ。運転免許証で優良運転者に「ゴールド免許」が与えられるのに倣って、定期健診などで健康管理に努めた人の医療保険の自己負担を3割から2割に引き下げる。いわば医療版ゴールド免許というわけだが、そもそも「交通違反」と「疾病リスク」を同列に扱うとはムチャクチャな発想だ。
進次郎たちは提言の中で〈医療介護費用の多くは、生活習慣病、がん、認知症への対応である。これらは、普段から健康管理を徹底すれば、予防や進行の抑制が可能なものも多い〉と決めつけているが、がん患者の中には遺伝的要因が強く影響して発症する人もいる。世の中には生まれつき病を抱えた人だって大勢いるのに、提言はこう続ける。
〈現行制度では、健康管理をしっかりやってきた方も、そうではなく生活習慣病になってしまった方も、同じ自己負担で治療が受けられる。これでは、自助を促すインセンティブが十分とは言えない〉
進次郎たちは表現こそソフトにまとめているが、発想自体はどこぞの“炎上アナ”と変わらない。9月に自身のブログで〈自業自得の人工透析患者なんて、全員実費負担にさせよ!無理だと泣くならそのまま殺せ!今のシステムは日本を亡ぼすだけだ!!〉と暴言をつづって、完全に仕事を干されたアノ人である。
オレたちの払っている保険料が無軌道に支払われていると言いがかりをつけ、医療コストがかさむ老人や病人を敵視する――。進次郎たちの提言は、この国の一部にはびこる偏狭的で不寛容な歪んだ風潮をいたずらにあおるだけである。
経済アナリストの菊池英博氏に提案の感想を聞くと、カンカンになってこう言うのだ。
「進次郎氏たちは所得だけでなく、ついに人間の健康にまで格差を拡大させるのかと驚愕します。今の時代、お金持ちほど健康維持に気を配れます。人間ドックや高級ジムに通えるのも、優良食材でデトックスに励めるのも、豊富な財力があればこそです。逆に雇用の不安定な人々は年に一度の健康診断さえ受けられないのが現実です。つまり、所得の格差が疾病リスクに大きな影響を与えているのに、健康管理に努められる恵まれた人々の自己負担を低くするのは、ロコツな金持ち優遇策です。提言の根底には、父親の純一郎元首相と同じカネが全ての新自由主義がうかがえます。『自助努力を促す』と言いながら、貧しい病人に肩身の狭い思いをさせる血も涙もない発想ですよ」
進次郎たちの弱者切り捨ての発想は、格差固定の差別社会を助長する結果を招きかねない。
ひょっとして米国のエージェントなのか
進次郎のように幼い頃から健康にカネをかけてこられた裕福な“お坊ちゃま”たちは、いざ病気になっても医療負担を低減されるし、その分を高度先進医療費などに回せる。一方で生まれながらに難病を患ってしまった低所得層の自己負担は据え置かれる。本来なら、こうした不幸な人たちこそ医療費を低減させるべきなのに、進次郎たちは容赦なく見捨てる。長期に及ぶ医療負担を賄えず、治療をあきらめざるを得ない人たちは救われないのだ。
埼玉大名誉教授の鎌倉孝夫氏(経済学)は、こう指摘する。
「進次郎氏らの提案は、やたらに『自助を促す』ことを強調していますが、社会保障の基本は『公助』です。そして日本の国民皆保険制度が優れているのは、国民が納めた保険料を通じ相互に連帯して支え合う『共助』が徹底されてきたためです。医療の現場に『自助』を求める発想からは、国民一人一人をコストの対象としかみなそうとせず、コストのかかる老人や病人を“金食い虫”と忌み嫌う考えが透けてみえます。行き着く先はアメリカ型の医療崩壊で、医療の恩恵を受けられるのは健康をカネで買える富裕層のみ。貧しい人々は満足な治療を受けられないというイビツな社会です。それこそが、『自助』という言葉で市場原理主義を推し進める進次郎氏らの望みなのではと思えるほどです」
進次郎たちの提言は「健康ゴールド免許」の他にも、突っ込みどころが満載だ。年金の受給開始年齢の上限を現行の70歳からさらに引き上げ、働く高齢者にいつまでも保険料を負担させる「人生100年型年金」も盛り込まれている。
定年を越えて働いている高齢者の多くは、年金だけでは老後資金を賄い切れず、何とか体が動くうちに「たくわえ」を増やそうとしている。進次郎お坊ちゃまは、そんな実態に目もくれず、さらに受給開始年齢を引き上げるなんて乱暴すぎる。ますます貧しい「下流老人」を増やすだけである。前出の菊池英博氏はこう言った。
「日本の国民皆保険制度を揺るがすような進次郎氏らの提案に、米国の保険会社は大喜びでしょう。彼らは皆保険制度こそが、日本における医療保険のシェア拡大を妨害していると目の敵にしてきた。将来の総理候補と目される与党の“ホープ”が、皆保険の崩壊を促すなんて願ったりかなったりです。また、進次郎氏は党農林部会長として農協改革と称し、金融部門の切り離しを目指しています。この提案だって、農協マネーを狙う米国を喜ばせるだけですよ。進次郎氏は初出馬の直前まで米国に留学し、“ジャパンハンドラー”の牙城とされる保守系シンクタンク『米戦略国際問題研究所(CSIS)』の非常勤研究員を務めていました。あまりにも米国寄りの提案の数々には、ひょっとして米国政府のエージェントなのかと疑いたくもなります」
進次郎の正体みたりで、こんな男が首相になったら、父親以上の“米国のポチ”になるに違いない。
核兵器禁止条約 交渉決議
その瞬間、国連の議場は歓声に包まれた
世論と運動 世界動かす
(しんぶん赤旗)2016年10月29日
「決議案は採択されました」。国運総会第1委員会のサプリ・ブカドゥム議長がこう告げると、議場は「ウォー」という歓声とともに拍手に包まれました。圧倒的多数の国が、核保有国の抵抗をはねのけてオーストリア主導の決議に賛成しました。推進力になったのは被爆者をはじめとする核兵器廃絶を求める世論と運動です。
(ニューヨーク=島田峰隆写真も)
新しい主流が誕生
採択された決議「核兵器廃絶の多国間交渉の前進」は、核兵器禁止条約など法的拘束力のある措置の交渉を2017年に始めるよう国連総会に勧告した国連作業部会の報告書を具体化した内容です。
核保有国はいまだに1万5000発を超える核弾頭を持ち続け、核不拡散条約(NPT)で義務付けられた廃絶への誠実な交渉は進んでいません。
ここ数年、核兵器の非人道性を告発する運動が広がり、国際会議も3回開かれました。このなかで核兵器を法的に禁止する措置の国際交渉を求める声がいっそう強まり、昨年採択された国連総会決議は「核兵器のない世界」を実現する「具体的で効果的な法的措置」を議論する作業部会の設置を決定。作業部会は今年、断続的に開かれ、国運の会議の来年開催を勧告する報告書を圧倒的多数の支持で採択しました。核保有国は作業部会に参加しませんでした。
今年の第1委員会の議論では、多くの国が「核廃絶交渉の前進がないなかで新たな段階に進むまたとない機会だ」(フィリピン)と歓迎しました。
国連加盟国の約3分の2を占める非同盟諸国、東南アジア諸国連合(ASEAN、10力国)、33力国でつくる「中南米カリブ海諸国共同体」(CELAC)、アフリカ諸国、アラブ諸国…。主要な国家グループが足並みをそろえて、勧告や決議案に支持を表明しました。
決議案の共同提案国になったニュージーランドは「各地域の声が一点に集中し、新しい主流がつくられた。その共有された未来が、来年の会議招集だ」と強調しました。
保有国の抵抗退け
核兵器廃絶の交渉を監視する「リーチング・クリティカル・ウィル」のレイ・アチソン氏は「禁止条約ができれば核兵器の維持や近代化は違法だと問われる。核抑止力に依拠した軍事同盟も同様だ。交渉過程の段階でも国民の監視が今以上に強まる」と意義を語ります。
それだけに核保有国5力国(米英仏中口)は「安全保障で核兵器に依存する国々がどうして核兵器に汚名を着せる交渉に参加できるだろうか」(米国)などと激しく抵抗しました。これに北大西洋条約機構(NATO)諸国など核の傘にある国々が追随しました。
これらの国は▽ステップ・バイ・ステップ(一歩一歩)の接近こそが現実的で試され済みの方法だ▽核兵器は安全保障に不可欠だ▽禁止条約は国際社会を分断する一方的な動きだ-などの理由を挙げて、他の国々に決議案に反対するよう促しました。
一方、決議案に賛成する国々は核保有国の主張を一つ一つ突き崩す討論を続けました。
非同盟諸国を代表して発言したインドネシアは、保有国が核兵器の近代化を進めている事実などを示して「いわゆるステップ・バイ・ステップの接近が核兵器廃絶に具体的で体系的な進展をつくれていないことは明らかだ」[新しく包括的な方法を取るときだ]と強調しました。
エクアドルは「核兵器はだれにとっても安全を保障するものではなく、むしろ人類全休にとって永続する危険の源だ」と指摘。トリニダード・トバゴも「国の名声は平和をつくり、維持する能力にこそある」と述べました。( ゚ー゚)( 。_。)
禁止条約の交渉開始を一方的な措置だとする主張にアイルランドは「作業部会に参加しなかった国々は、除外されたのではなく、選択してそうしたのだ」と反論。交渉に背を向ける核保有国を批判しました。
こうした指摘に核保有国からは明確な反論はありませんでした。
市民社会局面開く
来年3月には核兵器を禁止する動きが始動します。この局面を切り開いてきた力は、被爆者をはじめとする核兵器廃絶を求める運動です。
日本被団協の藤森俊希事務局次長は第1委員会の会期中、ヒバクシヤ国際署名推進連絡会を代表してニューヨークを訪問。国運本部でブカドゥム議長に会い、日本で集めた56万4240人分の署名目録と400人余りの知事、市町村長、地方議会議長の署名を手渡しました。 議長は、「署名は被爆者の方々が人間の倫理や社会的責任に訴える力を持っている証拠です」と激励しました。
議長は、「署名は被爆者の方々が人間の倫理や社会的責任に訴える力を持っている証拠です」と激励しました。
国運作業部会の議長を務めた在ジュネーブ国運・国際機関タイ政府代表部の夕ニ・トーンパクディ常駐代表は、第1委員会の関連イベントで、条約の交渉が始まると核の傘の下にある国々も対応を問われるとし、「そこでまた国会議員や市民社会が大切な役割を果たすことになる」と期待を表明しました。
日本の反対に批判
日本政府を代表した佐野利男軍縮大使は「核保有国と非保有国の建設的な協力を通じた実際的で具体的な措置が唯一の効果的な方法だ」として、核兵器禁止条約の交渉開始を求めませんでした。
同氏は「核軍縮に向けた努力を進める上では安全保障を考慮に入れる必要がある」などと核保有国に同調。核保有国には「自発的に達成できる小さなステップであっても、できるだけ多くの具体的な軍縮措置を取るよう求める」と述べるなど、核保有国と全く同じ態度を示しました。
オーストリア主導の決議に日本が反対したことについて「核兵器廃絶国際キャンペーン」(ICAN)のベアトリスーフィン事務局長は「決議は被爆者をはじめ核兵器の非人道性を問う流れの中でできたものだ。それに日本政府が反対したのはたいへん悲しく残念だ。日本政府は核兵器が合法だと考え、禁止に反対なのかと問わなければならない」と批判しました。
わが子を荼毘に付す母親
・・これが現世と思えない地獄だ・・
「戦争する国」本質あらわ
関西学院大学教授
原水爆禁止世界大会起草委員長
冨田宏治さん
核兵器禁止条約の交渉開始を決定する決議の採択に唯一の被爆国・日本の政府が反対したことは、被爆者の願いに背を向ける許しがたい愚挙です。
日本は本来、共同提案に加わって、唯一の被爆国にふさわしい役割を果たすべきでした。
米国は同盟国に対して、この決議に反対するよう文書で要請していたと伝えられています。日本政府はこの要請に応え、被爆国としての立場をかなぐり捨てたのです。
「抑止力」(=核抑止力)の強化を掲げて、戦争する国づくりにまい進してきた安倍政権が、その本質をあらわにしたともいえるでしょう。
日本の反対にもかかわらず、12月には国連総会でも、この決議が賛成多数で採択され、来年3月には核兵器禁止条約の交渉が開始されることとなるでしょう。
この交渉を促進させる市民社会の圧倒的な世論、それに形を与える「ヒバクシャ国際署名」運動の一層の推進が必要です。
平和の泉
のどが渇いてたまりませんでした
水にはあぶらのようなものが
一面に浮いていました
どうしても水が欲しくて
とうとうあぶらの浮いたまま飲みました
―あの日のある少女の手記から
第026回ライトアップジャーナル 小出裕章先生「子どもたちに原子力を暴走させた責任はない」
自由なラジオ Light Up! 026回
「ベラルーシで甲状腺がんを治療しつづけた医師、菅谷昭・現松本市長と小出裕章さんとの特別対談! in 松本」
https://youtu.be/2-743egUy7w
第026回ライトアップジャーナル
ベラルーシで甲状腺がんを治療しつづけた医師、菅谷昭・現松本市長と小出裕章さんとの特別対談! in 松本
http://jiyunaradio.jp/personality/journal/journal-026/
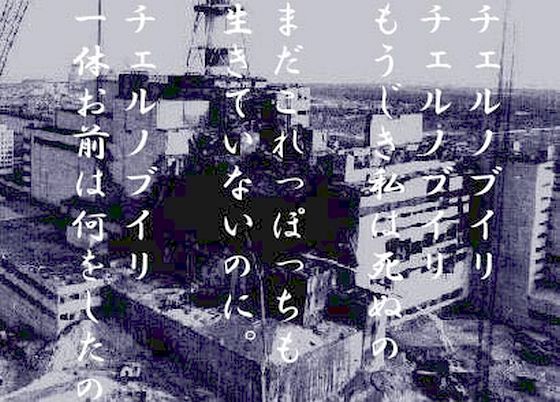 チェルノブイリ
チェルノブイリチェルノブイリ
おまえは不幸を持ってきた
わたしはもうじき死ぬの
まだこれっぽっちしか生きていないのに

-前半-
いまにしのりゆき:
今週は長野県の松本市からお届けをしております。ここからは、元京都大学原子炉実験所助教の小出裕章さんにも入って頂きます。小出さん、よろしくお願いします。
小出さん:
よろしくお願いします。
いまにし:
小出さん、やっぱり松本市、暑い大阪から来たら、ほんと過ごしやすいですねえ。
小出さん:
はい。大変快適な街です。空気が美味しいし、まるじゅう山だし、街中にも温泉がある。こんなにいい街があったんだ。もっと前から住みたかったなと思うぐらいに、いい街だと思います。
いまにし:
なるほど。それで小出さんですね、この松本市を京都大学退官されてから移住の地に選ばれたということなんですけれども。やはり、菅谷市長の影響が大きかったんでしょうか?
小出さん:
はい。一番は、まず私、暑いのが大嫌いなので涼しい街に行きたいと。そして、東京とか大阪のような大都会はまっぴらごめんだと思っていました。そして、新幹線が通るようになってしまうと、みんな何かミニ東京のような街に変わっていってしまって、面白くない。だから、地方の小ちゃな都会で、それもちゃんと文化を大切にして、年をとっても健康に生きられるような街であって欲しいと。それで探しました。
そしたら、松本という街は本当に私の願ってる通りの街だったわけですし、そして、今、いまにしさんもおっしゃって下さったように、そこの市長が菅谷さんだということだったわけです。この菅谷さん、大変素晴らしい方なわけで、その菅谷さんが市長をしてくれている街に行きたいと私は思いました。ただ、それ以上にと言うか、その時に思ったのは菅谷さんを選ぶ市民がいるんだということで、私自身もその市民の一人になりたいという、そういう思いで松本を最終的に選びました。
いまにし:
はい。菅谷市長、今の小出先生のお話いかがでしょうか?
菅谷市長:
いやー、ありがたいですし、それに僕は本当にこういう巡り合いって言うんですかね、まさか小出先生が松本に住まれるなんて事は、もう考えたことなかったわけですから。
いまにし:
お二人はお知り合いになられてから、かなり長いんでしょうか?
小出さん:
私は、菅谷さんがチェルノブイリで子供達の治療にあたって下さってるということを大変ありがたいなと。専門的な知識を持ったお医者さんが、その知識を使って子供達を助けてくださるということは、大変ありがたいと思っていたのです。私もチェルノブイリに何度か行きましたが、97年の1月に私またチェルノブイリに行った時に、菅谷さんはもう既にベラルーシに住んでいて、そこで医療活動をされて。

菅谷市長:
ちょうど1年目ぐらいですよ。
いまにし:
なるほど、なるほど。そうなんですねえ。
小出さん:
それで、私、菅谷さんのアパートをお訪ねして、ご馳走になったという。それが初めて。
菅谷市長:
ご馳走ではないんですけどね。
いまにし:
はいはいはい。
菅谷市長:
本当にね、僕ね、ここにね、自分がつまらん本に書いてるんですけど。ちゃんと日記つけてるんですけど。ただね、ちょっと聞いて下さいよ。1月26日、日曜日なんですよ。
「零下10度、久しぶりに晴れ上がった青空を見る。午後、日本からの二人の訪問客あり。彼らは、某大学の研究スタッフ。軽く飲みながら歓談した。二人は、基本的には脱原発の立場にある。しかし、彼らの弁によると、単に原発に反対しても運動の発展性がない。現在の生活様式を含め、日本人自身の価値観を変えていく必要があると話してくれた。価値体系の見直し。なるほど。その通りかもしれない」
という風に書いてある。
いまにし:
はい。それは、「チェルノブイリ命の記録」という菅谷市長の著書ですねえ。はい。
菅谷市長:
ですから、その時にやっぱりね、この後、私言ったんですね。「じゃあ、私がこの二人の研究者に対して、そのような市民運動をもっと広範囲に展開していけないものかと尋ねるも、明確な返答は得られなかった。彼ら自身、先頭を切って、そこまでやっていく気持ちはなさそうだ。その後、ソーメンを作って出すと、『これは上手い』と日本人らしく音を立てて食べてくれた」って書いてあるんですよ。
いまにし:
ソーメン美味しかったですか?
小出さん:
そうです。美味しかったです。
菅谷市長:
ですからね、向こうにいるからソーメンなんてないじゃないですか。
いまにし:
そうですね。はい。
菅谷市長:
で、食べてくれましてね。でも、その僕は小出先生がまさか松本においでになるって。今日もそうですけど、こうやって対談するこういう状況っていうのは、人生っていうのは、本当になんか深いものがあるなあと言うか、不思議だなあと思ってますがね。
いまにし:
なるほどねえ。そうなんですよねえ。それで、菅谷市長ですね、そのベラルーシにいらっしゃる時は、どういう地域で医療活動に従事されておられたんでしょうか?
菅谷市長:
そうですね、私、これ91年から95年までは現地7回入ってますが、これは、どちらかと言えば、大学に休みをもらいながら、比較的、汚染された地域で子供の検診をやってました。汚染検診を。それと併せて、やっぱりがんセンターを訪問しますと、手術した子供たち見てますけども、だんだん増えてきていますもんですから、「これはもう日本から来てちょっとやるっていうのは無理だなあ」っていうことで、私はちょうど生き方のことも出てましたから、96年からは2001年まで5年半は、現地で「やっぱり自分はそこでもってやるしかないなあ」と思ったもんですから、やってきました。
いまにし:
なるほど。いわゆる現地でもう住んで、ずっと医療活動に。
菅谷市長:
医療活動。
それは、ミンスクの首都で。ただ、私はその5年半の中には、ミンスクで3年半やった後、今度、一番汚染されたゴメリーの州立がんセンターに移って、そこで1年半やって、最後の半年は原発から90キロのモウゼリーっていう街へ行きまして、そこで検診をやったんですけども。「もっといて欲しい」って言われたんですけども、退職金があの時に1100万だったんですね。25年の。国家公務員の。
あそこに行くと、1年に200万使うんですね。やって行けたんです。200万で。そうすると、5年で1000万ですね。残り、あと100万あったから、残りはあとモウゼリーで6カ月いて、全部使い果たしたんです。
いまにし:
そうなんですか。全部使い果たしてご家族怒りませんでした?
菅谷市長:
いやー、もう全然なかったですね。そういう事は。
いまにし:
そうなんですねえ。
菅谷市長:
ええ。それはもう国で貰ったお金は国に返すっていうことでやりましたから。ええ。でも、ちゃんと神様は、また次の仕事見つけてくれたから。食べていけりゃあいいんですよ。
いまにし:
なるほどねえ。小出さん、そういう菅谷市長の医療活動に取り組まれる姿勢っていうのは、どのように現地で見られてましたでしょうか?お訪ねになられて。
小出さん:
普通ですね、日本で例えば、大学のお医者さんになるというような人は、功成り名を遂げてるわけですし、そのまま、その場で勤め上げれば、みんなから尊敬されるような存在であるはずなのですけれども、菅谷さんは全然違ったんですね。先ほど、ご自分でもおっしゃったけれども、死ぬ時に納得して死ねるのかということが、菅谷さんにとっての凄い大切なことだったわけで。
自分の地位も何もかも全部捨てて、今おっしゃったように、退職金も全部使い果たすという、そういう事でご自分が納得できるような生き方を選ぶということで、ベラルーシに行って下さったわけだし。まさに、菅谷さんは甲状腺のほんとエキスパートだったわけであって、ベラルーシの子供たちにとってはそういう人が来てくれる。そして、菅谷さんが本気でそこで自分の力を使おうとしたわけであって、素晴らしい巡り合いがそこで出来たんだと思いますし、ありがたいことだなあと私から見ると思いました。
いまにし:
はい、菅谷市長どうでしょう?日本にいらっしゃる時は、それまで原発の問題とか、なんかお考えになられる事っていうのはあったんでしょうか?
菅谷市長:
実際、そういうメカニズムっていうのは、一応、話は聞いております。例えば、甲状腺のガンになるメカニズムとか。でも、そういう事よりも、やっぱり本当にガンになってる子供を前にしますと、これはほんとに罪もないと言うか。そういう人に対してこういう事をするっていうのは、いかに放射線物質っていうのは大変な物だ、エラいもんだなあっていうのはやっぱり思いますからねえ。こういうのを実際見てると、これはもう変な話ですけど、やっぱり無くさなきゃいけないなあっていう風には思いますよねえ。
いまにし:
なるほどねえ。分かりました。その辺のお話ですね、また後半戦に続けていろいろ伺いたいと思います。前半戦そろそろお時間となりました。この後ですね、お知らせと音楽の後に続けまして菅谷市長、そして小出さんに話を伺っていきたいと思います。
-後半-
いまにし:
今回は長野県松本市からジャーナリストの私、いまにしのりゆきがお届けをしております。ゲストはお二方、松本市長の菅谷昭さん、そして、小出裕章さんにもおいで頂いております。菅谷さん、今年の7月に、またベラルーシの方へ行かれたということなんですけれども、何日間ぐらい行ってらっしゃったんでしょうか?
菅谷市長:
実質的には5日間でしたね。これは、やっぱり行くのに往復でも4日かかる。2日、2日ですから。ですから、大変厳しい日程で行って参りました。
いまにし:
具体的に、ベラルーシ共和国のどちらに行かれたんでしょうか?
菅谷市長:
首都のミンスク、それからあとゴメリー州へ行きまして、ゴメリー市から少し離れた所にある高度の汚染地域です。ホットスポットエリアの方へ行ってきました。
いまにし:
それで、チェルノブイリの原発事故からちょうど30年になるわけなんですけれども。今回、実際に行かれまして、昔、菅谷市長が向こうで医療活動されておられた時と比較してどうでしょうか? 状況は。
菅谷市長:
チェルノブイリの原発から30キロゾーンっていうのは、もう相当高度に汚染されて、今でも居住禁止区域になってますね。ところが、こういう所はあちこちにホットスポットエリアっていうことであるわけですね。あちこちに。ゴメリー市から近くのそのホットスポットエリア前も行ってましたから。4年前に行ってました。今回もどうなってるかっていうことで行ってきました。150キロぐらい離れてたんですよ。

いまにし:
150キロ離れた所にもホットスポットがある。はい。
菅谷市長:
それは、福島も同じなんですよ。だから、局所的にやっぱり放射能の雨とか雪とかなって、ポンポンとあちこち落ちるもんですから。そうすると、放射性物質のエリアだけ汚染されると。
その所へ行ってきましたけど、結論は、結局、30年経ってももう除染してるんだけども除染しきれない訳ですよね。もう諦めてるわけですよ。
ですが、そこはもう相変わらず、国からは住んじゃいけないと。居住禁止区域なんで。ただ、そこにはお年寄りがやっぱり戻って来てますね。もうね。自分のもう汚染地でもいいから、そこで死にたいと。最後は。あるいは、お墓守りたいっていう。そこのおばあちゃんにお会いしましたんですけれども、結局、そこのエリアは3つの老夫婦が住まわれてるんですけど。
いまにし:
3家族。はい。
菅谷市長:
3家族ですねえ。亡くなると、多分そこの村はなくなっちゃうんです。もう除染しきれないんです。
いまにし:
小出さん、今、除染の話が今出ました。今、福島第一原発の事故の後、もう除染をせなあかんということで、あっちこっち除染してます。帰りましょうということを国が呼びかけ始めましたけど、大丈夫なんですかねえ。今の話伺ってて。
小出さん:
まず、今、いまにしさんも除染という言葉を使われましたけれども、相手にしてるのは放射能なんですね。

人間には、放射能を消すという力がありません。ですから、言葉の本来の意味で言えば、汚れを除くということは出来ないのです。ある特定の場所にある汚染を別の場所にどっかに移動させるということしか出来ないわけで、今、止む無くそれをやっている。

でも、消したわけではありませんから、移動させた放射能のゴミがもうそこら中に積み上がってしまっていて、それをどうしていいか分からないという、そういう状態になっているわけです。そして、今、菅谷さんもお話下さったように、30年経っても除染というか移染がなかなか効果が上がらないというような現実もあるわけであって、福島の場合も、事故から5年経ちましたけれども、まだまだ厳しい状況にある。私達が今、向き合っている一番重要放射性物質はセシウム137という名前の放射性物質で、それが半分に減るまで30年かかる。福島からまだ5年しか経っていないわけで、汚れ自身はまだまだほとんど減っていないという状況なわけですね。
そして、これ皆さんほとんどお気づきになっていないというか、忘れさせられてしまっているのですが、福島第一原子力発電所の事故が起きた当日に、“原子力緊急事態宣言”というものが宣言されました。その為に、今、日本は緊急事態下にあるのだから、これまでの法律を守らなくてもいいということで、様々な特殊法というのが出来て、従来の法律が反故にされてしまったわけですが、その原子力緊急事態宣言は、事故から5年半以上経ってる今も、実は解除されていないのです。
ですから、日本というこの国は緊急事態宣言下にある国なわけですが、この緊急事態宣言は、ではいつ解除できるのかと言えば、先ほど聞いて頂いたように、汚染が半分に減るまで30年もかかるというそういう事なわけで、実は、この緊急事態宣言は今後何十年も解除できない、そういう国だということを私たち日本人はきちっと知らなければいけないし、本当であれば住んではいけない所にたくさんの人々、子供達も含めて捨てられてしまっている緊急事態だという理由で捨てられてしまって、それが今後、何十年も続いていくしかないという、そういう国なのです。
いまにし:
はい、分かりました。それでですね、今回、菅谷さん、チェルノブイリ行かれまして、なんかこういう点が今までと変わったなあとか、なんか印象深いような所がもしありましたら、教えて頂ければと思うんですけども。
菅谷市長:
健康に関してですね、向こうでは保健省って言ってます、こっちでは厚生労働省みたいな所ですね。そういう所の国の役人さん、あるいはまた私のお世話になってたがんセンターのドクター達、それから、また一番汚染されてるゴメリー州の州の保健局にも行ってお話を伺いました。国の行政関係の人っていうのは、もう今は汚染の状況も影響も心配ないぐらいなことを言われるんですけども。
いまにし:
なんか日本とよく似てますねえ。小出さんねえ。
菅谷市長:
現地行って、そして保健局の局長さんは前から知ってるもんですから、正直なことを話してくれます。やっぱり、この汚染されたゴメリー州の中でいくと、例えば、大人も含めた方々の4割から6割はもう健康状態が悪いんだと。慢性的疾患があるとか。それから、またある所に行くと、子供達が大変ある意味で元気がないということで、その具体的に、例えば免疫能力が落ちちゃっているから、非常に上気道感染って風邪引きやすいとか治らないとかって、
こういう事があるとか。あるいは、また周産期医療の問題、産婦人科医に聞きますと、やっぱり早産とか死産。あるいは、また先天異常も増えてるとか、こういうのの問題があるとか。
いまにし:
そんな中で、ご専門の甲状腺の方はいかがでしょうか?
菅谷市長:
でね、甲状腺に関しては、子供はもうないわけですよね。基本的には。放射性ヨウ素自身が8日ぐらいでもって半減期が。そうすると、半年ぐらい経つと、その影響力が無くなりますから。甲状腺がんに関しては、子供はもう影響ないと。ところが、今、大人が増えてるんですね。
これは2通りあって、1つはもともとの自然発生ガン。我々でもなるガンはいくらでも起こりますから。自然発生がんと。もう1つが、小さい頃にわずかな被ばくを受けてる子供達が大人になってから徐々にそれがガン化して増えてきている可能性ってあるもんですから。だから、放射線誘発性の甲状腺がんっていう表現しますけれども、それが健診対策しっかりしてくると、やっぱり見つかってくるわけですよね。だから、そういう意味でも今、大人のガンが増えてるんですね。これが、どちらかっていうのは証明できないもんですから。
少なくとも甲状腺がんに関しては、子供は15歳未満の子供はないという。但し、もっと大きな今の20代、30代、40代っていうのは、こういう方々のガンが増えてきてる。ガン、甲状腺はね。でも、それ以外のガンは、他にもいくらもあるわけですから。そういうものが増加してる。でも、本当にこれが放射線の影響がどうかっていうのは、そこの証明がつかないから。あとは疫学的に、今後ずっとしばらく見ていかなきゃいけない。そうすると、向こうのドクター達も言ったのが、「ナガタブレイミアって。時間が必要なんだよ」って言うんですよね。

いまにし:
ナガタブレイミアっていうのはロシア語ですか?
菅谷市長:
ええ。ブレイミアっていうのはタイムなんですよ。ナーダがニードなんです。ですから、時間が必要なんですよ。「これからもずーっと継続して見るしかない」って言ってますね。
いまにし:
小出さん、これ日本でも福島の事故があって、これ低線量被爆については、これから大きな問題、大きな課題になってくると思うんですけれども。そんな中、さっきも申し上げたようにですね、「いやいや、地元の人にはそろそろ帰りましょう」みたいな呼びかけが始まってる。いや、こんなんで大丈夫なんかなあと本当にヒヤヒヤするんですが。
小出さん:
ヒヤヒヤどころか、本当にひどい国だなあと私は思います。もともとその被ばくというものが危険を伴うということは、もう学問の常識なのです。その為に、世界中で法律で被ばくの限度を定めるというような事をやって、人々をできる限り、被ばくをさせないようにしようということでやってきたわけですけれども、福島の事故が起きてしまった途端に、日本というこの国では、先ほども聞いて頂いたように、緊急事態だということで、被ばくの限度も取っ払ってしまい、一年間にそれまでは1ミリシーベルトが限度だと言っていたのに、20ミリシーベルトまではなんでもない。みんな帰れというようなことを今、日本の国は言っている。そして、一年間に20ミリシーベルトという被ばくの限度というのは、かつて私自身がそうであったように、放射線業務従事者と呼ばれる非常に特殊な人間。

つまり、仕事として放射線を扱って給料をもらうという、そういう特殊な人間に初めて許した基準を、赤ん坊にも適用してしまうというような事をやろうとしているわけです。今の菅谷さんがおっしゃって下さったけれども、そういう被ばくの所で、どういう障害が起きてくるかということは、私はもう様々なものが出ると思いますが、それが、被ばくと本当に関係してるかどうかということは、いわゆる疫学という学問の分野で証明するしかないわけで、大変長い時間がかかってしまう。そして、時間がかかって証明した時には、もう被害自身は出てしまうという、そういう事になってしまうわけであって、もっと慎重に、注意深く子供達を守るということを本当は国がやらなければいけないと私は思います。
いまにし:
菅谷さん、その低線量被ばくの影響と思われることっていうのが、先ほど、風邪が引きやすいですとか免疫力が落ちるというような話があったんですが、菅谷さん自身も講演で、要するにチェルノブイリエイズなんていう言葉があるということでご紹介されておりますが、この辺について、ちょっと解説頂けましたらいががでしょうか。
菅谷市長:
エイズはご承知の通り、やっぱり後天性の免疫不全という状況ですから、これは、チェルノブイリの場合だったら、その影響、その免疫不全というのは、放射線の被ばくによって人体の免疫系が障害を受ける。結果として免疫不全。それが、チェルノブイリエイズという表現になるわけですね。
いまにし:
なるほど。それは、もうチェルノブイリ周辺では、もう当たり前のようになりつつある?
菅谷市長:
もうお父さん、お母さん達にも4年前にお会いした時も、子供達に対いて免疫機能の検査やってますから。やっぱり、明らかに低いんですよね。
いまにし:
なるほど。例えば、一般の子供さんが100あるとしたら、大体どれぐらいなんでしょうか?
仮に。
菅谷市長:
そういう風に言われたら、相当だから汚染の状況によっても違います。それでもやっぱり、その状況っていうのは、例えば、6割から7割になっちゃうって事ですよね。
いまにし:
そんなに減るんですか?
菅谷市長:
ええ。でも、高度の汚染地の所は、ほんとに変な話ですけど、健康の子供はいないっていうことまで言われるぐらいですから、やっぱり、なんかの病気があるっていうことですよね。それが、免疫状態が低下する以外にも、ほんとに元気がないとか、要するにある意味では、耐久力がないとかね。なんとなく元気がないっていうの、これだから物事が長続きしないとか、いろんな事があるんですよね。だから、そういう風な状況っていうのが、今、小出先生お話になったけど、将来これどういう事出るか分からないですから。だから、僕はそれが誤診かもしれないけども、これがもし誤診で元気な子供に会ったら、こんな嬉しい誤診ですからね。
それ今、戻そうと今お話言われたように、僕は考えられないことだなあと思って。今回、ベラルーシに行った時に、そういうドクター達も日本の状況に関心持って知ってるんですよね。「なんで日本はそんな事やってるんだ」って不思議がってますよ。
いまにし:
なるほどねえ。チェルノブイリ周辺で現実問題大変なことになっているわけですから、それを見習えば必然と答えは違った答えが出るんじゃないかという風に考えられておられるんでしょうねえ。おそらく。
菅谷市長:
そうですね。「どうして、もっと厳しくしないか」って言ってますよ。「どうして、日本はあんなに甘いのか」って。だから、僕もう答えられませんでしたよ。そうやって聞かれて。
いまにし:
そうなんですねえ。
菅谷市長:
うん。だから、恥ずかしかった。
いまにし:
なるほど。分かりました。それでですね、話少し変わりまして、東日本大震災が起きた福島第一原発が事故というのを聞かれまして、菅谷さんですね、市長としてどういう事やらなあかんと思いましたか?その時は。
菅谷市長:
だから、すぐ子供達守らなきゃいけないと思いました。原発自身の対応っていうのは、小出先生たち専門家がみんなが考えることであって、僕らは向こうに行って、医療者とした時に「絶対にチェルノブイリの二の舞をさせちゃいけないな」ってすぐ思いましたね。だから、子供だけはしっかり考えていかなきゃいけないと思っています。もちろん大人も含めるんだけども。
しかし、子供の方がはるかに感受性高いわけですから。被ばくに対して。だから、僕としては、すぐ避難させるような状況でも、もっと範囲を広げろとか、あるいは、ホットスポットが出てきますよとか、あるいは、あの時はやっぱりヨードの内服をした方がいいんじゃないかとかっていうのは、田舎でもって僕言ったが、ちっとも聞いてくれませんでしたね。こっちで僕言ってましたね。すぐね。こっちの新聞で取り上げて、ホットスポットって言っても、当初分かんなかった。みんな。何の事かって。今、当たり前に言うけど。
それは、僕はチェルノブイリのことで学んでるからそんなまでないし、当初、日本は10キロ範囲で。そんなもんじゃない。50キロだって、まだ駄目だよとか。だから、そんな事ですよね。だから、知らない人がみんなやってたわけですね。実際のところは。口では、放射能災害って対応なんて言ってるけど、いざ起こってみたら出来てなかったから。これは、小出先生なんかが一番よくお分かりと思いますよ。
いまにし:
そうですねえ。
そんな中で、いわゆる市長として原発事故にあたって、松本市ではこういう風に取り組んでいかなければいけない。こういう供えが必要ではないかとか、事故を受けられたその教訓として取り組み始められたことですとか、お考えですとか。
菅谷市長:
そうですね。松本は原発ないですけど。しかし、ご承知の通り、やっぱり新潟の柏崎の刈羽原発とか。
いまにし:
石川県もね志賀原発。
菅谷市長:
志賀原発ある。そして、うちは浜岡ですね。
いまにし:
浜岡から真北ですよね。位置的に言うと。
菅谷市長:
大体あそこから180キロ離れてます。
いまにし:
先ほどおっしゃられたベラルーシ、チェルノブイリでは150キロの所にホットスポット。
菅谷市長:
ありますからね。
いまにし:
はい。
菅谷市長:
200キロ、300キロ飛びますから。だから、それを考えると風向きなんかになりますから。そういうのの対応っていうことで、私はこういう松本市はないけども、早速もうこれ作りましたね。
いまにし:
なるほど、なるほど。
菅谷市長:
ですから、もう災害へんで、これはもう松本市ではもう24年から作りまして、いわゆるその医療救護活動マニュアルで、原子力再編、これ、うちの医師会の先生、或いは、また歯科医師会とか薬剤師会の先生が一緒になって相当しっかり考えてきまして。松本でもそういうことがあったらどうするかとか、或いは、松本避難したら来る人がいたらどうするかとか、こういうようなマニュアル作って、対応に、或いは、今でもそうです。
うちは、ヨード剤をちゃんと備蓄してますからね。観光客のやつも。だから、要りますからね。この時、起こったらどうするかとか、そういうようなやっぱり危機管理とか、そういう事やっぱりやっていかなきゃいけないと思ってるんですよ。ここでも。
いまにし:
小出さん、こういう市長さんがいらっしゃると心強いですね。
小出さん:
松本は菅谷さんがいて下さるし、やって下さってるわけで。でも、松本だけやってもダメなわけですし、もっともっと広い範囲で取り組んで欲しいと思います。
いまにし:
ですよね。こういうチェルノブイリをなんで手本にしないんでしょうねえ。チェルノブイリを手本にすれば、もう少し変わってくると思うんですが。小出さん。
小出さん:
それは、でも昔から日本で原子力をやってきた人達というのは、日本の原子力発電所に関する限り、絶対に事故なんて起きないと言っていたわけですし、「防災計画も不要だ」「住民の避難訓練も必要ない」という風に彼らは言いながら、今日まで来てしまったわけです。残念ながら、福島の事故も起きてしまったわけですけれども。でも、未だに彼らは、原子力発電所を再稼働させる。
或いは、場合によっては、新規に造るというようなことまで言っているわけで、原子力発電所は大丈夫なんだ、そんな危険なもんじゃないんだということをどうしても彼らは言い続けたいわけだし、福島のことも先ほどからいまにしさんもおっしゃって下さってるけれども、汚染地に人を帰してしまう。もう大丈夫なんだというようなことを彼らはやろうとしている。そうなれば、ちゃんとその防災計画を立てるなんていうことは、むしろ、それをやればやるだけ彼らはその危険を皆さんに知らせてしまうことになるわけですから、あまりやりたくない。
知らん顔をして、「安全なんだ、安全なんだ」と今まで通りにいきたいと、たぶん彼らは思っているんだと思います。
いまにし:
なるほど。菅谷市長ですね、そういう今、日本の原子力政策の中で、今年の松本市の平和祈念式典のちょっとメッセージを拝見させて頂きました。その中でですね、今のような原子力政策でいいのかなあというような思いをするような一説もあったんですけれども、その辺について、ちょっとご意見を伺わせて頂きましたらいかがでしょうか。
菅谷市長:
この時は、原爆を含めての核廃絶ということで言いますけど。僕、原発だって核によるものですから、あれ、両方とも核なんですよねえ。なんて言うんですか、訳し方がマズイんで、原発なんてNuclear Plant 、Nuclearなんですよ。あれ。だから、本当は核だと思うんですよ。あれねえ。
そうすると、僕は片方の原爆の時みんなワイワイやるけど、どうして原発の時はあんまり声が上がらないか不思議でならない。僕は、両方とも核なんですよね。で、この2つの物を形が違う形だけど、日本人は2回経験してるんですよね。そうするとね、もっと僕らはある意味で、核がもたらす人類社会への負の側面っていうものを改めて真剣に考えなきゃいけない時が来てると思うんですよねえ。
この辺は、私より小出先生が強く言ってくれてます。僕は本当に正直言ってね、あの子供達の姿見たら、これで核は絶対考えなきゃいけないって、そう思います。
いまにし:
そうですねえ。小出さん、いかがでしょうか?
小出さん:
はい、もう菅谷さんが一番根本的なことを今、おっしゃって下さったわけで、核兵器も原子力発電所も同じNuclearで、もともと同じものなんだということを皆さんちゃんと知らなければいけないし、核兵器には反対するけれども、原子力発電はいいというような考え方、そのものは間違えだということに気がついて欲しいと思います。
いまにし:
どうなんでしょうか?チェルノブイリ、ベラルーシではそういう考えはあるんでしょうか?核兵器もダメ、原子力発電もダメという。
菅谷市長:
あれはやっぱり、あの国の体質としては、今そういう事あんまり声上げませんよね。ルカシェンコ大統領が、やっぱりあまり今回の原発事故のことはもう終息したっていう方向でやってるから、あまり言うなと。今回行きましたら、やっぱり原発造るんですよね。
いまにし:
また新しく?
菅谷市長:
ええ。だから、そういう方向ですけれども、国民も今の時点ではあまり言えないんですよね。気の毒だなあと思います。
いまにし:
なんかね、日本とちょっと似たよいうな状況があるわけですよねえ。
菅谷市長:
似てます。そうです。ちょっとねえ。
いまにし:
なるほど分かりました。なんかほんとに、話がなかなかほんとに尽きないんですけども、お時間となってしまいました。今日は、松本市の菅谷昭市長、そして小出裕章さん本当にありがとうございました。これからも、お二人のご活躍をお祈りしております。
菅谷市長:
ありがとうございます。どうも。
小出さん:
ありがとうございました。
プロジェクトX・挑戦者たち
「チェルノブイリの傷 奇跡のメス」
https://youtu.be/hK00Xq8v40w
人類史上最悪の事故と対峙した、一人の日本人医師と、現地の人々の闘いを描く。
1986年、旧ソ連ウクライナ・チェルノブイリ原子力発電所で爆発。大量の放射性物質が発生。風にのった放射性物質は、北方のベラルーシに降り注いだ。その後、この地方の子供たちに甲状腺ガンが多発。
現地の病院では首筋に大きな傷を残す手術が主流だった。
その事実を知った、一人の日本人医師がたちあがった。

解説 チェルノブイリの汚染と福島の現在の汚染
小出裕章(京都大学原子炉実験)
広河さんが視た
チェルノブイリの現在
DAΥSJAPAN編集長の広河さんは、2014年3月から4月初めにかけて、チェルノブイリに行った。その際、広河さんは、福島でも使用している放射線測定器(ホットスポットファインダー)を持参し、チェルノブイリ原発周辺や10キロ圏の廃墟になった町、30キロ圏の村々の空間線量を測定した。その結果が、本号で詳しく報告されている。
そこに広河さんが書いているように、福鳥県が、今、学校の施設利用の基準にしている空間カンマ線低率に比べ、チェルノブイリ原発の4号炉そばの線量はずっと低い。また、ウクライナで事故後人が避難し、廃墟となっている村々と同じぐらいの線量のところに、福島では人が住んでいる。
チェルノブイリ原子力発電所事故では、1平方キロメートル当たり15キュリー(55万ベクレル/m^2)以上のセシウム137で汚染された村々から約40万人の人々が強制避難させられた。そして約14万5000平方キロメートルが1平方キロメートル当たり1キュリー(3万7000ベクレルm^2)を超える汚染を受けた。そうした汚染地は、法令に従えば、放射線管理区域にしなければいけない。しかしそこに500万人を超える人々が棄てられた。
環境中での放射性物質の動き
物理的な減衰と環境中での移動
放射性物質を人間の手で消すことはできない。しかし、それぞれの放射性物質には寿命がある。たとえば、セシウム137は30年経てば、半分に減ってくれる。同じセシウムの同位体であるセシウム134の場合には2・06年経てば半分に減ってくれる。そしてまた環境中では物質は移動しており、基本的には濃密な汚染地から周辺へと汚染は拡散していく。1986年4月26日に発生したチェルノブイリ原子力発電所事故からすでに28年以上の歳月が流れた。そして当初の汚染は、その歳月の流れによってかなり減ってきてくれた。
セシウム134はセシウム137に比べて約3倍強い放射線を出すが、チェルノブイリ原子力発電所で放出されたセシウム134の量はセシウム137に比べて、約半分だった。それを考慮し、事故直後に1平方キロメートル当たり15キュリー(55万ベクレルm^2)のセシウム137汚染を受けた上地での空間ガンマ線値がどのように推移してきたかの計算値を図1に示す。この図にはセシウムの寿命による減衰のみを考慮した場合と、環境での移動(注1)を併せて考慮に入れた計算価を示した。
毎時O・6マイクロシーベルトを超える場所は放射線管理区域にしなければならないが、事故直後にはセシウムからだけで毎時3・Oマイクロシーベルトの空間カンマ線量があったはずだし、直後には、寿命が比較的短いその他の放射性核種もたくさんあったためずっと高い放射線量であったはずだ。しかし、10年もたてば、セシウム134も含め寿命の短い放射性核種は次々となくなってきたし、28年たった今では。環境での移動を考慮しなくても毎時0・66マイクロシーベルト、環境での移動を併せて考えれば、毎時O・20マイクロシーベルトまで減っている。
また、セシウム137について、ある塲所での空間ガンマ線最にどれだけの距離からの汚染が寄与しているかを表1に示す。この表によれば、全体の3分の1の被曝は、測定点から5メートル離れた場所までの汚染から与えられる。また、全体の3分の2の被曝は、30メートル離れた場所までの汚染から来る。逆に言うと半径5メートルまでの汚染をはぎ取って移動させれば、被曝の3分の1を減らすことができるし、30メートルまでの汚染を移動できれば、3分の2の被曝は避けることができる。チェルノブイリの周辺でも、人々が頻繁に立ち入る場所はそれなりに汚染対策が取られたであろうから、図1に示した計算値よりもさらに空間ガンマ線量は減っているはずである。広河さんがチェルノブイリ周辺で測ってきた測定値は、ほぼこうした計算と合致している。
被曝と成長盛りの子どもたち
ICRPによれば、1ミリシーベルトの被曝を1億人がすれば、5000人ががんで死ぬ。でも、その危険度の評価は、1977年のICRPの勧告では1250人ががんで死ぬというものだった。発がん死危険度の評価価は、歴史が進み、データが蓄積するにしたがって増加してきたし、私が信頼している米国の医学・物理学者、故ジョン・W・ゴフマンによれば4万人である(注2)。そして、図2に示すように、発育盛りの子どもたちは放射線に対する感受性が高い。30歳を過ぎれば、放射線感受性はどんどん低下していくが、そうした世代にこそ、原子力の暴走を許した責任がある。
放射線に被曝することは、微量であっても被害がある。だからこそ、日本というこの国も被曝について、法令で限度を定めている、一般の人々に対しては、1年間に1ミリシーベルト以上の被曝を加えてはならない。1ミリシーベルトなら安全だからではない。被曝は危険だが、その程度の被曝はその他の危険と比べて我慢できるだろうという社会的な基準である。私のような放射線業務従事者の場合は、1年間に20ミリシーベルト以上の被曝をしてはならないと法令が定めている。それは、他の仕事でも労働災害の危険があるから、放射線を収り扱う労働者もその程度の被曝の危険は我慢すべきだとして定められた。
ところが、福鳥第一原発事故後、日本政府は従来の法令を反故にした。今は、緊急時だから、法令を守る必要がなく、1年間に20ミリシーベルトを超えない場所には、人々に帰還せよと指示を出した。20ミリシーベルトというのは、先に記したように放射線業務従事者に対してのみ許された基準であるが、それを赤ん坊も含め、成長盛りの子どもたちに許容しろというのである。
福島原発事故による汚染
福鳥原発事故の場合、大気中に放出されたセシウム137とセシウム134はほぽ同量であった。そして、1年間に20ミリシーベルトの被曝をする地は、セシウム137とセシウム134がそれぞれ1平方メートル当たり30万ベクレル、合計で60万ベクレルの汚染地に相当する。そうした場所ではセシウムからだけで、事故直後は毎時2・6マイクロシーベルトの被曝をしていたはずだ。もちろん、他の短半減期の放射性核種の汚染もあったから、事故直後の空間ガンマ線量率ははるかに高かった。しかし、事故後3年以上たった今、すでに空間カンマ線量に問題となるのはセシウム137とセシウム134だけである。その地に棄てられた人々が30年後までにどのような被曝をするかを計算したものが図3である。
計算に当っては、セシウムの物理的な減衰とともに環境中での移動も併せて考慮している セシウム134からの被曝は、10年以降はほぽ問題にならない。一方セシウム137からの被曝は、環境中で移動する成分からの寄与が比較的早く減るが、その後は長期間にわたって被曝を増加させていく。仮に30年その地で生活すれば、合計の被曝量は70ミリシーベルトを超えるし、その後も被曝は続く。そして、30年間の合計被曝量の半分は事故後5年で受けてしまう。避難するのであれば、最初の5年問が大切なのである。すでに人々は3年を超えて、彼の地に棄てられ続け、一度避難した人たちも帰還せよと国から指示されている。これが法治国家というものか?
子どもたちには、原子力を暴走させた責任はない。福島原子力発電所の事故に対しても責任がない。そして彼らこそ被曝に敏感で危険を一手に負わされる。子どもたちの被曝を防ぐことは、原子力を暴走させた、あるいはそれを止められなかった大人たちの最低限の責任である。

トランプ氏当選とTPP衆院通過 (¬_¬)なんでやるの?

大接戦米大統領選 トランプ氏の勝利
懸念・期待 迷いながら選択
激戦州の有権者の声は
(しんぶん赤旗)2016年11月10日
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-11-10/2016111003_01_1.html
米大統領選挙が実施された8日、激戦州の北東部、南部の投票所を訪ね、有権者の声をききました。民主党のクリントン候補、共和党のトランプ候補それぞれに入れた人たちから出てくる言葉は、格差の拡大など現状に対する懸念や怒り、それを打開する方向への期待が入り交じっており、迷いながらの選択であることをうかがわせていました。
(ノースカロライナ州ロッキーマウント=遠藤誠二、ペンシルベニア州フィラデルフィア=洞口昇幸)

「庶民 まともに暮らせるのか」
「政治をかえる絶好の機会」
ノースカロライナ州の町、ロッキーマウントに向かう高速道路をまたぐ路上では、「トランプ」と書かれたポスターを掲げ有権者にアピールする市民の姿をみかけました。
投票所では、クリントン、トランプ両陣営の運動員が、投票の仕方や候補者の紹介などを訪れる有権者に説明していました。
アフリカ系の中年女性、リンダさんは、「今回の選挙の争点は、人口の1%の人たちに富が集中する経済システムを変えるかどうかです。一部の大企業がもうけをあげるのではなく、庶民がまともにくらせるようにしてほしい。トランプ氏は自身の利益のことしか考えていない」と話します。
たいして白人の中年女性は、「経済、移民、同性婚。選挙の焦点はたくさんあったが一番の問題は、女性候補者による私的メールの使用など犯罪まがいの行為。今回はトランプ氏が勝利し政治をかえる絶好の機会。もしクリントン氏が大統領になったら弾劾にかけられるべきだ」と言い切りました。
「歴史をつくろう」
ペンシルベニア州最大の都市フィラデルフィア。投票場に向かう道すがら、「投票済」を表すシールを胸元などに貼り付けた通行人が目立ちました。
歩道にはチョークで、「歴史をつくろう」「投票場はこちら」などの文字が。環境保護団体の人たちが市民に投票を呼び掛けたり、投票場の場所を知らせたりするイベントを路上でくりひろげていました。
投票を終えた白人の男子大学院生(23)は、「クリントン氏にそんなに多くは期待していないが、どちらに大統領の資質があるかで選びクリントン氏に入れた。トランプ氏の政策には中身がなく、(経済やテロで)不安感を持つ人々をあおるだけです。とにかく中間層や勤労世帯の暮らしを良くしてほしい」。
白人の看護学生のクイン・クレッグさん(22)は「クリントン氏の外交政策、中東のシリアに関連する公約で、危険な部分があると思います。でもトランプ氏と比較して、クリントン氏が大統領になった場合の政策決定のほうが、最悪な事態を避けられると思いました」と迷いながらの選択であったことを語ります。
「答える必要ない」
ロッキーマウント、フィラデルフィアの双方ともトランプ支持という有権者の口は概して重く、「支持した理由は」という質問に、「答える必要はない」と怒る人もいました。
経済格差広がり、中間層消滅
既存政治への不信・怒りを反映
接戦となった米大統領選挙を制したのは共和党候補のドナルド・トランプ氏でした。政治経験の全くないアウトサイダー(部外者)候補のトランプ氏が民主党候補のクリントン前国務長官を抑えて勝利した背景にあるのは、経済成長や繁栄から取り残された有権者の既存政治に対する怒りや不信です。
「雇用がなく、人口は減り、地方都市は荒廃するばかりだ。このままでは未来がない」(トランプ氏を支持する30歳男性)。「医療や教育を受けられない人々が多すぎる。こんな国を次の世代に残せない」(クリントン氏支持の46歳女性)。各地の取材で出会った有権者が共通して語っていたのは“このままでは米国が立ち行かなくなる”という切迫した危機感でした。
米国の経済政策研究所(EPI)によると、2009年から13年にかけて富裕層上位1%の収入の伸び率は残りの99%の約25倍になりました。これまでにない経済格差が広がり、中間層が消滅し始めています。
中高年の自殺増加
今春発表された研究によると、米国民の現在の自殺率は過去30年で最も高くなっています。特に中高年で増加しており、専門家は背景に「貧困や絶望」があると指摘します。若い世代でも、学費ローンを利用した大学生の4人に1人が滞納や債務不履行の状態です。努力すれば夢を実現できるというアメリカンドリームは消え去ろうとしています。
「腐敗した既存政治がつくったのは貧困だけだ。特権を持ったワシントンの連中に、置き去りにされた中間層の声を聞かせよう」
トランプ氏は自らが既存の政治家でないことを強調し、国民の不満や怒りを吸い上げました。「強い米国を取り戻す」という公約のもと、工場の海外移転や鉱山の閉鎖などによって失われた雇用を回復すると力を込めて訴えました。
同氏はイスラム教徒の入国禁止やメキシコ国境への壁建設、女性蔑視など過激な発言・暴言で物議を醸しました。また法人税の大幅減税や経済活動のいっそうの規制緩和を提案するなど、国民や労働者の利益にかなった経済政策を掲げたわけではありません。
それにもかかわらず勝利したことは、現状を変えてほしいと願う有権者の不満や怒りの根深さを示しました。
クリントン氏は「すべての人のためになる経済が必要だ」と語り、富裕層や大企業が利益を上げれば庶民に回るという「トリクルダウン理論」を批判しました。オバマ政権の政策の継続を掲げ、富裕層や大企業への増税、学費ローンの負担軽減、最低賃金引き上げ、製造業の雇用回復などを公約しました。
しかし上院議員や国務長官を務め、ウォール街から多額の献金を受け取る同氏が、有権者の目に既得権益を代表する政治家と映ったことは否めません。国務長官時代に私用メールを公務に使った問題も影響し、さらに苦戦を強いられました。
変革求める運動も
今回の選挙は候補者の暴言や中傷で、米国史上で最も険悪な論戦になったとされます。一方で予備選段階では格差是正を正面に掲げたサンダース上院議員が善戦し、変革を求める運動が広がりました。
「政治的大変革が必要だ」と訴えたサンダース氏の論戦は、ウォール街の高額報酬や企業献金、低すぎる最低賃金、国民皆保険の欠如など、米国の直面する課題を争点に押し上げました。
サンダース氏の主張に共感した20~30代の若者が大挙して運動に加わり、うねりとなった運動が今後どういう展開をみせるのか。注目点の一つです。
(ワシントン=島田峰隆)


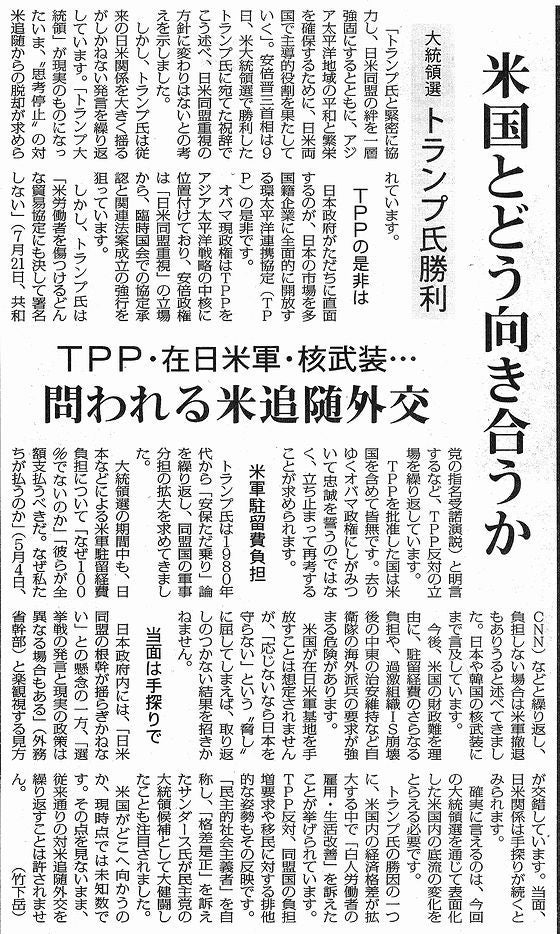
ヒラリーもトランプもTPP反対なのに日本だけがなぜ強行するのか? 安倍政権のTPPインチキ説明総まくり
(リテラ)2016.10.30
http://lite-ra.com/2016/10/post-2657.html
「結党以来、強行採決をしようと考えたことはない」と言ったのは誰だったのか。──安倍政権は早ければ11月1日に環太平洋経済連携協定(TPP)承認案と関連法案を衆院で強行採決する見込みだという。
しかし、一体何のために政府はこれほどまでにTPPに前のめりなのか。安倍首相は「日米関係の強化」などと述べ、政府筋も「オバマが成立したがっているのだから仕方がない」と言うが、当のアメリカの世論はTPPに批判的で、トランプもヒラリーも反TPPの姿勢を強調。さらにオバマ大統領が任期中にTPP発効の承認を議会で得ることは難しく、アメリカが批准する可能性はゼロに近づきつつある。こうした事態に自民党の茂木敏充政調会長も「TPPも通せないような大統領は、私はアメリカの大統領じゃないなと思いますね」と言い出す始末だ。
「アメリカのためのTPP協調」だったならば、日本にもはや意味をなさなくなったはず。なのになぜ強行採決までして押し進めようと躍起なのか。その理由は、呆気にとられるようなものだ。
「オバマなんてたんなる言い訳で、TPPは経産省の“悲願”だからですよ。戦前、軍部が悲願のために暴走したのと同じで、走り続けてきたものをもう引き返せなくなっているだけ。とくに安倍首相の主席秘書官である今井尚哉氏は経産省出身で第二次安倍政権のTPP交渉を後押ししてきた人物。官邸も“TPPありき”で進んできたので、何の合理性もないんです」(大手新聞政治部記者)
制御不能のフリーズ状態に陥りながら、満足な説明もないままTPP承認案・関連法案はいままさに強行採決されようとしているというのだ。国民を馬鹿にするにも程があるだろう。
しかも、安倍政権は馬鹿にするだけでなく、嘘の説明によって国民をあざむき続けている。
まず、安倍首相は「TPPの誕生は、我が国のGDPを14兆円押し上げ、80万人もの新しい雇用を生み出します」と今年1月の所信表明演説で述べたが、これは空言虚説と言うべき恣意的な数字だ。
そもそも、安倍政権は2013年の段階では「TPPによって10年間でGDPが3兆2000億円上昇」と公表していたが、これに対して理論経済学や農業経済学、財務会計論などの多岐にわたる研究者たちで構成された「TPP参加交渉からの即時脱退を求める大学教員の会」は、同年、「GDPは約4兆8000億円減少」「全産業で約190万人の雇用減」という影響試算を出している。
さらに、アメリカのタフツ大学も今年1月、「日本のGDPは10年間で0.12%(約56億4000万円)減少、約7万4000人の雇用減」という影響試算を公表。これらは政府とはまったく真逆の評価だ。
この影響試算の食い違いについて、元農水相でTPP批准に反対してきた山田正彦氏は著書『アメリカも批准できないTPP協定の内容は、こうだった!』(サイゾー)で、政府試算は〈関連産業や雇用への影響など、ネガティブな面を考慮に入れず、地域別の試算もなされていないため国民生活への悪影響が出てこない〉ものだとし、一方の「大学教員の会」やタフツ大学の試算はネガティブな面も含めて試算された結果であることを指摘している。つまり、政府試算は〈ネガティブな面をほぼ無視した数字〉でしかないのだ。
しかも、安倍首相は昨年10月のTPP大筋合意の後の記者会見で、農産物重要5品目(コメ、麦、牛肉、豚肉、乳製品、砂糖)の“聖域”を死守したとし、「国民の皆様とのお約束はしっかりと守ることができた」「関税撤廃の例外をしっかりと確保することができました」と語ったが、これもとんだ詭弁だ。山田氏は前掲書で、〈重要5品目の分野が586品目あり、そのうちに関税が撤廃されるものは174品目、残りは関税が削減されるものなので、それだけでも約3割は「聖域は守れなかった」と断定できる〉と批判する。
さらに、同年11月に公表された協定案では、アメリカ、オーストラリアなど5カ国と、相手国から要請があれば協定発効から7年後には農林水産物の関税撤廃の再協議に応じる規定があることがわかった。これはあきらかに日本を狙い撃ちした規定であり、7年間の“執行猶予”を与えられただけだったのだ。
にもかかわらず、テレビは大筋合意を政権の言うままに「歴史的快挙」などと大々的に取り上げ、「牛肉や豚肉が安くなる」「これで品薄状態のバターも安価で手に入りやすくなる」などと強調。報道によって、他方で甚大なリスクがあるという事実を隠してしまったのだ。
少し考えればすぐわかるように、輸入品が増えることによって国内の農畜産物が大打撃を受けることは明々白々で、廃業に追い込まれる生産者は続出するだろう。となれば、食料自給率も低下するのは必然だ。日本の食料自給率は2015年のデータでもカロリーベースで39%と主要先進国のなかでも最低水準なのだが、農林水産省は2010年の試算でTPPが発効されれば食料自給率は14%に低下すると発表している。それでなくても命に直結する食を海外に依存している状態であるのに、もしも気候変動で農作物が凶作となり輸入がストップしても、そのとき国内に広がっているのは生産者のいない荒廃した農地だけだ。
それだけではない。アメリカなどでは牛肉や豚肉、鶏肉などに発がん性リスクが懸念されている成長ホルモン剤を使っており、食肉だけではなく牛乳などの乳製品にも健康リスクへの不安は高まる。くわえて心配なのが、遺伝子組み換え食品の問題だ。前述した山田氏は〈TPP協定では、何とこれらの遺伝子組み換え鮭など数多くの遺伝子組み換え食品を安全なものとして、域内での自由な貿易を前提にさまざまな規定が置かれている〉と指摘し、現行では遺伝子組み換え食品には表示がなされているが、これもTPP協定下ではできなくなってしまう可能性にも言及。そればかりか、「国産」「産地」といった表示もできなくなる可能性すらあるのだという。
しかし、こうした問題点は氷山の一角にすぎない。TPPをめぐる問題は、挙げ出せばキリがないほど多岐にわたる。たとえば、山田氏が前掲書で提起している問題を一部だけ取り出しても、この通りだ。
・リンゴやミカンなどの果樹農家が打撃を受け、水産業・関連産業で500億円の生産額減少
・残留農薬や食品添加物などの安全基準が大幅に下がる
・薬の臨床試験や検査が大幅にカット。また、ジェネリック薬品が作れなくなる可能性
・医薬品はさらに高額となり、タミフル1錠7万円のアメリカ並みかそれ以上に
・健康保険料が現在の2〜3倍になり、国民皆保険も解体される可能性
・パロディなどの二次創作物が特許権に反するとして巨額の損害賠償を求められるように
・政府はプロバイダを規制できるようになるため「知る権利」「表現の自由」が大きく損なわれる
・外国企業から訴えられるために最低賃金引き上げができなくなる
そして、最大の問題が、「ISD条項(投資家対国家間の紛争解決条項)」だ。前述した遺伝子組み換えの食品表示などもISD条項が問題の根本にあるが、それはISD条項が企業などの投資家を守るためのものであるためだ。しかも、国内法ではなく国際仲裁機関が判断を下すISD条項は、〈最高裁判所の判決よりも、ワシントンD.C.の世界銀行にある仲裁判断の決定が効力を生じることになっている〉(前掲書より)。これは日本国憲法76条第1項「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」に反することになる。さらに〈私たちに憲法上保障されている基本的人権もTPP協定によって損なわれていくことになる。憲法25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とあるが、TPPでは貧富の格差がさらに拡大して、金持ちでないと医療も受けられず、安全な食料も手に入らなくなってくる〉のだ。
昨年、来日したノーベル経済学者のジョセフ・E・スティグリッツ教授は「ISD条項で日本国の主権が損なわれる」と指摘したというが、この言葉通り、TPPはわたしたちのいまの生活を悪化させるだけでなく、憲法という根底さえも崩す。そう、「TPPは、グローバル企業のロビイストたちが書き上げた世界の富を支配しようとする管理貿易協定」(スティグリッツ教授)でしかないのだ。
このような問題点は国会でも野党が追及、参考人質疑でも専門家から厳しく指摘がなされたが、安倍首相は「TPP協定には、わが国の食品の安全を脅かすルールは一切ない」などと大嘘をつくだけで、同じように山本有二農水相も石原伸晃TPP担当相も納得のいく具体的な説明を一切行っていない。情報開示を求められた交渉記録さえ、いまだ黒塗りのままだ。
国民からあらゆるリスクを隠蔽し法案を強行採決する──特定秘密保護法や安保法制でも安倍首相のそのやり口を見てきたが、またしても同じことが、いままさに繰り返されようとしているのである。
(野尻民夫)


TPP法案が衆院通過 トランプ氏当選翌日に・・・(16/11/10)
https://youtu.be/Ir-8bEGD8tg
【謎】日本だけのTPPが本会議で採決され衆院通過!?公共放送NHKは「うまいッ 抜群に辛くて香り高いしょうが!」 「凄ワザ!紙飛行機で飛距離対決」を放送!?
(健康になるブログ)2016/11/10
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/24041

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161110-00000044-mai-pol
環太平洋パートナーシップ協定(TPP)の承認案と関連法案は、10日の衆院本会議で与党と日本維新の会の賛成多数により可決され、衆院を通過した。
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2016/11/tppnhk-b264.html
このトランプ氏が当選を果たした翌日に、日本の国会が、TPP承認案を衆院本会議で強行採決することは正気の沙汰でない。
しかも、この衆院本会議をNHKはテレビ中継せず、
「うまいッ 抜群に辛くて香り高いしょうが!」
「凄ワザ! 紙飛行機で飛距離対決」
などの再放送を行った。
このようなNHK=日本腐敗協会はいらない!
とほとんどの主権者が判断するだろう。

なぜ日本はTPP採決を急ぐのか?
「米国の批准あり得る」
(東京新聞【こちら特報部】ニュースの追跡)2016年11月3日
環太平洋連携協定(TPP)承認案と関連法案の衆院特別委員会での採決が二日、延期された。とはいえ、政府が成立を急いでいることに変わりはない。米大統領選では両候補ともTPPに反対している。それなのになぜ急ぐのか。「米国が批准する可能性はないとはいえない」。NPO法人アジア太平洋資料センター(東京)の内田聖子共同代表はそう語る。
(安藤恭子)

内田さんは衆院特別委でTPP反対の立場から参考人として発言している。
「米国のTPP批准はあり得る。オバマ政権が八日の米大統領選から新大統領就任までの二ヵ月間(影響力を失うレームダック期)に議会の承認を得て批准するかもしれない。そうした動きが出てきている」。内田さんはそう指摘する。
注目したのは、米共和党の有力議員で製薬業界と深くつながるハッチ上院財政委員長をめぐる報道だ。
ハッチ氏はバイオ医薬品の臨床データ保護期間をめぐり、TPP参加十ニカ国が「実質八年」で合意したことに反発。米国と同じ十二年を主張してきた。保護期間が長いほど、ジェネリック薬品(後発薬)が作れなくなり、新薬を開発する米業界の利益につながるためだ。
ところが米通商専門誌は先月二十八日、ハッチ氏とオバマ政権がこの問題で合意したと報じた。ハッチ氏は「(議会で)批准に協力してもいい」と述べ、日本を含む参加国に交渉スタッフを派遣したという。
先月中旬には、米農務長官がTPPの年内批准について楽観的な見通しを述べるなど、TPPをオバマ氏の「実績」につなげる動きが相次いでいるという。
米有力議員 オバマ政権に「協力」の報道
米国では、北米自由貿易協定(NAFTA)後の大量失業の教訓や、TPPの経済効果は限定的とみる米政府の試算から反対の世論が強い。内田さんも米国での批准のハードルの高さは認めつつ「ハッチ氏のような動きは、企業側が政府に自分たちの要求をのませる代わりに『レームダック批准』への協力を持ち掛けている表れでは」とみる。
TPPの発効は、参加国の国内総生産(GDP)の合計の八割近くを占める日米の批准が前提だ。内田さんは「安倍政権がいち早くTPPを承認すれば、その動きはTPPを批准したいオバマ政権に対して追い風になる」と、成立を急ぐ日本側の意図を推測する。
対オバマ政権だけではない。十一の関連法案の中には、著作権の保護期間を五十年から七十年に延長し、権利者の告訴がなくても捜査当局が著作権侵害を摘発できるようにする著作権法改正案が含まれている。
関連法案はTPPが発効した時点で効力を持つとの条件がついている。だが、政府側は十月のTPP特別委での答弁で、現時点では発効に先立って関連法の改正をするつもりはないとしながらも、「一般論としては、TPPの発効を待たずに著作権法の改正を行うか否か、あらためて検討する」と含みを持たせた。
内田さんは「米国の批准がなくても改正される恐れがある。同案には創作活動を萎縮させるといった批判も強い」と懸念する。
採決をめぐる攻防は大詰めだが、内田さんは「TPPは貿易自由化に向けて、内容が変わり続けるエンドレスゲームだ。農業や食の安全、医療、保険共済などさまざまな分野で規制緩和を求められる恐れがある。米国が批准する以前に、日本側が『配慮』する可能性がある。水面下で何か起きているのか、注視していく必要がある」と話した。
Congress “Don’t Duck Democracy!”NoTPP!
「レームダック期の議会採決は絶対にさせない!」


そもそも総研 2016年11月10日
トランプ氏勝利 TPPで日本は得する?損する?
https://youtu.be/j8OyCQIiG-k
第027・028回ライトアップジャーナル
自由なラジオ Light Up! 027回
「 こんなに危ない!共謀罪 」
https://youtu.be/b7-gMkVHQlk?t=17m29s
17分29秒~第027回ライトアップジャーナル
なぜ今、甲状腺検査見直し?
http://jiyunaradio.jp/personality/journal/journal-027/

矢野宏:
福島第一原発事故の健康への影響を調べるため、福島県の全ての子供達を対象にしている甲状腺検査について、福島県の小児科医の先生達が組織する小児科医会が、検査の対象の規模を縮小する等の見直しを、県に要望しました。
このままだったら県民に不安が広がるというのが、その理由なんですけれども、果たして、この時期になぜこの甲状腺検査を縮小するのか?今日は今中哲二さんと電話が繋がっています。今中さん、今日もよろしくお願い致します。
今中さん:
はい、こちらこそよろしく。
矢野:
福島県は、事故が起きた2011年度から事故当時18歳以下だった子供達を対象に、甲状腺検査を実施してきました。30万人以上が受診し、今年3月末の時点で172人が甲状腺がんか、或いは、がんの疑いがあると診断されました。このような状況の中で、甲状腺検査の縮小の狙いは何なんでしょうか?先生、どう思われますか?
今中さん:
私にもよく分からないんですけども、皆さん、いろんな先生方の意見を聞いてみると、甲状腺がんがたくさん見つかっていることは確かです。
矢野:
はい、そうですね。
今中さん:
それが、何が原因かということで、いろんなまた意見が出て議論されているわけなんですけれども。その中で、不安をあおるから縮小するというのは、なんか話が反対なような気がしますね。
矢野:
そうですよね。これだけの数が出ているんだから、きちんとやっぱり検査すべきですよね。
今中さん:
これから、もっときちんと検査しなければいけないというのは、基本的にとるべき態度だと思いますよ。
矢野:
今中さんは事故当時からおっしゃってましたが、福島県の子供達だけではなくて、被爆しているのは福島県だけじゃないんだということで、日本全国の子供達を調べろとおっしゃってますよね。
今中さん:
結局ですね、たくさん見つかっていることは確かです。その原因が何かというのをきちんと明らかにしようと思ったら、他の地域と比較することが必要だと。それとあと1つですね、チェルノブイリの場合、私、ですから20年前にずっと眺めてて、チェルノブイリ事故の後に生まれた子供からは甲状腺がんがほとんど出てない。
矢野:
事故の後ですね。
今中さん:
そういうのはありました。そのデータを私、事故から10年後ぐらいに見て、「やっぱり、もう事故が原因である」と。ヨウ素被爆が原因であるというのを確信した覚えがありますねえ。
矢野:
なるほど。チェルノブイリ事故の場合は、事故から5年後から甲状腺がんが増えた。
今中さん:
たくさん観察され始めたのは、4年後ぐらい。

ベラルーシでの甲状腺がん発症率の1997年以降の推移
矢野:
4年後ぐらい。
今中さん:
岡山の津田先生あたりは、「2年後ぐらいから増えてるよ」と言ってますけども。
矢野:
福島の場合は、その事故直後から、そういう子供達の甲状腺がんが見つかったり、がんの疑いがあるという風に診断された子供が増えてきた。
今中さん:
そうですね。1年後に、最初の1件目が見つかったんですかね。
矢野:
そうでしたね。
今中さん:
それから、どんどんどんどん増えてきましたから。
矢野:
だから、そこをポイントにして、「これは福島第一原発事故の影響ではない」という声も、一方で聞こえるわけなんですけど。果たして、そんなことあり得るのかなと思うんですが。
今中さん:
それは、熱心に検診をすれば、これまで見つからなかったがんが見つかるという、いわゆるスクリーニング効果ということで、そういうことも、もちろん考えられると思いますよ。
だけども、福島原発事故というものがあって、その周りに甲状腺がんが増えてる、たくさん見つかっているということですから、「これは事故が関係しているぞという観点からきちんと調べなきゃいけない」というのが私の意見ですけども。

矢野:
そうですよね。この甲状腺癌というよりは、そんなに軽視していいものなのでしょうか?そんな軽いがんなんでしょうか?
今中さん:
私、お医者さんじゃないので詳しい事はわかりませんけども、読んだ限りでは、そんな進行は早くないと言うんで、いわゆる死亡するリスクですか、致死率も少ないんで、そんなに慌てて手術するとか、そういうことも必要ないというような事は、一般的には言われてるようですね。
矢野:
なるほど。ただ、子供達に多く出ることで、その子供達っていうのは進行が早いということがありますよね。そういったとこがちょっと不安なんですけど。
今中さん:
子供さんはやっぱり大人に比べて、先々将来が長いというんで。子供達に甲状腺がんの手術をするというのは、いわゆる「過剰診断」だという言い方をされていますね。
矢野:
はい。しかし、その過剰診断だということで、選択制になれば、隠されていることが、また隠されてしまうんじゃないかという風に、私は思ってしまうんですけども。
今中さん:
もしもですね、ここで甲状腺の検査を縮小されるようになりますと、ますます私、福島の人々の不安が大きくなるんじゃないかという気がしますね。
矢野:
そうですよね。本当に当事者にとってみて、やはりそれは本当に大きな不安なんですから。それをきちんと県なり国なりがやはり責任を持ってきちんと検査するべきですよね。
今中さん:
もちろん私、福島の方に直接お聞きしたわけじゃありませんけども、ある意味ね、子供も大人も含めて、みんな病気になるわけですよね。なんらかの形で。そして、その病気が一体何が原因かと言った時に、今の状況で、例えば福島の子供さんが、甲状腺がんや白血病やなんなりになった時に、皆さん、これは原発事故のせいではないかと、きっと思われると思うんですよね。そういう時に、きちんと説明する資料としては、福島だけでなく日本全体の子供達の健康状態のデータというのをきちんととっておく必要があると。
矢野:
この甲状腺検査の縮小というのは、その逆行ですよね。まさに。
今中さん:
そうですね、私には、そういう気がします。
矢野:
親にとっては、本当に子供が大丈夫なのかどうかというのは本当に大きな不安を抱えてのことですから。やはり、これはきちんと検査してもらいたいものですよね。
今中さん:
そうですよね。はい。
矢野:
甲状腺がんだけではなくて、今後ですね、白血病とかそういった更なる大きながんと言いますか、因果関係というのは出てくるんでしょうか?
今中さん:
もちろん、そういう問題もありますから、私、事故の後からずっと言ってるんですけども、甲状腺の調査にしろ福島県が中心になってやってますよね。
矢野:
はい。そうですね。
今中さん:
いつも言ってるように、これ変なんですよ。なんか国が県に丸投げしているような形になってまして。そうじゃなくて、国が中心になって、もっと福島県だけでなく、もっと周りも含めて、そして、日本全体を見渡せるような調査をする必要があるんだと思います。
矢野:
なるほど、分かりました。国が県に丸投げするんではなくって、国が中心になって、今後も検査すべきだということですね。
今中さん:
はい。
矢野:
先生、本当にありがとうございました。
今中さん:
はい、どういたしまして。
「甲状腺検査必要ない」の仰天!
福島母たち 届けられた
県通達への憤怨
子供たちの甲状腺がん発生率が通常の約200倍になるのに、県は病気の実態を隠ぺいしようと「検査縮小」へと動き始めていた―
(女性自身)
原発事故後、福島県が行ってきた甲状腺検査。最近、それを縮小しようという動きがある。チェルノブイリでは事故5年目から患者が急増したのだが……。

「娘は3年前に、県の検査を受けて甲状腺がんと診断されました。検査や治療をしている福島県立医大が混んでいて、再検査に半年待たされているうちに、リンパ節に転移してしまったんです。もう少し早く検査・手術ができていれば、再発や転移のリスクも減らせたはず。それなのに、検査を縮小するなんてありえない」(50代女性・郡山市在住)
福島県内で、甲状腺がんと診断された患者や母親が、こんな怒りの声を上げている。なぜなら、福島県で原発事故後に実施されている、子供の甲状腺検査を縮小しようとする動きがあるからだ。
福島県では、原発事故後、放射線の健康影響を調べるため、「福島県民健康調査」が実施されている。事故当時18歳以下だった約38万人に対して行われている甲状腺検査も、この一環。福島県が甲状腺検査を行っているのは、`86年のチェルノブイリ原発事故のあと、ロシアなどで子供の甲状腺がんが急増したから。国際機関も、被ばくの影響で増えたと認めているがんだ。
子供の甲状腺がんは、通常100万人に2~3人の割合で発生する病気。福島県でも事故後2巡目の検査までに、174人の子供の甲状腺がん(悪性含む)が見つかり135人が手術を受けた。1巡目の数字で比較すると、通常の約200倍の発生率ににもなる。
にもかかわらず、福島県の小児科医会は「いっせいに検査することで、放置しておいても健康や命に影響のない、潜在がん々を見つけているにすぎない。甲状腺検査をすることで、子供に負担をかける」などとして、甲状腺検査の規模を縮小するよう、8月に福島県へ要望書を提出した。
このような動きを踏まえて、本誌はネット上でアンケートを実施(内容は次ページコラム参照)。

事故当時、福島県に住んでいた18歳以下の子を持つ親の約95㌫(回答数186人)が、甲状腺検査を縮小することに「反対」と解答した。
甲状腺がんと診断された患者や家族でつくる「311甲状腺がん家族の会」や、国内外の120を超える市民団体らも、検査を縮小せず、むしろ拡大してほしいという要望書を9月はじめに福島県へ提出。
こうした経緯から、福島市で9月14日に開かれた、「県民健康調査」の在り方を議論し、検査結果を評価する「県民健康調査検討委員会」(以下、検討委員会)が注目された。
そこでは、甲状腺検査縮小の動きについても議論がなされた。出席していた多数の委員から、「チェルノブイリで甲状腺がんが増えたのは、事故後5年目以降。福島でも、甲状腺がんが増えているのだから、被ばくの影響も排除せず、今後も検査を続けていくべき」といった意見が出た。
しかし、座長の星北斗氏(福島県医師会副会長)は、「甲状腺検査をこれまでも縮小すると言ったつもりはない」と弁明しながらも、「検査を拡大してほしいとか、逆に辞めてしまえとか、いろんな意見があるのも事実。検査の結果を評価しながら、検査の在り方については、議論していく必要がある」と、煮え切らない結論を述べるにとどまった。傍聴していた福島県伊達市内に住む母親は、不信感をあらわにしてこう語る。
「今回は、反対の声が多くあがったので、検査縮小の議論を強行できなくなったのでは。注意しないと、また縮小の話しが持ち上がるかも」
実際、検査縮小の準備は、福島県自体が着々と進めていたことがわかっている。
「これ、見てください。これを読んだら、検査なんて受けなくていいと思いますよね」
いわき市から東京都に母子で避難中の今井美幸さん(仮名・40歳)は、そう言って、福島県から検査対象者に送られてきた「甲状腺検査のお知らせ」という書類を見せてくれた。そこには、現在行われている3巡目の検査について、こんな文言が書かれていた。
「甲状腺の特性上、治療の必要のない変化も数多く認めることになり、ご心配をおかけすることもあります。そのため、甲状腺の超音波検査による検診は、一般的には行われてきませんでした。(後略)」
まるで、検査を受けないほうがいいかのような書き方だ。しかし、記者が15年までに行われていた2巡目の検査対象者に送られた「甲状腺検査のお知らせ」を入手したところ、3巡目になかった文言が。
「検査1回目の受診の有無や検査結果にかかわらず、受診することをおすすめします」
福島県は2巡目の検査まではこう記し、甲状腺検査を受診することを推奨していた。さらに注目すべきなのは、3巡目の検査から検査の同意書に「同意しません」という欄が新設されていたことだ。ここにチェックを入れると、追加で検査案内があったとしても、もう送られてくることはないという。だが事実上の“検査縮小”だと思わせる動きはこれだけではない。
自覚症状が出てからだと”遅い”可能性も
「甲状腺検査のお知らせ」とは別に、県から送られてくるA4版4ページの「甲状腺通信」という冊子がある。
16年8月発行の1ページ目にあるQ&Aの項目には、「甲状腺検査は必ず受診しなければならないのでしょうか?」との問いが……。その答えには、「小さな甲状腺がんは、治療をしなくても多くは生命に影響しない。個別には、どれが進行する甲状腺がんなのかを十分に識別することは困難です」などと、あたかも、甲状腺検査は必要ないと誘導するかのような文章が並んでいる。
「検査に“不同意”だった子に、あとからがんが見つかって、万が一病状が悪化していたら、誰が責任をとってくれるのでしょうか」
と前出の今井さんは憤る。
記者の取材に対して福島県は、「県としては甲状腺検査を縮小するつもりはありません。多くの方に受けていただきたいと思っています」(保健福祉部県民健康調査課・課長/小林弘幸氏)と返答した。
しかし、14日の検討委員会後の会見で、「甲状腺検査のお知らせ」から、受診を勧める文言が削除されたのはなぜかと尋ねられても担当課長は口ごもるばかりだった。

県の検査に詳しい医療ジャーナリストの藍原寛子さんはこう危機感をあらわにする。
「検査に“同意しない”子が増えると、学校の検査で、受けたい子が受けづらい空気になる。検査を縮小する口実にされてしまう恐れがある」
じつは、前出の検討委員会の座長である星氏も8月の地元紙の取材に「検査することで具体的に“デメリット”を被った人もいるので、甲状腺検査の対象者を縮小することも視野に入れ、検査体勢を再検討する」と語り波紋を呼んでいた。記者は、星氏を直撃し、縮小の論拠のひとつになっている、検査を受けるデメリットについて聞いた。
「“デメリット”ですか? 数年ごとに検査を受けなくちゃいけないし、再検査になれば細胞診も受けなくちゃいけない。がんの疑いありと診断されたら、手術で傷が残ったり薬を飲み続けなくちゃいけなくなったりすることも」
しかし、早期発見をして治療することは、検診の“メリット”でもあるはずだが――。
「被ばくによるがんを見つけてもらった子供にとってはメリットですが、手術の必要がない“潜在がん”の子供にとっては、寝た子を起こされたようなもの。手術した中に一定数は、“潜在がん”が含まれていることはたしか。なかには『切らなくていいものを切った』と思われる方がいるかもしれません」(星氏)
検査を縮小したい側に配慮をして“潜在がんがある”と言いたいのかもしれないが、実際に切らなくてもいいがんを切っているとしたら、恐ろしい話だ。「311甲状腺がん家族の会」の代表世話人・武本泰氏は、星氏の意見についてこう語る。
「そうだとしたら確かに、医療訴訟に発展しかねない大問題。さらに潜在がんかもしれないから、検査を受けなくていいというのは患者の“知る権利”の侵害でしょう」
検査をしたうえで、“潜在がん”の可能性が高い場合は、経過観察すればいいと思うのだが、それについて前出の星氏はこう反論する。
「子供の甲状腺がんは前例が少ないので、潜在がんか被ばくによるがんかを見分けることは不可能。そもそも、被ばくとの因果関係を裏付けるには、患者の初期の放射性ヨウ素による内部被ばく量を知る必要がありますが、肝心なそれがわかっていないのです」
星氏の意見に対し、福島県の甲状腺検査のアドバイザーでもある甲状腺の専門医で、兵庫県にある隈病院院長の宮内昭氏の意見はこうだ。
「検査することで一定数、潜在がんが見つかることは確かです。それでも、福島県立医大で手術した症例を見るかぎりでは、腫瘍が1センチ超えていたりと、手術は妥当。経過観察していいとは言えない」
さらに検査を縮小すべきではない理由をこう付け加えた。
「見つかったがんに対してどう治療するかは、今後の課題ですが、検査は縮小せずに今まで通り行うべき。そうでなければ調査としても成り立たなくなり、今までの検査がムダになります」
また、甲状腺がんの患者を支援する「3・11 甲状腺がん子ども基金」の顧問を務める内科医の牛山元美氏は早期発見・早期治療が望ましいと指摘する。
「子供の甲状腺がんは、進行が早く転移もしやすいと言われていますが、他のがんと比べて予後はいい。それでも自覚症状が出てからだと甲状腺を全摘出することになったり、声帯の動きを調節する反回神経がマヒするなどの後遺症が出る可能性もあります」
と、早期発見・早期治療が望ましいと指摘した。ある女性は検査の必要性について、本誌アンケートにこう書いた。
「甲状腺がんは予後がいいといわれているからか、治療しなくても大丈夫と信じて再検査の通知を受けても受診しない知人がいます。しかし、思ったより進行が速いと言いますから、検査が縮小されたら不安です」
子供の甲状腺検査を含む「県民健康調査」は、「県民の健康を長期的に見守る」という名目で始まっている。わずか6年目にして規模縮小の議論が出る背景について前出の藍原さんはこう語る。
「国が、低線量被ばくの影響を隠蔽し、今も続いている広島・長崎の原爆訴訟や、今後、起こるかもしれない福島の健康被害の賠償などを認めたくないからでは」
これ以上、子供の命が切り捨てられることがあってはならない。
取材・文/和田秀子
自由なラジオ Light Up! 028回
「 シベリア、ヒロシマ、そしてこれから……。 戦争を静かに描き続けた父・四國五郎のぶれない思い 」
https://youtu.be/nf7bctu7w_A?t=17m16s
17分16秒~第028回ライトアップジャーナル
福島第一原発の労働者の白血病による労災認定について
http://jiyunaradio.jp/personality/journal/journal-028/

いまにしのりゆき:
今日のライトアップジャーナルは、元京都大学原子炉実験所助教の小出裕章さんがお住まいになられております長野県の松本市役所におじゃまをして直接お話をお伺いしたいと思います。小出さん、よろしくお願いします。
小出さん:
はい、よろしくお願いします。どうも松本までおいで下さってありがとうございました。
いまにし:
いえいえ、僕、松本について第一印象、凄く大阪と比べて涼しいなあと思うんですが。先生、実際、松本に暮らし始めて1年ちょいぐらいですか。いかがでしょうか?
小出さん:
はい。この町は、大変快適な町です。町がコンパクトに出来ていますし、生活する為には、本当に必要なものが全て手近で揃うという町で、松本市民の9割が、「この町はいい町だ」と言うというぐらいなのですが、それがすぐに納得できると思いますし、この町に来てよかったと思っています。
いまにし:
分かりました。それでですね、8月19日に厚生労働省は、東京電力福島第一原発の事故の収束作業にあたっている50歳代の男性の作業員の方が発症しました白血病についてですね。要するに、原発の収束作業の業務が原因だということで、労災認定をしました。
福島第一原発の収束作業の被爆による労災認定は、今回が2例目ということですが、小出さん、このニュースを聞かれまして、どのようなご感想をお持ちでしょうか?
小出さん:
少な過ぎると思います。おそらく、もっともっとたくさんの人々が収束作業に従事しながら様々な病気になっているはずですし、もちろん白血病ということでも、もっと症例は多いのではないかと思いますし、その他様々な病気で亡くなられている方いらっしゃるはずだと思います。ただし、それを労災として認定しない。被爆による労災として認定しないという、そういう制度が出来てしまっている。そのことを悪例と言うんでしょうか。残念ながら、まだ2人しか認められないということだと思います。
いまにし:
この男性作業員の方はですね、事故のあった2011年4月から白血病という診断を受けられた2015年1月までの間、3年9ヶ月間というかなり長期にわたって、原発の中で機械の修理作業等に従事をされていたということなんですが、積算の被爆線量は54.4ミリシーベルトとなっています。54.4ミリシーベルトと言うと、この被爆量どのように見ればよろしいでしょうか?
小出さん:
例えば、一般の人というのは、1年間に1ミリシーベルト以上被爆してはいけないというのが日本の法律ですから、その一般の人とすれば、もう50年分以上という被爆をこの間に彼はしてしまったということになるわけです。





そして、一般の人でない放射線業務従事者と呼ばれている被爆労働に従事する労働者の場合は、1年間に20ミリシーベルトです。
3年9ヶ月この方働いていたわけですから、マックスで言えば70ミリシーベルトぐらいまでは
まあ被爆してもいいというような事になっているわけですが、それでも54.4ですから、かなり限度のぎりぎりまで被爆をさせられながら働いてこられたんだと思います。
いまにし:
そうですね。当然個人差があるわけで、仮に3年間でその70ミリとかで被爆をしても大丈夫な方もいらっしゃれば、やはりそうでない方もいらっしゃるということで。上限ぎりぎりまで大丈夫なんだという見方というか、部分というのは、必ずしも100パーセント安全保障するものではないということですね。
小出さん:
もちろんです。そのまま1年間に20ミリシーベルトという限度があるわけですけれども、その限度はどうやって決められているかと言うと、他の仕事でも労災で死ぬ方がいるじゃないか。
被爆作業でも被爆によって死ぬのは、むしろ労災として当たり前だと。1年間に20ミリシーベルトまでは我慢させると言って決められているわけです。それに、ほとんど限度近くに被爆しているわけで、そういう方がいわゆる労災として病気になるということは、むしろ初めから予定されているという、そういう形の死に値しているわけです。
いまにし:
なるほど。福島第一原発の収束事故ですね、こういう形で労災認定されるされないに関わらず、いろんなケースでお亡くなりになられたり、大怪我をされたりしている方々がいらっしゃるわけなんですが、こう見ていると、なんか最後いつも辛い思いをされるのは、一番最前線の現場で頑張って頂いてる作業員の方、労働者の方かなあと思えてなりません。
一方、東京電力なんかは、全く誰もろくすっぽ責任を取らないまま、この暑い夏涼しい所で仕事をしているというような、こういう何と言うか、不合理な状況というのはいかがお感じでしょうか?

小出さん:
今、自民党という政党が政権を取っていて、安部さんという人がトップにいるわけです。彼は経済最優先と言って、労働者の雇用がどんどん良くなってると言うわけですけれども。実際には全然そうではないと、私は思うわけです。
正規雇用の労働者はむしろ減っていて、非正規の労働者はどんどん増えていると。福島の場合も、それが正に縮図のように現れている。
実際の現場で被爆労働に従事するのは、非正規の労働者ばっかりになってしまっている。
仮に、東京電力の労働者が被爆労働に従事して、被爆限度に達したとしても首を切られるとはないわけですね。むしろ、被爆労働から外れて、別の労働に従事しながら給料をちゃんともらえるわけですけれども。
現在、福島原子力発電所で被爆をしながら作業をしている人達は、被爆限度に達してしまうと即首を切られてしまうという、そういう労働者が今戦っているわけです。そういう場合には、そういう労働者を雇用している雇用主の方も、労働者を失ってしまうことは困るので、自分の被爆している量をごまかせと、労働者にむしろごまかし方まで手取り足取り教えながらごまかさせるわけですし、私は悲しい事は、労働者の方がむしろ自分の被爆量を小さく見せなければ首を切られて仕事がなくなってしまうという、そういう立場に追い込まれているわけで、誠に嫌な現場だと思います。


いまにし:
はい、分かりました。ありがとうございました。今日のライトアップジャーナルは、長野県松本市から小出裕章さんと共にお送りしました。
台湾の原発労働者の遺体を六年後に掘り起こすも、肺とその周辺が全く腐敗していなかったという恐ろしい写真
隠された被曝労働 - 日本の原発労働者 物語
https://youtu.be/mJTuWVDjarg
1995年 イギリス Channel4
「被差別部落民に対して原発への仕事を斡旋していた」
下請け・日雇いが支える原発の実態
https://youtu.be/wuvwO1RlIVo
福島第一原発では、労働者が多量の放射線を浴びながら事故処理に当たっています。しかし事故が起きなくても労働者は日ごろの定期点検で放射線にされされています。原子力を利用する上で避けて通れない、労働者の被ばくについて考えます。
【消えた作業員】NHK・追跡!AtoZ「福島第一原発 作業員に何が?」
使い捨ての構造でないと、今のところ成り立たっていかない
http://dai.ly/xkj5tt
20111217
報道特集「暴力とピンハネ…原発作業現場で起きていたこと」
https://youtu.be/DBJaBskMvD8
下請けが四次、五次、六次と延々と広がる原発労働の巨大な構造。
グーグル検索語に日本語として初めてランクインした東京電力は、「元請け会社がどんな下請け会社に発注するかは自主的な判断に任せている。
当社として個別の雇用関係などについては分かりかねる」中には派遣業として認可されず登録すらしていない会社もある。
「二重派遣は違法」だと問い詰められても、「皆やっていること」と笑い飛ばす業者。
ピンハネが横行し、暴力沙汰すら起きていても、東京電力は公式見解をただ繰り返せば、それで無関係だと高をくくって知らん顔だ。
NHK・ETV特集
「ルポ 原発作業員 ~福島原発事故・2年目の夏~」
故郷を放射能に汚染されてなお、原発での仕事を生活の糧にせざるを得ない作業員たちの日々

http://bww.jp/r/2012/08/20/%E5%8E%9F%E7%99%BA%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E5%93%A1%EF%BD%9E%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E5%8E%9F%E7%99%BA%E4%BA%8B%E6%95%85%E3%83%BB%EF%BC%92%E5%B9%B4%E7%9B%AE%E3%81%AE%E5%A4%8F%EF%BD%9E/
福島第一原発では、事故から一年たった今も毎日3000人の作業員が事故収束作業にあたっている。その6割が地元福島の人だ。故郷を放射能に汚染されてなお、原発での仕事を生活の糧にせざるを得ない。作業員たちはどのような状況に置かれ、どのような思いを抱えているのか。福島県東部の浜通りにある2つの下請け企業の協力を得て、その日々を見つめた。
大手プラントメーカーの下請けとして事故前から原発の仕事を続けてきた「東北イノベーター」。毎日12人の従業員が第一原発の仕事に向かう。事故前から20年以上、福島第一原発を中心に定期検査やメンテナンスの仕事を続けてきた。
事故後、第一原発の現場では、毎時数ミリシーベルトを超える高線量の場所が数多くあり、毎日の被ばく量も「0.3」「1.8」と“ミリシーベルト単位”だ。そうした高い被ばくを伴う現場に夫を送り出す家族は不安な日々を送っている。
原発事故後、現場には大量の作業員が必要となり、これまで原発の仕事とは関わりの無かった人たちも原発での仕事を始めている。川内村の「渡辺重建」では、震災で仕事を失った若者たちに声をかけ、去年(2011年)7月から第一原発での仕事を始めた。みな事故前は、バスの運転手やアパレル工場、ゴルフ場など、原発とは関係の無い現場で仕事をしてきた人たちだ。一年間で、40ミリシーベルト近くの被ばくをしており、法令の限度内とはいえ、健康への不安を感じている。
こうした下請け作業員の不安に地元福島で40年以上向き合ってきた石丸小四郎さん。被ばくによる労災 支援などを行ってきた石丸さんのもとには、今、作業員たちから現場の実態が寄せられている。その聞き取り調査から、原発での労働実態やその問題点も明らかになってきている。
20161016 UPLAN【前半】
小出裕章「生命と被曝」
(樋口健二さんと小出裕章さんのコラボトーク)
https://youtu.be/x-YMzaewvSQ
20161016 UPLAN【後半】
樋口健二さんと小出裕章さんのコラボトーク
https://youtu.be/mn9jXkjL1QI
第029・030回ライトアップジャーナル そんなに「核」が欲しいのか!(`・ω・´)
自由なラジオ Light Up! 029回
「本当のことをどこまでも書き続けたい 清武英利が語るノンフィクションの真髄 」
https://youtu.be/U4rWZg8Kl30?t=20m2s
20分02秒~第029回ライトアップジャーナル
廃炉に向けて動き出した高速増殖炉もんじゅ 〜「もんじゅと核燃サイクルの行方」について
http://jiyunaradio.jp/personality/journal/journal-029/
崩壊熱で赤熱する原子力電池用の プルトニウム238
いまにしのりゆき:
小出さん、よろしくお願いします。
小出裕章さん:
よろしくお願いします。
いまにし:
夢の原子炉と言われました高速増殖炉「もんじゅ」、廃炉に向けた調整が始まりまりました。一方で、官民をあげて高速炉開発会議というのを設置し、核燃サイクル政策について、更なる維持をしようという話も出ております。
今日は、この「もんじゅと核燃サイクルの行方」についてお伺いしたいと思うのですが。
小出さん:
はい。少し基本的なことから話をさせて頂きたいのですが、皆さん、原子力の燃料はウランという事はご存知だと思います。そして、原爆というものについて、広島と長崎に落とされたということもご存知だと思います。そして、原爆の場合には、広島に落とされた原爆は確かにウランで作られていたのですが、長崎に落とされた原爆はプルトニウムという物質で作られていました。
私、今、ウランと言いましたけれども、地球の地底に眠っているウランを掘ってきた時に、核分裂する能力を持っているウランはわずか0.7パーセントしかないのです。現在の原子力発電で使えるウランは、要するにそれだけしかないわけで、何か原子力は夢のエネルギーで、未来のエネルギー源のように言われましたけれども、核分裂する能力を持っているウランを使う限りは、簡単に枯渇してしまうのです。
その為に、原子力を推進している人達は一つの夢を描きました。ウラン全体の99.3パーセントを占めている核分裂する能力のないウラン。もともとはただのゴミになってしまうようなウランをまた燃料に使いたい。どうするかと言うと、プルトニウムという物質に変えることによって、それを原子炉の燃料に使おうと考えたわけです。
先ほど、私、長崎の原爆がプルトニウムで作られていたと聞いて頂きましたけれども、もともとプルトニウムというのは自然界には全くないのですが、役立たずのウラン、それに中性子を吸わせると、自動的にプルトニウムに変わるという、そういう物理的な性質を持っていて、米国は長崎の原爆を作り出したわけです。
そして、今聞いて頂いたように、原子力を推進している人達は、役に立たないウランをプルトニウムに変えることで原子力の燃料を生み出して、未来のエネルギー源にしようという夢を描いたのです。そして、役に立たないウランを効率的にプルトニウムに変えるという原子炉が高速増殖炉という名前の原子炉でした。
プルトニウムを燃やしながら、どんどんと役に立たないウランをプルトニウムに変えていく、燃料を増殖していくということで、高速増殖炉という名前が付けられたのです。世界中の原子力を推進してきた人達が、何とか高速増殖炉を造り出して、原子力というものが少しでも意味のあるエネルギー源にならないかと言って格闘してきたのですが、世界中が「これはダメだ」ということで、もうみんな撤退してしまったのです。
世界の高速増殖炉開発スケジュール 長期計画策定会議 参考資料より
日本だけが最後まで高速増殖炉というものにこだわって、もんじゅは全く動かない。それなのに1兆円以上のお金をかけてしまったという、まことに馬鹿げた夢を追い続けた国というのが、この日本だったのです。
いまにし:
20年以上ですね、もんじゅ稼働してからなるんですけども、本当に原子炉を動かしたのは1年にも満たない。たった200何日かということで、全くの無用の長物というような事だったわけですよねえ?
小出さん:
200何日というのも、フルパワーで動いたのではなくて、ただ原子炉が動いたというだけであって、全く意味のない原子炉になってしまいました。プルトニウムを増殖していくという目的を果たすためには、原子炉を冷却するための材料として水が使えないのです。
そのために、ナトリウムという物質を使いました。ナトリウムというのは水に触れると爆発してしまいますし、空気と触れると燃えてしまうという。
https://youtu.be/Ptz7D_jOY1I
そんなもの到底、工業的には使うことができないという程の危険な物であって、それをでも使わなければ意味がないということで、何とかやろうとしてきたわけですけれども、あまりにも危険だということで、世界中が撤退してしまったわけですし、もんじゅも1995年にナトリウム火災というものを起こして、結局、動かないということになりました。
いまにし:
はい。しかし、もんじゅはダメだったけれども、核燃サイクルはまだやりますというのが今回、国の立場なんですけれども、最後に、その辺についてはいかがお考えでしょうか?
小出さん:
原子力というのは、プルトニウムを生み出して利用するということが出来ない限りは、エネルギー源にならないのです。石油に比べても数分の1のエネルギーしか出せませんし、石炭に比べれば数十分の1のエネルギーしか出せないという、まことにバカバカしい資源だったのです。それを何とか原子力というものが良い物だと言おうとするのであれば、プルトニウムに変えて利用できるということを言い続けなければいけないのですけれども、その言い続けるために必要な物が高速増殖炉と使用済み燃料の中からプルトニウムを取り出すという再処理、それを2つを合わせて核燃料サイクルと言ってるのですけれども、「それをやるのだやるのだ」とこれからも言い続けない限りは、彼らは原子力の正当性を言えないということになってしまっているわけです。

いまにし:
なるほど。ある意味、原子力マフィア、原子力村を維持するが為の高速増殖炉であり、核燃サイクルというような見方もできるんでしょうか?
小出さん:
そうです。自分達の存在意義を失わないためには、どうしても言い続けなければならないわけです。でも、そんなもの決して出来ないわけで、これまでも1兆円も捨ててしまって何も出来なかったということなわけですから、もういい加減に嘘をつくのをやめなければいけないと私は思います。
いまにし:
分かりました。小出さん、ありがとうございました。
小出さん:
はい、ありがとうございました。
BS朝日・午後のニュースルーム 2013年5月17日
特集:原子力政策の“落とし穴”
高速増殖炉「もんじゅ」真の姿とは!?
日本が「核燃料サイクル」にこだわり続ける理由は、「使用済み核燃料=資産」という電力会社の経営問題と、「潜在的な核武装」という意味合い/田坂広志氏
http://dai.ly/xzyi3c
点検漏れ9800カ所以上! 巨額の税金が無駄に?
もんじゅが運転停止へ“夢の原子炉"の今後、核燃サイクルは極めて難しい夢の物語。
増殖するのは燃料だけでなく「核のゴミ」も推進派こそが原発の可能性をつぶす。
求められるのは原子力環境安全産業と脱原発交付金
もんじゅ核燃サイクルの落とし穴とは?
なぜ続ける?まわらない「核燃サイクル」
もんじゅ廃炉なら…高速炉撤退考える時
(東京新聞【こちら特報部】)2016年9月27日
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2016092702000140.html
政府は高速増殖原型炉「もんじゅ」を廃炉にする方向性を固める一方、新たに官民の「高速炉開発会議」を設置し、核燃料サイクル政策を維持しようとしている。フランスとの共同開発などに活路を見いだそうとするが、日本側の都合だけでうまく事が運ぶのか。もんじゅの頓挫が明らかになっているのに、勝算のないまま研究開発を続けていけば、今後も無駄に国費が失われていく恐れがある。
(沢田千秋、池田悌一)
実用化ヘ見通し立たず
維持費 年200億円 基礎研究なら1桁減
「電力会社が支援できないと表明した時点で、もんじゅの継続は難しいと思っていた。高速増殖炉の研究開発を見直すなら、当然、日本の核燃料サイクルの見直しもすべきだ」
元内閣府原子力委員会委員長代理で、長崎大核兵器廃絶研究センター長(原子力工学)の鈴木達治郎氏はそう話す。
原子力規制委員会は昨年十一月、もんじゅを運営する日本原子力研究開発機構に「安全に運転する資質がない」と「最後通告」を突き付け、代わりの運営主体を探すように求めた。規制委は、名称変更にすぎない組織改編も認めないとクギを刺し、電気事業連合会も「電力会社は引き受けない」と突き放した。この時点で、もんじゅの廃炉は避けられない運命となっていた。
政府は今後、フランスとの高速増殖炉の共同開発を模索する一方、使用済み核燃料を再処理し、加工したMOX(プルトニウムとウランを混ぜた混合酸化物)燃料を一般的な原発で使うプルサーマル発電を続けようとしている。
このプルサーマル発電に、鈴木氏は疑問を呈する。「MOX燃料は一回使用すると、プルトニウムの質が悪くなり、二回目はほとんど使えなくなる。プルサーマルだけで核燃料サイクルを確立するというのは理論的に破綻している」
MOX燃料の廃棄処分にこそ、目を向けるべきだという。「高速増殖炉の実用化が見えない中、使用済みMOX燃料はもう再利用できない。高速増殖炉を切り離してプルサーマルでサイクルを回すというのはあり得ない。原子力の専門家も電力業界も経産省も分かっているのに、国民をごまかしている。MOX燃料をどう捨てるか、いつかは必ず扱わなければならない」
ただし、高速増殖炉から一切、手を引くべきだという意見には、鈴木氏はくみしない。「高速増殖炉には優秀な人材が多く携わっている。維持するに値する技術やノウハウを、世界の研究で活用できる」と説く。
「もはや一国ではやっていけないが、次世代炉として有力な選択肢の一つ。この先、百年、二百年単位で原子力を扱うなら、資源効率という持続可能性を追求するため増殖炉は必要になるかもしれない。日本がいつまで原子力をやるか分からないが、新しいアイデアにつながる研究開発手続けることは、人材確保にもつながる」
また、世界では、増殖炉とは別に、プルトニウム処分用の高速炉の開発も進んでいるという。「核燃料の処分、廃棄のための新しい研究分野はいくらでもある。世界を見ても、もはや高速増殖炉という目標は優先順位としては低い。MOX燃料の地下への直接廃棄を検討しながら、使用済み核燃料処理の新しい技術開発について、基礎基盤研究の国際協力を進める道は残されている」
そうした研究は、もんじゅの年間維待貨二百億円より一桁少ない予算で十分可能だという。「直接廃棄と研究開発の両輪を並行すればよいのではないか」
仏と協力 活路開ける?
ASTRID計画 主導企業は経営難 計画遅延
「開発継続の是非議論が先決」
高速増殖炉は冷却材に液体ナトリウムを使い、中性子を減速させずに高速で利用し、MOX燃料を核分裂させる。消費する燃料よりも多く核燃料を作り出す次世代原子炉として期待されてきた。
その実用化には、高度な知見、技術が必要だ。そのため、まず、発電設備のない「実験炉」で基礎的な研究を行う。次いで、発電できる「原型炉」を稼働させる。経済性を検証する「実証炉」を安定的に運転させることができるようになれば、一般的な発電所と同様に電気を供給する「商用炉」の運転が可能になる。
日本の研究開発は一九六0年代に本格化した。原子力機構が七四年に実験炉「常陽」(茨城県)を完成させ、計七万時間の運転を実現した。第一段階はクリアしたといえるが、二OO七年に原子炉内でトラブルを起こし、現在は停止中。
続いたもんじゅは九一年に試験運転を始めたが、九五年にナトリウム漏れの火災事故を起こし、開発が滞った。一兆円以上の国費をかけたが成果はなく、第二段階の「原型炉」でつまずいたというわけだ。
年内には、もんじゅの廃炉が決まる方向だが、世耕弘成経済産業相は「高速炉開発の方針は堅持する」と明言した。官民の「高速炉開発会議」を新設して、今後も高速増殖炉開発を続けるという。見据えるのが、高速増殖実証炉「ASTRID(アストリッド)」計画のあるフランスとの共同研究だ。
アストリッドは、フランス政府と原子力大手アレバが、原子力施設が集中するマルクール地区で建設を進める。二O一九年をめどに基本設計を終え、三O年ごろに運転開始予定という。
実は既に、一四年八月、原子力機構がアストリッド計画で技術協力手することで合意している。その三カ月前、安倍晋三首相がフランスを訪問し、共同研究の推進を約束していた。
アストリッドの開発はどこまで進んだのか。原子力機構報道課の担当者は「職員をフランスに派遣するなどして、昨年までに概念設計を終えた。今年から基本設計に移り、予定通り一九年までに設計を完成させる方向だ」と話す。これまでに技術協力で使われた総額は、「手元の資料では分からない」という。
この先の技術協力は不透明だ。フランス側が求めているのは、もんじゅによる燃焼テスト。世耕氏は「常陽も再稼働していく」と発言しているが、原型炉でなく実験炉のデータで、フランス側は納得するのか。原子力機構の担当者は「フランス側がどのような条件でのテストを想定しているかにもよるが、常陽で対応できるものは協力していく」と話す。
だが、規制委が「資質」を問題視した原子力機構が技術協力を続けてよいのか。また、高速増殖炉開発の第二段階を越えられなかった日本が、第三段階に進む必要があるのか。
原子力資料情報室の伴英幸共同代表は「高速増殖炉は研究を重ねても、実用レベルに達する見通しが全く立たない。もんじゅがダメだからアストリッドに軸足を移すと安易に考えるのではなく、開発継続の是非をきちんと議論することが先ではないか」と指摘する。
「アレバは赤字続きで経営危機に陥っており、アストリッド計画は当初より五年遅れている。共同研究で、日本は資金だけ引っ張り出されることになりかねない」と警告し、政策転換を求める。「高速増殖炉は原発と比べ、はるかにコントロールしにくい。福島の原発事故後、受け入れる自治体があるとは考えにくい。撤退が合理的だ」
自由なラジオ Light Up! 030回
「現場記者が見てきた『原子力ムラ』。 〜矛盾に直面する地元、そして都会の無関心〜」
https://youtu.be/o6wx0XBaZmQ?t=18m
18分00秒~第030回ライトアップジャーナル
防衛費から大学へ補助金支給するという問題について
http://jiyunaradio.jp/personality/journal/journal-030/

西谷文和:
今日は、今中哲二さんに繋がっています。今中さん、よろしくお願い致します。
今中哲二さん:
はい、こちらこそよろしく。
西谷:
今中さん、今日は『防衛費から大学へ補助金支給ってどういう事?』と題してお送りしたいと思いますが。今中さん、これ調べてみますと、防衛費5兆円超えてるじゃないですか。その内のこれ大学へ、これ軍事研究なら大盤振舞するということで、去年は2016年度は6億円だったんですけど、来年は110億円。

今中さん:
はい、それは凄いですね。
西谷:
これ凄いお金ですよねえ。これ今中さん、普段その研究費を削っておいて、戦争に関する研究なら、こんだけ大盤振舞って、これどう感じられてます?
今中さん:
とにかく防衛庁、防衛相ですか。やっぱり大学の先生なりをいろいろ取り込んでいきたいという意図があるんだと思いますよ。
西谷:
決して武器の研究だけではない。つまり、いわゆるデュアルユースですね。民生技術も使えるから両方いけるからということで、このお金を使ってくれと言ってるんですが。このセンスって、どういう風にお考えですか?
今中さん:
そういう意味ではいわゆる技術、科学技術というやつは、要するに、使い方の問題なんで、軍事か商業用民生用かという区別のないものは山ほどありますよね。
西谷:
そうですねえ。
今中さん:
ロケットでもそうですし、ロボットでもそうでしょうし、コンピューターでもそうですすし、原子力だってそんなもんですから。
西谷:
そうなんです。原発だって電気を発電する平和利用でありながら、核兵器をつくれるという。こういう事でしょ?
今中さん:
だから、やっぱりそこで問われるのは、研究者側の基本的なスタンス。特に社会との関わりをどう考えるかという事だと思いますねえ。
西谷:
ノーベル賞取られた方がおっしゃってるんですが、すぐに役立たないけれども基礎研究は大事だと。
今中さん:
そうですねえ。大隅先生なんかは、いわゆる今の大学の中では心配されてるんだと思いますよ。
西谷:
今あるすぐに役立つものばかり求めると、学問というのが細っていく可能性ありますよね?
今中さん:
と言うかね、一番最悪なのは、いわゆる大学の今の先生、研究者がいわゆる法人化になってから、任期制が導入されてるんですよね。
西谷:
任期制というのは例えば……。
今中さん:
5年とか10年。
西谷:
5年とか10年で研究しなさい。
今中さん:
それまでにちゃんと成果をあげなさいと。そうしなければ、その後、再任されるかどうかは分かりませんよ、というような。
西谷:
という事は、すぐに結果出せということになってしまうわけですか?
今中さん:
そうですね。はい。ですから、結果を出さなきゃいけないということで、自分の立場なり、自分のスタンスを考えていくというような余裕がだんだんだんだん無くなってくるんだと思いますよ。
西谷:
はい、そんな事でですね、今、デュアルユースの話が出て、原発は正にそうではないかという話がありましたけれども。
今中さん:
原発は一番最初からそうです。
西谷:
両方という。
今中さん:
はい。
西谷:
僕らから見たら誤魔化されていたという風に思うんですけども。
今中さん:
っていうか、軍事事業から始まってるわけですから。はい。
西谷:
そうか。それでね、ちょっと具体的にお聞きしたいのは、もんじゅが廃炉になったと。それで、もんじゅの使用済み燃料を再処理するRETFというのをね、私、福井県の明通寺の中嶌哲演さんという住職さんから初めてお聞きして、これリサイクル機器試験施設というらしいですけど。
今中さん:
はいはい。もんじゅの再処理の特徴は、爆弾にするのに良いプルトニウムが出てくると。
西谷:
それね、中島住職もおっしゃってたんですよ。このプルトニウムが物凄い純度が高いから、だから、このRETFで出てくる再処理された物は……。
今中さん:
そうですね、原爆向きのプルトニウムが出来ると。
西谷:
これ、正に長崎型原爆じゃないですか?
今中さん:
そうですよ。
(a)全体図 (b)一部断面の拡大
図―9 プルトニウム原爆の構造と材料
西谷:
ねえ?
今中さん:
はい。
https://youtu.be/UTdy1Yp1h5A
西谷:
これを1200億円もかけて、この施設を造ってるということは……。
今中さん:
造ってたんですけども、今はもう止まってると思います。
西谷:
今、一時休止ですか?
今中さん:
はい。
西谷:
でも、核燃料サイクルは諦めてないわけでしょ?日本は。
今中さん:
そうですねえ。ですから、もんじゅがあんなにひどい状態なのに、まだまだ息も絶え絶えですけども、なかなか無くならないというのは、やっぱり、裏にそういう核兵器なり何なりの問題があるんだと思いますよ。
西谷:
でも、これも膨大な無駄遣いですよねえ。こういう物を造ってるっていうこと自体。
今中さん:
これはね、福島の事故が起きたのはもう5年前ですかねえ。その後、原子力をどうするかといった話が出た時に、もし核燃料サイクルを止めちゃうと、いわゆる核抑止力が無くなるぞというような事は読売新聞の社説に出たりしましたから。
日本は原子力の平和利用を通じて核拡散防止条約(NPT)体制の強化に努め、核兵器の材料になり得るプルトニウムの利用が認められている。こうした現状が、外交的には、潜在的な核抑止力として機能していることも事実だ。
核抑止論!(#ノ`皿´)ノコラー!!!
西谷:
なるほど。そうですかあ。という事はですね、やはり、大学にその軍事研究なら大盤振舞するということと併せてですね、やっぱり、この国は、表立っては言いませんが、その裏の理由としては、やはり軍事大国になりたがってるっていうことでしょうか?
今中さん:
軍事大国というか、要するに、核兵器を開発する潜在的能力をずーっと蓄えておくというのが
原子力政策の裏に流れてると思います。

西谷:
なるほど。だから、やっぱりこんな事故が起きても、それはこだわっておられるということですね?今、日本の政治家の皆さんは。

今中さん:
はい。
西谷:
はい、よく分かりました。今中さん、どうもありがとうございました。
今中さん:
はい、どうも。
西谷:
以上、ライトアップジャーナルでした。
2012年6月18日
「不滅のプロジェクト ~核燃料サイクル 迷走の軌跡~」
http://dai.ly/xrpkhj
日本の原発から出た使用済み燃料は1万5千トン。行き場のないまま原発敷地内などに保管されている。
ゴミである使用済み燃料の処理方法が無いまま稼働を続ける原発は、トイレの無いマンションと揶揄(やゆ)される。この問題を一挙に解決する方策として模索されてきたのが「核燃料サイクル」だった。
その夢のサイクルが、福島原発事故をうけて原子力行政が問い直される中、根本的に見直されようとしている。将来に向け、私たちはいまどのような選択をすべきなのか。それを考える前提として核燃料サイクル60年の足取りを知っておくことは必要だ。
日本では、原発開発が始まった当初から「核燃料サイクル」が目標にされた。
使用済み燃料を再処理してプルトニウムを取り出し、再び燃料として利用する「核燃料サイクル」は、資源小国のエネルギー問題と、放射性廃棄物というやっかいなゴミ問題を一石二鳥で解決してくれる夢のプロジェクトとしてスタートした。
サイクルの要となる高速増殖炉は、プルトニウムをウランと混ぜて燃やし、使用前よりも多くのプルトニウムを作り出すことができるというもの。これを確立することができれば、理論上、千年はエネルギー問題から解放されると期待されてきた。
この「核燃料サイクル」の計画からその後の経緯までの内幕を、赤裸々に記録した録音テープがある。
日本の原子力政策を中枢で担い続けてきた、政・官・財・学の中心人物が、非公式で開いていた「島村原子力政策研究会」の会合を録音したテープだ。国家プロジェクトとして始まった核燃サイクルがさまざまなう余曲折の中で迷走していった過程が語られている。
日本の核燃サイクルは「トリウム」という軍事利用できない燃料を使ったものが研究された。しかし、実現を急ぐ政界の意向から英米から既成技術を輸入することに方針転換された。
英米で開発されていたのはトリウムではなく「プルトニウム」を使った核燃サイクルだった。プルトニウムは核兵器の材料になる。
1960年代に中国やインドでの核開発に脅威を感じたアメリカは、70年代に日本の核燃サイクルに待ったをかけてきた。この圧力は日本に「焦り」と「意地」を生じさせ、冷静な開発を困難なものとしていった。
計画開始から半世紀以上が経過した今、まだ核燃サイクルは実用化されていない。そして使用済み燃料の問題は依然として解決していない。「一石二鳥」どころか「二兎(にと)を追う者、一兎(いっと)も得ず」の状態になっている今、核燃サイクルという夢を追ったプロジェクトの経緯を検証し、問題の所在を明らかにする。
20160123 UPLAN
槌田敦「沸騰水型原子炉の欠陥」
-核兵器生産可能な原子炉-
https://youtu.be/XY-WgI8jBXM
「軍学共同」反対シンポジウム【第1部】
https://youtu.be/SiikQBr8p8Y
「軍学共同」反対シンポジウム【第2部】
https://youtu.be/zsKdqCtNUj0
「軍学共同」反対シンポジウム【第3部】
https://youtu.be/OuTaXZShsXY
第031・033回ライトアップジャーナル
自由なラジオ Light Up! 031回
「DAYS JAPAN若き編集長が語る「いのちのものさし」」
https://youtu.be/AMNbA9tFEjk?t=15m9s
15分09秒~第031回ライトアップジャーナル
三反園鹿児島県知事の決断と川内原発の差し迫った危険性
http://jiyunaradio.jp/personality/journal/journal-031/
いまにしのりゆき:
今日のライトアップジャーナルは、元京都大学原子炉実験所助教の小出裕章さんがお住まいになられております
長野県の松本市、松本市役所にお邪魔をして直接お話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
小出裕章さん:
はい、よろしくお願いします。
いまにし:
先立ってですね、この番組にゲスト出演を頂きました松本市の菅谷昭市長はですね、いわゆる甲状腺疾患を研究されているお医者さんでもいらっしゃいますよねえ。
菅谷昭市長:
はい。
いまにし:
日常のそういう生活ですとか防災面でですね、チェルノブイリや福島の教訓をいわゆる松本市の市政に活かすのかという事を凄く真剣に取り組んでおられるなあという印象を受けたのですが、小出さん、実際、お住まいになられていかがでしょうか? 松本市。
小出さん:
今、いまにしさんがご紹介下さったように、菅谷さんは元々お医者さんだったわけで、人間の健康ということを何よりも大切にするという方です。市長になられてからも、健康寿命延伸都市というのを彼の旗印にしていまして、健康に豊かに生きられるという、そういう人達をこの街で増やしていこうとして、様々なことを彼がやってきて下さっていて、有難いと私も思っています。

いまにし:
小出先生も寿命伸びそうですか?
小出さん:
ええ、もう私は大阪にいた時は、もういつ死んでも不思議でないと思いましたけど。こちらに来てからは、とにかく山に囲まれて空気は美味しいし、温泉はもうそこらじゅうにあるしということで、こんな所だったら長生きできるかもしれないなぐらいに思うようになっています。
いまにし:
なるほどなるほど。飲み過ぎには気をつけて下さい。
小出さん:
そうですね。それが一番の私の場合はがんだと思います。
いまにし:
そんな中でですね。鹿児島県の三反園訓知事がですね、それまでは川内原発再稼働を推進してきた前の知事の伊藤さんの原発推進するやり方はあかんということでですね、「原発をなくし、鹿児島を自然再生エネルギー源にしよう」という主張を展開され当選されました。
小出さん、非常にこの三反園新知事のですね、この新しく出されましたキャッチフレーズていうのは良いなあという印象があるんですが、いかがでしょうか?

小出さん:
はい、私もそう思います。私は元々政治が大嫌いで、政治には関わらないとこれまでも発言をきましたけれども、今はもうそんな事を言ってられないほど、日本の政治がひどい状況になってきたと思います。

自民党政権によれば、とにかく経済最優先。原発でも何でもどんどん再稼働。本音を言えば再稼働どころではなくて、原発の新規建設までしたいと彼らは思っているわけです。
残念ながら選挙をすると、自民党がまた勝ってしまうというような状況の中で、実際に原子力発電所を抱えていた。そして、保守王国とも言われていた鹿児島県で、原子力発電に抵抗しようというような知事が生まれたということは、私にとっては大変ありがたいことだと思いました。
いまにし:
はい。それでですね、以前にも少しお伺いしたのですが、熊本の大きな地震がありました。川内原発ですね、熊本の地震があった所っていうのはそんなに距離離れてません。そういう一つ皆さん不安に思われてる中で、やはり原発をちょっと見直した方がいいんじゃないかという、この知事の考えっていうのは非常にマッチしてるなあという気がするんですが。

小出さん:
はい。再稼働に許可を与えた伊藤知事自身が、「もし事故が起きてしまえば、住民を避難させることは難しい」というようなことを初めから言っていたわけです。

そして、今、いまにしさんおっしゃって下さったように、熊本地震がありまして、あの地震というのはたまたま熊本で起きて、西や東に動きながら熊本県、或いは大分県の辺りで動いたわけですけれども。あの地震は、実は中央構造線という日本最大の活断層の一部で動いたわけで、それがもう少し南の中央構造線で動いたとすれば、川内原発の真ん前で動いてしまうという大変危機的なことを、あの熊本地震が教えてくれているわけですし、たぶん三反園さん自身はそのことも意識して、「大きな事故は絶対まず起こしてはいけないんだから、まずは止めなさい」ということだと思います。

いまにし:
はい。小出さん、川内原発、万が一事故が起こった場合、どのような固有の問題が発生すると思われますでしょうか?
小出さん:
行ってみられたらいいんですけれども、川内原発が立地されてる所、云わば、いわゆる過疎地と呼ばれてるような所なわけで、道路事情もよくありませんし、仮に地震あるいは津波のようなもので福島の原子力発電所の事故が起きたけれども、同じような状況になれば、おそらく避難道路自身がもう通ることができないということになりますし、津波がもし押し寄せてくるとなると、川内原発というのは河口にあるのですけれども、川沿いにまた津波が遡上していって、その川沿いの道も使えなくなる。



あるいは、川沿いからまた海の津波が逆流してきて、川内原発を襲うというようなこともあるかもしれませんし、九州というのは巨大カルデラという、巨大な火山の爆発というのが度々あったということが分かってるわけで。鹿児島の今、桜島ですね噴火してますけど。

いまにし:
そうですね。もう年中噴火してますよねえ。
小出さん:
あそこの鹿児島湾っていうのは、実は巨大なカルデラの痕なんですね。

ですから、あそこでまたもう一度噴火するようなことになれば、火砕流が川内原発を襲うというようなこともあり得るというか、実際にもう過去にはそういうことが起きているわけであって、そうなれば道路が通れるなんてことは到底ないわけですから、住民は逃げることもできないだろうと思います。

いまにし:
はい。それで、三反園知事ですね、「原発は絶対に事故を起こしてはいけない」と「だからこそ、九州電力は停止して再点検すべきではないか」という主旨のお話をされています。これまさに正論なんですが、九州電力ほとんど耳を貸そうとはしませんねえ。( ̄^ ̄)凸
小出さん:
全然しないですね。九州電力だけでなくて、関西電力も高浜原発を一度は再稼働させたわけです。どこの原子力発電所をやってる電力会社も全く反省もしていないわけですし、反省どころか彼らは逆に、これからもし再稼働して事故を起こしたとしても、福島第一原子力発電所の事故の場合にそうであったように「誰も責任を取らずに済む」、「誰も処罰をされないで済む」ということを彼らは教訓として学んでいるわけですから、もう彼らとしては怖いものは何にもない。どんどんやって、事故になっても俺達は知らないと逃げることが出来るという風に、思っているわけです。
いまにし:
そうですね。ほんとに困ったもんですけれども、何とか三反園知事には一石を投じる意味でも頑張って頂きたいものですよねえ。
小出さん:
そうですね。是非、頑張ってほしいです。
いまにし:
ありがとうございました。
今日のLightUpジャーナルは、長野県松本市から小出裕章さんに直接お話を伺いました。
そもそも総研 20140724
そもそも火山が噴火しても原発は問題ないのだろうか?
http://dai.ly/x2219al
そもそも総研 20160818
そもそも熊本地震の後、原発は大丈夫なのだろうか?
http://dai.ly/x4pgusf
もう一度言う、福島原発事故の主犯は安倍晋三だ! 第一次政権時に地震対策拒否、事故後もメディア恫喝で隠蔽…
(リテラ)2016.03.11
http://lite-ra.com/2016/03/post-2055.html

東日本大震災から今日でまる5年。いまだに17万人以上の被災者が避難生活を強いられているなか、昨日夕方、安倍晋三首が官邸で記者会見を行った。
「皆さんのふるさとへの熱い思いが大きな力となって復興は1歩1歩確実に前進しています」「東北の復興なくして日本の再生なし。その揺るぎない信念の下に希望に満ちあふれた東北をつくり上げていく」。そう、決まり文句のようなスピーチをした安倍首相だが、一方、先日再稼働直後後に原子炉が緊急停止した高浜原発について問われ、こう答えた。
「地元理解を得ながら再稼働を進めるというのが政府の一貫した方針であり、この方針には変わりはありません」
今後、どんなトラブルがあっても原発再稼働を進める気でいる安倍首相。しかし、当然のようにこの会見でも、どの記者も決して“あのこと”には一切触れようとしなかった。そう、他ならぬ安倍晋三こそ、原発事故の“戦犯”だという事実だ。
実は、安倍首相は、第一次政権時の2006年、国会で福島原発事故と同じ事態が起きる可能性を指摘されながら、「日本の原発でそういう事態は考えられない」として、対策を拒否していたのだ。だが3.11の後、安倍氏は当時の民主党菅政権の事故後対応のまずさを攻撃することで、また、事実を追及するメディアを「捏造だ!」とがなりたてることで、自らの重大責任を隠匿してきたのだ。
以下に、本サイトが以前、この安倍氏のフクシマにおける大罪、そして、その責任逃れのために行ってきた数々のメディア圧力を明かした記事を再録する。3月11日の今日、ぜひとも、じっくりとお読みいただきたい。
(編集部)
リンク先に続く

自由なラジオ Light Up! 032回
「届け思い。あなたのもとに! 一途に真っすぐに生きるものたちのために」
https://youtu.be/5J5g3PtMP-8
【渾身の一発ギャグ】櫻井よしこ氏「『もんじゅ』の活用こそ日本の道です」朝日新聞意見広告
(健康になるためのブログ) 2016/11/16
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/24184


「むしろ世界はいま、高速増殖炉を最終目的とした高速炉発電の時代に入っているのです。」ですと…
アホか!本音をはっきり言いなさいよ!!「核兵器のためにプルトニウムが必要だから、もんじゅは止めてはいけません」と!(゚Д゚#)ゴルァ!!
自由なラジオ Light Up! 033回
「広告代理店からの巨額な広告費に支配されるメディアを疑え!」
https://youtu.be/z0Orj-Q8-ks?t=18m25s
第033回
原発とプロパガンダ〜巧妙に仕組まれた日本のメディア報道と広告〜
http://jiyunaradio.jp/personality/journal/journal-033/

おしどり(マコ);
いつもこの時間は原発の話題をお届けしているのですが、松本の小出先生と電話でおしゃべりしたりね。今日はスタジオのお客様、本間龍さんとこのコーナーを進めてまいります。
本間さん、よろしくお願いします。
本間龍さん:
よろしくお願いします。
おしどり(マコ);
本間さんは原発事故の後、広告代理店と原発、電通と原発みたいな本をいっぱい書かれてますよね。岩波新書から今年4月に発売された『原発プロパガンダ』等、いろいろ原発と広告代理店の電通などのお話を本を出されてますけれども。やっぱり、原子力、原発に広告代理店はめっちゃ入ってるんですか?
本間さん:
もうめっちゃ入ってましたよねえ。今も入ってますけど。結局、3.11の事故の前、割と日本国民っていうのは原発に寛容だった。「あってもしょうがないんじゃない」みたいな、そういう空気が強かったじゃないですか。あんまり反対してなかった。
「それは何でなのかなあ?」って考えた時に、誰かがやっぱり国民に対して、「原発は安全だよ」とか「原発は必要だよ」っていうそういう何か気持ちを植え付ける。誰かが何かしないと、そもそも普通の人は原発のことなんか誰も分かんないじゃないですか。しかも、大体が海沿いにあって、そんな簡単に見に行けるものでもないしね。「じゃあ、それは一体誰がやったのか?」って考えていくと、それってほとんど広告なんですよね。結局、東電とかね。
https://youtu.be/F1SJJYm2iGM
おしどり(ケン):
僕も小っちゃい時からテレビとかで。
本間さん:
CMやってたでしょ?
https://youtu.be/E48xSBosc5k
おしどり(ケン):
はい。日曜日とかになったら凄くそういうコマーシャル見たなって、今、改めて思いますね。
本間さん:
結局いろいろ調べていったら、原発広告って、もう40年ぐらいの歴史があって。
これは朝日新聞さんがね細々調べたんだけど、だいたい新聞雑誌広告で原発広告に40年間で費やされた金額が大体2兆4千億円ぐらいだろうという莫大な金額。
おしどり;
凄いですねえ。
本間さん:
凄いでしょ。更に、そこにテレビとかが乗っかってくるからね。もっともっと莫大な金額になるわけですよ。
それをじゃあ誰がそうやってメディアと東電とか関電とかね、あの人達とメディアを繋いでいたのかって言ったら、それもう広告代理店しかないわけです。その間に立ってた広告代理店っていうのは、やっぱりもう電通とか博報堂っていうことに。でも、ほぼ電通だけどね。
おしどり(マコ);
そうですよねえ。でも、原発事故の後、その40年前からなんでしょうけど、今、原発事故のなんかいろんなね問題を環境省が動いてるじゃないですか。これは、私、研究者とか環境省の中の人に聞いたんですけど、それ昔は環境庁だった時代は、そんななんかハードなことやってなくて、パンダちゃんとか自然大切にしようとか、割とそういうような仕事だった時は、めっちゃ広告代理店と電博にお金を卸して、いろいろイベント組んで自然大切にしようイベントやってたから。
原発事故があって、いろいろイベントっていうか公聴会とか地元の会とか説明会とか汚染問題どうこうっていうのを全部やっぱり電博に、前と同じようにやってもらってるっていう。
だから、一番お金持って行ってるのは電博じゃないかっていう話を中の人に聞いて、「あっ、そうなんですか」みたいな。
おしどり(ケン):
あっ、そうか。税金っていうことですか?
おしどり(マコ):
うん。そうそうそう。凄いなと思って。
本間さん:
大体、政府系のそういったピーアール予算の半分は大体、電通が大体持って行ってるよねえ。
おしどり(マコ);
凄いですねえ。
本間さん:
そうよ。それ、だって全て合わせれば200~300億円ぐらいになるからね。
おしどり(マコ);
凄いなあ。
本間さん:
持って行っちゃってるから。これ重要なお仕事だよねえ。
おしどり(マコ);
そうですよねえ。
おしどり(ケン):
でも、最初に龍さんがおっしゃった、その40年の歴史、事故前の40年間で大体2兆4千億円っていう金額出ましたけどね。これ、今、廃炉とかにかかってるお金とかって考えると、もう数年で2兆も。
本間さん:
ほんとだよねえ。
おしどり(ケン);
お金の感覚が分からなくなってきますねえ。大きすぎて。
本間さん:
それで重要なのは、それだけのお金が広告としてテレビ局、ラジオ局、新聞社、雑誌社に流れてる。そうなったら何が起きたかって言うと、結局、その広告費一度もらっちゃうと、もう来年からその広告がなくなるのがみんな嫌だから、だから、その原発について疑問の記事とかね、ネガティブな記事っていうのをみんなだんだん書かなくなってちゃったんだよね。それが結局、3.11直前の状況までそういう形が続いていって、誰も警告鳴らさない。
だから、もう東電もやりたい放題やっちまって、結局、安全面もお金もケチったと。そういう事がやっぱり事故に繋がっていくっていうね。だから、やっぱり結局、このメディアと原発って言うと、簡単には思い付かないかもしれないんだけど、かなり恐ろしい繋がりがあって、結局、巨額なお金が流れたことによって、メディアがきちんとした報道をしなくなってしまって、事故が起きたっていう風に僕は思ってるんだよねえ。
だから、そこは、そういう事を何回かいろいろ調べて本にしてるっていうことで。これは、メディア自身は、みんな脛に傷を持ってるから、みんな自分じゃあ書かないわけよね。
おしどり(マコ);
でもね、原発事故の後にいかに取材をしてて、「会見でこれだけはっきり言ってるけど、こんなにニュースにならないの?」っていうのを思い知らされたんで、それが、もうずーっと昔からだったんだろうなあっていうのは。
おしどり(ケン):
報じられてることのギャップにビックリしますもんねえ。
本間さん:
いっぱいそういう話はあるよねえ。
おしどり(マコ);
いや、でもトビアス、ドイツ人のスイス大学に行ってる研究者から。彼がプロパガンダを研究、調査されててフィードバックしてて、いろんな国に行って、いろんな広告とかプロパガンダのなんか調査をしてて、日本に来たとき時々会うんですけど、「フランスとかも原子力使ってるから、日本みたいじゃなの?」って聞いたことがあったんですけど。なんかトビアスによると、「日本は世界で類を見ないくらいプロパガンダが有効な国だ」って言うんだよね。恥ずかしいですよね。
おしどり(ケン):
成功しているっていう。
本間さん:
そうそうそう。
おしどり(マコ);
「なんかテレビとか新聞に出ていることは、全て事実だって思う人間が一番多い」って言ってました。
本間さん:
そうね。やっぱり正直っていうかね。
おしどり(マコ);
正直ですか?バカがつきませんか?
本間さん:
そうかもしれないんだけどね。やっぱり、それを物事を疑うっていう論理的に疑うっていう教育をされてないんだよね。日本人はね。結局ほら、もう学校に行ったら先生の話をこうやってずーっと聞いて、別に反発しないでずーっと静かに聞いて。
「えーっ、おかしいんじゃないの?」って言ったら、そういう生徒はほらね指されなくなるとかね。それこそいじめられるとかになっちゃう。だけど、だから、「本当はそういう全然ロジカルじゃないよね」とかね、「事実と違うんじゃないの?」とか、そういう事を疑うっていうのを、なんか日本の教育ってやっぱりずーっとやってないなって感じはするよね。特に高校生ぐらいまで。大学は、またちょっと別だけどね。高校生ぐらいまでにそういうのがないと、結局、なんだかテレビ、新聞、雑誌で書いてることみんな本当だっていう風に思っちゃってんじゃないかなっていう気はするね。
おしどり(マコ);
そうですね。教科書丸暗記みたいな。
本間さん:
そうそうそうそう。それで点数取れる人が偉いっていうことになっちゃってる。
おしどり(マコ);
そうですね。ヤバイな。教科書丸暗記みたいに新聞とかテレビ見てたら、めっちゃ怖いですよね。
本間さん:
そうですね。
おしどり(マコ);
でも、そういうことでしょ?
おしどり(ケン):
そうか、書いてることをね。
おしどり(マコ);
そう。教科書が間違ってないっていう前提で、そういう物の読み方しかしてない人が大人になって働いて、テレビとか新聞も「うん、なんか大手のメディアだし、かしこそうな人が行ってるから、もうこれは正しい」って常に受け取ってたとしたら凄い怖いですよね。
本間さん:
恐いよねえ。タレントの何とかっていうのがねえ。最近、タレントの人が、テレビでなんかやってたりすることが凄いある。でも、ああいう人達はニュースの現場なんか知らないしねえ。ただ読んでるけど、でもねえ。ジャニーズの誰それが読んでれば、「○○君は嘘は言わないわ」なんて勝手に思うファンもいるわけでしょ。だから、そういうことだよね。そうやって使われちゃう。
おしどり(マコ);
そうですよねえ。ほんとだ。そう私、原発事故の取材をしてて、なんかあっちこっち行ってね、いろんな地域に行って話を聞いて、それでその自分達で判断して動いてた人って、ちょっと面白いんですけど、落ちこぼれとか不良が多いんですよ。それ面白いなと思って。
おしどり(ケン):
落ちこぼれって、マコちゃん一言で言いますけど、学校のそういう勉強とかそういう中での落ちこぼれっていう意味だよね?
おしどり(マコ):
そうなん。自分の頭で考えることをめっちゃしてる。
おしどり(ケン):
そうよねえ。
おしどり(マコ):
なんかその国が守ってくれるとかじゃなくって、「いや、俺の家族は俺が守らないといけないんすよ」みたいな人が、自分達で判断をして、スパーンって早く動いてるっていう例をいくつも見て。そのいろんなお医者さんとか学校の先生とかをね、いろいろお話を伺ってて聞いてても、その原発事故の後、独自で動いてるお医者さんとか学校の先生とかって、その必ずしもエリートじゃなくって。でも、自分で考えて自分で動くみたいな。誰が何と言おうと、自分の判断しか信じないみたいな。「国がこう言ってるから大丈夫ですよ」とか「教科書でこうなってるから大丈夫ですよ」っていうような人達は、自分で判断しなかったなあっていう。
本間さん:
まあ、そうだよねえ。だから、プロパガンダがやりやすいっていう国になっちゃってるっていうね。
おしどり(マコ);
そうですね。本当にCMとかテレビのニュースとか記事を作ってるのは、書いているのは、お金を出しているのはどこかっていうのを考えながら、ちゃんと情報を摂取しないといけないっていうことですねえ。
おしどり(ケン);
そうですねえ。ええ、悪いって話よりも、そのお金がかかってちゃんと宣伝されて広告打たれて僕達の所に入ってきてるということを分かっておくということが大事ですよね。
本間さん:
そのシステムがあるんだっていうことを知っていて見てるのと、知らないで見てるのとでは全然捉え方が違うよねえ。
おしどり(マコ);
そうですよねえ。いや、ほんとそう思います。はい、ありがとうございました。今日のライトアップジャーナルは本間龍さんと共にお届けしました。

40年間で2兆4000億円もの「電気代」が原発プロパガンダに消えた!? 日本のメディアを牛耳る巨大広告代理店「電通」の実態に迫る!~岩上安身が『原発プロパガンダ』著者・本間龍氏に訊く
(IWJ) 2016.10.13
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/338266
ゲスト 本間龍「原発広告をめぐって」 鈴木耕の原発耕談
https://youtu.be/aEhb27nTkkA
第034・035回ライトアップジャーナル
自由なラジオ Light Up! 034回
「なぜこの国は『永続敗戦国家』になってしまったのか? 」
https://youtu.be/G9D-uydAtCk?t=18m17s
18分17秒~第034回ライトアップジャーナル
こんなにも地震が多いのに、原発再稼働していいの?
http://jiyunaradio.jp/personality/journal/journal-034/
西谷文和:
今日は、今中哲二さんと電話が繋がっています。今中さん、今日もよろしくお願い致します。
今中哲二さん:
よろしく。
西谷:
今中さん、今日は『こんなにも地震が多いのに原発を再稼働していいの?』というテーマでお送りしたいと思いますが、地震多いでしょ。この前、鳥取で起こったじゃないですか。調べてみたら、鳥取では1943年にも起こってる。
今中さん:
そうですね。はい。
西谷:
これ戦中だったので、あまり報道されてませんけどね。その5年後に福井大地震が起こってるんですよ。1948年。
今中さん:
福井でもありましたね。はい。
https://youtu.be/AEZfL6-n-F4
西谷:
これ今、もしこの公式に当てはまると、あと5年後に福井大地震がきたら、これ大変やなあと思うんですけど。
今中さん:
まあ予言になりますけど、よう分かりませんね。
西谷:
でも、15基もあるじゃないですか。福井県に。
今中さん:
福井で地震が起きたら大変ですし。
西谷:
大変でしょ?
今中さん:
ただね、原発を造り始めた頃の地震に対する考え方っていうのは、凄く甘かったですよ。今だったら、皆さん、地震は断層が揺れてすべって起きると。
西谷:
正に熊本なんかそうですね。
今中さん:
みんなそう思ってますよね?
西谷:
はい。
今中さん:
ですから、40年前、50年前は偉い先生方も断層というのは地震の後だと。それで地震が起きるのは、また別だと。
西谷:
そんなことおっしゃってたんですか?
今中さん:
ええ、そんな事を言ってました。それで、私がですから、今の職場に来た1976年頃は地震の起き方というのが議論になってました。ですから、今問題になってる伊方原発ですけども。
西谷:
伊方というのは四国にあって、中央構造線。
今中さん:
あれは中央構造線のその上に乗ってるんですけども、電力会社や国は「あれは断層ではない」とか。
西谷:
えっ?断層ではないって言ってるんですか?
今中さん:
そういう話をしてました。
西谷:
いや、あれは断層でしょ?
今中さん:
はい。誰が見ても断層なんですけどね。それで、断層であっても動かないとか。そういう事で、当時、例えば伊方原発で考えられたのは、あの太平洋で起きる大きな地震。
西谷:
南海トラフとか。
今中さん:
というか、それが一番大きな影響があると。それで、その後、どんどんどんどんいろんな新しい知見、新しい地震のデータ等が得られてきて、どんどんどんどん厳しくなってますよ。これは間違いないです。
西谷:
この状態で動かすということは、おそらく狂気の沙汰ではないかと思うんですが、どうでしょう?今中さんから見て。
今中さん:
動かすということは、我々が受けるリスクがどんどんどんどん大きくなると。
西谷:
でも、このリスクが大きくなりましたよって。それで、「でも、やりましょうか」って言って、ほとんどの人思わないと思うんですけど。なぜ、ここまで拘るんでしょうか?
今中さん:
私にも分かりませんねえ。電気そのものは足りてますし、余ってる状態ですよね。じゃあ、原発に経済性があるかと言うと、これもかなり疑問ですよね。
西谷:
例えば、使用済み燃料棒を冷やすだけでも、何十年ってかかるんでしょ?
今中さん:
はい。もしも事故を起こしたら、福島を見たら10兆円とか20兆円とか。
西谷:
膨大に膨れ上がりましたよ。この前の。
今中さん:
お金かかりますし。
西谷:
この前の専門会議で、かつて言ってた値段の何倍にもなりましたからねえ。
今中さん:
そうですねえ。はい。
西谷:
そういう意味では、なぜ動かすのか?今中さんでも分からないまま、動かそう動かそうとしているのが今の日本。
今中さん:
どういう力がどういう風に働いているのか。
西谷:
そうですね。ほんとに、そういうその闇の部分で再稼働をされようとしている原発ですが、やはり、こんなに地震が多いから、即刻止めていかないといけない、廃炉にしないといけないということでしょうか?
今中さん:
はい。
西谷:
はい、よく分かりました。今中さん、今日はどうもありがとうございました。
今中さん:
いえ、こちらこそどうも。
地震のたび「原発大丈夫?」 いつまで
(東京新聞【こちら特報部】)2016年11月23日
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2016112302000168.html
二十二日早朝の福島沖地震では、東京電力福島第二原発3号機(福島県富岡町、楢葉町)の使用済み核燃料プールの冷却装置が一時停止した。幸い大事には至らなかったものの、多くの人が肝を冷やしたに違いない。3・11以降、災害が起きるたびに「原発は大丈夫か」との心配が頭をよぎる。地震大国ニッポンで原発再稼働に血道を上げる愚。いつまで事故の恐怖におびえ続けなければならないのか。
(木村留美、安藤恭子)
福島第二の核燃料プール冷却停止
楢葉町民 不安また不安
福島第二原発が立地する楢葉町の住職早川篤雄(とくお)さん(七七)は「真っ先に頭をよぎったのは、原発は大丈夫かということだった」と振り返る。
東京電力によると、午前六時十分ごろ、3号機の使用済み核燃料プールの冷却水を循環させる系統が地震の影響で自動停止。安全を確認した上で午前七時四十七分に冷却を再開させた。プールには核燃料二千五百四十四体が保管されているが、水漏れや放射性物質の漏えいはないとしている。
早川さんは、あらためて原発への憤りを感じている。「第一原発は、大きな津波が来たらひとたまりもないのではないかと、地震が起こるたびに冷や冷やする。第二原発も使用済み核燃料を取り出さない限り、不安は払拭されない」
「5年前の爆発を思い出した」
楢葉町議の結城政重さん(六九)は、避難先の福島県いわき市で今回の地震に遭遇した。「3・11のように原発が爆発するのではないかと怖かった」
第二原発の四基は、二O一一年三月の東日本大震災以降、停止中だが、東電は再稼働に含みを残している。結城さんは「地震自体は揺れが収まればすむことだが、原発はそれだけですまない。議会の中にも第二原発は再稼働すべきだという人がいるが、あり得ないことだ」と憤る。
富岡町から福島県会津若松市に避難中の主婦古川好子さん(五三)も東電や政府の姿勢が許せない。「立地自治体の人たちが経済的な理由から動かしたい気持ちは分からないわけではない。でも、原発事故が起きた時の被害はあまりに大きい。五年前の事故をなきものにしようとして再稼働しようとする政府や東電にはふざけるなという思いだ」
国内以上に海外の関心は原発に向いている。英BBC放送(電子版)は「地震による原発損傷の兆候はみられない」と断った上で、3・11の福島第一原発事故の被害に触れた。ロイター通信も、第一原発など周辺の原発の状況を伝えた。英経済誌「エコノミスト」のデイピッド・マックニール記者は「日本政府の原発に対する発言を海外メディアが信用していないからだ」と指摘する。
「世界的に見ればフクシマはチェルノブイリ事故と同列に考えられている。安倍晋三首相が『アンダーコントロール(制御されている)』とアピールしても、実際にはいろいろな問題がある。福島での地震と聞けば、原発を思いおこすし、記者らも五年前の地震への思い入れもあるだろう」
日本を訪れている外国人旅行者からも不安の声が漏れた。東京駅近くで母親と買い物中のシンガポール人女性(二七)は「ホテルで寝ているところに地震がきた。シンガポールでは地震がないので驚いた。原発の放射能が心配になった」。
米国人女性(三二)らは「報道で地震を知った家族から心配するメールが届いた」と困惑した様子だった。
3.11のトラウマ 国民多くが抱える
政府「問題ない」に不信感
最大震度7の地震が連続して起きた四月の熊本地震では、稼働中の九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)への影響が不安視された。政府は最初の揺れから二日後に「プラントの状態や、モニタリングポストに異常はない」と発表。同市では震度4が観測されたが、原子炉を自動停止させるレベルよりかなり小さいとされ、運転は継続された。(¬_¬)
七月の県知事選では県民の不安も背景に、川内原発の一時停止を公約に掲げた三反園訓氏が初当選した。九電に即時停止を求めたが拒まれた。ー号機では、定期検査と並行して熊本地震の影響を調べる「特別点検」を実施しているが、2号機は稼働中だ。
豊後水道を挟んで四国電力伊方原発(愛媛県伊方町)から最短で約四十五キロの大分県では、復数の市町議会が、再稼働への反対や慎重な対応を求める意見書を可決した。原発に近い日本最大の断層帯「中央構造線」の活発化を恐れてのことだが、政府は原子力規制委員会の新規制基準の審査に適合した原発は再稼働させる方針で、八月には3号機が再稼働した。
「政府や電力会社が言う原発の状況に不信感がある」と話すのは、川内原発建設反対連絡協議会会長の烏原良子さん(六八)だ。熊本地震で最初の大きな揺れがあった後すぐに、同原発の事務所に状況を電話で問い合わせたところ、「大丈夫です」と即答されたという。「点検中と言ってくれれば、まだ信用できたのに」と顔をしかめる。鹿児島に震源地が広がることを恐れ、高速道路や新幹線が使えなくなる現実を知ったことで「市の避難計画なんて役立たず。熊本のような地震がここで起きたら、逃げられない」と確信した。
十月には鳥取県で震度6弱の地震が発生。中国電力島根原発(松江市)は運転停止中で異常は確認されなかったが、原子力資料情報室の伴英幸共同代表は「多くの国民が地震と原発事故を結び付けて見るようになった。熊本、鳥取と続けば、次は原発が立地する中央情造線や南海トラフ沿いで起きないか心配する心理がはたらく」と説く。
伴氏は、メルトダウン(炉心溶融)の公表が遅れるなどした福島事故を機に、災害時の原発広報が信用されなくなったとみる。
「十分な根拠を示さず拙速に『問題はない』と発表するやり方は、熊本地震も福島沖地震も通底し、国民の不安を解消できない」
元京都大原子炉実験所助教の小出裕章氏も、福島沖地震で「原発は大丈夫か」と考えた。福島第二原発の使用済み核燃料プールの冷却設備が停止したと聞き、さらにひやりとした。「プールに亀裂が入り、放射能が漏れる事態も想定した。いつまで不安を抱え続けなければならないのか」
精神科医の香山リカ氏は「多くの国民が3・11の不安をトラウマ(心的外傷)として抱えている。原発の冷却ができないといった今回の情報は当時をフラッシュバックさせ、原発の爆発や、食べ物の放射能汚染など、先を見越した『予期不安』が心の中で起きている」と分析する。
ネット上などで原発への不安を口にすると非難される風潮も、ストレスを高めているようだ。香山氏は「政府が再稼働を進めれば、原発はいつ終わるとも知れないので、事故への恐怖は洛ち若くことがない。今すぐでなくとも、将来的に全ての原発を廃炉にしていくんだというビジョンを示さない限り、国民が抱える不安感は今後も増す一方だ」と警鐘を鳴らした。
『フタバから遠く離れて 第二部』映画オリジナル予告編
https://youtu.be/H3YpWH-g2qk
自由なラジオ Light Up! 035回
「福島県双葉町現地ルポ(第1部)
& 前西成区長が振り返る公募区長の3年8か月(第2部)」
https://youtu.be/rDDlujUWsZk?t=5m51s
5分51秒~第035回ライトアップジャーナル
Light Up!ジャーナル特別編:福島県双葉町ルポ・未だ続く帰還困難区域の高線量
http://jiyunaradio.jp/personality/journal/journal-035/
いまにしのりゆき:
先だって、私は福島県双葉町ご出身の大沼勇治さん。自由なラジオLight Up!にも何度かご出演頂いておりますが、大沼さん、ご出身の福島県双葉町、今も期間困難区域に指定されているということで、なかなか簡単に足を踏み入れることができないのですが、大沼さんと二人で双葉町の方に行ってきました。
子供の頃ですね、大沼さんが作られました原子力明るい未来のエネルギーという看板ですね、ちょうど一年程前に外されまして、町はえらい変わった印象でありました。福島第一原発事故で故郷を追われたことから、愚かな原子力政策に反対をし続け、その看板のアーチを震災遺構として残す活動も大沼さんはされてきました。看板ですね、先程も申し上げましたように昨年12月、老朽化を理由に取り外されてしまいました。
双葉町、今、どないなってんのかと思いまして今回は足を運びました。
その大沼さんのルポをこの後お届けしますが、5年と8ヵ月経ちました福島第一原発の事故、その放射能の現状について、元京都大学原子炉実験所助教の小出裕章さんにお電話でお話を伺います。小出さん、今日も宜しくお願い致します。
小出裕章さん:
はい、こちらこそ宜しくお願いします。
いまにし:
小出さんですね、私、大沼さんと一緒に双葉町に行ってまいりました。今も、やはり非常に放射線量が高い場所が数多くあります。そして、所謂、ホットスポットというような感じで、急に高放射線量がガーッとアップするような所が双葉町ですとか、同じく隣接します大熊町ですとか、そういう所にあります。そして、モニタリングポストですね、放射線量を計測する機械が設置されておるのですけれども、いつもあれを見て、「これ、どのようにして計測してるのかなあ?」と思うのですが、ちょっとその辺、先生教えて頂けますでしょうか?
小出さん:
はい。今、いまにしさんが見て下さったというモニタリングポストというのは、空間ガンマー線量というものを測定しているものだと思います。空間、今、ある時には放射性物質自身が空気中に漂ってる時もあるわけですし、事故の初期を過ぎれば、空気中にあったものが地面に降り注いで地面にくっついているわけですけれども、そういうものから、空間のある場所でどのぐらいの放射線を浴びてるのかということを測定しているものです。
いまにし:
はいはい、なるほどなるほど。それで、このモニタリングポストというのはどうなんでしょうかねえ。示してる値というのは正確なものなんでしょうか?
小出さん:
国の手によって設置されてるモニタリングポストというのは、私はインチキだとむしろ思っています。というのは、例えばモニタリングポストを設置する時に、周辺を整地しているはずだと思います。そういう時には、その場所のまず汚れた土を例えばはいだり。仮にそれがないにしても、その上にコンクリートを打ってしまったりするわけですから、所謂、普通の何も手を加えない場所での空間線量率というものに比べれば、かなり低い値をもともと表示しているはずだと思います。
いまにし:
なるほど。その中で、私が双葉町に行った時に、1.147マイクロシーベルトという普通では考えられないような高い数値だと思うのですが、記録しているような所もありましたが、この数値というのは小出さんから見られていかがでしょうか?
小出さん:
私は長い間、京都大学原子炉実験所で放射能を相手に働いていました。放射能を扱う時には、原子炉実験所の中に入っても、どこでも放射能を扱っていいというわけではなくて、放射線管理区域という指定された特別な場所でしか扱うことができません。そして、1時間あたり0.6マイクロシーベルトを超えるような場所というのは、必ず放射線管理区域に指定しなければいけない。人々の立ち入りを禁じなければいけないという、そういう場所だったのです。今、いまにしさんは1.4とおっしゃった。
いまにし:
1.147ですね。はい。
小出さん:
普通の人はそんな所に立ち入ってはいけない。私のような人間が仕事上、どうしてもしょうがなくて入る場合でも、そこに入ったら水も飲むなというそんな場所なのです。今、双葉町の広大な場所が未だにそうやって汚れてしまっているということです。
いまにし:
なるほど。それで小出さん、大沼さんからちょっと質問がありましたのでいくつか伺います。
「双葉町に帰還する度に、高い放射線量の区域なので防護服が支給されます。しかし、目だけは何も用意されていません。放射線量と目の関係について、ゴーグル等を付けた方がいいのでしょうか?」とおっしゃられてます。
小出さん:
はい。「つけた方がいいのか?」と問われてしまえば、もちろん付けた方がいいです。但し、あの防護服というのは、ガンマー線を遮る力はもともと何にもないのです。ですから、汚れが体に付着するのを防ぐという、ただそれだけの意味しかありません。ですから、「目の所にゴーグルをかけた方がいいか?」と言われれば、もちろん目の部分に放射性物質が付着するのを防ぐという意味では、やった方がいいと私は思いますけれども、今現在、双葉町で大量の放射性物質が空気中に漂ってるということはないはずですので、目という極小的な部分をゴーグルで覆うということで、避けられる被ばくの量はそんなに多いとは私は思いません。但し、目も被ばくをしますと、白内障になったりするということが既に分かっていますので、できればした方がいいと思います。
いまにし:
そうなんですか。目も被ばくすると、白内障になる可能性が結構あるんですねえ。
小出さん:
はい、あります。
いまにし:
はい。あと、私なんかも双葉町に夏場なんかに行くと、結構、途中疲れて道端で座って休んでしまうことがあるのですが、大沼さんはその辺を凄く心配されておられて、「やはり、地べたに直接座ると、被ばくしやすくなるのでしょうか?」と伺われておられます。
小出さん:
はい。大沼さんはその時に、防護服を着ていらっしゃるんだと思いますが、防護服を着た状態で座るということになると、放射性物質自身は防護服にくっつきますので、大沼さんの身体に付くことはないはずだと思います。そして、防護服を脱いでしまえば、防護服にくっついた放射性物質から被ばくをするということはなくなるわけです。但し、ガンマー線自身は全く避けられませんので、防護服を着た状態であっても地面に座れば、地面が汚れていますので余計な被ばくをしてしまいますし、防護服が汚れた状態でそれを着続けていれば、ずーっとまたガンマー線で被ばくをしてしまうということになりますので、出来るならば座ったりはしない方がいいと思います。
いまにし:
はい。そして、次ですね、大沼さんが伺いたいなとおっしゃられておったのがですね、「この5年8ヵ月の間、半減期で消滅した放射能とそうでない放射能がありますが、空間線量計を持っていくのですけれども、空間線量だけに頼っていて大丈夫なのでしょうか?」ということを聞かれております。
小出さん:
もちろん大丈夫ではありません。今の半減期のことを話して下さいましたけれども、原子力発電所から放出された放射性物質の中には、いわゆる寿命が長いか短いかということで大きな違いがあります。例えば、ヨウ素131という放射性物質があって、それが現在、福島で見られている子どもの甲状腺がんを引き起こした主要な原因だと私は思っていますけれども、そのヨウ素131は8日経つと半分に減ってくれる。また8日経つと、その半分になるというように、かなり急速に減ってくれて、今現在、5年8ヵ月経っているわけですが、もうヨウ素131は全くないのです。逆に、寿命の長い放射性物質もあって、私が一番問題だと思っているのはセシウム137という放射性物質ですが、それは半分に減るまで30年かかる。
事故からこれまで5年8ヵ月経ってるわけですが、まだほとんど減っていないまま汚染が続いているのです。それが、これからずーっと人々を被ばくさせ続けるということになります。
空間ガンマー線量というのを、今皆さん測っているわけですけれども、そのほとんどはセシウム137からきているものです。ですから、空間ガンマー線量を測っていれば、その場所を測ってる、
その場所の周辺がどの程度セシウム137で汚れているということぐらいは目安として分かると思います。但し、特別な場所では未だに空気中にセシウム137が舞い上がってきていたりする場所もありますので、空間ガンマー線量だけを測るというやり方では不十分だと私は思います。しかし、一人一人の住民達、避難をした人達が空間ガンマー線量を測ることすらなかなかか難しいと思いますし、ましてや空気中に漂ってるセシウムを測定するということは、基本的にはもうできないと思うしかないと思います。
いまにし:
はい、分かりました。小出さん、ところで小出さんは先日、双葉町の町長をされておられました
井戸川克隆さんにお会いになられたというようにお話を伺いましたが、どのようなお話をされたんでしょうか?
小出さん:
はい、井戸川さんとは時々お会いする機会がありますが、一番最近彼とお会いしたのは11月1日でした。多分、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、世界的な名ピアニストのクリスチャン・ツィメルマンさんという方がいらっしゃって、その方が東京でコンサートをやるということで、私も招待して頂いたのです。
私そのコンサートに行きましたら、井戸川さんも招待されていたということで、その場所でお会いしました。
いまにし:
どのような感じのお話をされましたでしょうか?
小出さん:
事故があって5年8ヵ月、ほんとに超人的に活動されてきたと思います。お疲れにもなっているし、彼自身がかなりの被ばくをしたということで、事故直後にも鼻血を出したということもあったわけですが、未だに鼻血が出るし体調が良くないと。凄い疲れやすいというようなことを彼はおっしゃっていました。
いまにし:
はい。それで、先程お話が出ましたポーランドのピアニストのクリスチャン・ツィメルマンさんについてちょっと教えて頂きたいのですけれども、ちょうど東日本大震災の時には東京にいらっしゃったということで、毎年のようにチャリティーコンサートを続けておられるということだったのですが。
小出さん:
はい。私がツィメルマンさんから招待されたコンサートも、彼自身が無償で出て下さったということでした。ポーランドという国で彼が生まれた、私と確か6歳違いで、ちょうど今60を過ぎた頃だと思います。昔から美男子でしたけれども、今は真っ白な白髪になって、ますます素敵な風貌になっていました。
福島の事故を東京でたまたま出会ってしまって、それ以降、福島の人達にとにかく寄り添わなければいけないということで、チャリティーコンサートのようなことをずーっとやってきてくださった方です。
いまにし:
そのコンサートを聴かれたご印象はいかがだったでしょうか?
小出さん:
はい、彼は、こうやって限定つけるのよくないですけれども、多分一番いいのはショパンだと私は思いますが、私が聴かせて頂いたのはベートベンでした。でも、大変力のこもった演奏で、若い団員達と大変スリリングな掛け合いの演奏で、私はそれを聴けただけでも良かったと思っています。
いまにし:
はい。ここで小出さんから頂戴しましたクリスチャン・ツィメルマンさんのメッセージがあります。このメッセージですね、とても素晴らしいので、是非リスナーの皆様にも聞いて頂きたいと思いまして、その一部をご紹介させて頂きます。
小出さん:
はい。ありがとうございます。
いまにし:
小出さんと一緒に、是非皆さんお聞き下さい。
朗読は鵜飼一嘉(うかいかずよし)アナウンサーです。
いまにし:
小出さん、ほんとに素晴らしいメッセージですねえ。
小出さん:
はい。私はこのメッセージを添えて、約1週間ぐらい前だったと思いますが、コンサートの招待状を頂きました。私は11月1日という、その日1日だけは空いていたのですが、31日も2日も別の約束が入っていてどうしょうかと悩みましたけれども、このツィメルマンのメッセージを見たらばもうどうしても行くしかないと思って、当日日帰りで松本から出掛けました。ほんとに素晴らしい方でした。
いまにし:
もう日本では、今、福島第一原発の事故が忘れ去られよう、逆に、忘れろ忘れろと云わんばかりの政府ですとか東京電力の姿勢が垣間見えるのですが、一方で、忘れてはいけませんということを発信して頂いてるツィメルマンさん。本当にありがたく思いますよねえ。
小出さん:
はい。福島第一原子力発電所の事故を起こした責任というのは東京電力や日本の政府にあるわけで、私は彼らを犯罪者と呼んでいます。
彼らを徹底的に処罰をしなければいけないと思っていますが、逆に、彼らから見れば、とにかくこの事故をなかったことにさせてしまいたい、忘れさせてしまいたいということで、周到な行動を彼らはとっているわけです。
でも、ツィメルマンは、彼は忘れないと言って下さってるわけですし、その為に、彼ができることを自分でやるんだということを言ってくださって、実際にそれをやって下さっている。
ツィメルマンさんが世界的に本当に素晴らしいピアニストだということは、おそらくほとんどの方が認めると私は思いますが、それ以上に、彼は人間として素晴らしと私は思いました。
いまにし:
分かりました。小出さん、ありがとうございました。
小出さん:
いえ、ありがとうございました。
Ballade NO.1 in G Minor.Op23
(作曲:Fryderyk Franciszek Chopin・演奏者:Krystian Zimerman)
https://youtu.be/Ce8p0VcTbuA
いまにし:
それではここで大沼勇治さんと訪れました福島県双葉町、帰還困難区域の様子をお聞き頂こうと思います。大沼さんの考えられました標語のアーチ、看板がありました双葉町のメインストリートで、大沼さんにいろいろお伺いしました。現地でのルポを録音でお聞き頂きます。
いまにし:
大沼さん、看板がなくなって1年が経ちました。なんかこれまである看板が急になくなると、えらく風景が変わってしまったなあと思うんですが、現実この場所に立たれていかがでしょうか?
大沼勇治さん:
そうですね。全く別の場所になってしまい、自分の故郷じゃない気がします。何ですかね、これまでいろいろ原発と共に歩んできた町そのものも終わった感じがして、ただそれを残すことで、やっぱり全てありのまま伝えたかったんですけども、なんかその過去まで全てを否定されるかのような感じで、やはり、この場所で残したかったですねえ。
いまにし:
双葉町ですね、ちょうど1年前にも、私と大沼さんはこの看板のあった場所に来ていたのですけれども、あれから1年、全く今も人通りがなく、まれに警備のための車が通るだけという寂しい感じがするのですが、もともとここは双葉町のメインストリートだったわけですよね?震災前は。
大沼さん:
そうですね。ここは商店街や駅に向かうメインストリートでして、それで多くのこの時間、町民の方が行き来してました。車も結構走ってました。
いまにし:
見た雰囲気では1年前とほとんど変わらず、ひと気が全くなく、ほとんど時が止まったままかなあという気がするのですが。
大沼さん:
そうですね。今日驚いたのは、街中の商店街に大きなイノシシがいたんですね。それはびっくりしました。山でしか、たまに夜とかしか見かけなかったんですけども、街中で人がいないと分かってるせいか、動物の糞のようなものが沢山あったりですね。大きな通りは、確かに倒壊した家屋等が少し整理されたみたいなんですけども、その他の道は全然変わってないので、全然、復興してるとは思えないですね。
いまにし:
大沼さんの考案されました原爆の標語の看板撤去されまして、その後どうなってるんでしょうか?
大沼さん:
はい。まず、役場敷地内の場所にそのままシートを被せて、16メートルあった看板の方はそのまま置かれてて。先月、福島の県立博物館さんの方でアクリル板だけ運んで、それで「明るい未来」の「み」だけがちょっと線量が高かったみたいなので、第二原発のけがやクリーニング場で高圧洗浄かけて線量を落として、それで運んだということを聞いて。とりあえず、アクリル板の方はきちんとしたとこで保管されてるので、そういった面では安心なんですけども。肝心の鉄板の方はやっぱりサビによる塩害腐食によって、今も劣化し続けてるので、そちらの方はちょっと保管して欲しいなと。
また何らかの形で早く展示して。痛まないうちにですね。それで伝えたい思いですね。
いまにし:
双葉町もしくは福島県がどこかに展示、皆さんが見れるような状況になるということなんでしょうか?
大沼さん:
そうですね。その震災以降のプロジェクトというのが博物館さんの方でやってるみたいで、県立博物館さんの方で、何らかの形で展示される可能性はあると思います。あと、その東北大学さんの方で3D映像の測量のデータ残してるみたいなので、その3Dでは見れる日が来るのではないかと思ってるんですが。やはり、現物の看板とそのアクリル板が一体化されて展示されるのが理想なので。それは、復興記念講演に展示される可能性はあると役場の職員の方はおっしゃってたんですけども。まだ、ここ2年ぐらいは動かないという風に。その間、劣化しないことを祈るばかりです。
いまにし:
まだ原発の終息作業も充分に進んでいない中、双葉町の未来というのは、大沼さんから見られてどうあって欲しいという風に、今お考えですか?
大沼さん:
そうですね。原発と共に舵を切った町が、現代、中間貯蔵施設により放射性廃棄物の汚染されたものが運ばれて、なんか人からゴミに変わってしまったので、ここにいつか僕も子供達を連れて、自分の故郷だというのを伝えたいんですが、まだちょっとこの状況では厳しい感じがします。
ゴミバックが5段ぐらい積んでるのを見ると、なんかそこがかつて住宅があった場所が津波にさらわれて、仮置き場になってる光景、そこからまた草が覆い茂ってるという光景ですね。ほんとにせつないです。
いまにし:
はい。大沼勇治さんに伺いました。ありがとうございました。
大沼さん:
ありがとうございました。
いまにし:
実際に双葉町に行ってみますと、本当にゴーストタウンというのか、死の街というのか、全く人通りもなく、活気もなく、原発事故の奥深さというのを思い知らされます。そして、つくづく国と東京電力の無責任さというのも考えさせられます。心の傷の深さを感じずにはいられない、そんな取材になりました。
以上、今日は特別編でお送りしましたLight Up!ジャーナルでした。
原発避難者13万人の選択 事故から3年
http://dai.ly/x1fiih9
東京電力福島第一原発の事故から3年。未だ故郷に帰れない原発避難者は13万人いる。いま国は事故以来、前提としてきた避難者の「全員帰還」という方針を転換し、年間50ミリシーベルトを超える帰還困難区域の2.5万人には事実上の“移住”を求め始めている。その一方、3.4万人が暮らしていた年間20ミリシーベルトを下回る避難指示解除準備区域では、住民の早期帰還を進めようとしている。
故郷へ帰ることを諦めざるを得ない避難者。逆に放射能への恐れから帰れといわれても帰りたくない避難者。それぞれが現実を突きつけられ、厳しい選択を迫られているのだ。番組では13万人が直面する震災3年目の現実を取材。原発避難者を救済するために何が必要か考える。






